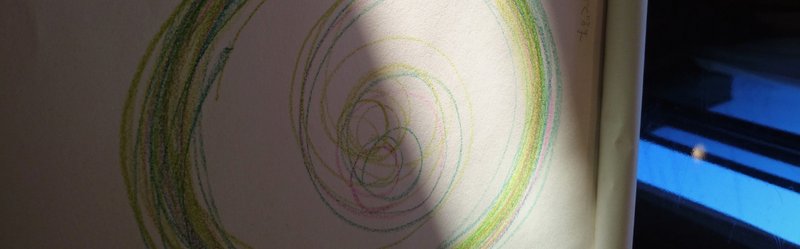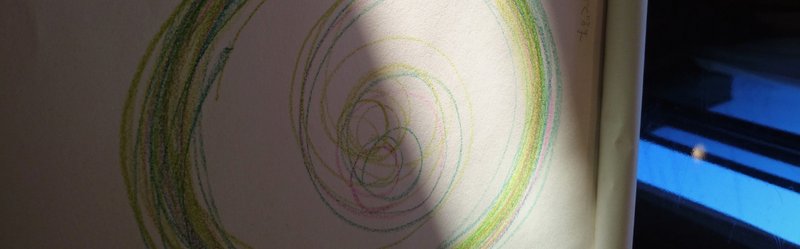6/22自閉症の生徒対策で片付けを始めたら
片付けができない!!言い訳をするわけじゃないけど、(いいわけだけど・・)
里子に出していたアップライトのピアノが突然に帰ってきたころには父の看護におれていて、教室の整理どころでではありませんでした。で、とりあえずな感じでグランドピアノを隅に移動してもらい、反対側の壁にアップライトをおいてもらいました。その頃から、自閉症の生徒の態度がむっちゃわるくなって、今まで目に入らなかった引き出しが目についてものを引っ張り出したり、ほおりあげたり、で、私もついダメ出しの数が多くなっていたか