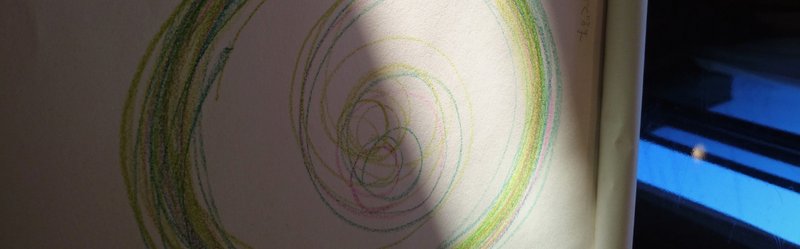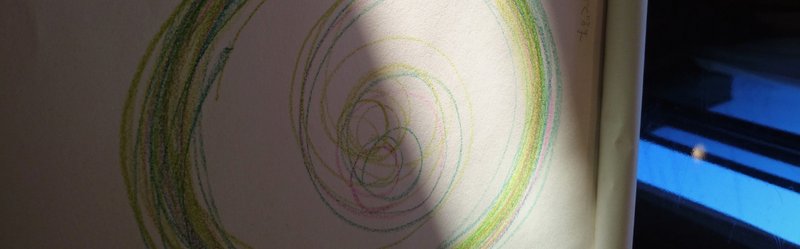”音楽を描く”ワークショップ6月
愛媛は感染者数も減ってきていることもあり、音楽室も隣の部屋を開け広く使いながら、月1回の大人の音楽ワークショップ「音楽を描く」utena drawing を行いました。
もう多分5年近くになるこのメンバーでのワークショップ。
感覚的にはこなれてきているし、体感もドローイングも随分変わってこられていて、いつもにこにこして皆さんたのしそうではあるのですが、そろそろ、受動的なワークでは物足りないのではないかなと思ったりします。ほんとうなら、歌ってみたり、笛を吹いたりしてアウトプッ