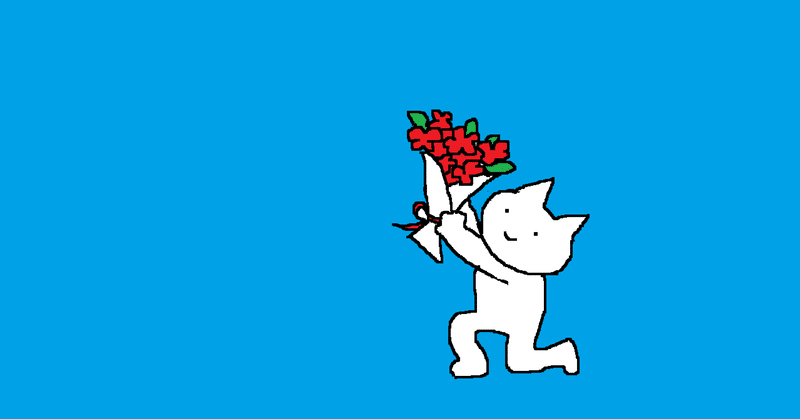
かぐや姫と見合いをした五名の正体
かぐや姫の結婚を取り巻く場面の解説です。竹取物語の中でかぐや姫は帝との結婚について暗に受け入れ、三年間の文通を行ないますが、それ以前に大規模な見合いの場面があるのはよく知られています。
かぐや姫の見合いの場面について
この場面では一般的に五人の偉い方がやってきて、かぐや姫から無理難題を押しつけられ、その挙句に誰も敵わず、かぐや姫は独身のままこの場面を終えます。
この場面には、かぐや姫の美しさを助長すると同時に、文学としての教養やいわゆる頓智(とんち)が感じられると同時に、時代の時世への皮肉のような含みが見られるという風に解釈されています。かぐや姫がいかに美しいかを表すのに、家に男共が群がる様子は非常にわかりやすく、良家の男が身分を顧みず、同じく裕福な美女とはいえ竹取の翁の屋敷へぞろぞろとやってくるのは充分過ぎる演出だというのです。
さらに、この場面は長いです。本来の主役である竹取の翁やかぐや姫からも視点が映り、それぞれの男の冒険が長々と書かれ、一般的には大幅に削られます。五名の内には怪我をして寝たきりになったり、命を落とした者もいましたが、そこまでわざわざ描かれることは稀です。
最後に、彼らの失敗をかぐや姫はどこか粋で皮肉に言い表します。ここに竹取物語の文学性が凝縮されているという見方もあります。
かぐや姫と正式に見合いをした五名の正体
写文の中でも、その五名にはそれぞれに名前と身分がはっきりとあります。
・石作皇子(いしつくりのみこ)
・車持皇子(くらもちのみこ)
・右大臣阿部御連(あべのみむらじ)
・大納言大伴御行(おおとものみゆき)
・中納言石上麻呂足(いそのかみのまろたり)
彼らは数百年もの間、物語の登場人物とされてきましたが、江戸時代には国文学者の加納諸平(かのうもろひら)によって実在の人物がモデルなのではないかと指摘されます。その研究内容は昭和元年に「竹取物語考」として刊行されました。
竹取物語考に書かれた五名の正体は以下の通りです。
・多治比嶋(たじひのしま)…石作皇子
・藤原不比等(ふじわらのふひと)…車持皇子
・阿倍御主人(あべのみうし)…阿部御連
・大伴御行(おおとものみゆき)…大伴御行
・石上麻呂(いそのかみのまろ)…石上麻呂足
多治比嶋は石作氏を一族に持ち、藤原不比等は母方の性が車持であることから推測される架空人物で、後の三名はほぼ同名で登場しているといいます。身分も各々共通します。
このことから推測される竹取物語の意義は「藤原氏の批判」です。五名とも藤原鎌足を始祖とする藤原氏と深い関わりを持ち、時の権威ある勢力の一端の担った人物達。彼らをかぐや姫に求婚し、結局は醜態を晒すことで、作品の中で彼ら(ひいては権力そのもの)を否定したと考えられるのです。
この場合、五名ともが飛鳥時代(五九二年~七一〇年)後期から奈良時代(七一〇年~七九四年)前期にかけて実在したことなどから、写本では語られていない竹取物語の時期設定が奈良時代初期であることも併せて推測されています。
五名への無理難題
同時にこの場面は、竹取物語の文学性を広く知らしめるに至った重要な場面でもあり、五名の男がそれぞれに頼まれ、捜索や工夫をした後には彼らとのやり取りがあり、最後には結論付けてかぐや姫は小粋な言葉を数々残しています。物語の全体にもそういった言い始めのような記述は多いのですが、この場面は際立っています。
かぐや姫はまず、男らに「志」の提示を求めます。要は浮気などしない意思、また姫を想う心の深さ、行動などです。
・石作皇子には、天竺(てんじく=今のインド)にあるという「仏の御石(みいし)の鉢」を。
・車持皇子には、東の海の向こうにそびえる蓬莱(ほうらい)という山にある「玉の枝」(根が銀、茎が金、実が真珠の木の枝)を。
・右大臣阿倍御連には、唐(今の中国)にいる「火鼠(ひねずみ)の皮衣(かわぎぬ)」を。
・大納言大伴御行には、龍が首に付けている「五色に光る珠」を。
・中納言石上麻呂足には、燕(つばめ)の産むという「子安貝」を。
五名はこれらの難題を示され、一応は引き受けて挑むが全員失敗します。その折にかぐや姫と文を交わし、後にはかぐや姫から皮肉の言葉を呟かれたりとします。
石作皇子=仏の御石=恥を捨てる
・石作皇子は偽物の仏の御石の鉢を作り、かぐや姫に送ったが突き返され、鉢を捨ててまた言い寄ろうとします。そのことから厚かましい様を「はぢ(鉢)恥を捨てる」と言うようになりました。
車持皇子=玉の枝=魂離る
・車持皇子も同様に玉の枝の贋作を腕の立つ職人達に作らせたが、かぐや姫は見抜けず、婚姻の準備が進もうとします。しかし費用を貰っていなかった職人達が屋敷に押しかけたことで暴かれてしまい、皇子は自らの所業を恥じては姿をくらまします。このことから正気を失う様子や魂の抜けた様を「玉さかる(魂離る(たまさかる)」と言うようになりました。
阿倍御連=火鼠の皮布=あへなし
・阿倍御連も偽物を用意した一人ですが、本人は本物といわれた火鼠の皮布を取り寄せています。かぐや姫に差し出したところ、火に決して燃えぬというその品を試すことになり、実際に火にくべるとあっけなく燃えてしまいます。このことから上手くいかないことを「あへなし(阿部無し)」と言うようになりました。
大伴御行=龍の首の珠=堪え難い
・大伴御行は龍を探して海に出発したが、荒波に遭い、病気になって目を李(すもも)のように腫らせて逃げ帰ります。かぐや姫には会うことせず、後に世間では彼の李のような腫れ目を「たへ(食べ)難い」または「たへ(堪え)難い」と言うようになりました。
石上麻呂足=燕の子安貝=甲斐なし
・石上麻呂足は燕の巣を家来に見つけさせて子安貝を探したが、巣は見つかっても貝は見つからず苦戦し、また一つの巣を見つけたところで自ら上り、貝を掴んだと思ったら燕の糞でした。このことから努力の報われないことを「甲斐(貝)なし」というようになります。
余話として、さらに彼は糞を掴んだまま地面に落下し、その怪我が元で寝たきりになってしまいます。かぐや姫は彼の容態を聞き知り「待つ甲斐がない噂は本当ですか」という旨の手紙を寄越します。彼は「骨を折った甲斐はあったが、私を救う匙(医者の匙の意、櫂(かい)とも時に言い表す)はないのでしょうか」という返書をした後に亡くなります。かぐや姫は彼を気の毒に思い「甲斐はある」と言い換えました。
見合いの場面は風刺文学であるという結論
五名の話には、差異はあれどもかぐや姫の思惑通りに結婚は叶わず、彼らは多くの財産や信用、また命までも失います。かぐや姫は彼らの事柄を元にいくつかの言葉を作り、それらは現代でも使われています。
まとめると、五名のおそらく実在した人物を手玉に取って恥をかかせた上、文学的な風刺の言葉で占める、という一連です。かぐや姫を美しい女であると演出しながら、偉い男を情けなく描き、さらに高尚な文学として成り立たせているのです。
深く疑ってみると、これら三つの要素に優先順位はあったのかとも考えられます。
「かぐや姫をより美しい存在と見せる」
「文学としての成立」
「偉い身分への風刺」
もしかぐや姫の美貌をより読者に根付かせたいのであれば、場面の主観を男達に変えて尚且つ長尺にする必要性は見られません。
また文学的に作品を高めるのであれば、実在の人物達をわざわざ出現させる必要性は感じられません。
すると、実在の人物を元にした五名が登場することにこの場面の最も大きな狙いがあったようには見えるのです。皆が権力のある面々で、それも同じ勢力にある者達。少なくともこの見合いの場面に関してだけは、時の権力者勢を風刺的に書き表した狙いは信憑性深く感じ取れます。
そのことを理解されているのかいないのか、例えばテレビやラジオ、絵本などで簡単に竹取物語が伝えられる時、見合いの場面は簡略化されています。
