
Voice of “usen for Cafe Apres-midi” Crew
2019 Early Autumn Selection(8月26日〜10月13日)
橋本徹(SUBURBIA)を始めとする
「usen for Cafe Apres-midi」の選曲家17人が
それぞれのセレクトした音楽への思いを綴る
「Voice of “usen for Cafe Apres-midi” Crew」
詳しい放送内容はこちら
D-03 usen for Cafe Apres-midi
http://music.usen.com/channel/d03/
橋本徹(「usen for Cafe Apres-midi」プロデューサー) Toru Hashimoto
秋の訪れを告げる風をときおり肌に感じながら、今回もメロウ&グルーヴィーで心地よい楽曲を中心に、計34時間分を新たに選曲した。
金・土・日の夕暮れの特集も「夏の果て〜初秋のGood Mellows」と題して。新譜も引き続き大充実で、このEarly Autumn Selectionで特に重要な役割を果たしてくれた推薦作のジャケットを24枚掲載するので、ぜひその中身の音楽の素晴らしさにも触れてもらえたら嬉しい。
とりわけチャンス・ザ・ラッパーの『The Big Day』は、ミックステープ世代として台頭した彼の失われゆくCDへの愛着とオマージュを感じさせる構成で、僕の『Heisei Free Soul』とのシンクロニシティーを感じずにいられなかった。何よりも、聴いていてポジティヴな気持ちにさせてくれる音楽であることが素晴らしいのだけど。
追記:
前回のSummer Selectionが始まる前日、七夕の朝に訃報が届き言葉を失ってしまったジョアン・ジルベルトの死。今回のEarly Autumn Selectionでは、「usen for Cafe Apres-midi」のメンバー17人それぞれが、ジョアンへの追悼の意をこめた選曲を織りまぜ、セレクター・コメントでもジョアンへの思いを綴ることにした。
ジョアンの楽曲はすべて好きで、もちろん来日公演もすべて観た世界一好きなミュージシャンだが、僕が選んだのは自分にとって究極の一曲「Undiu」。ある夜ひとり耳を澄まし瞑想していたら、僕がボサノヴァに強く惹かれるきっかけになったエヴリシング・バット・ザ・ガールのベン・ワットが「ドラムンベースは新世代のボサノヴァだ」と言った意味が感覚的に理解できた。
ジョアンのライヴを初めて観たのは2003年の初夏、パリのオランピア劇場。東京で観るという夢は永遠にかなわないだろうと、「usen for Cafe Apres-midi」のプロデューサーだったヒロチカーノと旅したのだった。そのときに感じた信頼関係、心の絆が僕に20年近く「usen for Cafe Apres-midi」を続けさせてくれていると思う(そう、ジョアン・ジルベルトは「usen for Cafe Apres-midi」の精神的支柱なのだ)。最後のアンコールでガット・ギターで爪弾かれたのはシャルル・トレネのシャンソン「残されし恋には」。それまでに体験したことのない静かな感動に胸を震わされた。会場中に美しい波紋を描くように歌の輪が広がっていった、そのセンティメンタルな余韻は、今も僕という人間の奥底にある心の柔らかい部分に優しくこだましている。

Moonchild『Little Ghost』
Bryony Jarman-Pinto『Cage And Aviary』
Taylor McFerrin『Love's Last Chance』
Kainalu『Lotus Gate』
Clairo『Immunity』
Haim「Summer Girl」
Hope Tala『Sensitive Soul』
Melo-Zed『Zachary』
Chance The Rapper『The Big Day』
YBN Cordae『The Lost Boy』
Tobi Lou『Live On Ice』
Anti-Lilly & Phoniks『That's The World』
Salami Rose Joe Louis『Zdenka 2080』
GODTET『II』
Sanctuary Lakes『Sanctuary Lakes』
CFCF『Liquid Colours』
Marinero『Tropico De Cancer』
Fox Academy『Angel Hair』
Jacob Collier『Djesse, Vol.2』
Burna Boy『African Giant』
Mayra Andrade『Manga』
Asi『Minimas』
Luiza Brina『Tenho Saudade Mas Ja Passou』
Mateo Kingman『Astro』
本多義明(「usen for Cafe Apres-midi」ディレクター) Yoshiaki Honda
初秋と言えば自分の中では秋の始まりというより、どちらかと言えば夏の終わりというイメージが強く、9月などはまだ夏を引きずっている季節。夏のアルバムで何作かお気に入りがあった中で、そんな夏を名残惜しく思う気分に合うのはDucktailsの『Watercolors』でした。夏らしい曲はもちろんあるものの少し切ない曲もあり、夏の最果てのこのシーズンにすごくマッチします。もしかしたらマット・モンデナイルも夏から夏の終わりを意識して曲と順番を決めたのかも、と思わせるアルバムでした。
7/6に天国に旅立ったジョアン・ジルベルトを想い、自分が選曲を担当する木曜~日曜の12時〜16時の最後の曲に、ジョアンの曲を選びました。これからも永遠に語り継がれるボサノヴァの神様に、自分なりに敬意と追悼の意を表したつもりです。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

Ducktaills『Watercolors』
中村智昭 Tomoaki Nakamura
彼こそが真のボサノヴァ。ジョアン・ジルベルトの作品は、もちろんそのどれもが素晴らしい。中でも個の表現者としての姿を見事に捉えた『Joao Gilberto』(邦題『三月の水』)が、生涯のバイブルであることは間違いない。しかしながらスタッフとして過ごしたカフェ・アプレミディ最初の10年と、2010年のオープンから今日に至るまでのBar Musicにおいて、最も再生回数が多いアルバムはこの『Joao Gilberto En Mexico』(邦題『彼女はカリオカ』)だ。特に「Farolito」から始まるB面は、いつ何時どんなシチュエイションであっても、お客様との大切な時間をより特別なものにしてくれる。ありがとうジョアン、安らかに。そして僕たちは、これからも渋谷で毎晩ずっと一緒だよ。

Joao Gilberto『Joao Gilberto En Mexico』
Dinner-time 月曜日18:00~24:00
Cafe Apres-minuit 火曜日0:00~2:00
添田和幸 Kazuyuki Soeta
今回のセレクションでは癒しを求めてドイツはバイエルンのSimon PoppことPopp、Gaussian CurveのメンバーでもあるYoung MarcoやCarmen Villainの新譜などアンビエント・フィールな作品に惹かれましたが、一枚を選ぶとなると全編心地よい浮遊感に包まれたアルゼンチンのコルドバを中心に活動するバンド、Asiのセカンドを推したいと思います。そして最後には先日亡くなったJoao Gilbertoに追悼の意を込めて最も好きな「Undiu」を選びました。初来日時の空調を切った静寂の中での感動は今でも忘れることができません。

Popp『Laya』
Young Marco『Bahasa』
Carmen Villain『Both Lines Will Be Blue』
Asi『Minimus』
Dinner-time 火曜日18:00~24:00
Cafe Apres-minuit 水曜日0:00~2:00
中上修作 Shusaku Nakagami
この文章を読んでくださっている皆様は、コンサートに何を期待するでしょうか。憧れのミュージシャンに会える。わたしの好きな、あの曲を生演奏で聴ける。理由はいろいろあるけれど、音楽ファンは大抵コンサートに足を運びます(仮に好きなミュージシャが故人であっても、今では生前のドキュメンタリー映画や過去の記録をたどることができます。映像での体験も視野に入れましょう)。そう、わたしも同じ理由で様々なスケジュールを管理しつつ、いそいそとコンサートに出かけます。15年前の東京国際フォーラムのときもそうでした。
飛行機嫌いで有名だった彼の来日なんて夢物語かと思っていました。彼は何かと気難しいというウワサで、楽しいはずのコンサートに出かけるのに何かこちらが緊張せねばなりませんでしたが、それよりも「憧れの彼に会える」という大きな期待を持って会場に歩を進めました。しかし、席についたら何だか蒸し暑い。9月も半ばでしたが、残暑は尾を引いて外気は30℃を超えていたはずです。それなのに空調はなぜかあまりご機嫌よく動いていない様子でした。席がおおかた埋まり(もちろん全席ソールド・アウトです)、いよいよ彼の登場か、と思ったときにこんなアナウンスが。「本日演奏される彼の命に従って、会場の空調は全てストップさせていただいております。悪しからずご了承ください」。<なんだと?><マジかよ……>こんな溜息にも似たどよめきが会場を埋め尽くすも、なんだか皆うれしそう。わたしも「彼ならそうするだろう」と心の中で少しニンマリとしました。しかし、アナウンスから15分経っても彼は出てこない。20分、25分、と時間が過ぎてゆく。あまりの暑さに頭が朦朧としながら、志を同じくする会場の全ての人が彼に向かってエールと拍手で出迎えようとしている。皆、始まる前からなんだかとても興奮している。そしてアナウンスから30分、ついに照明が落ちた!
気がつけば3時間。わたしは朦朧とした頭を抱えながら会場を出た。いや、なんだか名残惜しくて会場は出たものの、なかなか外に出る気がしなかった。彼の演奏をこの目でしっかり観たはずだ。しかし、今しがたこの身に起こったことはなんだか夢の中のような、例えばLINNのLP-12のように良質なターンテーブルを中低域が充実したOctaveの真空管アンプを繋ぎ、イタリアの官能を感じさせるSonus Faberのスピーカーで出力したような、解像度は明瞭ではないが自然な粒立ちで、しかも余韻が長い音のシャワーを浴びてきたような。そんな印象だった。
記憶をたどろう。たったひとり、彼はステージで淡々とガット・ギターをつま弾き、猫背のまま唄っている。それは長年レコードで聴いてきた、あの人のあのままの音だった。なんという再現力。なんという欲のなさ。練習魔で有名だった彼の練習場所はリヴィングでもスタジオでもなかった。そう、浴槽である。理由はいろいろ考えられるが、まぁそれはいいだろう。この日に起こったこと。それは適温の湯船のような中で、長年聴いてきたレコードをとてつもないクオリティーの音で聴いていた、ということ。とても残念だが、ここに誇張は全くない。コンサートなのに何も起こらない。ただ日常が紡がれただけ。こんなコンサートを実現できたのは彼しかいない。しかし、実はこれこそがBossa Novaなのではないか。
J.G.さん、安らかに。

Joao Gilberto『Live At Umbria Jazz』
Dinner-time 水曜日18:00~24:00
Cafe Apres-minuit 木曜日0:00~2:00
髙木慶太 Keita Takagi
現人神が本当の神様になってしまった。
ジョアン・ジルベルトは本人が意図も意識も全くせぬままに世界の音楽地図とたくさんの人の人生を決定的に変えてしまった人だと思う。
先日もトロピカリズモにスポットを当てた選曲をする機会があり、カエターノ・ヴェローゾやジルベルト・ジルの初期音源の素晴らしさと、アート・リンゼイが50年に及ぶ呪縛とさえ表現する、その後のブラジル音楽シーンへの影響力の大きさにたじろぎながら、彼らとてジョアンが現れなかったらブラジルの怒れる若者のひとりに過ぎなかったかもしれないことを思い茫然となった。
今回はジョアンを精神的な父あるいは祖父とするブラジル音楽を中心に選曲した。

Joao Gilberto『Joao Gilberto』
Dinner-time 木曜日18:00~24:00
Cafe Apres-minuit 金曜日0:00~2:00
FAT MASA
ウーター・ヘメルと言えば、橋本徹さんとご一緒した2007年の北海道ツアーのDJイヴェントで知ったミュージシャンであります。今回のアルバム『Boystown』ではその思い出あるファースト・アルバム『Hamel』から、「Breezy」のビッグバンド・アレンジが冴え渡る素晴らしいテイクが収録されてます。他の曲も素晴らしいですが、「Breezy」を聴くとリリース当時に脳内ワープします。早いものでもう12年前ですが、色褪せない思い出と新しいテイクで、また煌めき出したウーター・ヘメルを繰り返し聴き直したくなります。
追記:
ジョアン・ジルベルトを偲んで。
ジョアンとカフェ・アプレミディは切っても切れない関係が僕にはあります。
たまたま、何気なしに持っていたジョアンのアルバム『Amoroso』。大学生の頃、中古レコードで入手して聴いてはいたが、気分に合わなかったのか、大人しいラウンジ的な音楽だなぁと思ってしばらく放置していた。
「Suburbia Suite」のディスクガイドを手に入れ、カフェ・アプレミディの初期のコンピCDにこのアルバムの曲「Tin Tin Por Tin Tin」が収録されていて、陽の目を見なかった我が家のライブラリーから、『Amoroso』はめでたく一軍入りしました。
聴き直しながら、入手した時の印象と随分と違った感触があったこと、大人しいラウンジ的なイメージがしっくりきたこと、何よりも橋本さんが紹介した盤の中に所持していたレコードがあったことに、自分自身が成熟したような気分になり嬉しくなりました。
ジョアン・ジルベルトさんのご冥福をお祈りいたします。
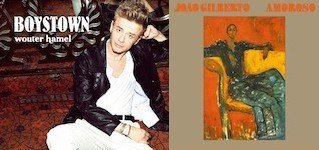
Wouter Hamel『Boystown』
Joao Gilberto『Amoroso』
三谷昌平 Shohei Mitani
「ボサ・ノヴァ」という音楽に触れたのはイギリスの二人組のユニット、エヴリシング・バット・ザ・ガールが最初だったかもしれない。ただ当時、「ボサ・ノヴァ」という音楽は高校生の僕には「大人が聴くお洒落な音楽」といった印象で、聴くには小っ恥ずかしさを感じていた。ましてその創始者と言われるジョアン・ジルベルトはあまりに王道すぎた。彼の音楽に僕がしっかりと向き合えるようになったのは、それから何年も経った大学生の頃だ。彼のイメージを大きく変えさせられた曲が「Undiu」である。名盤『Joao Gilberto』(1973年)に収録されている曲で、決して多くはない彼自身の手によるものだ。「ウンデュ~」とひたすら繰り返し歌われるその曲はある意味狂気をも感じさせ、僕をワクワクさせた。ひたすら美しい世界を構築するために努力を惜しまないアーティストの姿がそこにはあった。「Undiu」については今回、ReligoとMamao e Papaiaによるカヴァーを選曲させていただいた。
そして後半はジョアン自身の演奏を6曲立て続けに選曲させていただいたが、最後はボサ・ノヴァ第一号と言われている「Chega de Saudade(想いあふれて)」を選んだ。ジョアンの演奏は一瞬にしてその場の空気を変える。なにげなく弾き語っているようであるが、そこには緻密に計算された世界があった。まさに彼こそが「ボサ・ノヴァ」であり、多くのフォロワーを生み出したことは皆が知るところである。心より哀悼の意を捧げたい。

Religo『Religo』
Mamao e Papaia『Album do Bebe』
Joao Gilberto『Chega de Saudade』
渡辺裕介 Yusuke Watanabe
ジョアン・ジルベルト永眠。ネオ・サイケとかイギリス・インディーが棚を占領していた10代のレコード棚。雑食な友人のアパートの棚に美しい女性の絵のジャケット『Amoroso』。アコースティック・ギターにごく自然に語りかける歌声。アコースティックな世界が壮大な心地よい草原でゆったりしているような風景が目に浮かぶと、すぐに中古レコード屋に買いに行った想い出。今となっては、トミー・リピューマがプロデュースで、アレンジがクラウス・オガーマン。とか大人な表現が言えますが、10代という音楽に対して鎧のない純粋に素晴らしいと感じさせる力があった時代ならではの魅力。至急実家のレコード倉庫にてジョアンを中心に選曲させていただきました。久々Silvio Cesarの素晴らしさも再認識。同時にWalmir Borgesの最新作も素晴らしかった。

Joao Gilberto『Amoroso』
Silvio Cesar『Som E Palavras』
Walmir Borges『Melhor Momento』
Dinner-time 金曜日22:00~24:00
Cafe Apres-minuit 土曜日0:00~2:00
富永珠梨 Juri Tominaga
2019 Early Autumn Selectionのベストワンは、アルゼンチンはラプラタ市出身のコンテンポラリー・フォルクローレ男女デュオ、ワグネル・タハン・デュオの3枚目のアルバム『Dos』から「Viento (Octavio Tajan)」をセレクトしました。二人の紡ぎ出す爽やかなハーモニーと、伸びやかに響くギターのアルペジオ。どこまでも広がる早秋の澄んだ青空を、心に伸び伸びと描いてくれる傑作です。どこをとっても「素晴らしすぎる!」としか言いようのない楽曲なのですが、特に後半からラストにかけて展開される、美しくもドラマティックなピアノの旋律には思わず息をのみます。どこか懐かしさを感じさせる、メロディアスで親しみやすいサウンドも魅力のひとつです。ぜひチェックしてみてくださいね!
*******************************************************************************
ジョアン・ジルベルトへの追悼の想いを込めて。
私にとってジョアンの音楽は、幼い頃の母との思い出と繋がっています。中学生の頃、音楽好きの母から「この音楽はすごくいいから聴きなさい」と、特に何の説明もなく、ある日突然、ジョアン・ジルベルトのカセットテープ(アルバムだったのか、母の編集盤だったのかは覚えていません)を渡されました(その後、アストラッド・ジルベルトのカセットテープも同じような状況で渡されました)。生まれて初めて聴く、ポルトガル語の不思議な響きと、今にも消え入りそうな独り言みたいな小さな歌声に、最初は衝撃、というか戸惑いを感じました。「大きな声で情熱的に歌い上げるのが歌手」なのだと思い込んでいた中学生の私にとって、それはそれは物凄くショッキングな体験でした。
ミニマルに反復される美しいメロディーと、どこまでも穏やかな歌とギターのハーモニー。聴き込んでいくうちに、今まで味わったことのない甘美な心地よさと、ほのかなトランス状態がすっかりクセになってしまった私は、テープがダメになるまで、何度も繰り返し聴き続けました。それからもう一度、ジョアンの音楽を耳にするようになったのは、たぶん二十歳を過ぎた頃だったように思います。
おとなしく人見知りがちな男の子が、私にだけ心を開いて、小さな声で「ないしょのおはなし」をしてくれている……。あの頃、そんなイメージを抱きながら、ジョアンの歌声を聴いていました。そのせいなのか、今でもジョアンの歌を聴くたびに、幼い頃に出会った初恋の男の子を思い出すような、ちょっと甘酸っぱい気分になってしまいます。
「usen for Cafe Apres-midi」のセレクターとして、ジョアン・ジルベルトへの追悼の想いを込めた一曲は、1973年の『Joao Gilberto』に収録されている、幼い愛娘ベベウのために書かれた可憐なワルツ曲「Valsa」をセレクトしました。オリジナルやカヴァーも含め、幾度となくセレクトしてきた、思い入れの深い作品。聴くたびに心がふわりと温かくなる大好きな一曲です。
ジョアンさん、宝石のように美しい音楽をありがとうございました。どうぞ安らかに。

Wagner Tajan Duo『Dos』
Joao Gilberto『Joao Gilberto』
小林恭 Takashi Kobayashi
はじめての海外旅行は20歳のときに体験した真夏のインドへの旅だった。
ニューデリーの蒸し暑さと香辛料の香りと客引きで押し寄せる人の波の中でキーの高い女性が歌う歌謡曲がラジカセから大音量で聞こえてくる。忘れがたい記憶が今も蘇る。
あれから30年以上の時が経った。現在は高層ビルが立ち並び、ITバブルで桁外れの高額所得者が増え、原付タクシーのリクシャーもUberで呼べばすぐ来てくれると、一緒に旅行した友人が随分と変化した最近のインド事情を教えてくれた。
では最近の音楽事情はどうなのか? しばらく前に聞いたParekh & Singhは欧米人さながらのポップ・ミュージックを作り続けている。去年の年間ベストにも加えたGanavyaもインド出身だ。
そして今回紹介する最近出会ったLifafaは、インドの楽器や旋律とアンビエント、ハウスなどのエレクトロニック・サウンドのミックスが心地よく、ムンバイのビート・メイカーchrmsは、インドのミュージシャンかどうかわからないようなアーバン・メロウなサウンドを作り出している。インターネットの普及で世界中の様々な場所からハイブリッドなサウンドが現れている今に楽しく耳をかたむけている。
先日他界したジョアン・ジルベルトがボサノヴァをアメリカに渡って演奏していた頃はどうだったのだろうか?
ゆっくりと流れる情報の中でゆっくりと新しいハイブリッドな音楽として受け入れられた時代だったのだろう。
それから延々と様々な音楽が混じり合い、ずっと繋がっていって現在にいたっている歴史を体験していると思うと感慨深い。
きっとインドの若いミュージシャンも、知らないうちになにかしらジョアンの音楽にも触発されているのではないだろうか?
このように世界各地の音楽を聴くことができる今に感謝しながら、これからも音楽の旅の妄想を続けていきたい。

Parekh & Singh「Newbury Street」
Lifafa『Jaago』
chrms『Lover Boy』
Joao Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil & Maria Bethania『Brasil』
ヒロチカーノ hirochikano
「Izaura」と「Valsa」。
彼が創ったその神髄が聴こえると同時に、シアワセの瞬間が音に残されたこの曲を、決して文章では綴ることのできないあふれる想いと、哀悼の意を込めて、ここに捧げます。

Joao Gilberto『Joao Gilberto』
吉本宏 Hiroshi Yoshimoto
吐息の奥に晩夏の倦怠感を感じる夜。イングランド南部ドーセットの南海岸のリゾート地ボーンマスから届けられたネオ・ソウル・シンガー、ジョージー・スウィートの「Sorry」のメロウな歌が身体に沁みる。
追記:
ジョアン・ジルベルトは「'S Wonderful」歌いながら何を想うのだろう。アルバム・ジャケットに添えられた、ジョアンがその歌を弾き語りしながらヘレン・キーンの部屋で撮影されたという土井広介によるフォトグラフの表情にそのこたえを探す。彼の来日公演の演奏姿を思い出しながら。どうぞ安らかに。2019年7月。

Georgie Sweet「Stories」
Joao Gilberto『Amoroso』
高橋孝治 Koji Takahashi
今回の初秋セレクション、まず22時からのディナータイム選曲はシアトル出身のアーティスト、ピーター・ミッチェルのプロジェクト、Hibouの7月にリリースされたばかりのニュー・アルバム『Halve』から、爽やかでメランコリックな「Clarity」をオープニング・ナンバーに、アメリカ合衆国メリーランド州のボルチモアで2004年に結成されたドリーム・ポップ・バンド、ビーチ・ハウスが2015年にリリースした6枚目のアルバム『Depression Cherry』の冒頭を飾る幻想的な「Levitation」に繋げ、2019年に入ってから発見したお気に入りアーティスト、Vansireの作品は6月にリリースされた「Metamodernity」を今回はセレクト。続いてノルウェイのインディー・ポップ・バンドStrange HellosのヴォーカリストでもあるBirgitta Alidaが5月末にリリースした煌めき感のあるサンシャイン・ポップ「When I'm With You」や、ブルックリンのエレクトロ・ポップ・デュオ、チェアリフトの活動でも知られるキャロライン・ポラチェックの6月に発表された新作「Door」、3月に来日公演を行ったボストン生まれのクレア・コットリルによるプロジェクト、クレイロのリリースされたばかりのデビュー・アルバム『Immunity』より、ローファイなヴォコーダー・サウンドが心地よい「Closer To You」、そしてVansire 同様に2019年に入ってから存在を知りお気に入りアーティストとなったローズマリー・フェアウェザーの「On The Radio」など、夏から秋に移り変わるこの時期にぴったりの涼しげな女性ヴォーカルの作品を続けてみました。次にオーストラリアはシドニーで活動するジャーマンゴ・ドリーミングのタイトル通り清々しい風を感じる「Breeze」や、イギリスはマンチェスター出身のホースビーチのまもなくリリース予定のデビュー・アルバム『The Unforgiving Current』より先行シングルとして5月にリリースされた「Dreaming」、再び登場のビーチ・ハウスの「Myth」は2012年リリースの4枚目のアルバム『Bloom』からセレクトしたドリーミーなナンバー。また、ロサンゼルスのインディー・ポップ・トリオPure Midsのアコースティック・ギターの爪弾きが清涼感をもたらすニュー・シングル「Everything We Wanted」や、アメリカはペンシルヴェニア州ピッツバーグ出身のドリーム・ポップ・カルテット、Drauveのデビュー・シングル「Haunted」も初秋選曲を爽やかに彩る素敵な作品です。そしてチャンネル・ディレクターの本多くんが教えてくれた、ニューヨークはブルックリンを拠点に活動するシンガー・ソングライターTothのとびきりメロウでスウィートな「Song To Make You Fall In Love With Me」は今回のセレクションの中でも特にお気に入りのナンバーで、この作品は5月にリリースされたデビュー・アルバム『Practice Magic And Seek Professional Help When Necessary』からのセレクトです。さらにルイジアナ州ニューオーリンズを拠点に活動しているスターマン・ジュニアの、ちょっぴりけだるくダウナーなヴォーカル・スタイルが特異なヒーリング効果を生んでいる「Speed」をピックアップし、ディナータイム前半の最後にメッセージ・トゥ・ベアーズの8月にリリースされたばかりのニュー・アルバム『Constants』から静謐な響きを放つ「Small Light」を選んでディナータイム・セレクションを折り返します。
ディナータイム後半は学生時代からの友人でコンコルド・グラフィックスのデザイナーであり、最近はOWLというブランド名で超軽量の財布を中心にアウトドア関係のグッズをデザインしてネット販売している相馬章宏くんから教えてもらった、ニューヨークを拠点に活動するホーリー・ハイヴという3人組バンドによるグレイトなレイドバック・スウィート・ソウル「Oh I Miss Her So」からスタート。この作品は6月に7インチ・ヴァイナルもリリースされましたが、この7インチのB面には60年代にテキサスで活躍したチカーノ・バンド、サニー&ザ・サンライナーズの「If I Could See You Now」のカヴァーがカップリングとして収録されていますが、こんなレア曲を(1969年のシングル「Should I Take You Home」のB面!)カヴァーするとは恐ろしいセンスの持ち主です。続いて4ADから作品をリリースしているニュージーランド出身のシンガー・ソングライター、オルダス・ハーディングの4月にリリースされた通算3作目となるニュー・アルバム『Designer』よりオープニング・ナンバーの「Fixture Picture」をセレクトし、選曲に柔らかな波を作ります。そしてアメリカ出身というぐらいしか今のところ情報がつかめていないHelladustyというアーティストの5月にリリースされたデビュー・アルバム『Secret Suenos』に収録されているドリーム・シンセ・ポップ「Delete You」や、スティーリー・ダンの「Peg」の歌詞からバンド名を付けたというロンドン発の4人組バンド、ブループリント・ブルーの3月リリースのデビュー・アルバム『Tourist』のアルバム・タイトル・ソング「Tourist」でさらに心地よい揺らぎを作り出し、イギリスの4人組バンドThe Yacht Clubと混同しそうですが、こちらはライアンくんという男の子がひとりでやっているYot Clubというプロジェクトの思わず笑顔が零れる青春歌謡「Won't Take Too Long」や、イギリスはロンドンで活動するホットライン・シンドロームの最新作「Jewellers Using Karate」などの作品で、湖畔に反射する陽の光のような煌めき感を演出します。さらにアメリカはヴァージニア州シャーロッツヴィルのアーティスト、Kate Bollingerの6月リリースのニュー・アルバム『I Don't Wanna Lose』よりセレクトしたアンニュイなフランス語の響きがメロウに揺れる「Je Rverai A Toi」や、アンニュイさではKate Bollingerに少しも引けを取らないモデル/写真家としても活動するハンナ・コーエンの4月リリースの3枚目のアルバム『Welcome Home』からシングル・カットされた「This Is Your Life」、コケティッシュなウィスパリング・ロリータ・ヴォイスが魅力のサンフランシスコのアーティスト、ララの「Dizzy」などの可憐で妖艶な魅力の作品もピックアップ。そして艶めかしい雰囲気の後にオーストラリアはブリスベン出身のJyeの6月にリリースされたニュー・アルバム『Piccadilly Perfume』収録のサイケデッリクなまどろみに包まれる「Hard to Fall」と、DinaとFaroの男女二人組によるJadu Heartなるユニットの8月にラフ・トレードからリリースされたニュー・アルバム『Melt Away』より先行シングルとしてリリースされた「Wanderlife」をセレクトすることで、さらに落ち着いた雰囲気を作ります。その後ブループリント・ブルーの「Roll On」や、ホーリー・ハイヴのヴィブラフォンの響きもクールな「This Is My Story」、イントロがスリー・ ディグリーズの「天使のささやき」を彷彿とさせるThe Harmaleighsの「Don't Panic」など、ソウル・フィーリング溢れる作品を続けてディナータイムのクライマックスを迎えます。そして最後にスフィアン・スティーヴンスの新作「With My Whole Heart」をピックアップしてディナータイムはフェイドアウトしていきます。
24時からのミッドナイト・スペシャルは「華麗なるアレンジの世界」と題して流麗なストリングスを配した作品や、ゴージャスなホーン・セクションを聴かせる作品、はたまた清楚な室内管弦的アレンジを施した作品を集めて構成してみました。まずはこの特集の骨格であり鍵となる作品としてピックアップしたのが、ピチカート・ファイヴが1987年にリリースした生のストリングスやブラスを贅沢に使用し発表された記念すべきファースト・アルバム『Couples』から、ヴォーカル・トラックを抜いたカラオケ盤として1995年にリリースされた『A Quiet Couple』です。この作品に収められたいくつかの楽曲をこの特集の要所要所にセレクトしながら今回の特集をお届けします。まずはこのアルバムから、ソフト・ロックの名曲で、フリッパーズ・ギターも名曲「Goodbye, Our Pastels Badges」で引用していたロジャー・ニコルス&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ「Love So Fine」の印象的なドラム・プレイのイントロをモティーフにした「そして今でも(What Now Our Love)」をイントロダクションに、ペイル・ファウンテンズがデビュー曲である「Just A Girl」を1985年にロビン・ミラーのプロデュースによってゴージャスなストリングスやコーラスを加えて煌びやかに再構築した作品に繋げました。この作品はペイル・ファウンテンズの最後のシングルとなった「... From Across The Kitchen Table」の限定でリリースされた7インチ2枚組ヴァイナルに収録されたのが初出ですが、このレコードがリリースされた当時、この情報を知ってダメもとで名古屋は大須にあった自分の青春時代においてとても重要な存在である「円盤屋」というレコード・ショップに注文して、数日後に入荷の電話をもらったときの身が震えるほどの感動は今でもしっかり覚えています(笑)。話はちょっと脱線しますが、ロビン・ミラーが1974年当時義理の兄弟だった元ローリング・ストーンズのギタリスト、ミック・テイラーと共に、ニッキー・ホプキンスやビリー・プレストン、ボビー・キーズなどの名うてのセッション・ミュージシャンを起用して制作したにもかかわらず、ミック・テイラーのストーンズ脱退に伴いレコード会社のアトランティックが本作のお蔵入りを決定してしまい、以来幻のアルバムと呼ばれていた『Cat’s Eye』が、久しぶりにロビン・ミラーのことを考えていたこのタイミングで、オランダのApcor Books And Recordsというレーベルからリリースされたのにはびっくりしました。LPは300枚、CD(ボーナス・トラック入り)は500枚限定ということなので、興味のある方、そしてローリング・ストーンズのファンの方は急いで手に入れてください(笑)。続いてエヴリシング・バット・ザ・ガールが1986年にマイク・ヘッジスを共同プロデューサーに迎え、荘厳なるオーケストレイションを施し制作された「ねえ君、星がきれいに輝いているよ」との意味を持つタイトルもロマンティックな『Baby, The Stars Shine Bright』から「A Country Mile」をセレクト。ライドのギタリストであり、元オアシスのベーシストであるアンディー・ベルの元奥さんでスウェーデン出身の女性アーティスト、イーダの1997年リリースのノスタルジックで黄昏感のあるストリングスの響きが美しい「Sorry Sorry」から、こちらもスウェーデン出身のシンガー・ソングライター、デヴィッド・パグマーによるユニットMontt Mardieが2007年にリリースした、ストリングスや高らかに鳴らされたトランペット、そして楽しく転げまわるクラリネットの響きが楽しい「Set Sail Tomorrow」をピックアップ。さらにスウェーデンのヨーテボリで結成された、セルジュ・ゲンスブールの「Les Sambassadeurs」という作品からバンド名を取ったサンバサダーが2010年にリリースしたサード・アルバム『European』もこの特集にぴったりのゴージャスなオーケストラ・アレンジが全編にわたって施されている作品です。正直いわゆるスウェディッシュ・ポップといわれる作品の多くは自分の好みから外れるものが多いのですが、この作品は壮大なるオーケストラ・アレンジが素晴らしく、全編を通して大好きな作品となりました。そこでこの作品から数曲を今回の特集に選んでいるのですが、まずは柔らかなピアノの旋律から徐々にストリングスの響きが重なり盛り上がっていく「Stranded」をセレクト。その後にアレンジの魅力といえば忘れてはいけないプリファブ・スプラウトの作品の中で、特に生のオーケストレイション・アレンジの美しさが爆発している「Hey Manhattan! (JFK Version)」に続けました。そして自分の中ではパディー・マクアルーンと同様に敬愛しているアーティスト、ティム・フリードマン率いるフレイザー・コーラスの作品でピックアップした「Typical」もまた、フルートやクラリネットに絡むヴィブラフォンの響きの美しさに感動を覚えます。徐々に選曲の流れが盛り上がってきたところで、またサンバサダーの『European』より、アルバム中一番の盛り上がりをみせるアップテンポなナンバーの「Days」をピックアップ。そしてこの特集前半の盛り上がりの頂点に選んだ作品がペイル・ファウンテンズの「Thank You」です。この番組のリスナーの皆様には言わずもがなな作品ですが、先に挙げた1985年版「Just A Girl」同様にこの作品もロビン・ミラーがプロデュースを担当した作品ですね。シャーデーやエヴリシング・バット・ザ・ガールが彼のプロデューサー・ワークとしての代表作として語られることが多いのですが、自分にとってロビン・ミラーの代表作といえばこの作品につきます。そして多幸感という言葉がありますが、自分的にはその言葉がぴったりと当てはまるのがこの作品だと思っています。ここでペイル・ファウンテンズの思い出話をもうひとつしますと、この1982年にリリースされたレコードを手に入れたのは1983年の高校1年のときで、名古屋の地下街にある「音楽堂」というお店で購入しました。新星堂のシリウス・コレクションの1枚としてリリースされていた「Just A Girl」に感動して、「アコースティック」というキーワードを明確に意識するようになり、次はどんなサウンドを聴かせてくれるのだろうかと期待を膨らませてこの「Thank You」の12インチ・ヴァイナルを購入したのですが、その日はとても天気のよい日曜日で、昼すぎにレコードを抱えて帰宅すると家には誰もいなく、これはラッキーと思い居間に置いてあるステレオにレコードをセットして大音量でこのレコードをかけたのです。するとスピーカーから流れてきたのは、荘厳なオーケストラル・ポップで、眩しいほどの陽の光が射し込む部屋の中で、流れてくる音楽とその環境がぴったりマッチしていたこともあり、とても感動して立て続けに3回連続でこの曲を聴いた思い出は一生忘れないと思います(マイク・オールドフィールドの「Moonlight Shadow」を初めて聴いて感動したときも同じような状況でした・笑)。そしてここでまたピチカート・ファイヴの作品から涼しげな「七時のニュース (Seven O'Clock News)」をインタールードで挟み一旦クールダウン。以降はベル&セバスチャンのラフ・トレードに移籍する前のJeepster Recordings期のラスト・シングルとして美しいストリングスを配して2001年にリリースされた「I'm Waking Up To Us」や、またしても登場のイーダによるワルツのリズムに美しいオーケストラが絡む秋の詩「Sweet September Rain」、テリー・ホールがカラーフィールド解散後に結成したテリー・ブレア&アヌーシュカのファースト・シングル「Missing」、前回の「Back To 90s」特集でも取り上げたファズボックスのお色気SF映画『バーバレラ』の主題歌カヴァー・ソングなどをセレクトし、ミッドナイト・スペシャルの前半最後には折り返しのインタールードとしてピチカート・ファイヴの『A Quiet Couple』からジョン・セバスチャンの名曲カヴァーである「Magical Connection」をピックアップして後半に続きます。
後半はフレイザー・コーラスのデビュー曲である「Sloppy Heart」の再録アルバム・ヴァージョンとプリファブ・スプラウトの「A Prisoner Of The Past」からスタート。前者で聴かれるオーボエを吹いているのがドリーム・アカデミーのケイト・セント・ジョンで、フルートを吹いているのがクリエイション・レコードのボスであるアラン・マッギーの奥さんのケイト・ホルムズっていうのは豆知識。後者はパディー・マクアルーンによるセルフ・プロデュース作品ですが、見事なまでにトーマス・ドルビーと共に作り上げてきた世界をパディーひとりの力で表現しています。しかしそこまでの道のりにはトーマス・ドルビーからの奨励やアドヴァイスが多分にあったらしく、ライナーノーツにはその感謝が綴られていますね。そして正規では1989年の『Shoebox Full Of Secrets』というアルバム1枚しかリリースされていませんが(なんとつい先ごろ90年代終わりにリリース予定だった幻のセカンド・アルバム『Low Beat Folk』が日本限定で世界初CD化されました)、いまだに日本で根強い人気を誇るアンディー・ポーラックの「Forever」も控えめながら美しいオーケストレイションが聴ける作品です。ここで豆知識をもうひとつご紹介しておきますと、先のプリファブ・スプラウトの「A Prisoner Of The Past」に参加していたファティマ・マンションズのNick Bagnallはアンディー・ポーラックの作品でもベースを担当しているのです。続くスーパートランプの「Lord Is It Mine」も中盤からの盛り上がりを彩るオルガンやオーボエの響きが美しい大好きな作品です。以前この作品を取り上げたときにも書きましたが、この作品は1979年にグループが放ったメガヒット・アルバム『Breakfast In America』に収録されたもので、リリース当時小学6年生だった自分はシングル盤で購入した「Breakfast In America」のB面曲としてこの作品を知りました。そして感動のあまり音楽の授業でこのレコードをかけてもらったのですが、洋楽に馴れていなかった当時の名古屋の小学生にドン引きされてショックを受けた悲しい思い出の作品でもあります(笑)。続くコーギスの「とどかぬ想い」との邦題で日本盤シングルもリリースされていた「If I Had You」は、音楽の嗜好がはっきりとネオアコというものにロックオンされた高校2年のときに初めて出会いました。それは毎週のように通っていた名古屋のウッドストックで進められて購入したベスト盤(ジャケットはUK版の「If I Had You」のシングルと同じ絵柄というのも好ポイント)にこの作品が収録されていたからなのですが、ベスト盤の中で一番アコースティックな響きを持った作品だったので、試聴させてもらった瞬間から大好きになりました。そしてアナログ不遇の1996年リリースのため、ヴァイナルが今では高値で取り引きされているビューティフル・サウスの『Blue Is The Colour』に収録されている、室内管弦楽のようなシンプルなストリングス・アレンジが上品で美しい「Little Blue」から、エヴリシング・バット・ザ・ガールの「Cross My Heart」に繋げました。この華やかな作品も『Baby, The Stars Shine Bright』から選んだものですが、エヴリシング・バット・ザ・ガールといえば最近出版され、小山田圭吾くんが「英国音楽」という言葉を使って推薦帯を書いたことだけでも感動してしまったトレイシー・ソーンの自伝『安アパートのディスコクイーン』はとても読み応えのあるものでしたね。性格的に重箱の隅をつつくのが好きな人間なので、興味深い話が次から次に語られるこの本には圧倒されました。次に選んだニック・ヘイワードの「When It Started To Begin」はまさに「華麗なるアレンジの世界」という言葉が当てはまる作品で、勢いよく鳴らされるドラムのイントロ、高鳴るホーン、転がるピアノ、楽しそうにリズムを刻むパーカッション、作品を華やかに彩る女声コーラス等が見事に調和し、心が躍るという言葉がぴったりの作品です。そしてこの作品ととても相性のよい作品が、ピチカート・ファイヴの「おかしな恋人・その他の恋人(Odd Couple And The Others)」で、この2作品を繋げることでとても気持ちのよい流れができたと思います。その流れに続くのが前半でも取り上げたJeepster Recordings期のベル&セバスチャンの『Fold Your Hands Child, You Walk Like A Peasant』に収録されていたハープシコードに絡む流麗なストリングスが美しい「The Model」。ゴー・ビトウィーンズの作品からはこちらも賑やかなストリングスの流れが作品を華やかに彩る1987年の「Right Here」をピックアップ。この作品にキング・オブ・ルクセンブルグ名義でサイモン・フィッシャー・ターナーがバッキング・ヴォーカルで参加しているのはこれまた豆知識。そして三度目の登場となるサンバサダーの「Sandy Dunes」は、次にセレクトしたヴァネッサ・パラディのレニー・クラヴィッツがプロデュースしてヒットした1992年のシングル「Be My Baby」との相性が抜群で、ミッドナイト・スペシャル後半のクライマックスとなっています。そして大好きなルーファス・ウェインライトの個人的には一番好きなアルバム『Want』より、至福の時とドラマティックな感動が溢れる「I Don't Know What It Is」をセレクトして、今回の特集のフィナーレを迎えます。エンディングには7/6に亡くなられたジョアン・ジルベルトに捧げる1曲を選んでほしいとの橋本さんからのリクエストがあったので、この特集にもふさわしいトミー・リピューマの繊細なプロデュースと、全編にわたるクラウス・オガーマンによる壮大なアレンジが素晴らしい1977年リリースの『Amoroso』より「Triste」をセレクトしてみました。
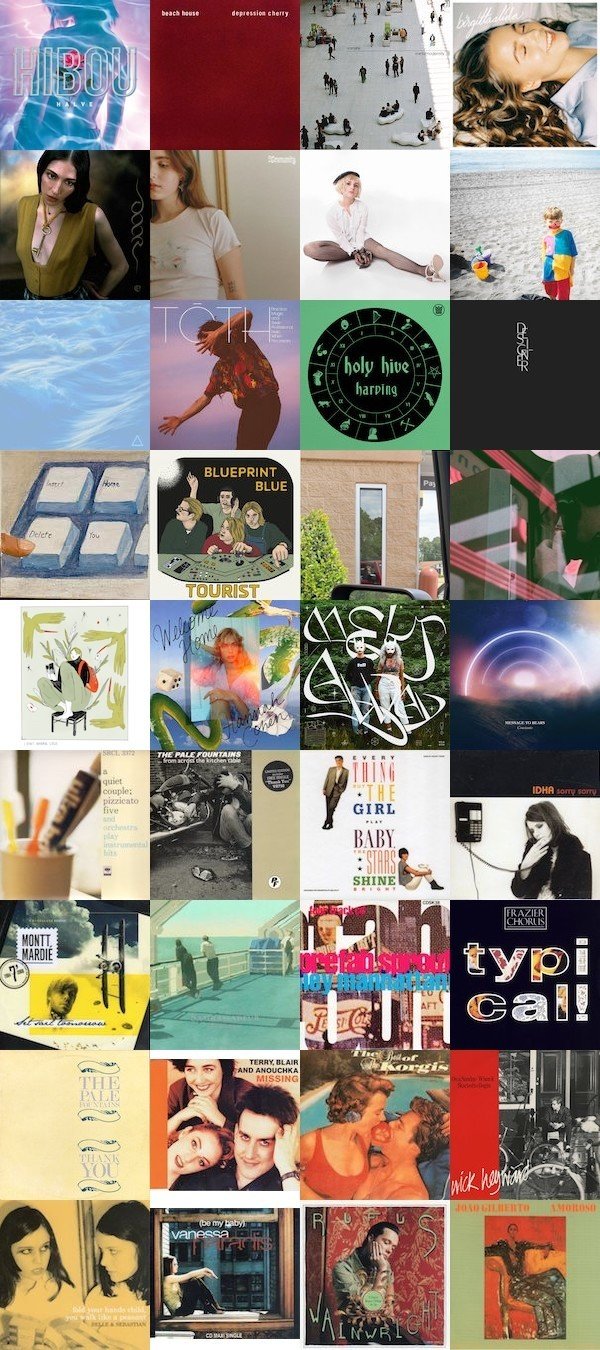
Hibou『Halve』
Beach House『Depression Cherry』
Vansire「Metamodernity」
Birgitta Alida「When I'm With You」
Caroline Polachek「Door」
Clairo『Immunity』
Rosemary Fairweather「On The Radio」
Horsebeach「Dreaming」
Pure Mids「Everything We Wanted」
Toth『Practice Magic And Seek Professional Help When Necessary』
Holy Hive『Harping』
Aldous Harding『Designer』
Helladusty「Delete You」
Blueprint Blue『Tourist』
Yot Club「Won't Take Too Long」
Hotline Syndrome「Jewellers Using Karate」
Kate Bollinger『I Don’t Wanna Lose』
Hannah Cohen『Welcome Home』
Jadu Heart『Melt Away』
Message To Bears『Constants』
Pizzicato Five『A Quiet Couple』
The Pale Fountains「... From Across The Kitchen Table」
Everything But The Girl『Baby, The Stars Shine Bright』
Idha「Sorry Sorry」
Montt Mardie「Set Sail Tomorrow」
Sambassadeur『European』
Prefab Sprout「Hey Manhattan!」
Frazier Chorus「Typical」
The Pale Fountains「Thank You」
Terry, Blair & Anouchka「Missing」
The Korgis『The Best Of The Korgis』
Nick Heyward「On A Sunday / When It Started To Begin」
Belle & Sebastian『Fold Your Hands Child, You Walk Like A Peasant』
Vanessa Paradis「Be My Baby」
Rufus Wainwright「I Don't Know What It Is」
Joao Gilberto『Amoroso』
Dinner-time 日曜日22:00~24:00
Cafe Apres-minuit 月曜日0:00~2:00
山本勇樹 Yuuki Yamamoto
7月の上旬、突然ジョアン・ジルベルトの訃報が届き、しばらくはぽっかり心に穴が空いた気分でしたが、今は穏やかな気分で、彼の音楽に触れています。彼の音楽がもたらしてくれた大きな幸せと、多くの思い出が、自分の宝物です。このアーリー・オータムの選曲は、そんな気持ちも反映されて、全体的に優しくあたたかな雰囲気に仕上がったと思います。冒頭には、ギタリストのコンハード・パウリーノによる「Isaura」のカヴァーを選び、最後はジョアンの「Wave」を置いてみました。僕にとって、「Wave」はやはりこのヴァージョン。クラウス・オガーマンの美しいストリング・アレンジも格別です。何度聴いても心が震えます。秋のはじめに、テラスでお茶を飲みながら、BGMで流れてきたら、どんなに素敵なことでしょう。ジョアンの音楽が、これからもずっと、「usen for Cafe Apres-midi」で流れることを願って。

Joao Gilberto『Amoroso』
Lunch-time~Tea-time 月曜日12:00~16:00
武田誠 Makoto Takeda
ジョアン・ジルベルトの音楽とのはじめての出会いというのは、当時新品で買った『三月の水』の日本盤レコードでした。MP規格のポリドール盤。音楽系の学校に通い始めた10代後半の頃。廉価盤だからかなのか盤の厚みがやけに薄く、部屋のライトに近付けると、盤越しにその灯りが見えるようなレコード。本当のことを言えば、自分から率先してそのレコードを買った訳ではありません。耳にしたことのない音楽をもっと聴いてみたい、そう思っていた若かった僕に、その頃新宿のレコード店で働いていた尊敬する先輩が作ってくれたミックステープにジョアンの「三月の水」と「ウンデュー」が入っていたのです。ミニマルなパーカッション・パートとガット・ギターのモダンな響き、囁き声のような歌、そして密室的な音像。それは、そのときとても好きだったチェリー・レッドやクレプスキュールのレコードにもどこか繋がるような内省的で静謐でインテリジェントな佇まいを感じさせながらも、今までの音楽経験の文脈を越えた南米の詩情豊かな響きにあふれ、訳もわからず引き込まれていました。そしてそのままレコードを入手。だから、後にこれが“ボサノヴァ”というブラジル音楽の中のジャンルのひとつ、と知らされたときも、この確立された美しい音の世界から抜け出すことができず、ロンドンのクラブ・シーンから花開くブラジル音楽のブームが押し寄せる90年代までは、ジョアンのこれと、サイモン・ハルフォンがスリーヴ・デザインを手がけたアストラッド・ジルベルトのベスト盤、あとピエール・バルーが奏でた音楽だけが、僕にとっての“ボサノヴァ”のすべて、だったのです。
その夢見のような音楽でその存在感を強く印象づけた偉大な音楽家。人生観を変えてしまうような音楽との出会いをきっといつまでも新しいリスナーにもたらしていくことでしょう。

Joao Gilberto『Joao Gilberto』
Lunch-time~Tea-time 火曜日12:00~16:00
waltzanova
不特定多数の方が耳にする「usen for Cafe Apres-midi」の選曲というのは、アノニマスな匿名性と記名性の間でのバランスを取る作業だと思います。これまでの僕はセレクターであるという事実の方に意識が行っていて、記名性の側に振れていた気がします。今回も決して匿名的なセレクションになってはいないのですが、「usen for Cafe Apres-midi」としてどう聴こえるのか? ということを考えながら選曲に臨みました。
オープニング・クラシックはジョージ・ガーシュウィンの「Lullaby」でスタート。弦の穏やかな響きが夏の疲れを癒してくれるようでもあり、少し早い秋を連れてきたかのようでもあります。続いてはレオナルド・マルケスの『Early Bird』からのソフト・サイケデリックなボサノヴァ・ナンバーを。リリースされたのは昨年の秋以降だったので、ちょうどアナログ化のタイミングでこの時期にピックアップできて嬉しい限りです。CTIへのオマージュのようなジャケットも素敵ですね。「dublab.jp suburbia radio」でも選曲されていたKainaluの『Lotus Gate』も良作でした。夏が終わっていくメロウなムードが“Early Autumn”にぴったりだと思っています。カフェ・アプレミディのアグスティン・ペレイラ・ルセナ追悼イヴェントで選曲もされていた武田吉晴さんの『Aspiration』も素晴らしいアルバムでした。アルゼンチン・ネオ・フォルクローレやポスト・クラシカルを感じさせるサウンドはとても映像的。遠い昔のことが自然と思い出されるようです。今回は美しいワルツ・ナンバー「Allayer」をセレクトしましたが、アルバム全体を通じて名品揃いなので、「usen for Cafe Apres-midi」のファンの方には強く推薦しておきます。
僕の周囲の音楽好きの間でちょっとした話題を呼んだフィリップ・ベイリーの『Love Will Find A Way』。脇をロバート・グラスパーやデリック・ホッジら現代ジャズ界のキーパーソンたちが固めていますが、いわゆる話題性だけの起用でないことは彼らの今までの仕事を振り返れば一聴瞭然。逆に言えば、フィリップ御大のミュージシャンシップの高さを裏づけるものと言えるでしょう。僕と同じか少し上の世代の人は、どうしても「Easy Lover」の人というイメージが先に来てしまうのではと思いますが(僕は「宇宙のファンタジー」のMVでクルクル回っている彼の姿が脳裏に浮かんでしまいます・笑)、良い意味で予想を裏切られる快作です。カーティス・メイフィールドやインプレッションズ、トーキング・ヘッズなど、選曲にもメッセージ性が。僕はこの作品を機にEW&Fの『Spirit』を聴き直し、フィリップ・ベイリーのファルセット(中でもタイトル曲は絶品です)と、制作中に急死したチャールズ・ステップニーに捧げられたというこのアルバムの素晴らしさに改めて気づかされました。チャールズ・ステップニーつながりということで書いておくと、ライアン・ポーター新作からのロータリー・コネクション〜ミニー・リパートンのカヴァー「Memory Band」もこの季節にぴったりの出来でしたね。
追悼コーナーに行きましょう。6月に亡くなったドクター・ジョンことマック・レベナック。いわゆるニューオーリンズR&Bを世に広く知らしめたアーティストです。僕はオリジナル・ラヴの「フィエスタ」や佐野元春の「インディヴィジュアリスト」でセカンド・ラインというリズムを知ったのですが、それをたどるとドクター・ジョンのルーツであるニューオーリンズに行き着くことを知りました。『風の歌を聴け』リリース時、某雑誌で田島貴男が木暮晋也と自らの音楽的ルーツをたどりながら行った対談で『Gumbo』も挙げられており、当時一緒に音楽を掘り下げていた友人とこのアルバムを聴いて興奮したのを覚えています。ここではブルージー&オールド・タイミーな「So Long」をウィリー・ネルソンの「Moonlight In Vermont」などと組み合わせ、ラスト前の時間帯としてみました。
最後は七夕の朝に訃報が飛び込んできたジョアン・ジルベルトの追悼です。「今回のセレクションの最後にジョアンの曲を置いてほしい」という依頼が来て、最初は愛聴盤である白盤の「Valsa」で迷わず決まりかと思っていたのですが、最後に「Aquarela Do Brasil」に差し替えました。というのも、僕にとってのジョアン初体験がこの曲だったからです。高校1年生のときに10年ぶりのジョアンのニュー・アルバムが出て、紹介記事が雑誌に載っていました。それを読むと「ジョアンはボサノヴァの法王である」と書かれていました。「法王」の意味はいまいちピンと来なかったのですが、とりあえず「スゴイ人なんだ!」ということは頭に刷り込まれました。そんなある日、学校帰りにガールフレンドとCDレンタルショップへ行くと、なんとジョアンの件のアルバムが並んでいました。『Joao』ともう一枚、同時再発された『Brasil』です。ガールフレンドは気になっている僕を見て、「私、このお店の会員だから借りてあげようか?」と言ってくれたのです。『Joao』と『Brasil』か迷いに迷ったあげく、僕は『Brasil』を借りてもらいました。数日後受け取ったカセットテープを聴くと、それまで聴いてきたどれとも違う音楽がありました。その魔力に取り憑かれたのは言うまでもありません。奇跡の初来日公演も素晴らしいものでしたが、このときの感激に勝るものはありません。そしてジョアンの音楽の魂は、あのつぶやくようなヴォーカルはもちろん、何よりも自身が発明したバチーダということが感じられる曲でもあります。天国で心のままに永遠に続くバチーダを奏でてください。僕のヒーローでもあるブラジルの英雄、アイルトン・セナもきっと聴いていることでしょう。
「これらよりも良いものを挙げるならば、もはや沈黙しかない。そして沈黙をも凌駕するものがあるとしたら、それはジョアンだけだ」──カエターノ・ヴェローゾ
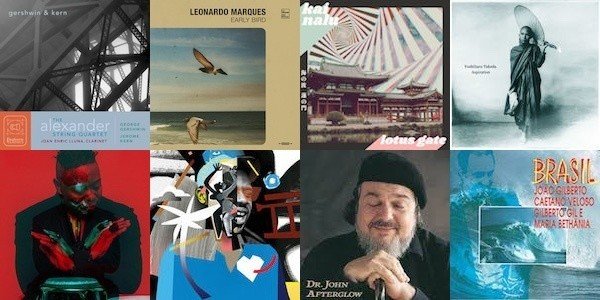
The Alexander String Quartet, Johan Enric Lluna『Gershwin & Kern』
Leonardo Marques『Early Bird』
Kainalu『Lotus Gate』
Philip Bailey『Love Will Find A Way』
Yoshiharu Takeda『Aspiration』
Ryan Porter『Force For Good』
Dr. John『Afterglow』
Joao Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil & Maria Bethania『Brasil』
