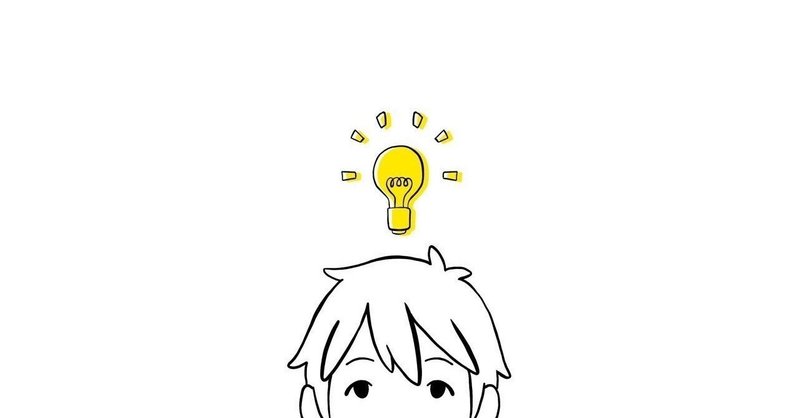
菩提まで、間もなく
わたしは言葉が好きだ。
小説やポスター、街ゆく人の会話など日常の中でも、時々好きな言葉を見つけては面白がっている。
それが例えば看板の文字なら、共に行く人の腕を軽くたたいて一緒に見てもらう時もあれば、ひとり目もとを緩めている時もある。
言葉といえば、最近読みかけの「菩提樹荘の殺人」という小説の題字をお風呂で思い出そうとしている時、空をかく人さし指は「菩薩」の文字ばかり繰り返していて、
手で文字を書くことが少なくなると言葉(漢字)も忘れてしまう、とはこういうことなのかなあ、と思ったりした。
この小説は有栖川有栖氏の作品で、この方の作品は、比較的読みやすいものが多い気がする。
(わたしが読んでいる作品は火村シリーズばかりのため、全てにおいてそうとは限らない)(だってバディものが好きだから)
その理由はなぜだろう、と考えた時、海外の児童文学に似ているからではないかと思い至った。
わたしがよく読んだ海外の児童文学では、地の文が主人公の一人称視点で、くだけた口調で話が進み、内省や注釈などがよく挟まってくる(例えば2行前とかこの文みたいに)(そしてカッコは全角!)。
この方の作品はそこまでくだけた文体ではないが、推理小説家アリスの視点で話が進んでいく。
だから、小説では読みやすいものが今のマイブームなのかもしれない、と思うのだ。文章を読むのには体力が要るが、文字を追うのはやめられない。
たっぷり体力をたくわえて、難解な2段組にこれから挑戦するのもきっと楽しい。
ところで、話し言葉については若干趣が異なる。
最近、最寄り駅のほど近くで2人乗りをしていたカップル?の会話が偶然耳に入ってきた。
(公道での2人乗りの是非と、盗み聞きのそしり、両方ひとまず横に置いておこう)
ペダルを漕ぐ方が「行くよ!」と声をかけると、
後ろに座る方が、笑いながら「このままだと間もなく
(自転車から)落ちそう」と話していた。
普段の会話の中に、「間もなく」という文語的な表現が混ざることで、物語の一節のように感じられた。
小説では、難しい言葉が使われがちだと思っているところに読みやすい言い回しで意外に感じ、
会話では、文語的な言葉が普段の会話でなにげなく使うものとして混ぜ込まれていることが、少し意表を突くような珍しい感触があって、おもしろみになったのだと思う。
良い意味で「ちぐはぐ」が面白い、と感じるこの感情は「ギャップ萌え」に入るといえるのだろうか。
自分の気持ち、好みを完全に理解するさとりの境地までは程遠い。
もし、いつかその菩提の地にたどり着くことがあるとするなら、
その時まで面白い、楽しいと感じることをゆっくり探していきたいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
