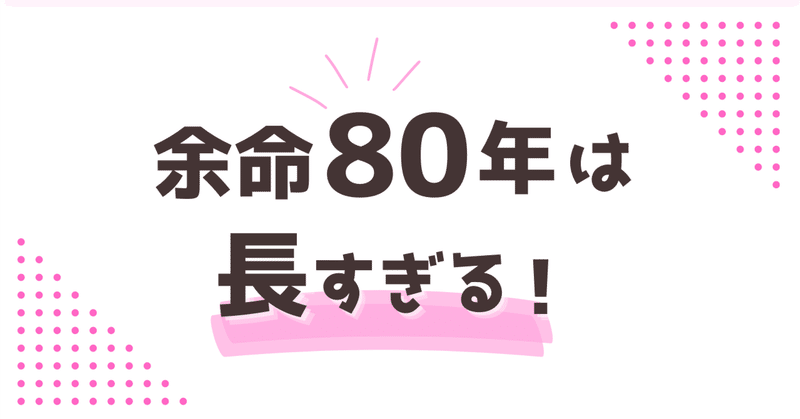
余命80年は長すぎる! 第1話
<あらすじ>
高校二年生の池原隼斗は、学校の帰り道バイクにはねられて病院に運ばれる。
病室で目を覚ましたら、かたわらには黒い姿のあきらかにこの世の存在ではなさそうな者が立っていた。そいつはゆっくりと顔を近づけてくると不気味な声で囁いた。
「お前は、これから80年後に死ぬ……」
こいつ死神!? ってゆーか80年後って、長くね!?
余命80年の宣告を受けた俺は、それからたびたび死神に出くわすことになってしまい……。
虫も、猫も、犬も、人間も。
命あるものはみんな、やがて死ぬときが訪れる。
そんなのはもちろん知ってるけれど、実感があるかっていうとそれは別だ。
高校二年生。健康で、たぶんちょっと顔が良くて、頭も良くて、全然快適に人生を送っているいまの俺なんかには、本当にそんな日が自分に訪れるなんてピンとくる話じゃない。目標とか強い意志とか覚悟とかそんなのがなくたって、たぶん俺らは普通に生きていける。今日も明日もその次も、なんかずーっとこんな毎日が続くんだろうなぁって、疑いもなく思ってる。
あのときまでは、そう、思ってたんだ。
学校の帰り道、前方から猛スピードで走ってきたバイクに、突っ込まれるまでは。
死ぬときって走馬灯を見るっていうだろ? あれホントだなって、思ったよね。走ってくるバイクがさ、なんでか俺のほうに向かって来て、嘘だろぶつかるって思った瞬間、やけにスローモーションになってさ、さっきのテストとか、父さんの顔とか、母さんの顔とかが浮かんでくるんだよ。
あぁ死ぬときってこうなんだ。
ってことは俺、死ぬんだな。
ぶつかって飛ばされる一瞬の間にそこまで考えれるんだから、走馬灯ってマジなんだよ。死ぬときに知っても、もうしょうがないけどな。
俺はおぼろげな意識の中で、かすかにサイレンの音を聞いた気がした。
目が覚めたら遠くに天井が見えた。視界の隅に揺らめく白いカーテンを見れば、病室らしい。
あれ? 生きてる?
どうやら俺は生きている。走馬灯、見た気がしたけど。と思って目を横に向けたら思わずギョッとした。黒いものがそこにいた。
人の形をしていた。等身は人間のそれっぽいし、目鼻もある。けれど身体がどうも灰色がかった色味をしていて人間ではない。たぶんちょっと透けてもいる。
うーん、これは死神ってやつじゃないか。
と俺の漫画で培われた知識が告げている。つまりそうゆう見た目の奴が俺のベッドの脇に立っていた。
俺は死んだのか死んでないのか果たしてこれから死ぬのか。判断に迷っていると、そいつはゆっくりと俺に近づいてきた。近づくにつれ寒気のようなゾロゾロとした空気が襲ってくる。そいつは俺の耳の近くまで顔(らしきもの)を寄せ、不気味に囁いた。
「お前は、これから80年後に死ぬ……」
……ん?
それだけを告げるとその黒いものはすーっと消えていった。
……80年後って言った? いまじゃなくて? は、はちじゅうねん後? 長くね? それいま言う必要あった??
めっちゃ長生きじゃんー。と思って俺は静かに目を閉じた。
再び眠りから覚めたときは親やら担任やら警察やらがやってきていて大騒ぎだった。どうやらバイクで轢かれた俺は救急車で搬送されたものの、特に命に別状もなければ大きな怪我もなく、いくつかの検査の後、翌日には退院できた。俺も拍子抜けだったし、なんなら医者も驚いていた。バイクに乗っていた男性のほうがよっぽど大けがを負ったらしい。
一日ぶりに自分の部屋に帰ると、そこにあの黒いやつがいた。
「!?」
夢だったかも、とちょっと思いつつあったのに普通にいる。普通に俺の部屋に来ちゃってる。
「お前なに!? やっぱ死神?」
そいつは黙っている。でも顔が俺のほうを向いているのはわかる。
「人間じゃあ、ないよな? さすがに」
「……」
「え、なに? 喋んない系?」
「……」
「俺が80年後に死ぬとか言ってたけど、気のせい?」
「……イヤ、それは本当」
いや、喋るんかーい! そしてそこはホントなのかい! 俺はため息をついた。正直ちょっと気も抜けた。
「あのさ、言ったら悪いけど普通こうゆう死神っぽいやつってもっとこう『お前もう死んでるぞ』とか『明日死ぬ』とか言うもんじゃない? そんでなんらかの命をかけた取引とか始まったりするかんじじゃない? 80年後に死ぬって言われてもさ、俺ってすっごい長生きだね☆ って感想しかないんだけど」
「……」
今度はだんまりかよ! 都合が悪くなるとだんまりするのは死神界でも常套手段なんですか? でも黒いやつがちょっと項垂れているように見えてきてなんか可哀そうになってきた。
「いや、俺別に死にたいわけじゃないからさ、いいんだよ、長生きでも」
「……」
「でも意味不明じゃん? なんでいま言うの?」
「……」
「てゆうかなんでここにいるの?」
「……」
「なにがしたいの?」
「……」
「隼斗ー? どうかしたのー?」という母さんの声がドアの向うから聞こえてきたので振りかえって「なんでもない」と即座に答えた。そして黒いやつのほうを向くと、そこには何もいなかった。消えている。
結局俺は長寿を告げられただけで、何もわからないままだった。
いまから80年後。いま俺は十七歳だから、九十七ってことかぁ。
特にたいした怪我もないからいつもどおり登校できた学校の教室で、俺は単純な算数の計算をしていた。「隼斗事故ったんだって? 大丈夫なん?」と言われるのに「よゆーよゆー」と返しながらも物思いに更ける。
すげーじじいになるじゃん。いま死ぬつもりもないけれど、かといってそんなに長生きする自分を想像してたわけでもない。不思議なもんだ。
ってゆうか、あの黒いのは本当になにがしたいんだ?
そのとき、ふと視界の端に黒いものが目に入った気がした。廊下のむこうに消えて言った気がする。俺は教室を出て消えた気配を探った。
階段のそばまで来たときあのゾロゾロとした感覚がして「いる」と感じた。階段の下をのぞけば、教員の古川優子が立っていた。古川の怯えた目線の先にはあの黒いものがいた。
見た瞬間「あいつだ!」と思ったが、よく見ると種類は同じだが微妙に違う個体だというのがわかる。死神はひとりじゃないという情報を頭にメモした。気づかれないように聞き耳を立てていると、死神らしき声が聞こえてきた。
「お前は、これから一週間後に死ぬ……」
古川がちいさくヒャッと声を立てた。俺もヒャッという気持ちで聞く。
すごく死神っぽい……! という第一印象を抱いてしまうのは、ここ数日の自分の実体験からすればしかたがないことだと思いたい。それにしても自分の他にも余命宣告を受ける人間がいて、しかもそれが俺の学校の教員だと思うと、死神の存在ってけっこうカジュアルなものだったのかと疑う。古川に行われた余命宣告は、まったくもってカジュアルな内容ではなかったけれど。
やがて黒いものはスッと姿を消し、同時にゾロゾロとした悪寒も消えた。古川は青ざめたまま呆然としている。
さて、これはどうしたものか。
古川はその日、受け持っている国語の授業のあいだ中、元気がなかった。それはそうだよな、と俺はひとりで納得していた。たぶんアレをどう判断すべきか迷っているんだろう。信じるのか信じないのか。俺もまだ、よくわからない。
古川優子はたしか三十そこそこくらいの年齢の国語教師だ。いつも黒髪を一つに結んでいて化粧っけはそんなにない。たぶん中学とかからずっと変わってないんだろうなと思う感じの素朴な雰囲気の人だ。いまは意気消沈してげっそり見えるけど、別に普段体調が悪そうな様子はなかったと思う。とても一週間後に死ぬ人間には見えない。
ほんとかどうかはわからないけど、成り行き上奇妙な経験をした同士として、やっぱり気になる。休み時間になって、俺はなんとなく古川の後をつけた。
とぼとぼ歩いてる。背中がいかにもショックに打ちひしがれていて、すごく可哀そう。なんだかいたたまれない気持ちになる。
職員室の近くまで来たところで古川はハッと立ち止まった。俺もあわてて空き教室に隠れる。隠れたままのぞいていると、古川の目線の先に科学教師の藤堂が現れた。藤堂もやはり若い教師でいかにも科学部にいそうなひょろりとした男だ。ふたりは何か話し始めた。
後ろから見える古川の耳が真っ赤に染まる。「大丈夫ですか?」「全然大丈夫です」という会話が切れ切れに聞こえてきた。古川がぶんぶん首を振って、藤堂の顔を見たり、目を逸らしたりしている。見てたら俺はまたいたたまれない気持ちになった。
絶対好きじゃん、古川って藤堂のこと。
俺がちょっと賢いからとか、死神が見える特殊能力を得てるからとか、そうゆうの関係なしにわかっちゃうくらい明白だ。藤堂だってこれは気づいてるだろ、と思ったけど、白衣の科学教師の乏しい表情からはなにも読み取れなかった。
しばし二人は話したのち、藤堂が先に職員室のほうに消えていった。残った古川がひとり佇んでいる。俺はすこし迷ったが声を掛けてみようと動いたとき、身体がロッカーにあたってガタンという物音が出た。その瞬間古川がヒャッと声をあげてあたりを見まわした。目を開いて遠目にも震えて、怯えている。
その姿を見ていたら声を掛けることは、できなかった。
俺の死神くんは、その夜、勉強している俺の横に現れた。
わざわざ夜中に参考書なんかひろげて夜更かししたかいがあった。もう慣れたもんである。
「よぉ、待ってたぜ」
「……」
オーケー。安定の無言だ。
「あのさ、今日俺の学校に死神きたんだけど」
「……!」
死神がギクッってかんじの反応をした。なんか俺、こいつの表情とかわかるようになってきてるかも。
「あれって、お仲間?」
「……」
無言だったけど肯定と受け取る。俺は足を組みなおして死神に面と向かった。
「お前たちが仲間だったら情報共有とかしてるのかもしんないけどさ。一応言っとくと、学校にきた死神、先生に一週間後に死ぬって言ってたんだ」
「……」
「先生、来週死ぬって、ほんと?」
「……本当だ。ソレがそう言ったなら」
今日はじめてこいつが声を出した。しかもいままで一番の長文を発音している。俺はその事実にちょっと驚いたが、貰った回答が重すぎて気落ちした。
「なんで? 先生ってなんで死ぬ?」
「……」
「ちなみにだけど、お前たちってdeathするノートとか持ってそうな雰囲気あるけど、そーゆうんではないよな?」
「……?」
ポカンとしたからたぶん違うんだろう。正直言ってはじめからとそれっぽいと思ってたけどそりゃぁそうよね。俺も誰かを裁きたい気持ちなんて全然ないから助かる。
「先生が死なない方法ってないの?」
「……ない」
段々と会話が成立ししつある。けれど会話が進むほど絶望感が増すばかりだ。俺はしばし考えこんで「ねぇお前って」と顔をあげたときには死神はもう消えていた。
ねぇお前って、本物の死神なの?
という質問も、だから声にならずに消えてしまった。
なにかしたほうがいいのか、なにかできるのか、よくわからないままで次の日も俺は古川の観察を続けていた。観察していると次第に古川優子という人間の解像度があがっていく。
古川は基本びくびくしている。いまは此の世のものではない化け物の存在を意識しているせいもあると思うが、そうでなくても、生徒にぶつかりそうになってビクッっとし、他の教師が怒鳴るのにビクッとし、そのたびに胸に抱えた教本にぎゅっと力を込めていた。
俺はつくづく不憫に思う。なにもこんな怖がりさんのところに現れて死を告げることないだろうに。このままじゃ彼女の残されたわずかな余命が、無意味に怯えて終わりそうだった。
それに観察してると古川がいつも藤堂を見てるってことが、よくわかってしまった。正確には藤堂のいる科学室のあたりをよく見上げている。中庭を挟んだむこうにあるその場所には必ずしも藤堂の姿が見えるわけでもないのに、古川は癖のように何度も見つめていた。そんなだから、たまに藤堂に会えたときなんかは毎回真っ赤になって話していて、見ているこっちが恥ずかしくなるくらいだ。三十すぎの女性に言うことではないだろうけど、本当に健気な乙女というかんじだった。
だからなおのこと、俺はハラハラする。古川には時間がない。俺が古川の寿命をあと六日、あと五日と数えてしまうのと同じように古川は自分の命を正確にカウントダウンしているはずなのだ。なのに毎日教壇に立って、たいして真剣でもない高校生たち相手に授業を繰り返している。この一コマ五十分の時間は、残された時間のすくなさにたいしてあまりにももったいないような気がした。
でもこれ以上奇妙な行動を起こして古川を怖がらせるのは避けたい。どうしたものか。
古川の寿命が残り四日になった日、俺は古川を呼び出した。
わからないとこがあるので残って勉強したい。すこし見てほしいから放課後教室にきてくれませんか、というようなことを言ったら、やや怪訝な反応を見せたものの、放課後に古川は教室にきてくれた。
俺は形だけひろげたノートと教科書を前に、ただ机に座ってやってきたその姿を見た。
「池原くん、どう? 進んでる?」
この生徒の名前は本当に池原くんで合ってるわよね、とでも思ってそうな口調で古川は言った。騙したみたいで気が咎めたけど、俺は単刀直入に本題に入ることにした。
「先生、ラブレターって、書いたことある?」
古川は目に見えてギョッとした。え、え、と言ってるから俺は続けた。
「ごめん、勉強は大丈夫なんだ。それでラブレター、書いたことある?」
「ないわよ、そんな……」
「そうなんだ。じゃあ書いてみれば?」
俺の言葉に古川はあきらかに困惑している。真意がはかりかねる、といった顔で古川は俺を見ていた。俺はゆっくりと説明を続ける。
「先生きっと文章上手でしょ。国語教えてるくらいだしさ。たぶんすげーいい手紙書けるんじゃない? だから書いてみなよ。好きな人に」
好きな人に、という単語で藤堂を連想するのか、古川はまた赤くなる。近くで見てるとけっこう可愛いひとなんだなと思えた。
「い、池原くん? いったい何を言ってるの? 急に変なこと、」
「真面目に言ってるよ」
「そんな真面目にって、」
「預かるから」
「……え?」
「書いたら俺すこしだけ預かっててあげるよ。『もしも』先生になにかあったら、そのときは俺がかわりに渡すから。その人に」
そう言うと古川ははっと真顔になった。ここ数日の出来事となにか結びついたような表情だった。
「もちろん書いて先生が直接渡すのが一番いいと思う。でもそれがもしできそうになかったら俺が預かるからさ。絶対に中を見たりなんかしないって約束するからさ。だから書いてみなよ」
古川は黙っている。きっと頭のなかは混乱しているだろうけど、俺にも他の方法が思いつかなかったんだ。
「お願いだから、先生」
お願いだから、なにも伝えないままで死ぬなよ。毎日見つめてた気持ちは絶対に言葉にするべきだよ。
そこまでは言えなかったけど、古川は、でも頷いてくれた。
「よくわからないけど、書いてみるわ。ありがとう」
おどおどとそう言って、古川は教室を後にした。俺はほっと息をした。変には思われただろうけど、怖がってはいなかったと思う。
オカシナことを言ってもギリ受け入れてもらえる自分のコミュ力と普段のキャラ作りに、このときばかりは感謝した。
次の日からは土日になって学校は休みだった。誰かの命の灯を気にして過ごす休日は、全然気が休まらなかった。あけて月曜、古川の寿命が残り一日となったその日、授業の終わりに廊下で古川に呼び止められた。
「これ」
と言って古川が差し出したのは、なんの変哲もない茶封筒だった。わりとデカい。
「中に、その、あの手紙がはいってるから。できればそれは見ないで持っててくれないかしら? 宛名とか……」
この茶封筒のなかに別途封筒に入った手紙が入っているというわけだった。俺は頷いた。
「大丈夫、見ないよ」
「ありがとう」
「でも、本当に自分で渡さなくていい?」
古川はキュッと唇を結んでからちいさく笑って俺を見た。
「その人にはきちんと自分から渡したいと思っているの。だからこの封筒は明日まで持っていて。明日になったら私ちゃんとこれを取りに来て、きっと渡すわ。わけのわからないお願いで、ごめんね」
わけわからなくないよ。古川が設けた『明日』という期日の意味を俺は正確に理解したけれど、それについては何も言わないでおいた。
古川にとって、今日告白してしまわないのは、明日から先も生きるという希望なんだと思う。生きて明日、想いを伝えるという希望なんだ。
お化けだか死神だかわからないものの言うことを信じる義理はない。無視する手だってある。でも物騒なことを言われれば怖いし気になるし、まさかとは思っても自分の人生を顧みる気持ちにもなる。だから古川はこうして手紙を書いてきたんだと思う。
ただ今日想いを伝えてしまえるほど、彼女は死神の存在を信じ切ってはいないし、この先の人生を諦めてはいないのだ。
そしてやっぱり俺も、明日から先があってほしいなって思っているんだと思う。
俺は手に持った封筒を、折れてしまわないように大事に鞄に入れた。
次の日、古川は学校にこなかった。
一人の教師が休んだことを気にかけている生徒は、たぶん俺だけだったと思う。
古川が亡くなった、ということが俺ら生徒に知らされたのは、さらに次の日になってからだった。
ご自宅にいる間に倒れられてそのまま、と校長が話しているのを「そうか病死なのか」と妙に冷静に聞いた。体調なんて、悪くなさそうだったのにな。
全校で集まった集会が終わったとすぐに俺は教室の鞄から茶封筒を取り出して走った。次の授業の予鈴が聞こえたが構わなかった。職員室に行って、他のクラスに行って、理科準備室の前でようやく見つけた。
「藤堂先生!」
藤堂は準備室の戸に手をかけたまま振りむいた。寝ぼけてるみたいな緩慢な動作だった。
「あぁ……えと……君は?」
それには答えないでぐんぐん藤堂のそばに歩いて行って、目の前に茶封筒を出した。藤堂が俺と封筒とを見比べている。なにか言おうとするのを遮るみたいに言った。
「古川先生から、あんたに」
別に中身なんか見てない。宛名の確認もしてない。でもこれがあんた宛だってことくらいバカでもわかるんだよ。こんなバカでもわかるようなことを、まるで自分だけの秘密みたいにして仕舞い込もうとしてた古川は本当に臆病でバカだと思う。
古川という名前を聞いて藤堂ははっと目を開いた。突然死した同僚からの何かを唐突に差し出してくるあまりよく知らない生徒、という状況をどう理解したのかはわからないが、藤堂はゆっくりと封筒を受け取った。
「そうか、ありがとう」
藤堂は丁寧に言った。眉毛が苦しそうな形を作る。なんだ、こいつも近くで見るとけっこうかっこいいんだなと俺は思った。お似合いだったんじゃん、あんたたち。
そうして俺はその場を後にした。
藤堂が手紙を見るところは、見てはいけない気がした。
なんとなくそんな予感はしていたが、帰宅して自分の部屋の机の脇に例の死神が立っているのを見て、やっぱりなと思った。
やっぱり今日は出てくると思った。
「ご無沙汰だな」
声を掛けても返事はない。俺はゆっくり近づいた。
「先生死んだよ」
もう一歩近づく。俺はこいつに会って、不思議なことが起きて、でもどこかで疑っていたんだと思う。現実味がなかったんだと思う。
「あのさ、」
近づけば足元からゾロゾロと嫌な感覚があがってくる。恐怖じゃない。死ってやつを飲み込んだみたいに腹の中が冷たい。
「お前、」
死神の鼻先まで顔を寄せる。もしかすると俺は震えているのかもしれない。
「……本物、なんだな」
呟くようにそう言えば、目の間の死神が、黙ってただ、俺を見ていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

