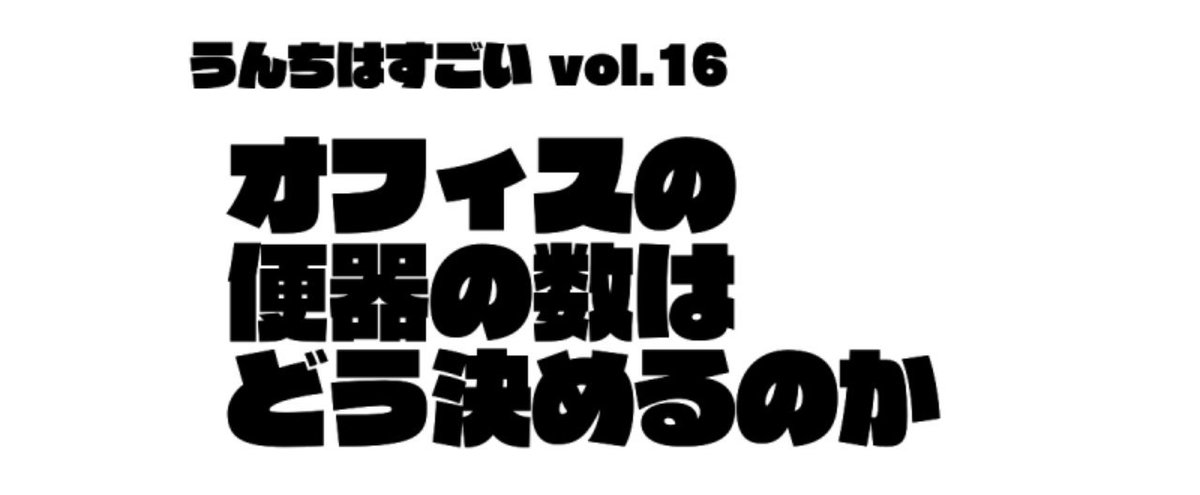
オフィスの便器の数はどう決めるのか
オフィスにはトイレが必要です。
そりゃそうですよね。もし、トイレがなければ、オフィスに滞在する時間が限られてしまいます。
以前、「トイレがとても大切な場所である理由」で、1日にトイレに行く回数は、だいたい6~7回くらいと書きました。
ということは、起きている時間を仮に16時間とすると、2時間~3時間に1回、トイレに行くことになるので、トイレに行かずにその場に滞在できるのは3時間くらいとなります。
ですが、それではオフィスで落ち着いて仕事ができません。
では、オフィスにはどのくらい数の便器が必要なのでしょうか?
多すぎれば過剰投資ですし、少なすぎればトイレ混雑を引き起こします。みなさんも「トイレ待ち」は経験したことがありますよね。余裕を持って待っている場合ならまだよいですが、切迫している状況でトイレが空いていないとパニックになります。
そこで、今回はトイレの必要数の計算方法について紹介します。
建物のトイレの面積はおもに便器の数で決まりますし、給排水設備の設計にも影響するので、便器の算定はとても大切なのです。
算定方法の前に紹介しなければならないことがあります。
それは、便器の必要数に関する法令です。たとえば、事務所は以下のとおりです。
オフィスでは、男女の雇用割合がある程度分かると思いますので、以下のようにそれぞれごとに算定することが基本となります。
【厚生労働省事務所衛生基準規則第17条1】
男性用と女性用に区別すること
男性用大便器:60人以内毎に1個以上(同時に就業する男性労働者)
男性用小便器:30人以内毎に1個以上(同時に就業する男性労働者)
女性用便器:20人以内毎に1個以上(同時に就業する女性労働者)
・同上 第18条
洗面設備を設置しなければならない(個数の規定はない)
つまり、最低でも、これはクリアしなければならないということです。
ちょっと話がそれますが、空気調和・衛生工学会の給排水衛生設備規準・同解説の技術要項・同解説に掲載されている例題では、2000年版までは男女比80%:20%という仮設定がなされていましたが、2009年版は50%:50%に見直しがされています。これも時代を物語っていますね。
ちなみに、先日お会いしたClara Greed教授(University of the West of England)によれば「ずっと長い間、女性はトイレ設備の不公平に苦しんできた。以前のロンドンのトイレは、男性25便器、女性5便器でした。」とのことでした。

公共空間にもかかわらず、これはひどいですね……。
必要便器数の算定式はこれだ!
それでは、本題の便器数の算定について。
この算定方法は、1983 年12 月、空気調和衛生工学会の適正器具数小委員会報告書としてまとめられた内容が元になっています。このときの専門誌を見てみると、各種の法令による基準や研究による提案値などが混在して、どれを採用すべきか判断に苦しむ場合も少なくなかったので、この課題解決のために作成したという記述があります。
具体的な方法は以下になります。
まず、オフィスは「任意形態利用」の建物として位置づけられているので、それに対応した算定条件表(下表)を用います。任意形態利用というのは、いつでも自由に利用できる形態のことを指します。逆に、劇場や学校などの休み時間や休憩時間にのみ利用するタイプは「限定利用形態」と呼ばれ、計算方法が異なります。

注a):( )内の時間は待ち時間(s)を、右の値は確立を表す。
出典:社団法人空気調和・衛生工学会SHASE-S 206-2009 p211
この条件表には、到着率、占有時間、待ち時間の評価尺度が示されています。
到着率というのは、利用人数が100人の場合に1分間に利用する人数を示しています。
また、占有時間は便器を使用している時間のことです。男子は1回あたりに大便器を5分使うという意味です。占有時間については実測値を採用しているので、おそらく当時の学会誌に掲載されている下表から設定したと思われます。

( )内は採用された例を示す。
出典:空気調和・衛生工学1984-7VOL.58 NO.7 p83
そして、待ち時間の評価尺度は、サービスレベルとも呼ばれており、どのくらいの時間を待たせるか、という指標です。レベル1は「ゆとりのある器具数」、レベル2は「標準的な器具数」、レベル3は「最低限度の器具数」です。
つまり、男子大便器の場合、10秒より長く待つ確率を5%未満になるようにするのがレベル1ということです。
ちなみに、村川三郎氏が昭和58年6月・日本建築学会論文報告集に掲載したデータによれば、事務所のトイレ混雑時に許容できる平均待ち時間は、大小便とも女性よりも男性の方が短く、男性に関しては、大便(75.8秒)の方が小便(42.7秒)に比べて30秒ほど長くなっていますが、女性ではそれほど差異が見られませんでした。
これらを踏まえて、適正器具数の算定図(下図)から必要数を決めることになります。

図 適正器具数の算定図出典:事務所の適正器具数(LIXIL)
(社団法人空気調和・衛生工学会のデータをもとに作成)
ただし、この報告書で示されているのは、事務所、百貨店・量販店、寄宿舎、病院(病棟)、劇場、学校の6つに限られており、設計者は「対象とする範囲で、便所に設置する衛生器具の利用人員とその男女の割合は、適切に予測するものとする」と記されています。
つまり、この算定方法は使っていいけど、しっかり、現場のニーズや状況を把握して考えてくださいね、ということです。
それにしても、先人たちの研究はすばらしいです。
今回紹介したトイレの器具数算定だけでなく、大便器汚物搬送性能に関する基準、汚物処理性能に関する技術的基準、くみ取り便所の構造に関する基準など、調査と研究の積み重ねによって導き出された基準が、今日の快適なトイレ環境を築いているのです。
情熱と愛を感じることができました。
排便は生理現象でその時によって緊急度も異なりますが、待てば待つほど、いらいらは募りますよね。
トイレの快適性は、健康面だけでなく生産性にも大きく影響すると思います。
これからのオフィスは大規模化や用途の多様化、ジェンダーなど、新たなニーズが生まれています。
トイレを設計する方々には、これまでの研究成果を存分に活かすとともに、ぜひ綿密な実態調査を踏まえて計画してほしいものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
