
[詩] ヒヤシンス
家の近くに、だれも住んでいない古い木造の洋館が建っていた。屋根は雨に朽ちかけ、壁や柱の白いペンキは剥げ、蔦と草花に覆われた窓ガラスはつねに曇っていた。あるとき未就学児の予防接種がそこで行われた。
眠たげな丸いランプがさがる玄関に飾られた青紫のヒヤシンスと、消毒液の匂い。どこかで手を洗いつづける水の音。上階の部屋から漏れる幼い子どもたちの泣き声。長い時間の樹液を含んだ琥珀色の廊下。ドアがひらきだれかが連れてゆかれるたびに暗い木の床に夕刻のひかりが差して。
注射への怖れはなく、しずかに朽ちてゆくものの内部にいることがわたしを安心させた。なぜかそこに母はいなかった。目がくらむほどあかるい部屋のなかで注射を受けたあともすぐには帰らず、ひと気のない階段の踊り場の窓から中庭を眺めていた。夕陽を反射した椿の木に囲まれて、ちいさな火が燃えていた。
背伸びをするときしきしと自分のくるぶしの骨が鳴く音がする。きしきしきし。窓枠のすみで干からびた玉虫の死骸。長いあいだひとの息にふれずに朽ちてゆくものの内部はあたたかい。
腰のまがった老婆がなにかを火にくべている。長いスカートのうえにエプロンを巻きストールをはおり、スカーフの翳で顔を隠したひとは外国の絵本のなかの農婦に見えた。燃えきれない白い紙がときどき風に舞った。投函されなかった手紙、あるいは書かれなかった日記だろうか。ひとの目にふれずに朽ちてゆくものはみなあたたかい。
おばあさん、わたしをどこか遠くへ連れていってくれませんか。埃と雨の跡で曇ったガラス越しにわたしはつぶやいた。
この町から離れた場所ならどこでもいいのです。わたしは遠くへゆけます。歩いてもゆけます。
数年後に洋館は壊され、わたしがおとなになったあとも、中庭のちいさな火は遠い子守歌となって燃えつづけた。
遠くへゆくために
遠くを見るために
手と足と 目を もらったのに
手足をやすめ 瞼を閉じて
ふかく眠るときにだけ
たましいは
火や雪のうえを 自由に駆けてゆけるのだから
もう 泣きながら歩くことはない
ただ 目を閉じればいい
だれからも遠い場所へとゆくために
おとなになってから旅をした。ひとりで。いちどだけ、ふたりで。そこが、わたしが望んだ遠く、なのかはわからないまま。数日間の冬の旅のおわりに、雪の広場を抜け、凍った川岸で、おおきなコートのひとつのポケットにふたつの手をいれ、熱い焼き栗を分けあって歩いた。
あの日いっしょに見あげたフレスコ画のガブリエルの手からこぼれる百合のひかりも、黒い川面に映る夜火事のような対岸のあかりも。生まれるまえについた嘘とおなじくらいうつくしかったから、もうなにも話さなかった。
夜ふけにホテルに戻ると、廊下の端の部屋から女の声がする。高く、低く歌い、なにかを求めているのか、拒んでいるのか。もしかしたら女の声などではなく、近くの暗い森の奥でさびしさに耐え切れずに鳴きだした鳥か狐の声かもしれない。
わたしたちはなにも話さなかった。泣いても叫んでも、もうことばは伝わらないから。永遠に離れ、遠くから思いつづけることでしか、だれかを知ることはできないのだと。
朝のホテルの窓からは廻廊に囲まれた狭い中庭が見える。庭のすみにはだれかに捨てられたように、もしくはふかく祈られたように、頭部の欠けた天使像が置かれ、そこにも雪がうすくつもっている。それは、チェックアウトのあと、つぎの列車を待つあいだに飲まれずに冷めていった一杯の紅茶の香りのように、だれからも少しずつ忘れられてゆく。
まだ眠りつづけるひとをのこし、わたしは中庭におりた。天使像のちいさな足のそばに貝のボタンが落ちている。雪に濡れた鳩がかすかに汚れたそのしずかな光沢をついばんでいた。海にも砂にも決して戻れずに溶けのこるものを慈しむかのように。
朝の雪の庭のまぶしさにわたしは目を閉じた。もう、泣きながら歩くことはない。ただ、目を閉じればいい。だれからも遠い場所へとゆくために。
部屋へとつづく冷たい石の階段をふたたびのぼりはじめたとき、すれ違った少女のくるぶしから、さいたばかりのヒヤシンスの匂いがした。

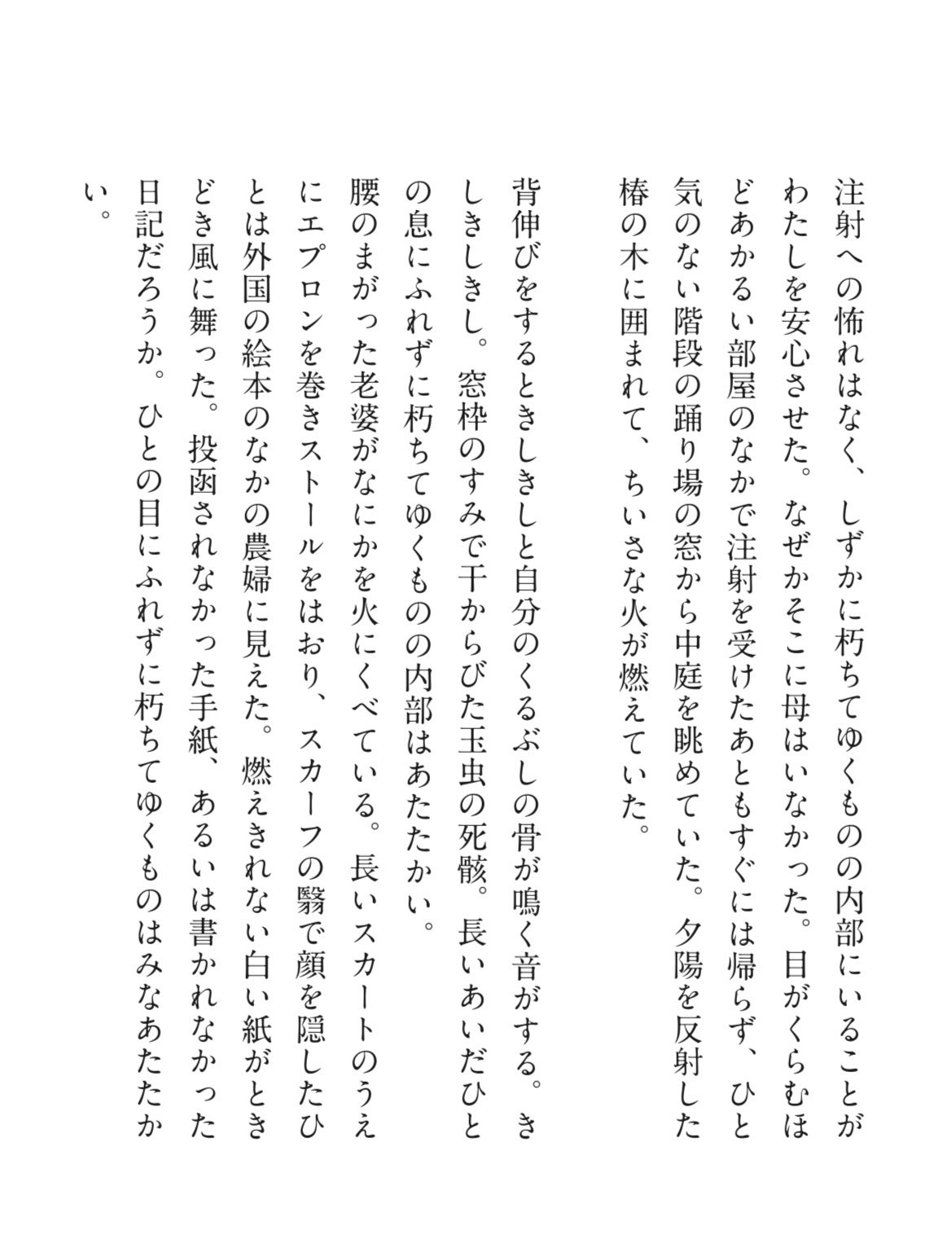


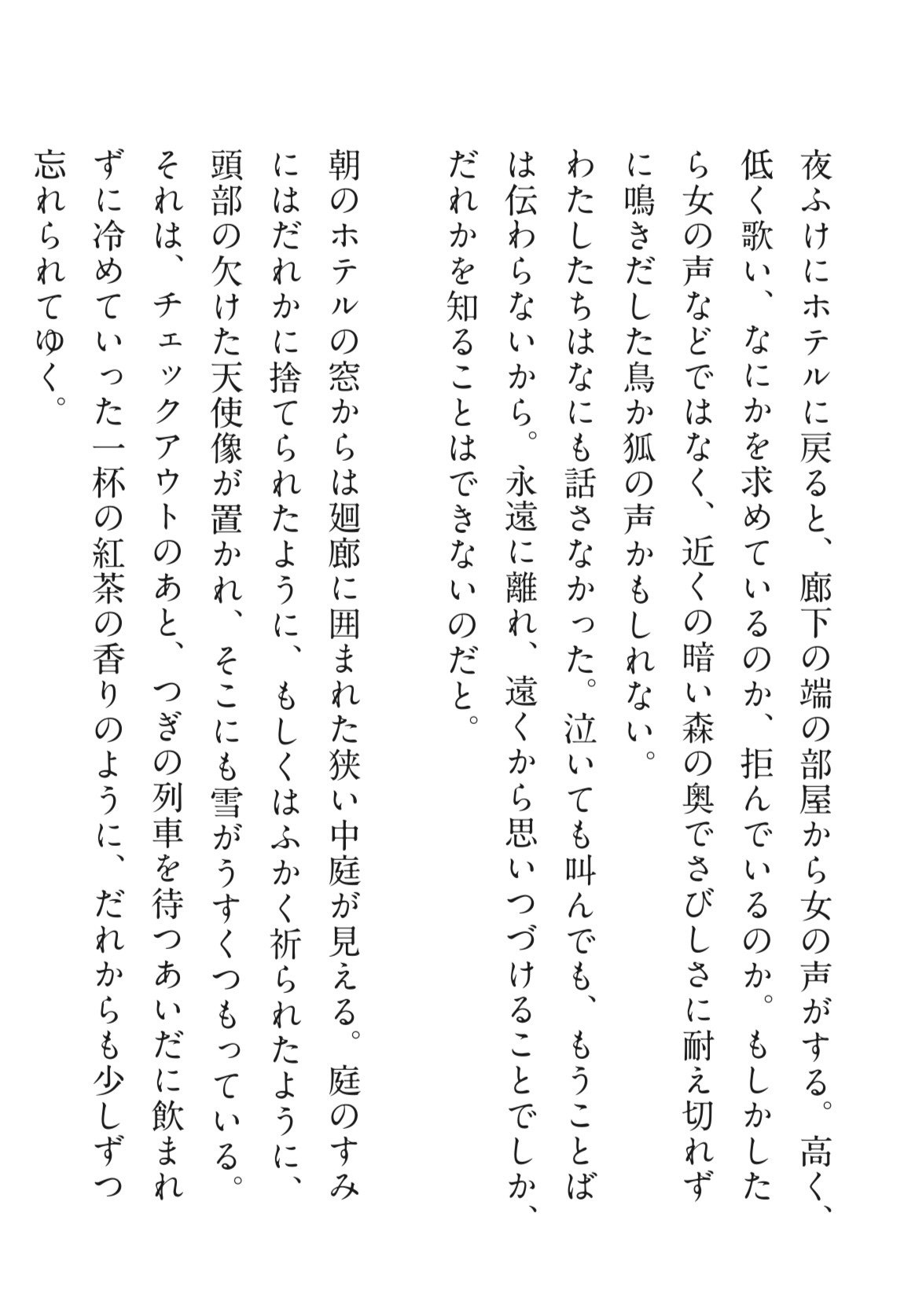

※この記事は12月25日中までの公開としておりましたが、
そのあともこの部屋を訪れてくださる方もいらっしゃるようなので、このまま残すことにしました。
お読みくださり、ありがとうございます。
詩「ヒヤシンス」は、詩集『微熱期』(2022年・思潮社)に収録されています。
『微熱期』にはこれまでの詩集にくらべて、散文詩が多く入っています。ぞれぞれ書き方を変えていますのでよろしければご覧ください。
詳細は下記の記事へ。
★七月堂古書部には署名入りの本もあります。
