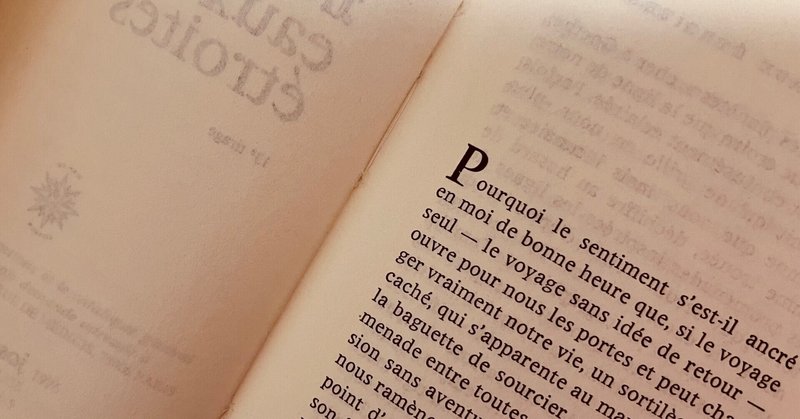
姿を消した本のこと(斎藤史の一首とともに)
数年前、詩集以外の本を一緒に作りましょう、と提案してくれた人がいた。
何かの企画を一緒に、とお声がけいただくことはあっても、そのすべてが実現するとは限らない。依頼する方とされる方の都合が合わなかったり、進めるうちに考えの方向が分かれてしまうこともあるから。
あのときも数か月、いや一年以上は、原稿のやりとりをしていたと思う。
打ち合わせのあとに原稿を送り、それについて意見をもらい、書き直し、社内での検討の結果、また企画の始まりへと戻り、新しい原稿を書き、ふたたび修正する、というように。
その人と上司の意見の相違もあったり、わたしもその分野の文章を書くこと自体に迷いがあり、自分でも納得できる何かになかなか辿り着けなかった。
そうこうしているうちに、その人は会社を辞め、わたしもその人以外の人に原稿を送る気持ちが薄れ、かたちの輪郭も見えないまま、その本は結局、消えてしまった。
それでも、その人とのやりとりから得たものはたくさんある。
原稿を送るたびに一読後の体温が込められた感想がすぐに届き、メールだけでは伝わらないから、とその人は必ず喫茶店で会うことを提案した。
約束の時間の数分前にわたしが店に着くと、その人はいつも同じテーブルの通路側の席に座っていた。そして人の気配に気づくと笑顔で立ち上がり、壁際の落ち着ける席を手のひらでそっと指した。
原稿についての丁寧な感想と修正点を伝えながら、私的なことに入りすぎずに、しかしこちらの日常を気遣うようにその人はいつも話した。
美味しいですよ、と教えてくれたその店のコーヒーの香りとともに、原稿のことから暮らしのなかの楽しみへと話題がふわっと広がってゆく。そんなひと時は、春の始まりに巻くスカーフのようにさりげなく暖かかった。
わたしもこれまでに広報誌や雑誌の編集をしてきたが、いろんな職場で出会った上司たちから、ほぼ同じことを言われたことがある。
できるだけ書き手には会って話すこと。こちらは毎日多くの人とやりとりしているけれど、相手にとってはたった一人の編集者であることを忘れずに……。
その人はいつも、目の前のたった一人を見ていた。
複数の人たちの集まりに人数合わせで呼ばれることがわたしは、子どもの頃から変わらずに苦手だ。それがどんなに楽しい社交の場だとしても参加しない。
目の前に座るだろう、たった一人の人を待つ。そして目の前の人に話し、その人の話を聞く。
それはシンプルすぎること。
しかしそんな単純な時間と思いから、いつのまに遠ざかってしまったのだろう……と日々の雑多な交流を振り返って思うことがある。
あのとき作られなかった本。そのページには何も書かれていない。
あれは、その人とだけやりとりした、一通の白い手紙のような本だったのかもしれない。
春が始まりにいつも、胸のなかで口ずさむ歌がある。
学生のときに読み、いまでも好きな、斎藤史の歌集『魚歌』の一首。
白い手紙がとどいて明日は春となるうすいがらすも磨いて待たう
多方向へ、ではなく。目の前の人に向けてたった一通の手紙を書くこと。そんなふうに書かれた手紙は、いつか真新しい季節をつれて、雲ひとつない青空から戻ってくるのかもしれない。
好きな文字を書けるように、と、白い紙を翼のように開いて。
