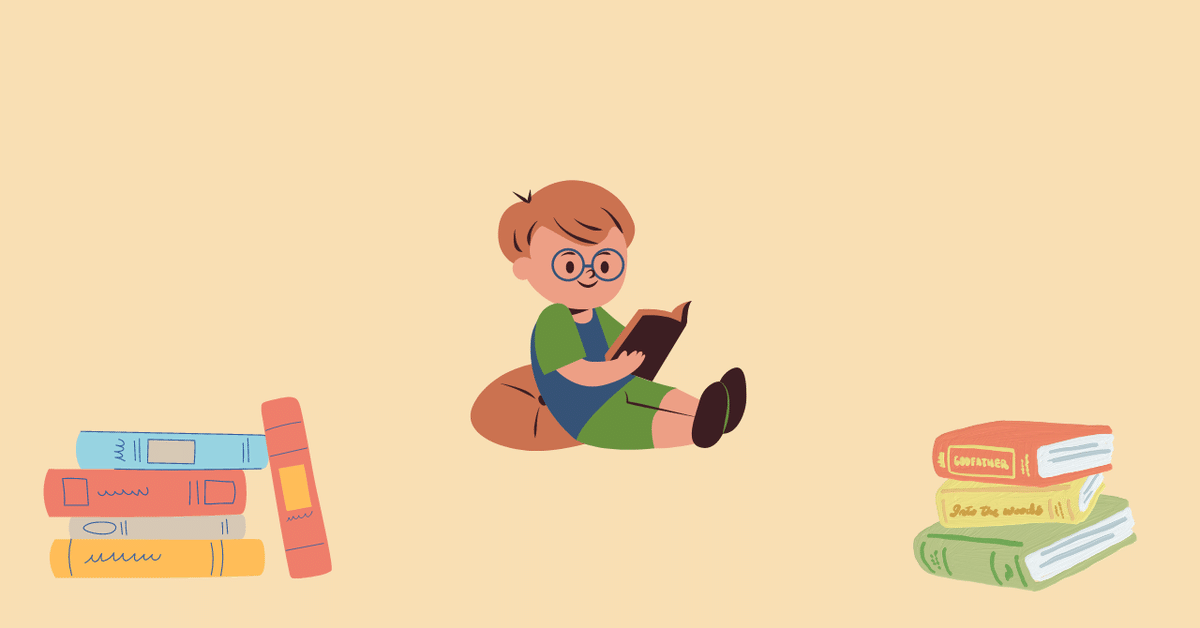
「#わたしを作った児童文学5冊」
今朝、Twitterで素敵なハッシュタグを見かけた。
ここに寄せられたいろいろな人のツイートを見ていくと、小学校や地域の公民館の図書室にたくさんの本が並んでいた情景がバァっと思い起こされて一気に懐かしくなってしまった。
ということで、ここでは私の思い出の児童文学5選を紹介していきたい。
①那須正幹『ズッコケ三人組』
小学校低学年のときに図書館で散々借りて全巻読破したシリーズ。
小柄でやんちゃなハチベエ、博識な読書家だがどこか不器用なハカセ、おおらかで心優しいモーちゃんというバラバラな三人組が、ときに衝突しつつもお互いに力と知恵を合わせてさまざまなことに取り組んでいくのがとても魅力的だった。
私が特に覚えているのは、想像で考えた学校の怪談が実際に襲い掛かってくるホラーを描いた『ズッコケ三人組と学校の怪談』、痩せるためにダイエットに懸命に取り組むモーちゃんをメインにしつつ健康の大事さを教えてくれる『ズッコケ三人組のダイエット講座』、縄文時代にタイムスリップしてしまい争いや事件に巻き込まれてしまう『ズッコケ魔の異郷伝説』あたりのお話だ。
ポプラ社のページにはさらに詳しいキャラ紹介や本の表紙画像がずらりと並んでいるので、私と同じようにズッコケ三人組を以前読んでいたという人がいたらぜひのぞいてみてほしい。
②令丈ヒロ子『若おかみは小学生!』
私の中で「青い鳥文庫といえば!」な作品。
同時期に同じくらい人気だった『黒魔女さんが通る‼︎』も好きだけれど、若おかみの方が先に出会ってしまったので、個人的にこっちの方が思い入れは強い。
両親を交通事故で亡くした小学6年生の主人公おっこが、祖母の経営する旅館で立派な若女将になるべく奮闘するという、今考えてみるとなかなかにハードなストーリー。
ゆうれいやオニといったキャラクター達も登場するちょっと不思議な旅館で成長していくおっこを見ていると、思わずこちらも元気になってしまうような作品だった。
③池田美代子『妖界ナビ・ルナ』
四神(朱雀・白虎・青龍・玄武)はこれで覚えた。
間違いなく児童向けではあるんだけど、ダークファンタジー的な要素も強くてところどころ怖く感じる部分もあったような記憶がある。
もうすぐ小学4年生になるルナが、ある夜かまいたちのような妖怪に出会ったことで、自身の秘密を知るようになり旅に出るというところから話が始まっていく。
ルナのうなじには封印されし第三の眼を持っていて、いつもはチョーカーのように首にリボンを巻きつけることでその眼を隠しているという設定があるのだが、これの影響でチョーカーに対して一時期めちゃくちゃ憧れがあった。
④松谷みよ子『ちいさいモモちゃん』
お母さんと一緒に公民館の図書室に行ったときに「これ読んでたよ!」とオススメされてから読み始めた。
そういう思い出も相まって、私の中で家族を描いた児童文学作品といえばこの本、という感じがする。
シリーズとしての名前は「モモちゃんとアカネちゃんの本」。
優しい雰囲気で進んでいき、主にモモちゃん・アカネちゃん姉妹とお母さんの3人のエピソードが語られていく。
シリーズ1冊目となる『ちいさいモモちゃん』は、モモちゃんが産まれたときからの数年間を描いているのだが、赤ん坊をこんな風に主人公として置いている作品を当時は読んだことがなかったので新鮮に思ったような気がする。
シリーズが進んでいくごとにモモちゃんも年齢も重ねていくのだが、誕生時から見守っていたせいで「小さかったモモちゃんがこんなお姉さんに成長するなんて…」という一抹の寂しさを抱えながら読んでいた。
⑤ミヒャエル・エンデ『モモ』
母の実家に遊びに行ったときにお祖父ちゃんがプレゼントしてくれた本だったと思う。
分厚かったからなかなか読むのをためらってたけど、今でもことあるごとにこの本のことを思い出す。
廃墟の円形劇場に住み着いたモモが近所の人と友情を育んでいく温かな物語でありながら、途中からは「灰色の男たち」に時間を奪われ、余裕を失い忙しくも虚ろな人生を送ることになってしまったかっての友人たちにモモがどう向き合っていくかという難題が登場する。
だから今でも仕事に忙殺している社会人を見たり、自分自身が時間を気にして思うように好きなことでも楽しめなかったりしていると、「まるで『モモ』の世界みたいだな」とふっと思うことで、人生において何が大事なのかを見つめ直すきっかけになる。
まるで現代の寓話のような物語だからこそ、特にこの本は自分に子どもができたときにも贈りたいし、そのときに自分でももう一度読みなおしたいと思っている。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
