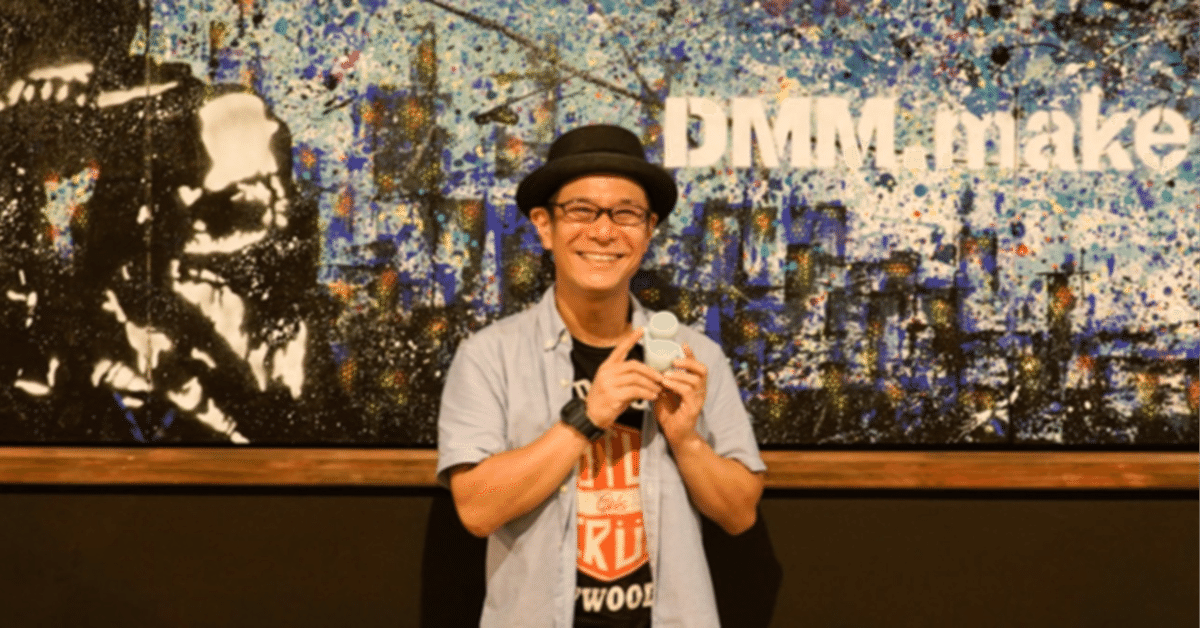
コア・コンピタンスを理解する
松山工業株式会社の鵜久森洋生です。私は毎週土曜日は、DMM.make AKIBAさん(以下、アキバ)の公式マガジン「MAKERS」向けの投稿を続けています。
今回は「コア・コンピタンス」という言葉について書き綴りたいと思います。
コア・コンピタンスとは
コア・コンピタンス(Core competence)とは、「企業の核となる分野」と私は解釈しています。競合他社を圧倒するレベルの高くて、真似できない確固たる能力と訳されることもあります。ただ、文字通りに訳すと私の解釈が合っているんじゃないかと感じています。
自社分析、例えばSWOT分析をした時に、「強み」の部分で出てくることの中で、他者と比べた場合に強みとなるものはなんだろう…実はこう考えると、自社のコア・コンピタンスを把握出来る可能性があります。SWOT分析は、マーケティングの基礎中に基礎なので、気のなる方は試してみていただけると嬉しいです。
松山工業のコア・コンピタンス
弊社のコア・コンピタンスは「サポート能力」です。製品化のご相談時、何か問題が発生した時など、他社と比べてサポートする能力が高まってきました。なぜ、ここまで言い切れるかというと、結果が伴ってきたからです。
例えば、他社ではギブアップしそうな難しい案件も真摯に対応し、かなりの確率で価格提示まで辿り着きます。また、製品的な問題が発生した際には、解決するまで決して逃げ出しません。
私の会社は、そういったパッと見は当たり前のようなことが出来るようにしたいと思い、「お客様のお役に立つために出来ること」という言葉を経営方針の軸としました。実は当たり前のようでいながら、効率化を追求すると忘れられがちになってしまうことだったりします。
そして、その部分を訴求していけば、お客様の満足度が上がり、ご縁を深めることが出来る…実は経営者になる少し前から、こんなことを考えて環境整備をするようになりました。特に不具合などが発生した際に、自社にとって都合が良い不誠実な判断にならないよう、「正道を歩む」というスタンスも普及させました。
お陰様で今、弊社では「忙しいから」「面倒くさいから」「不利になっちゃうから」といった理由で対応を渋るということがほぼ無くなりました。私も管理者もそれを許さないからです。当然、それがお客様から新たなご相談をいただく原動力になっています。
製品自体がコア・コンピタンスとなる場合
もしかしたら、ハードウェアスタートアップの方々の中には、自社製品そのものが、コア・コンピタンスになっている…そんなケースもあるかもしれません。知財もしっかり整備してあるし、当面は揺るぎない優位性が保てるはずだと考えていらっしゃるかもしれません。
それはそれで間違っていないと思います。例えば、少し前までのトヨタの強みは、明らかにハイブリッド技術など、トップランナーとして君臨したからこそたどり着いた高い技術力でした。
ただ、そんなトヨタもEV化の波に危機感を募らせ、新たな可能性を模索しています。技術だけを売りにしている場合、こういったケースが起こることを予期しておいた方が良いと感じます。
企業文化で核となるものを
私は幸い、コア・コンピタンスを企業文化の中に見出すことが出来ました。ありがたいことに、9月末の決算も好調を維持しています。そして、たった1つの言葉を発信し続けるだけで、社員が判断に迷うことが無くなりました。
アキバ会員の皆さんの中で、自社分析をしたことがないという方がいらっしゃったら、今回のコア・コンピタンスという言葉を思い出してください。隙間時間であったとしても、SWOT分析について考える時間を作るのは、とても価値があると思います。
もし、それでも…という方は、私にご相談ください。お役に立てるよう、時間を作りますので。
こんなことを語りつつ、今日のnoteを終えたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。感謝!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
