
コア体験からコアループへ
前回コア体験をゲーム的な見地から面白くするための要素について触れました。これでサービスの1回のコア体験をより良くすることができました。
では次にコア体験を繰り返していくコアループについて考えましょう。
コア体験とコアループとは
コア体験は抽象化すると、このようなインプットに対するアウトプットになります。Angry Birdsで鳥を飛ばすというインプットに対して、ブタが倒されるなどのアウトプットがあります。インプットを考える前の状況の把握や戦略の検討などもありましたね。
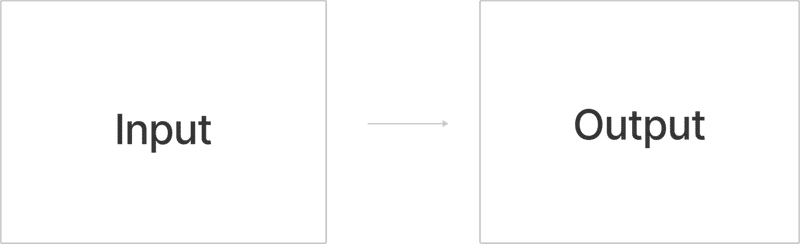
今回コアループという表現をしているものはアウトプットに対してフィードバックがユーザに戻り、次のインプットに反映されていくものです。

ドラクエで言う、1ターンや1戦闘がコア体験だとして、1ターンのコアループが戦闘になり、戦闘のコアループがレベルアップやダンジョンにつながっていきます。
1ターン終了後、当然敵や味方の状況は変わっていて、その状況の変化というフィードバックによって次のインプット・作戦は変わっていきます。
1戦闘終了後も、味方のHPやMP、薬草の残数なども変わっていて、ダンジョンをどう進んでいくのか、宝箱を取りに行くのか、あるいは町へ引き返すのか判断が変わっていきます。
重要なことはうまく行ったうまく行かなかったに関わらず、何が起こったのかの情報がユーザに提供され、次にどうしたらいいのかユーザが検討できることです。(clear feedback)
Clear Feedbackで次に繋げてもらう
メルカリで商品を出品して3日経っても売れませんでした。もちろん何も情報がなければユーザはなぜ売れないのか、どうしたらいいのかわかりません。
しかし実際は商品の閲覧数やいいねの数、コメントなどがあるので、
・そもそも見られてないな→タイトル変えてみようかな
・いいねはされるけど売れないな→値段が高いかな
など検討することができます。
そして修正を加えて再出品をして、またコア体験に移り、コアループが成立していることがわかります。
学校のテストでも合否だけの連絡しかもらえなかったら何が悪かったのか、何を勉強し直さないといけないのかわかりません。
ちなみにこの点において個人的にはCandy Crush Sagaは売れているタイトルですが好きではありません。プレイヤースキルも必要ですが、落ちてくるキャンディーがランダムなので運に左右されます。試行回数を増やさせるのが注力ポイントなのでしょう。
Clear Feedbackで喜んでもらう
話を戻して、失敗や反省のフィードバックの話だけではなく、成功した、何かを手に入れた、お金が増えた、などのフィードバックも当然大事です。
何をやった結果、何をもらったのか、をわかりやすく、かつ気持ちよく伝えてあげることでユーザのエンゲージメントは大いに高まり、もう一度その感情を味わいたいと思います。
かなり当たり前の話に聞こえますが、
・成功の通知が通知タブに小さく届いているだけ
・何か受け取ったけど何が起因だったのかよくわからない
・見た目があまり祝われている感がない
といったもったいない事例はよく見かけます。
一番ユーザの感情が上振れる瞬間はclear feedbackでわかりやすく、気持ちの良くなってもらいましょう。
ChallengeとReward
難しい課題にチャレンジして、達成することができたら大きな報酬を期待します。報酬にも実質的価値のある報酬や社会的・精神的価値のある報酬もあります。ユーザは頑張った結果に対して見返りが少ない、正当に評価されていないと感じたら、ネガティブに感じ離脱してしまうかもしれません。
ソーシャルゲーム運営経験者からするとパラメータ調整(レベルデザインなどの難易度調整やそれに応じた報酬)こそユーザに楽しみを感じてもらうために最重要な要素というのが理解できているのですが、未経験の方からするとそうではないケースもあるようです。
要件を満たす機能を開発すれば終わりではなく、その機能を通じてどんな感情の波を与えたいのか、そのためにどういうパラメータバランスであるべきかは非常に重要です。
ループしやすいか
また、これはゲームでしか当てはまらないことかと思いますが、コアループ、繰り返すという点で、やり直しやすいか(Replayability)は検討ポイントです。
Angry Birdsはいくらでもやり直せます。また一回のプレイも数分なので無駄になった時間もごくわずかです。
ドラクエで30分かけてダンジョンに挑んで途中で全滅してしまったら30分無駄になります。
プレイにお金やエナジーがかかる場合もやり直しには制限があります。
失敗した後の実質的・精神的ダメージが大きいと当然離脱に繋がります。投下したコストや時間が大きいほど、ユーザの成功へのプレッシャー、ヒリヒリ感が高まり、成功した時のカタルシスは大きいですが、バランスが大事です。例えば初心者ユーザにはあまり失ってしまうかもしれないコストへのプレッシャーを与えるよりもReplayabilityを重視した方が良いでしょう。
終わりに
どんなサービスであれ、ほとんど全てのサービスはユーザに繰り返し使ってもらうことを想定していると思います。そして多くのサービス運営者はユーザに何度も利用してハマって欲しいと思っているはずです。そのためには毎回の体験が独立試行な設計ではなく、フィードバックループが回って、ユーザが次へ次へ、もう一回もう一回と思うコアループ設計が必要になるはずです。サービス設計や企画の際にぜひ検討してみてください。
最後に、一緒にプロダクトを作ってくれる仲間を募集中です。UKを起点に世界でスポーツベッティング事業をやっていくのですが、普通に想像するものとあらゆる面で違った打ち手で攻めていきます。
𝗛𝗜𝗥𝗜𝗡𝗚 | 「仮想通貨 x ベッティング」「NFT x ベッティング」にビビッときた方は、エントリーをお待ちしております。気遣いもしがらみない、アスリートの未来のための大仕事です。狂ATE the FUTURE #スポーツベッティング
— ((( Panja ))) Next Sportsbook King (@naoe23) November 18, 2021
Calligraphy by 紫舟 @sisyu8https://t.co/6d5tIIQmd4
MeetyでもTwitterでもお気軽にご連絡ください。
本日現職PECOを退職し、副業先のカウシェも退職し、明日からJungle Xという異才と偉才が集う秘密結社でC向けグローバル市場に4回目のチャレンジをすることにしました。ベッティングと聞いて99%の人が「えっ」と思うでしょうが、世界の構造的課題を変えるシステムになります。させます。させましょう。 pic.twitter.com/39qk4xFqkj
— Yuji | SportsBetting PdM@Jungle X (@UG_Yuji) November 30, 2021
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
