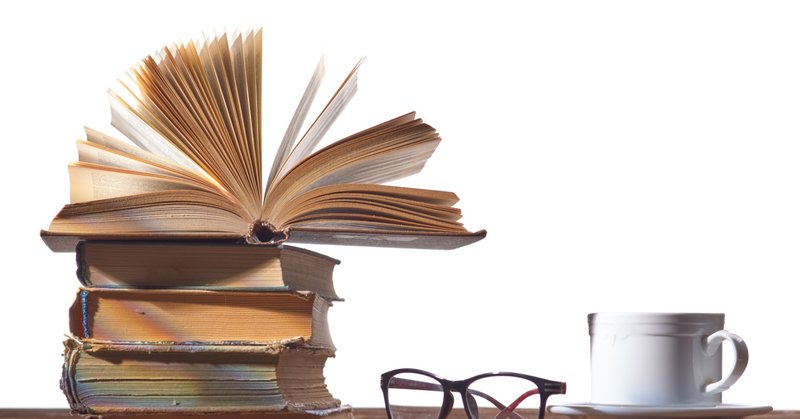
フリーライターはビジネス書を読まない(10)
自分の原稿のまま出版された
原稿を書き上げたのは締め切りの5日前。
自分で決めたスケジュールより2日ほど早くできたせいか、気分が少し楽だった。
これを推敲して、フロッピーディスクに保存して、プリントアウトして、編プロへ郵送する作業が残っているけれど、書き起こしていく作業が済んだだけでも、解放感は大きかった。
私の推敲方法は、当時から今もあまり変わらない。書き上げたらすぐに見直すことはしないで、一晩寝かせる。自分も寝る。
時間的に一晩寝かせる余裕がないときは、たとえ1時間でもいいから、原稿から離れる時間を設けて、なるべく原稿の内容と関係のないことをやる。
とにかく脳を別のモードで使うのだ。そうすると、あとから原稿を見直したときに、やや冷静な目で見られる……ような気がする。
当時のワープロで外部記憶媒体として主流だったのは、3.5インチのフロッピーディスクだった。2DDとか2HD、2HC(事実上2HDと同じ)というタイプがあって、2HDのほうが、ほんの少しだけ容量が大きかった。大きいといっても1.44MBだから、今なら画像1枚も入らないかもしれない。
でもテキストだったら、なんとか200ページ分ぎりぎり入った。
原稿に添える図表は類書からコピーして、どの項目に入るかを指定しておく。それをデザイナーが、本の体裁に合わせて引き直すのである。
プリントアウトした原稿、図表のコピー、フロッピーディスクを「原稿3点セット」と、勝手に呼んでいた。
原稿3点セットを編プロへ郵送する。それを編プロが受け取ったときが「納品完了」だ。
郵便局の窓口へもっていくリミットが、普通郵便で締め切り前日の午前中。プリントアウトに時間がかかって午後にずれ込んでしまったら、速達にしないと間に合わなかった。
その後、通常だと校正が戻ってくるはず。だが、このときは、戻ってこなかった。
そして3カ月ほど経って、
「本が出ましたよ」という添状と一緒に、見本版が2冊、編プロから送られてきた。
一般的に、版元からもらえる見本版は10冊。それを編プロと私で分けるから、ライターの分として2冊が割り当てられたのだろう。
さっそくページを開いてみる。
図表は、デザイナーの手で見事に生まれ変わっていた。気になるのは文章だ。一字一句検証したわけではないが、ざっと見渡したところ、私の原稿にほとんど手が加えられていない。
「あれで良かったんだ」と安心したと同時に、
「あれで良かったの?」という一抹の不安も覚えた。
駆け出しも駆け出し、ヒヨッ子にもならない、頭にまだ卵のカラをかぶったような新人が、ビジネス書を1冊書いて出版してしまったのだ。もちろん自分が著者ではなく、編著として編プロの名になってはいるけれど、
「本当にいいのかな?」というのが、正直な気持ちだった。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
