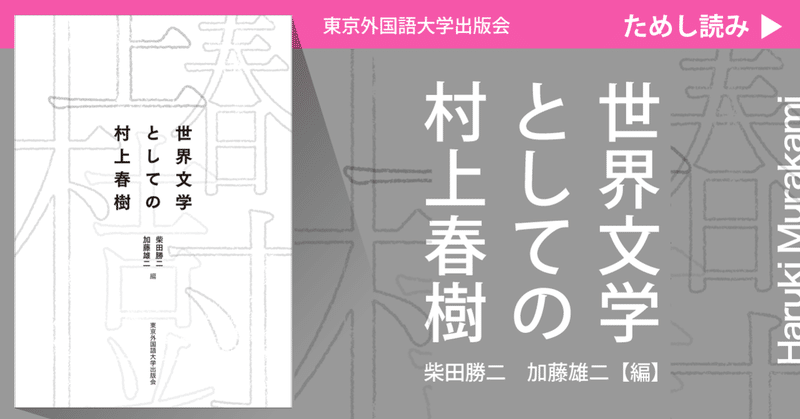
[ためし読み]『世界文学としての村上春樹』「まえがき」
グローバル化へ向かう状況に驚くべき柔軟さで適応し、絶えず新しい状況を作り出してきた村上春樹・Haruki Murakami。2015年刊行の本書は、その村上春樹文学のグローバルな「現在」を、日本、アメリカ、フランス、台湾、韓国の気鋭の研究者・翻訳家による論考、さらに中国、ロシア、フランス、スペイン/メキシコ、ポルトガル/ブラジルなど、各語圏の研究者によるエッセイから読み解き、捉えなおします。
本書の編者の一人、柴田勝二氏による「まえがき」で、各論考、エッセイのエッセンスを紹介しています。「まえがき」をここに公開します。
【目次】
まえがき 柴田勝二 ←公開
Ⅰ 村上春樹と世界
システムのなかの個人 村上春樹・カフカ・オーウェル 柴田勝二
無意識と神話の心 村上春樹の作品におけるバランスの問題 マシュー・ストレッカー
地方性から普遍性へ/普遍性から地方性へ コリーヌ・アトラン
村上春樹と英米作家たち 加藤雄二
『螢』、明滅する生への希求 『わたしを話さないで』と『其後 それから』に言及しつつ 蕭幸君
羊男は豚のしっぽの夢を見るか? 村上春樹の〈キャラクター小説〉化をめぐって 柳原孝敦
ライトノベルとして春樹を読む 趙柱喜
Ⅱ 座談会 世界のなかで村上春樹を読む
柴田勝二 都甲幸治 柳原孝敦 橋本雄一 加藤雄二(司会)
Ⅲ 外国語のなかの村上春樹
荒野の始まりと远东(ファーイースト)ダイアローグ・テーブル 橋本雄一・馮英華
「距離」を取る難しさ 崔在喆
村上春樹/Haruki Murakamiをめぐる翻訳・批評クロニクル 高橋留美
複雑な単純さ コリーヌ・アトラン
「ソ連崩壊」から見る現代ロシアの村上春樹ブーム 笹山啓
メキシコ若手作家の戦略と村上春樹 久野量一
読まれ始めたばかりの村上春樹 クニャ・ファウルスティヒ・ユーリ 武田千香
Ⅳ 村上春樹研究への眼差し
〈春樹論〉の流れと広がり 柴田勝二
村上春樹文学翻訳状況一覧
村上春樹関連年譜
あとがき 加藤雄二
執筆者紹介
◇ ◇ ◇
まえがき
村上春樹を現代日本の代表的な〈国際作家〉として取り上げるのは、もちろん目新しい試みではない。本論中でも言及しているように、これまでもそうした観点から編まれた本は上梓されており、それぞれに工夫を凝らした意匠で村上文学のもつ国際性、普遍性、あるいはそれと対比される日本文学としての特質を明らかにしようとしてきた。
本書もそうした試みの一環をなすものであることを否定するものではないが、編者が教員として勤める東京外国語大学は、こうした探求をおこなうのにふさわしい条件をもっていることも事実である。専攻語として二七言語の教育がおこなわれ、世界各国・各地域の言語・文化を研究する人間が集まっている本学の環境は、現代日本文学という母国の文化を外部からの眼差しを活用しつつ捉えるためにも強力な条件として働くはずである。外国文化を専門とする教員のなかにも村上春樹に一家言を持つ者は少なくなく、論考が公にされている場合もある。また当然研究のネットワークによって、外国で村上春樹に取り組んでいる研究者の情報もあり、そうした条件を生かすことによってこの〈国際作家〉をあらためて多角的に捉えることができるのではないかというのが、本書が編まれた起点的な動機である。
編集は日本近代文学を専門とする私(柴田)と、アメリカ文学の専門家でありまた村上文学の精読者でもある加藤雄二氏の協同によって進められ、学内、学外の様々な地域文化の研究者に加えて、アジア、欧米を中心とする外国在住の研究者・翻訳家に参加していただくことを旨として交渉をおこなった。結果として日本、アメリカ、フランス、台湾、韓国の論者の論考を収載することができ、また海外での翻訳、研究の状況として、中国、韓国、英米、フランス、ロシア、スペイン、ポルトガル(ブラジル)の各語圏での情報を紹介することができた。もちろん交渉したものの、公私の多忙などの事情によって論考、エッセイを得られなかった場合もあり、必ずしも文化地域を網羅することができたわけではない。とくに村上の読者が少なくないドイツとイタリアからの論考を収載するに至らなかったのは残念であった。しかし少なくとも本学で編まれた批評集としての色合いは出すことができたのではないかと考えている。
第Ⅰ部に収載されている海外からの寄稿の執筆者をここで簡単に紹介すると、アメリカのマシュー・ストレッカー氏は、ワシントン大学その他で日本文学を専攻し、東洋大学に勤務した後、現在ウィノナ州立大学で教鞭を執っている。Haruki Murakami’s The Wind-up Bird Chronicle: A Reader’s Guide (2002)、Dances with Sheep: The Quest for Identity in the Fiction of Murakami Haruki (2002)に次いで、二〇一四年に三冊目となる村上論The Forbidden Worlds of Haruki Murakami(2014) を上梓された。研究所の書評なども多数発表しており、現在アメリカ合衆国と世界で最も活躍している村上研究者の一人である。氏の論考に見られる一見日常的に映る村上作品のなかに、それを相対化する異界への回路がはらまれており、それがユング的な集合的無意識とも照応する形で神話的・古代的世界へと読み手をいざないつつ、その世界の多様性と普遍性を示唆するという読解は、欧米系の論者のひとつの代表的な観点でもあるが、村上文学の魅力の在り処を確かにいい当てているだろう。
台湾の蕭幸君(ショウコウクン)氏は谷崎潤一郎論で本学の博士号を取得した気鋭の研究者であり、現在は台湾に帰国して日本文学の研究・教育に携わっている。関心は谷崎にとどまらず明治期から現代に至る広範囲の文化現象に及び、近年は日本の植民地時代における台湾の映画文化の探求なども手がけている。台湾と日本の文学作品の比較研究も当然自家薬籠中のものであり、単に表層的な比較にとどまらず、アジアという社会的環境を共有することによってもたらされる、互いの人間の意識的な通底性と異質性を仔細に分析する手腕の持ち主である。今回は現代作家の頼香吟(ライシャンイン)と村上の対比に加えて、カズオ・イシグロという村上に劣らぬ国際的作家をも論評の網のなかに置く視野の広さを備えた論考を寄せていただいた。
フランスのコリーヌ・アトラン氏は、同国における現代日本文学の代表的な翻訳者の一人であり、村上春樹を中心として精力的な紹介をおこなっている。日本とフランスの間に文化的な橋を架ける貴重な存在である。本書に対しては批評的な論考と翻訳をめぐるエッセイを寄稿していただいたが、全体としては村上文学を翻訳することの問題点に触れつつ、その世界の普遍性と特殊性が論じられている。アトラン氏によれば、村上の作品は実はたいへんフランス語に移しやすい対象であり、ともするとそこに〈日本〉が埋もれて見えなくなってしまう傾向さえある。しかし村上文学はやはり紛れもなく日本文化の所産であり、むしろ翻訳においてその〈日本性〉を浮上させることに腐心するのだという。登場者の名前を外国人のそれに置き換えれば、そのまま〈外国文学〉になってしまうというのはしばしば耳にする村上文学への評だが、フランス語という媒体においてそれに抵抗するところにアトラン氏の翻訳者としての面目があるのだろう。
韓国の趙柱喜(ジョジュヒ)氏は村上春樹研究によってやはり日本で博士号を取得した新進の研究者で、サブカルチャーの観点から村上春樹を捉える研究に特色がある。本書に収載された論考でも「ライトノベル」として村上作品を読もうとする試みが示されており、日本と韓国のサブカルチャーとの重なりに論及された趣旨には強い説得力があるだろう。同時に両国の大衆文化の接近ぶりがうかがわれるのも興味深い。もともと村上は日本の私小説的な湿潤な風土に逆行した作風によってその個性が認知された作家であったわけで、趙氏が指摘するその「軽さ」が内外のサブカルチャーへの親しさをはらんでいるのは当然かもしれない。よしもとばななや山田詠美にしても漫画作家たろうとしたりまたその活動をおこなったりしていた時期があるが、サブカルチャーに通じていることは結果的にその作品世界の色合いをつくるだけでなく、その創作の源泉となっているとも考えられ、現代文学の生成力として看過しえない意味をもっているだろう。
なお日本の学外からの寄稿者である柳原孝敦氏は現在東京大学に勤務しているが、二〇一三年九月まで本学でスペイン文学の教鞭を執っていた研究者であり、本書では趙氏の論考とも通底する「キャラクター小説」という観点から村上文学を論じている。大塚英志の論を踏まえて書かれたこの論考では、「羊男」や「牛河」のような印象的な登場人物が、性格よりも漫画的なイメージが先行する形で造型されている様相が述べられているが、柳原氏によればこうした漫画的なキャラクターはスペイン語圏の作品にも見られ、現代文学の普遍的な特徴をなしているようである。
柳原氏が語っていることではないが、こうした漫画的ともいえるキャラクターの登場が、作品のリアリズムを相対化し、ストレッカー氏の強調する異界の形成に寄与していることは見逃せない。『1973年のピンボール』の「208」「209」にしても、現実世界の生活者ではないことは明らかだが、以前述べたことがあるように彼女たちは執筆時の一九八〇年代から送り込まれた形象であり、彼女たちのキャラクターが「僕」の生きる周囲の現実と違和をきたすことによって、この作品世界に複数の世界が共在していることが示唆されるのだった。『海辺のカフカ』のナカタさんなども現実には存在しえないコミカルであると同時にシリアスなキャラクターだが、こうしたキャラクターの存在が趙氏のいう村上の持つ大衆性の一つの所以をなすと同時に、現実世界の足元を崩して異界へと読み手をいざなう力の在り処ともなっていることは看過できないだろう。
英米文学との文脈を検討しつつ、「こちら側」と「あちら側」、意識と無意識など様々な二重性の輻輳をはらんで展開していく村上作品の機構を仔細に論じた、加藤氏の論考と合わせて読むと、村上春樹の創作における戦略というべきものが浮かび上がってくると思われる。また外部世界のシステムに絡め取られ、そこで自己を失いつつ同時にそれを生の条件として日々を送る登場者たちの様相を、カフカ、オーウェルとの比較のなかで論じた拙論も、こうした現実と非現実が錯綜する村上の世界と照らし合うことはいうまでもない。
こうした村上春樹の二重性は時間的な次元でも成り立っており、加藤氏の司会により柳原氏、柴田、及び本学で現代中国文学を講じる橋本雄一氏に加えて、アメリカ文学の研究者で先鋭な村上論の書き手でもある早稲田大学の都甲幸司氏を迎えておこなわれた第Ⅱ部の座談会では、村上のポストモダン性が議論の焦点となりながら、むしろポストモダン的ではない面の方に重きが置かれることになった。現在と過去を交錯させるのは村上の得意の手法の一つだが、『ねじまき鳥クロニクル』から『海辺のカフカ』や『1Q84』に至る流れのなかで顕著になってきたモダン的世界への回帰の志向は、ある意味では村上の本来の立ち位置を物語るものであるのかもしれない。
なお海外における村上文学の翻訳や受容の状況を紹介した第Ⅲ部では、中、韓、英、仏、露、スペイン、ポルトガルという語圏からの情報を収載しているが、本学の特色がうかがわれるコーナーともなっていると思われる。スペースの都合もあり内外にわたる執筆者の紹介は割愛させていただくが、様々な観点から興味深い情報を寄せていただいた執筆者の方々に深謝したい。
二〇一五年一月
柴田勝二
【編者紹介】
柴田勝二 しばた・しょうじ
東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授。専門分野は日本近代文学。明治・大正期から現代にいたる近代文学を幅広く研究・評論している。
加藤雄二 かとう・ゆうじ
東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授。専門分野はアメリカ文化、批評理論、比較文化論。国内外で活動し、小説、詩、音楽などを広く研究している。

【書誌情報】
世界文学としての村上春樹
[編]柴田勝二 加藤雄二
[判・頁]A5判・並製・296頁
[本体]2700円+税
[ISBN]978-4-904575-40-6 C0095
[出版年月日]2015年2月25日
[出版社]東京外国語大学出版会
※肩書は本書の刊行当時のものです。
※東京外国語大学では2021年現在、28言語を専攻語として開設しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
