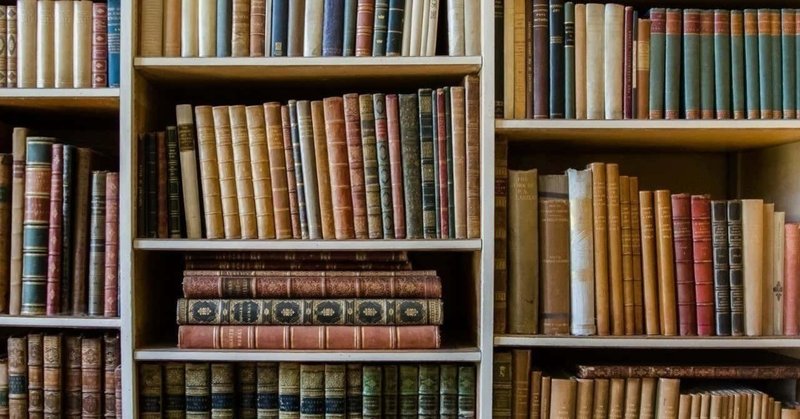
ゆるやかに、しなやかに、何より力強く
こんにちは!今回は一冊本を紹介!
流動型『学び合い』の授業づくり
— つっち~🌪️私立小の先生📮📚️ (@tuchiblanka) February 23, 2020
遅いインターネット
Amazonから届いたので随時読み進めます。
(シン・ニホンもほちい)@naotaka007 @wakusei2nd pic.twitter.com/wX28Jf1XV0
高橋先生の著書 流動型『学び合い』の授業づくり!
読み終わりました~。少し感想を書かせていただきます。
その前に・・・
私と『学び合い』についての関係性について先に述べておきますね。昨年度西川先生の本、水落&阿部先生の本、三崎先生の本と3種類『学び合い』関連の本を読み、算数の授業でゆるく実践をしていました。今年度はその実践から得た手応えと反省を生かして社会科の実践にエッセンスを取り入れる形で授業づくりをしました。(「質問作り」もやっています。)
昨年度の自分は1時間での実践、複数時間の実践に取り組み、「何か足らないな・・・」と頭打ち感を感じていました。今年度は単元を通しての実践を行い、まずまずの手応えと、結局45分の枠には縛られるなぁという閉塞感を抱きながらの実践終了となっています。
そもそもの話
そもそも、僕はどの教科でも毎時間『学び合い』の授業をやるような、がっつりとした実践者ではないですし(教科担任ということもあり)、もともと自分が学んでいた授業づくりの理論と親和性の高い部分で参考にしている程度なので、「それくらいの距離感の立場から見た感想」ということを前提として以下、読んでもらえるといいかなと思います~。
トピックは3つ!
①「見たいものしか見えていないかもしれない」という自覚
見取ることの難しさ、自分もひしひしと感じています。『学び合い』の弱点?というトピックに書かれているように「自分が見えているもの、感じていること」は「そのように切り取っただけ」ではないのか。と自問自答できるようになりたいと思いました。自分の実践に自信を持ちつつも批判的な視点で見つめることは自分もしていきたいと思います。(また、そのような議論ができる仲間がいるのはすごく強みですね)
②誰でも葛藤しながら前進している
私がつくった「私に頼らないクラス」は、本当に私に頼らないのでしょうか。
このフレーズが響きます。矛盾や葛藤の中で前進しようとしている強い思いを感じました。自分も常に迷っています。結局は「自分が環境を整えているから」だけでは?と。ただ、環境づくりの重要性はわかるし・・・それが僕らの仕事かなとも思うし・・・。悩みます。
③自分の手を離れたあとのことも考える
②とも繋がるトピックですが、進級・卒業・進学などの節目を越えて、環境が変わった時、自分の手立てはホントウにその子のためになるのだろうか。そもそも「その子のために」を大義名分にしてコントロールしようとしたり、自分勝手な実践でマウントをとったりしていないか。そのあたり深く考えさせられました。ビジョンもなく、「子どもたちに任せていますから!」は無責任だよなあ・・・。
終わりに
いやー、良い本でした。高橋先生の思いやストーリーがモリモリと綴られていて、教室の風景や授業での話し合いの様子がすごくイメージしやすかったです。何より、失敗談や悩み、抱えている葛藤を書いてくださった、その勇気。原体験として記してくださった、震災。それをなんとかして「教育」の力で乗り越えようとされてきた高橋先生の胆力と愛情。素敵な本です。もちろん、これから『学び合い』を実践しようとする先生にとっても道標となる一冊になるでしょう。
僕もがんばります!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
