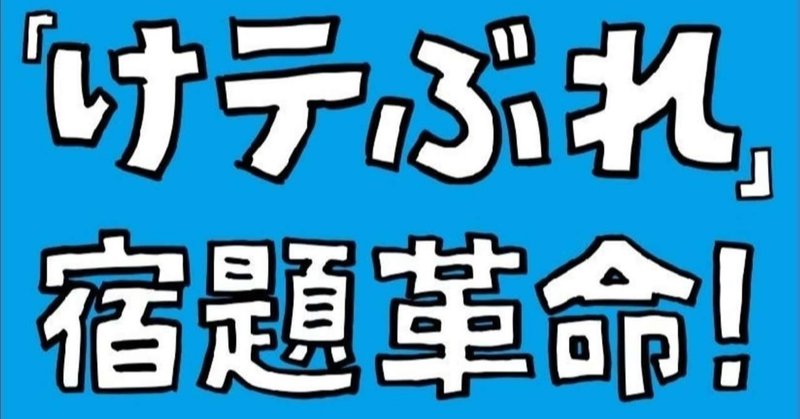
教科担任制でもできるけテぶれ実践!④
はい、おはようございます。休校やらなんやらで皆さん疲労困憊かと・・・。お疲れさまです。そんな時こそ思考をめぐらし、自分たちにできることは何か、全力で考えたいですね・・・(。-ω-)
前記の記事はこちら!↓
過去二回の記事ででステップ①「統一の宿題のテコ入れ」を紹介しました。
ステップ② アウトプットの場を確保せよ!!
統一の宿題を改善しまして、本気の丸付けができる子が増える。分析の視点がわかり、自分の学習を見つめることができるようになってくる。しかし・・・何かが足らない。統一の宿題が作業的なものから脱却しきれない・・・。
そうだ!アウトプットの場(小テストなどの実力チェックの場)がないんだ!!と気づいたのは導入から随分経ってからのことでした。SYOBON(´・ω・`)
自主勉は「単元テスト」というアウトプットの場に向かって取り組んでいくので、子どもたちも様々工夫をしながら取り組んでいました。交流会も盛り上がり、テストに向かう姿勢も、大分析に対する熱量も変わってきます。
だが!通常の宿題の作業感がまだまだ抜けない!なぜだ!どうしよう!と悩んでいるときに、ふと「宿題と同じ問題を小テストにしたらいいやん」と思いつく。そんなこんなで実践したことを「アウトプットの場の確保」として今回紹介します。
ゲリラ的に小テストを実施してみた
ある日の宿題が、少しひねった図形の問題だったんですよ。取り組みが甘い子が続出で・・・。そこで、次の日に急に「はい、これ解いてごらん」とモジュールで問題を渡すと・・・教室がザワザワ。
「あれ、昨日やったはずなのに・・・」
「余裕っすわー(ドヤァ)」
「・・・(答え映してたからやべぇ)」
みたいなリアクションでした。3人目の子は後で正直に教えてくれたので知ることができましたw
その姿から何を語るか
そこで「何でできないんだー!サボてるからだろー!チャントヤリナサイヨー!!」となると、せっかくのチャンスが台無し。
「どうしてスラスラ解けたのか。」
「どうして解けなかったのか。」
「じゃあ、これからどうするのか。」
子どもたちそれぞれが、自分の努力を認め、サボり心には向き合い、成長へと繋げる。そんなチャンスを生み出すには、やはり宿題でやっていることがどんな価値に繋がるのかを考えられるような場をこちらが保証しなければいけないと思います。
その宿題、やらせっぱなしになっていませんか?
教科指導の中でサイクルを回す
この流れは、小学校的な統一の宿題に効くだけでなく、教科担任として出した課題と繋げることもやりやすいですよね。自分の授業内で見届けることが可能なので、結果から子どもたちに語りかけることも可能だと思います。
そして、小テストの価値も変わってきますね。できない姿をペナルティーで追い込むのではなく、次への足場に。
とりあえず、今回はこのあたりで。具体的に教科指導との連動について、書いていこうかなと思ってます。多分。きっと。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
