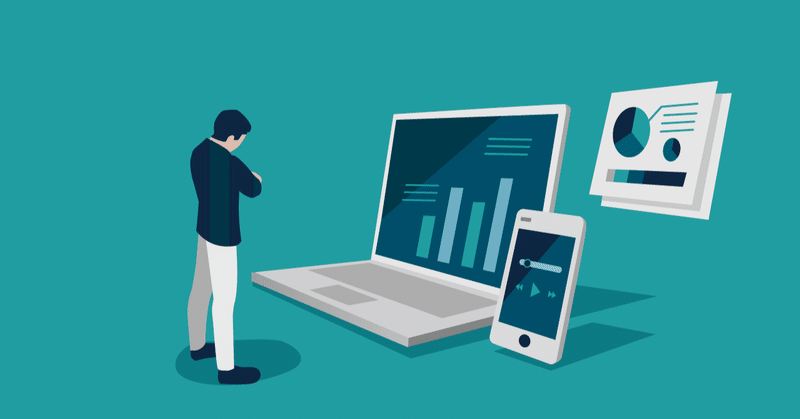
作家自身のマネジメントとは ~「作家2.0」に至らないの理由
先日、とあるラノベ作家が「感想がない」、「書きたくない」といって活動を休止を宣言した。この事は多少なりとも波紋を呼んだ。
ただ、これらの理由は私が思うに建前、いいわけだろう。
例えば、定食屋で「ごちそうさま」と客が言わないから店をたたむなど言った所で、何を馬鹿な話をしていると思う前に単に客が入ってないだけの話と簡単に推測できるだろう。
当然、この件に関しては真相は分からない。
だが、この程度の作家の言い分を素直に信じられるほど、現状は甘くはない。このコロナ渦の状況も相まって、どの業種であっても今までの仕事が成立していない。
こんな中で定食屋が「ごちそうさま」を言って貰えなかったからとやめるといっても、余計に信じる者はいないだろう。実際、この状況下で普通に客が入らず、店をたたんでいるケースは多い。
それにこのようなケースはここ最近でもこの一件だけでもない。そして、その背景はそれぞれで違っており、「感想がない」といったものでない。病気等で従来通り体が動かないといった話もちらほらあった。これも一件、二件の話ではない。
ただでさえ、紙の本が売れないと言われて続けている近年、すべてが今まで通りには行かない。更に追い打ちをかけたのがこの状況である。また、自身の変化もプラスされれば、そう簡単に立ち回りが出ないの当たり前である。
そこで「感想がない」、「書きたくない」といった、誰からも共感されそうな理由を言ったところで、それは綺麗事でしかない。
別に悪く言う気はないが、この状況下はもはや個人だけの話ではない。誰もが抱えている問題である。
私だって最近「仕事がない」、「お金がない」と嫌というほど聞いて、体験している。だから、同様なことは今は誰だって言えることである。
当然、愚痴を言うだけで解決するわけではない。少しは気は楽にはなるが。
なので、今回はこれにまつわる話を軸に語ってきたい。
作家自身のマネジメントとは
とある作家がやめた理由でもある「感想がない」、「書きたくない」、この二つを軸にして作家自身としてのマネジメントについて考えてみたい。
先に「書きたくない」。これは書籍にならない、要するに金を得ることができなければ、ここでの「書きたくない」はまったく別の意味となる。
作ったモノが売れないのに、作り続けることは損失以外の何もでも無い。
逆に売れているモノを作らない理由などありえない。
「書きたくない」というのは素直に「売れない」=「作れない」=「書けない」という構図で考えるが普通であろう。ここに関しても、とある作家も作品が売れてないことは示されていた。
「感想がない」も同様である。売れない以上、読者の声は当然小さい。また、「感想がない」は単純に質が良くも悪くもないという点に結びつく。
質が良ければ賞賛が、質が悪ければ苦情が来る。そのどちらでもなければ、本当にコメントに困る。
これは何も作品だけの話ではない。商品、食べ物であっても同様。「感想がない」モノとは感動を呼び起こさないだけである。
つまりは「感想がない」、「書きたくない」とは売れておらず、質もそこそこであると考える事が出来る。
ピーター・ドラッカーは著書の中でマネジメントを「組織に成果をあげさせるための道具、機能、機関」と定義している。
売れるという成果が達成できてないことは、マネジメントができてない証拠である。
そして、自身が書きたいモノを書いて、感想を得ることは今の時代、難しいである。いや、過去であっても同じかもしれないが、今は余計に難しい。
音楽や映画を例に出せば分かだろうが、ヒット作を生み出している要因は作品よりもプロデューサーによる部分が大きい。時代を読んで、適した題材を世に送り出しているのである。
そして、ヒット作は大きく感情すら揺さぶってくる。
時代遅れという言葉があるように流行は常に変わり、意図的に作るモノでもある。これらを読み取るのは職としてプロデューサーがいる。
名の売れた音楽家であっても、凄腕のプロデューサーの力を借りることはよくあることだ。
最近では作家自身であっても、作品、また自身に対してもこういったプロデュースが必要となっている。それをしないことには作品が売れることはもちろん、感想を得ることすら難しいのである。
また、こういったプロデュース、マネジメントが作家自身に出来なくとも、編集者といった職が存在する。これは会社であっても営業部等の部署があると同じである。何も個人プレイである必要も無い。
次はそういったマネジメントで作品を作り続ける場を例に語っていこう。
「小説家になろう」では文章力よりもプロデュース力が求められる
これもTwitter上でも話題になった話だが、「小説家になろう」でのランキング攻略法があった。結局の所は「小説家になろう」での流行に乗ること、読み手を飽きさせないことなど、文章力は二の次にした話である。
文芸としてみた場合、これらの姿勢は正しいかどうか、誉れがあるかは一旦抜きにする。
ただ、小説投稿サイトでPV数を稼ぐという事は、動画投稿サイトと比べて見ても正しいと言える。見て貰えない作品には意味がないからだ。
そのため、似たようなモノが溢れたり、似ているだけで中身がなかったりとする。だが、そんな内容であってもPV数を稼ぐ事は出来る。
そこも踏まえると、小説投稿サイト、動画投稿サイトでのランキングに乗るためにはプロデュース力、またマネジメントが必要である。
動画投稿サイトであればサムネイルから、小説投稿サイトならタイトルからといった具合に中身の見えない商品であっても、売るためにはキャッチコピーが必要となる。そして、受け手にあった内容を提供する。
だからこそ、ただ良い作品を作っても、ランキングに乗るのは難しい。まずは受け手に受けて取って貰う必要がある。これが第一条件である。
それが出来なければ、見て貰う機会すらない。結果、売れない、感想がないといった具合になる。そして、掴んだら離さないように冒頭から引きつけなくてもいけない。
流行を読み、受け手の需要にあってなければ、例え質が高くとも駄作と一緒に埋もれてしまうのだ。
ただし、小説投稿サイトのランキングに特化しすぎた作品作りはニッチになりすぎた。結果、一般市場に出た際は通用しにくい結果ともなった。それが悪名としての「なろう系」として揶揄されることになっている。
それでもニッチな需要がある為、売れないことはない。だから、書籍化という波はいまだ健在で、一定の市場も存在している。
確かに「小説家になろう」といった小説投稿サイト発の作品は爆発的に売れた作品も存在する。ただ、全体を見ればどうだろうか。
小説投稿サイト発の作品、全てが優れているのであれば、ラノベのランキングは塗り替えされているはずである。
このランキングでも小説投稿サイト発の作品は半分ぐらいある印象だが、それでも小説公募から出てきた作品も強い。また、小説投稿サイト発であっても売り上げランキングの性質上、古くからやっている作品がどうしても上位を占有してしまうのもある。
また、アニメ化効果なども売り上げには関わってくる。こうなると作家一人の力ではなく、ヒット作を押し出すプロデューサーの部分が出てくる。
そこにも世に求められている需要を満たさないとアニメ化なども企画は進まない。そして、アニメ化してもダメなら、売り上げを含めて効果も発揮しない。
売り上げという点でも真に良作である事よりも、時代、流行にマッチしたプロデュース、マネジメントをしてなければ売れないことにもなる。
「作家2.0」に至らないの理由
ただ、ここまで語ってきて作家ではない筆者が何を言っているのだと思う人もいるだろう。
しかし、私自身、生業、生活を立てるための仕事では工程管理といったマネジメントに関して携わってきた。そして、趣味の延長で電子書籍も出している。
これらを総合すれば、異業種から見た作家業における問題は十分に指摘は出来るだけの知見はもっていると考えている。当然、異論もあるだろう。そこは否定しないし、ご意見等は受け付けている。
しかし、こんな出版業界に籍を置かず、趣味で文芸にいそしむ私だからこそ語れる側面があるとだけは理解して欲しい。
さて、そんな異業種から見ても、今の作家像というのは従来のスタイルに固着していると思う。
別にこのブログに書かれている事だけではないが。
テレビなどで見ていても、今の工芸作家は独創的だ。いや、昔からの工芸品では今の生活様式にマッチしてないから必要とされていない。
お茶の飲む際に茶釜でお湯を沸かすなど、正式な場でもない限り今は誰もしない。そもそも、それら茶道具の大半が日常使い出来る人間など限られている。
だからこそ、従来の形ではなく今に適した形に変えていく必要が工芸作家には求められ、結果として独創的となっている。
例えば、茶道具はコーヒーを飲むための道具に変えるなどだ。
そして、優れた工芸品、職人に如何なる賞、箔を与えても、それに見合った使い手、買い手の方が今はいない。
もはや、工芸品とはこうあるべきでいったところで、ミスマッチでねじれた構図になっている。
これは工芸品に限った話ではない。農業とて協会に頼らない独自の品種、販売網を個人で形成する話なんて、近年では良く聞くだろう。また、気候等の条件に対しても勘を頼りにするのではなく、システム化するなども一つの変化だろう。
文章を書く人間、読む人間も同様で、今の時代、紙から電子媒体に文章をシフトしている。小説投稿サイトも然り、キュレーションサイトも然りだ。
作家、ライター業自体も紙に固着することは危険となっている。もはや、ネット専門でライター業をしている人も少なくないだろう。
そもそもがネットメディアという媒体が様々な形で存在して、既存メディアを押さえるほどにシェアを獲得している。
こんな時代では作家のバージョンアップした姿、あえて簡潔な比喩で言えば、「作家2.0」となっていく必要性はある。
だが、作家、こと小説家に至っては小説公募、名のある文学賞などの権威、ようするにお墨付き、看板がなければ真の意味での「先生」にはなれない職業といえる。
それに先のラノベの売上ランキングを見ても、小説公募から出てきた作品が強いのも、ここに理由があると言っていいかもしれない。
そして、作家になりたい人の目標とは、ここにあるのだろう。「先生」と呼ばれたいのであって、お金を儲ける為の作家になりたい人など少ない。
そもそも、「小説家 収入」と検索すれば簡単に分かるが、個々に飛び抜けていても、平均とすれば一般的なサラリーマン以下、更には安定性もない。
つまりはよほどの才能等がなければ、お金を儲ける仕事ではない。金を得ることが出来ないモノをもはや、「職業」と言っていいのか疑問ともなる。
そのためにも名のある文学賞などでお墨付き、看板がないと作家として売りにもならない。
私自身、過去にちょっとしたアンケートを採ったことがある。
少し参考までに質問させて下さい。
— T.T.T.WORKS(トリオール.ワークス情報局) (@TTTworks_horsph) May 27, 2020
小説投稿サイトで書籍化された方、もしくは書籍化を目指している方でどの程度の部数を目標としていますか?
総数19票のため精度は低いが、それでもこのアンケートで1万部超え目標とした人が30%(約6票)といる。
この1~10万部の間というのは、出版部数をある程度理解している人なら分かる様に、基本1万部ぐらいが初版で刷られる。そして、10万部程度ヒット作といわれる。
このアンケートを開始した時点で私は1万部超えを答える人はほぼいないと考えていた。それは作家という職業を理解していれば、最低でも10万部超えを狙わなければいけないことからだ。
つまり、1万部超えが目標などでは、ただ作家になりたいと言っているだけなのである。職としては考えていないのだ。
今回に辺り再度アンケートを取り直したが、収集率が悪いのが私個人の発信力の弱さを痛感させられる。それでも結果としては前回とほぼ同様である。
小説投稿サイトで書籍化された方、もしくは書籍化を目指している方でどの程度の部数を”目標”としていますか?
— T.T.T.WORKS(トリオール.ワークス情報局) (@TTTworks_horsph) August 26, 2020
前回も同様のアンケートをしたのですが、参考としたいので皆様のご意見をお聞かせ願えませんか。#拡散希望
そして、私が取ったアンケートの設問である1000万部超えであっても、極端な数字ではない。先のランキングで示されているよう、1000万部超えでランキングのTOP10にようやく入れるのだから。
むしろ、1億部ぐらいで夢があるなといったレベル。ただ、これでも名作漫画であれば余裕でクリアしているレベルでもある。
しかも今の時代なら、1万部程度を目標とするのならば、電子書籍、同人誌でやった方が収入的にも上であり、部数的にも達成は難しい話でもない。
Kindleでセルフパブリッシングでの売り上げで一躍有名になった『Gene Mapper -core-』は7000部の売り上げとある。
漫画の同人誌等を例に上げると更にエグいレベルとはなるし、話は脱線しかねないからやめておこう。
ただ、それは作家になりたい彼らには、自身で売る選択は余り取らないだろう。
なぜなら、作家になりたい真の目標は「先生」と呼ばれたいだけである。賞という権威で評価されることが目的なのである。お金はそれに付随すると考えているのだろう。
また結果として、やめる理由に「感想がない」、「書きたくない」といった言葉も出てくるわけでもある。「売れない」という言葉ではなく。
ゆえに「作家2.0」にほど遠い以前に、作家という職業は明治の文豪から変わらぬ様な従来スタイルに固着しているのである。
自身をプロデュースすることもマネジメントもすることもなく。
なら、「作家2.0」とはどんな形なのだろうか。これは次で語っていこう。
オリジナルの書籍ブランド
TYPE-MOONにはオリジナルの書籍ブランド「TYPE-MOON BOOKS」がある。ただ、書籍ブランドといってもISBNコードを取得していないため、書店には並ぶことはなく、ある種、同人誌と似た位置づけである。
それでも書籍ブランドとして展開している。
余談とはなるが、『小説家になろう』の中で書報掲載するには出版社・編集者を通したモノとされている。また、ISBNコードが必須項目となっている。
ただ、ISBNコードを取得することは今の時代個人であっても難しくない。
ゆえに、『小説家になろう』での書報掲載は個人出版に限りなく近い形でも抜け道はある。
さて、話を「TYPE-MOON BOOKS」に戻すが、ISBNコードがない書籍に対して、どのような価値があるだろうか。
先にも言った通り、書店には並ばない書籍だ。ただ、商品としては店には並んでいる。Amazonでも購入は出来る。
オリジナルの書籍ブランドとは何モノなのか。
そして、「TYPE-MOON BOOKS」での代表作は『Fate/Zero』であろう。この作品のこの後の展開、ムーブメントを考えるとどうだろう。
(『Fate/Zero』の文庫は星海社から出ているが、初出は「TYPE-MOON BOOKS」でのコミックマーケットでの販売からである)
また話は少し逸れるが、欧米の映画業界では、ハリウッドのメジャースタジオの傘下に属していない映画はインディペンデント、インディーズ映画として扱われる。
そのカテゴライズでは『スター・ウォーズ』シリーズの新3部作はジョージ・ルーカスが自ら制作費を出資しているため、「世界で最も贅沢なインディーズ映画」と言われている。また、自ら出資したことで、製作において横やりが入らず、脚本等の改変が避けられている。
ここは私の考えとなるが、TYPE-MOONもこういった流れは意識していると思う。自分の作品、キャラクターコンテンツを自社で管理することで、他社から意図しない改変を避け、収益を守る手であると。
そして、管理面だけでなく、独自の書籍ブランドを持つことは出版社に頼らない総合メディア事業の形成を考えているのだと思う。
そもそも、TYPE-MOONは同人ゲームから出てきた団体。
ある程度の制作から販売までの流れは経験として持っているだけでなく、そこに関わる人脈もある。わざわざ、何処かに仲介にするよりは自分達でやった方がデメリットはあるにせよ、メリットの方が上となるのかもしれない。
ただ、ここに関しては深く語るには、TYPE-MOONのブランドの設立から触れて語る必要があると思う。長くもなる為、話はここまでとしたい。
だが、今までも語った内容と照らし合わせると、これからを生きる戦略として一つの形だと思う。
個人ブランドでも戦えるスタイル、これも「作家2.0」と言えるのではないだろうか。そして、TYPE-MOONというブランドは『Fate/Grand Order』で明らかになったように、何十億という利益を生み出している。
これほどの成功例、過程もかなり明らかになっているのに、第二、第三のTYPE-MOONを目指す若き団体が世間を賑やかせてもいいはずである。
だが、今の所そんな話は聞かない。『Fate/stay night』でさえ15年と経っているのに。
そもそも、オリジナルの書籍ブランドは過去にもあった。それは姉妹社である。そう、『サザエさん』のコミックを出していた会社だ。
『鬼滅の刃』はなぜ人気絶頂で完結したのか?
さて、もう一つ、作家像に対して新しい風が吹いたと感じた話題を語ろう。
『鬼滅の刃』の連載完結は衝撃だった。確かに話の区切りでは特別、不思議なことではない。しかし、人気絶頂、これからも大きく稼げるコンテンツを完結させたことに驚かれた人もいるだろう。
そして、それは作家だけの判断ではなく、ジャンプ、集英社でも認めたことも更に驚きでもあったはずだ。
ただ、『鬼滅の刃』はスピンオフ、劇場版の公開など控えているため、完全にその作品群が閉じたわけではない。だから、稼げるコンテンツとしては継続している。そういう意味でも『鬼滅の刃』ブームを含めて、収束したわけでない。
この点では集英社としても安心できるポイントであろう。
となると、作品の完結は偏に作家の強い意志であったと推測できる。ただ、ここは噂はちらほらとあるが、真相としては分からない。
しかし、『鬼滅の刃』と類似したスタイル、人気絶頂で綺麗に完結したジャンプ作品は他にもある。これに関しては単行本内で作者自ら語っているため、それを元に考えてみよう。
その作品は『暗殺教室』である。この作品は初期段階で全体が決まっており、また、どのタイミングで打ち切られても話が綺麗に纏まるよう作られていると作者自ら語っている。
だから、人気があっても逆に引き延ばしは難しく、作品の完結は変えがたい部分があった。
ただ、その反面、作品の完結とともにアニメ、実写映画などのメディア展開も完結に向けて同時進行させていた。これは結末が決まっていたからこそ、出来る芸当である。
『鬼滅の刃』の完結に関しては、『暗殺教室』という前例があったからこそ成立したのではないかと、自分は考えている。そうでなければ、いくら稼ぎ頭となった新人漫画家がここまで強く言えることはないだろう。
それに綺麗に完結したところで次回作もヒットする可能性は絶対ではない。他のジャンプ作品から見ても、ヒット作の次回作は打ち切りになるリスクは高いぐらいだ。
なら、多少ダレてでも連載を続けた方が金銭の面でも安心はできるはずである。
ただ、そこも『暗殺教室』、『チェンソーマン』といったデビュー作からの次の作品でもヒット作となるケースも出てきている。ここもある程度、払拭している。
そして、これらはかなり売れることを前提として作られた作品であることは1話目から見て取れるからだ。ただ、『サムライ8 八丸伝』は…
これに関しては敢えて避けよう。
従来のジャンプ作品から考えれば、人気絶頂での完結はある種あり得ない様に見える。『ドラゴンボール』でも引き延ばしに関して、作中のキャラで明言しているほどの話である。
ただ、人気絶頂での完結は近年では前例はあり、それでも商機を失うことなく進められる事は証明されている。
この他にも、ジャンプ編集部全体でも意識改革が起こっているは見て取ることが出来る。作家だけでなく、編集部自体も新たな生活スタイルにあった漫画ライフの提供を考えている。
そういった背景があったからこそ、『鬼滅の刃』は人気絶頂であっても完結できたのかもしれない。それは次の世代に見据えたマネジメントの一環なのだろう。
漫画家と小説家の作家像の違い
割と作家、文書に接する職業に関してはステレオタイプの作家像という呪縛に捕らわれている気がする。ただ、プロの漫画家にはこの呪縛といった意識は少ない気がしていた。
それはなぜか、私自身最近になってこの違いに気が付いた。あくまで私の考えではあるが。
漫画家というのはそのペース配分上、専業、その上、複数人による分業制である必要がある。小説家等の作家は兼業でも成立して、基本は一人である。
この点でも漫画家はある種、会社経営であり、小説家は個人経営といえる。
ただ、どちらも個人事業主、フリーランスといえるので、この例えは少し違和感があるだろうが、あくまでこう考えると仮定したモノと理解して頂きたい。
また会社経営である以上、集団である。そして、漫画という技術的な作業である為、技術継承ととも精神的なアドバイスもされる。それはアシスタントからのデビューといった側面だ。
そして、アシスタントに対しても、給与が発生するため、漫画家はお金の管理も大事になってくる。会社経営の能力も必要となってくる。
一方、作家は集団の作業ではないため常に己が内面との向き合う時間が長い。そして、お金に関してもどうしても漫画家ほどの印象は薄い。それは兼業でなければ食べていけない点もあるからだろうか。
いわば経営者にならざる負えない漫画家と職人の様な精神性を持ち続けられ作家、小説家といったモノが違いではないかと、私はここ最近気が付いた。
そういった作業環境の違いがプロの漫画家にはステレオタイプの作家像という呪縛に捕らわれることが少ないのかもしれない。その反面、また違った重圧も存在するため必ずしも優れているといった安易な話にはならない。
そして、敢えて「プロの漫画家」としているのは、そういった経営者的な経験は「漫画家志望」にはないためである。
ここの「漫画家志望」に関しては『タイムパラドクスゴーストライター』で描かれている気がするので、気になる方はそちらを読んで頂きたい。
締めに向けて
延々と書いてきたことだが、当然これらは作家個人によって違う話である。
それでも、Twitter上での作家のやり取りを見ていると、皆が皆、ステレオタイプの作家像でいる様に感じる。
それを私個人、見ているとなんだかなあと思って今回このような形で書いたわけである。
恐らくといわず、今回書いた内容では指摘点、実際は違う点は多々あるとは思います。
ただ、このように書いた内容に関しては、そう感じさせる程度にTwitter上では似た話題が数カ月と経たない間に議論が作家間されています。
また、かなり大きな話題に発展した「#漫画家は自分が体験したことしか描けない」に関しても、いや議論の論点はそこじゃないと思ったり、今の時代から考えると創作界隈のいびつさを感じるのは私だけではないと思います。
また、事の発端は下記の通りだったにしても、論点は既に大きく逸れて、真相を話したところで収拾の付くモノでもありませんでした。
それに従来の興行スタイルはこの状況下で成立していません。世界的にも有名なエンターテイメント集団であるシルク・ドゥ・ソレイユも事実上経営破綻したいうニュースは我々の耳にも届きました。
ゆえにステレオタイプの作家像、ビジネススタイルだけで生き抜くことは、まずこの先では無理というのは確かです。何せ、世界的な名声を得ていても従来のスタイルでは経営破綻もしてしまうとニュースは伝えているからです。
そもそも、作家に関しても「感想がない」、「書きたくない」といってやめているのです。
ゆえに安易な言葉であっても「作家2.0」、新たな時代に適した姿にバージョンアップする必要があるのは間違いのないことなのです。
そもそも、作家側ではなく会社自体が新しい文芸を強力な資本を元に目指していたであろう、LINEノベルでも早々に終了した。
新たな会社が参入に対しても、既に余裕のない業界で今まで通りでは、生き抜くなど不可能と言いきった方が良いのかもしれない。会社よりも小さな存在、作家がこの中で生き抜くなど更に難題だろう。
そして、Twitter上で語られる従来の作家像で議論するのは同じく危険である。それはいままでは成功談であって、これからの成功例である可能性は低い。
記事内でも挙げたような、次世代でも生き抜ける成功者や他業種での取り組みなどを、むしろ参考にしなければならない。
ただ、BOOTHなどの個人間での販売スタイルでも「小説」と検索しても、結構な本数が出されている。実際、従来のスタイルに固着していない人もまったくいないわけではない。
こう語ってきた私自身、ステレオタイプに固着している部分は多々あったと思っている。
(ただ、このコロナ渦が切っ掛けであったにしろ、数年後には大きな転換期を迎えることはどの業界でも予測されていることであった。だから、コロナだけに責任をなすりつけるのは無責任な一面もあるとは思う)
おまけ 求めているモノを理解せよ
今回の記事内とは直接関係する訳でもないが、載せた方が良いと思った内容があったので載せておく。
🌸#ReVorn2020 🌸
— ReVorn-バーチャルアイドルオーディション-#ReVorn2020 (@ReVornProject) August 29, 2020
一般選考オーディション講評①
長くなってしまいましたが、参加してくださった皆様にとって、このオーディションに参加した意味が少しでも残れば嬉しいなと思います。
少し厳しく書かせていただいておりますので、ご承知おきください。 pic.twitter.com/tRiKdn73zY
正直、私が色々と語るよりもまず読んで頂きたい内容のため語らないが、今回の件でなくとも参考になる事は多いことである。
読んで頂き、もし気に入って、サポートを頂ければ大変励みになります。 サポートして頂けると、晩ご飯に一品増えます。そして、私の血と肉となって記事に反映される。結果、新たなサポートを得る。そんな還元を目指しております。
