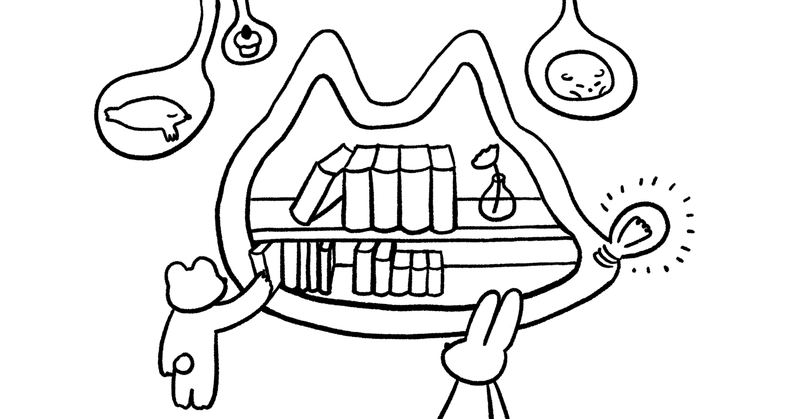
最近読んだ本『「愛着障害」なのに「発達障害」と診断される人たち 』
本の内容など
本来愛着障害というのは、5歳までに診断される名前であり、それ以降は愛着障害という診断名はつかない。
本当は養育環境に問題があるのに「発達障害」と診断されてしまう人が増えている。昔、子どもが自閉スペクトラム症になるのは母親の育児に原因があると言った医師がいたが、研究の結果、遺伝的なことが原因になっていると知れ渡ると、闇雲に親の育児のせいにできなくなった。そのこともあって、本当は愛着障害なのに発達障害の診断をしてしまう医師が増えているそうだ。
発達障害と愛着障害は専門家でも見分けることが難しく、合併していることもある。愛着障害であれば環境が改善すれば本人は別人のようになり、症状もかなり改善するのだそうだ。
支援を自治体から受けられなくなるため、本来その子の特性であるのに「障害」と判定され、障害というラベリングをされる子が増えている。
施設で大人数が一人の面倒を見るより少ない人数で面倒をみた方が愛着が安定しやすい。
今日の教育制度は高等文官試験の伝統を引きずる官僚育成のための教育。その子の特性に合っていない教育は、その子の特性を無駄と思わせ潰すことに繋がる。
非定型発達でも小さい頃から手をかけて安全基地を作り、不足していることを補うように気をつければ社会性が身につく。発達障害は障害ではなく、その子の生まれ持った特性だからだ。
回避愛着型スタイルはこだわりもなければ社会性がないというわけでもないが、人と深い関わりを持とうとしないため、選り好みの厳しい相手に出会したり、変に結束を求める会社に行くといじめや排除の対象にされてしまう。
日本人は遺伝的に環境に影響を受けやすいにも関わらず、アメリカの育児を取り入れてしまった。放っておいても子どもは育たない。
愛着障害には人を避けてしまうタイプと人に馴れ馴れしく接してしまうタイプなどがある。
子どもの診断方法としては、母親と子どもを一旦離し、また引き合わせたときの子どもの反応で分類する。親との関係が不安定であればあるほど、親に対する子の反応が複雑になる。
回避型→記憶が飛ぶ解離症状や反社会性パーソナリティ障害に移行することも。うつや不安障害にもなりやすい。自殺のリスクも安定型に比べると5倍ほど高い。感情に流されにくいため、冷静な判断が得意。仕事や趣味などでは高い集中を発揮したり、自己主張もする
抵抗・両価型不安型→不安障害や、うつなどを発症しやすい。女性の場合、産後うつになりやすい
無秩序型、統制型→回避型と不安型が錯綜している状態。境界性パーソナリティ障害や解離性障害に移行することも
→どの型ではなく割合でみる。
発達障害と愛着障害を見分ける
虐待やネグレクトの有無
修正困難な固執性、感覚の過敏性(自閉スペクトラム症では修正困難な固執性があり、愛着障害は柔軟性がある)
環境や関わり方の変化に反応するか(愛着障害は環境を変えると、状態が急激に変わる)
親や身近な人が安全基地になっているかどうか
情緒的な不安定さやネガティブな感情が強い(本来の発達障害であれば天真爛漫さや無邪気さがある)
天邪鬼な反応や振り回し行動(愛着障害に見られやすいのは、本心と異なる行動や言動をわざとする。拒否されればされるほど無理な要求をする)
依存症や顕示的自傷行動、解離症状。(本来の発達障害であれば他者の目線は意識していない)
反応や破壊行動が目立つ(本来の発達障害では愛着障害が合併しない限り反抗的になることはない)
性別による違い(発達障害になる割合は男性の方が多い)
感想
愛着障害や発達障害があっても起業家になったり、小説家になって後世に残るような作品を作る人もいますと本にはあったけれど、みんながそうなるのは難しいと思う。別に目立った存在にならなくてもその人にとって暮らしやすくなればいいのに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
