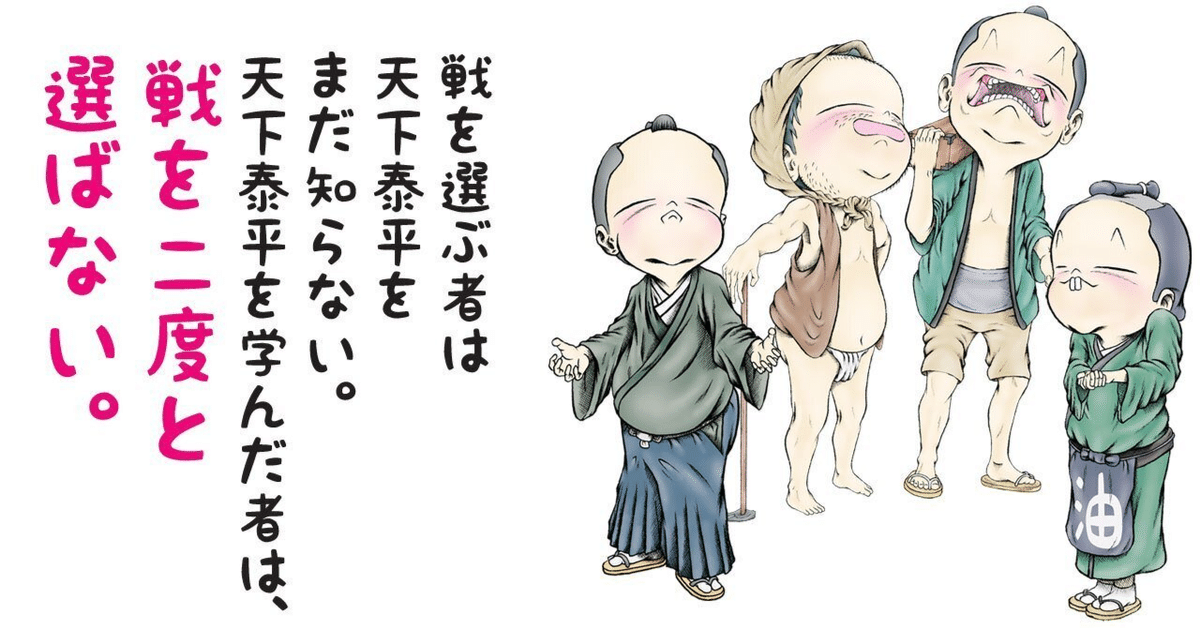
政治講座ⅴ1823「外交で不満があると直ぐ報復、恩を仇で返す恩知らず」
韜光養晦が中国の外交で、しばらく微笑外交を続けていたが、経済力が付くに従い馬脚を現して、戦狼外交で牙と爪を見せてきた。裕福になると民主化されると思ったが、逆に、覇権主義の顔をのぞかせてきた。恩を仇で返す行動を起こしている。二度と中国に投資することはないであろう。
不動産バブル崩壊で中国地方経済は過剰債務で阿鼻叫喚に喘いでいる。過剰債務と経済不振のために海外投資を中国に呼び込もうとしているが、戦狼外交や反スパイ法、覇権主義の牙と爪を見せられたので、危険を察知して近づく国はない。「君子危きに近寄らず」である。
今回はそのような報道記事を紹介する。
皇紀2684年6月20日
さいたま市桜区
政治研究者 田村 司
経済的に追い詰められた中国、手あたり次第のラブコールも袖にされ
Milton Ezrati によるストーリー

中国政府は破れかぶれになっているに違いない。国内経済も貿易も投資の流れも状況は見るからに思わしくなく、かつて世界を席巻した中国ビジネスへの熱狂は、米国でも欧州でも日本でも潮が引くように冷めつつある。米国政府は対中貿易で対決姿勢を強め、欧州連合(EU)や日本も米国ほどではないにしろ中国離れを加速させている。
こうした中、中国の指導者たちはここ数カ月というもの、分野を問わず先進国の実業家や政治家を口説こうと躍起だ。習近平国家主席は米国のビジネスリーダーたちを2度にわたって歓待し、中国がいかに彼らを高く評価しているかをアピールした。欧州を歴訪した際にも同様のもてなしをした。ごく最近では李強首相を韓国・ソウルに派遣し、日韓の経済界に対してはもちろん、両国首脳にも積極的なメッセージを伝えた。しかし、反応はいずれもあからさまな拒絶ではなかったにしろ、温かさはほとんど感じられないものだった。
中国政府が必死になる理由ははっきりしている。国内では深刻な不動産危機が収束する気配もなく、住宅購入や建設活動が停滞し、家計資産の目減りなどを理由に消費者は財布のひもを固く締めている。これに加えて、民間企業を敵視する習政権の以前の政策が響き、民間投資や事業拡大、雇用も停滞。対中貿易規制や、積極的なサプライチェーンの多角化と中国からの生産移転により、輸出の遅滞も起きている。
経済を下支えできる要因が内外に見当たらないがゆえに、中国政府は現状「魅力攻勢」としか評しようのない外交姿勢を取らざるを得なくなっているのだ。ねらいは、かつて中国の急速な発展を後押しした外資の熱意をいくばくかでも取り戻し、経済を活性化させることにある。
習主席は昨年11月、米サンフランシスコで開催されたアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議で米財界人と会談し、中国には豊かなビジネス環境があり外資を歓迎していると太鼓判を押した。今年に入ると、さらに多くの米ビジネスリーダーを北京に招待し、同じメッセージを伝えた。その直後には欧州歴訪でも同様の売り込みを行った。米国でも欧州でも人々は習主席を好意的に迎え、礼儀正しく友好的に接したが、さほど実質的な成果にはつながらなかった。投資の流れも貿易も大して回復していない。
直近では、韓国と日本に対しても同じような働きかけをしている。李首相はソウルで韓国の尹錫悦大統領、日本の岸田文雄首相と2019年以来となる3カ国首脳会談を行い、日中韓の貿易促進と対中投資を呼びかけた。李首相が日韓首脳に約束した内容は多くの点で欧米諸国に提示したものと同じだったが、さらに一歩踏み込み、2012年に浮上した後ほとんど停滞していた日中韓自由貿易協定(FTA)の交渉再開を提案した。東アジア3カ国の絆を強調することで、日韓のいずれか、または双方を米国との緊密な経済・外交関係から引き離そうとしているようにも見えた。
ソウルでも誰もが非常に礼儀正しかったが、李首相が目的を達成できたとは思えない。貿易やクリーンエネルギーなどの分野で協力を推進するといったお決まりの美辞麗句が踊った以外に、具体的な会談の成果と呼べるものはなかった。李首相は、経済・投資・貿易を安全保障や外交から切り離すことを主張したが、会談では安全保障問題をめぐって温度差が露呈した。
尹大統領と岸田首相はともに、北朝鮮のミサイル発射実験をはじめとする敵対的行為に歯止めをかけるため中国の協力を求めたが、李首相は韓国側に「貿易の政治化」をしないよう(自国のふるまいを棚に上げて)警告した他は、北朝鮮問題に言及しなかった。岸田首相は台湾周辺で中国が最近行った軍事演習に懸念を表明し、「台湾海峡の平和と安定」が日本と国際社会にとって「極めて重要だ」と李首相に伝えた。李首相が求める貿易と投資に関する進展はもちろん、ましてや3カ国のFTA推進など、安全保障問題をある程度解決しなければ望めないことが痛いほど明らかになった。
中国がこれまで貿易面で高圧的な態度に出たりせず、譲歩を要求したり制裁的措置を取ったりもしていなかったならば、経済・投資・貿易を安全保障・外交から切り離すといった提案は必ずやもっと生産的な展開を生んだはずだ。
中国は新型コロナウイルス感染症のパンデミックに際して重要な物資の輸出を停止し、中国に進出している外国企業に対しては独自技術や企業秘密を中国のパートナー企業と共有するよう要求した。外交問題をめぐり、日本への制裁措置としてレアアース(希土類)の対日輸出を禁止したこともある。今、中国政府はこうした過去のふるまいの代償を支払わされており、必死のほほえみ外交は望む結果を得られていない。
2024.02.28 08:30
確実に進む日米欧の中国からの「デカップリング」、データが証明

Shutterstock.com
米国や欧州各国、日本が調達先を中国から他国に移して多様化させる取り組みがうまくいっていることが、中国と世界各国のデータで示されている。これらの主要な市場はそれぞれ中国との貿易を著しく減らしている。中国企業は第三国へ進出し、あるいは他国で商品を積み替えて輸出しているが、そうした事業は中国貿易のデータには含まれていないため、データは調達先の多様化を多少誇張しているかもしれない。
中国企業のそうした工作により統計を鵜呑みにはできないだろうが、実際的にはそれほど大きな違いはないかもしれない。結局のところ、デカップリング(切り離し、経済分断)、あるいは欧州の人々が好んで使う「デリスク」のポイントは、中国の脅しに対する脆弱(ぜいじゃく)性を減らすことであり、第三国への移行はそれはそれで効果がある。
データで最も印象的なのは、対米輸出で中国がトップの座を失ったことだ。今やその地位はメキシコに移っている。この変化は主に、米国のバイヤーが調達先を中国から特にメキシコ、またベトナムやインドに移して多様化を図る独自の取り組みによるものだ。詳細はともかく、中国税関総署の直近のデータによると、2023年1月から同年11月の中国から米国へのスマートフォン輸入は前年同期比約10%減少し、ノートパソコン輸入は同30%減少した。インドからのスマートフォンの輸入、ベトナムからのノートパソコンの輸入は、比較水準が低いとはいえ、それぞれ4倍に増えている。
欧州のデータは完全にまとまっているわけではないが、ドイツの連邦統計局の発表によると、同国の中国からの輸入はこの1年間で13%減少した。中国とドイツの貿易関係は長い間発展してきたにもかかわらず、予備調査報告によると、ドイツへの輸出で米国が中国を上回った可能性がある。
日本と韓国も、少なくともある程度は中国から遠ざかっている。統計をどう解釈するかは、それぞれの中国との複雑な関係にもよる。日中、韓中の貿易の多くは、中国に設立された日本と韓国の事業所を中心に展開されている。2国は部品やコンポーネント、消耗品を中国の事業所に輸出し、そこで完成品にしてから輸入というかたちで国内市場に戻す。中国からの輸入に関するデータはまだ入手できないようだが、中国の情報筋によると、日本と韓国の対中輸出は減少しており、中国拠点の事業が重視されていないことを示している。同時に、米国勢調査局によると日本と韓国の対米輸出が増加し、今や中国を上回っていることもそうした事態を示している。
中国との貿易が活発になっている唯一の地域は、原材料や農産物の輸出に依存している経済圏だ。中国税関総署によると、ブラジルと中国の貿易は急増している。ブラジルから中国への輸出は昨年、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以前の水準を60%ほど上回り、ブラジルの中国からの輸入は50%増加した。いずれもパンデミック以前の水準は低かった。
オーストラリアも対中貿易が伸びている。2023年の中国への輸出は前年比17%増だった。この数字は将来の発展性を誇張しすぎており、中国が2020年にオーストラリアからの輸入品に課した懲罰的な関税を撤廃したことで、以前の貿易水準に追いついたことを反映しているだけの可能性がある。
ロシアも中国との貿易が急増し、主にエネルギーを輸出し、消費財を輸入している。西側諸国がウクライナ侵攻をめぐってロシアとの貿易を制限し続ける限り、中国とロシアの貿易は拡大し続けるだろう。
こうした動きの結果、中国の貿易の構成は著しく変化している。中国税関総署によると、中国の輸出入に占める米国の割合は2018年から2023年にかけて2.5ポイント低下した。日本のシェアは2ポイント近く、韓国は約1.5ポイント縮小。欧州のシェアは約0.5ポイント減った。
対照的にロシアのシェアは2ポイント、ブラジルとオーストラリアはそれぞれ0.5ポイント拡大した。東南アジア諸国連合(ASEAN)のシェアは2.5ポイントほど増えているが、これは互いの位置付けの変化というよりも、ASEANが比較的急成長しているためだ。こうした数字は小さなものに見えるかもしれないが、貿易の一般的な流れから見ると比較的短期間に驚くべき動きがあったことになる。
こうした状況からして、世界有数の経済大国が中国からかなりデカップリングしていることは確かだ。また、この動きはすぐに反転しそうにもない。何年にもわたって続いている傾向だ。米国では2018年に当時のドナルド・トランプ大統領が中国からの輸入品に高い関税を課したことが始まりだった。トランプは2019年にさらに関税を引き上げた。バイデン大統領はこれらすべての関税を維持し、さらに中国への先端半導体と半導体製造装置の販売、そして中国の技術への米企業の投資を禁止した。直近では、中国製の電気自動車(EV)の輸入に25%の関税を課す案も浮上している。
一方、日本はレアアース(希土類)を中国以外から調達するための国際的な取り組みを主導しようとしており、欧州連合(EU)は安価なEVを欧州市場で大量に販売しようとしている中国に罰則を科す措置を取っている。
最初にトランプが関税を課した時からそうしてきたように、間違いなく中国企業はメキシコやベトナムなどの第三国で事業を立ち上げたり、単に中国製品をこれらの国で積み替えたりすることで、締め付けを回避し続けるだろう。こうした動きは関税を回避できるかもしれないが、米政府は対抗策を取っている。中国企業の回避行動は、入手可能な貿易データの解釈を確かに混乱させるだろう。だが、そうではあっても、製品の流れに影響を及ぼす中国の力を弱めることになる。結局のところ、デカップリングがそもそもの目的だったのだ。
また、2020〜2022年に中国の政策で打撃を受けた供給の中断を回避するために、調達源を中国から多様化しようとする欧米や日本の企業の継続的な取り組みも、中国企業の締め付け回避の動きに妨げられることはないだろう。こうした傾向には明らかに持続性がある。
(forbes.com 原文)
EUとの貿易摩擦、中国はなぜ「豚肉」を選んで報復しようとしているのか―独メディア
Record China によるストーリー

独ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは18日、欧州連合(EU)と中国の貿易摩擦に関連し、中国はなぜ「豚肉」を選んで報復しようとしているのかとする記事を掲載した。
記事がロイター通信などの報道として伝えたところによると、中国商務省は、EUから輸入する豚肉とその副産物に対する反ダンピング調査を17日に開始すると発表した。主にスペイン、オランダ、デンマークを対象にしたもので、EUが数日前に中国製電気自動車(EV)への関税引き上げを決めたことに対する報復とみられている。
欧州委員会は12日、中国から輸入するEVに最大38.1%の追加関税を7月から課す暫定措置を発表した。
中国への最大の豚肉供給国であるスペインの豚肉生産者団体インターポークは、中国による1年に及ぶ調査により「EUと中国が合意に達するのに十分な時間」が与えられたと確信しており、中国当局に必要な書類をすべて提供すると述べた。
中国の調査は1年以内に終了する見込みだが、6カ月延長される可能性もある。
デンマーク農業理事会は17日、実際に関税引き上げなどの輸入制限が導入されれば、国内の豚肉業界が深刻な打撃を受ける可能性があると警告した。南米諸国や米国、ロシアなどの豚肉供給業者にとって中国で市場シェアを拡大するチャンスが到来するとの分析もある。
税関のデータによると、中国は昨年、60億ドル(約9420億円)相当の豚肉を輸入し、その半分以上をEUが占めた。EUからの豚肉輸出額はスペインが約15億ドルで最も多く、2位のオランダは6億2000万ドル、3位のデンマークは5億5000万ドル。(翻訳・編集/柳川)
韜光養晦(とうこうようかい)とは
2013年6月16日 3:30 日経
▼韜光養晦(とうこうようかい) 1990年代に最高指導者、トウ小平氏が強調した「才能を隠して、内に力を蓄える」という中国の外交・安保の方針。当時、中国は89年の天安門事件で孤立しており、爪を隠して国際社会での存在空間を広げつつ、経済力もつける必要に迫られていた。
参考文献・参考資料
経済的に追い詰められた中国、手あたり次第のラブコールも袖にされ (msn.com)
確実に進む日米欧の中国からの「デカップリング」、データが証明 | Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

