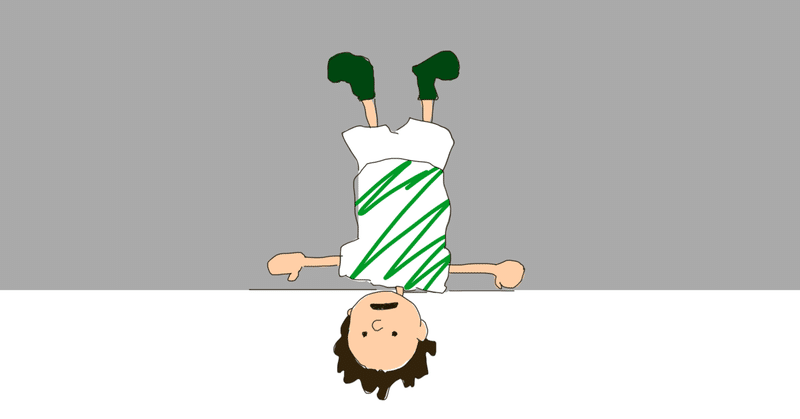
Photo by
wa_ka_wk
モンテッソーリ教育を知る第一章 『自立一歩目』
他のシリーズはこちらにまとめています。
自分でやりたがるのは子どもにとって大切な「自立への第一歩」
本の情報、僕の感想の交互でいきます!
・自立への道は「自分でする!」と叫んだ時から始まるのだ。
・自分でやりたがるのは、自分の思い通りに随意筋を使いこなせるように練習したいから。
・子供は自分の行動の主人公になりたい。大人は手を引いて見守るようにする。
なるほど〜。
「自分でやりたい」という気持ちは、自立の始まりなのか。
主体性ってことなんだろうな。
ついつい僕自身が子どもの人生の主人公になろうとしてしまうんだよな。
・子供はできないのではなく、やり方がわからないだけなのだ
子供をよく見、その子に必要なやり方を教えてあげることが必要なのだ。
・大事なのはやり方の教え方
言葉で教えるのではなく、ゆっくり動きを見せてあげることで
教えてあげた方が良い。
(耳で聴きながら、同時に見ることに集中するのは難しいらしい)
「言葉ではなく」が難しい〜(._.)
おしゃべりだからな〜。自分。
でも焦りに勝つということですね!
頑張って頑張らないぞ〜。
教え方ポイント
1. してみせるとき、言葉を添えず黙ってする
2. 子供がやりたがっている活動を、1つだけ取り出す
3. 動作を分析し、順序立てる
4. できるだけ動作をゆっくりにして、はっきり、順序立てて見せる。「してみせる技術」
5. 急がない。いつか見てくれる。何度も見せたらいいって精神で。
「取り出して順序立てる」の例:椅子を運ぶ
1. 一方の手で椅子の背を他方で腰掛けの中心を持つ。
2. 床から持ち上げる
3. 持ち上げたまま移動する
4. 床に置く
順序立てる、これが本当に大事で、あらゆることに通じてると思った。
一つ一つを区別して、順序を知り、秩序を作る。創世記だ。。。
「大人が無意識でやっている動きも、実は様々な部分に分けられる」
深い。
脳と体の連携を作り上げる
感覚器官→脳→運動器官
第一章では、
子どもの「自分でやりたい」気持ちを、折らない導き方を知ることができた気がします。
黙ってやり方を見せてあげる。
一つを取り出して、動作を分析し順序立てる。
この後の章でもある「秩序」がやはり重要なのだと思いました。
子どもの中にある「良いもの」を信じて。
焦りに負けるな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
