
ジャズとヒップホップが教えてくれるダイバーシティの本質
では、ダイバーシティ経営について、『価値観』と『思考法』という切り口で考えてみます。
そもそも企業活動において、ダイバーシティ&インクルージョンが必要とされている究極的な目的は?
「イノベーション創出」であると言い切っていいと思います。
ダイバーシティ経営は、多様な個性を持ったメンバーを集めて、「建設的な意見の対立」「創造的な摩擦」を作り出す環境に置くことで、チームワークとしてのイノベーション創出が実現できる可能性が高い組織形態に進化していきます。従って、『思考法』や『価値観』が違うメンバーを認めて受け入れることが大切です。
オーケストラ型組織は、ルールに従った計画通り(楽譜通り)の演奏を各メンバーは求められるわけですから、与えられたパート(楽器)を確実に正確に演奏できる人材が重宝されます。
仮に、オーケストラ型組織に、チャーリー・パーカーのような「誰も想像すらしなかったこと」を考えついて「そんな方法があったか」と驚くような方法を思いつく天才的な人が必要でしょうか?
楽譜が読めないウエス・モンゴメリーが重宝されるでしょうか?
不協和音になるだけで、組織とっても個人にとっても悲劇にしかなりません。
日本型経営企業(メンバーシップ型雇用)においては、「企業文化=価値観」と合う人を採用する傾向にあり、入社して企業文化にあう「思考法」を教えられます。
「お上への報告」と「やっていますという“アリバイ”作り」だけの【①なんちゃってダイバーシティ】を行っているだけで、破壊的イノベーションが創出されることは、あまり期待できません。

破壊的イノベーションを創出できるのは、左図の赤点線内にある【②求められるダイバーシティ】と【③オープン・イノベーション・ダイバーシティ】です。
アフリカ系アメリカ人は、自分たちが置かれた人種差別という厳しい環境下で「ジャズ」というイノベーティブな音楽を創造していきました。
時代に応じて、変化を続けながら進化することが出来た「ジャズ・コンボ型組織」が、 【②求められるダイバーシティ】に該当する組織と考えます。
DJが、伝統(古い楽曲)に新しい解釈を加えて、時代にあったトラックを創造して、そのトラックの上で、今のリアルなメッセージをラッパーが語り、新しいテクノロジーを積極的に取り入れた楽曲をリリースすることで、伝統を継承していくヒップホップが持っている『融合力』
こんな「ヒップホップ型組織」こそ 【③オープン・イノベーション・ダイバーシティ】そのものでしょう。
「温故知新」と言いますが、ヒップホップは、故きを温ねて新しきを創造する「温故創新」です。
【Tradition】:伝統をリスペクト 【Progress】:伝統を進化 【Originality】:個性を発揮
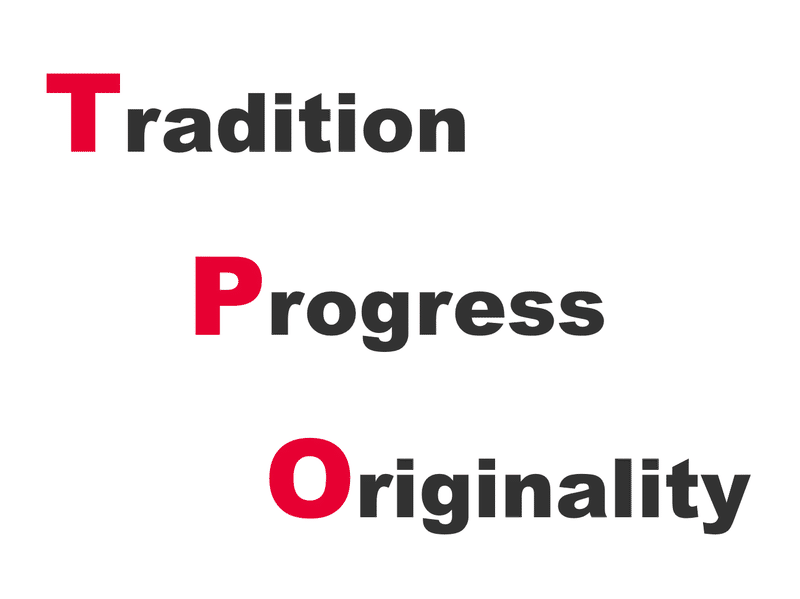
「ジャズ」と「ヒップホップ」の歴史を学ぶことによって、
マイノリティの視点からの『ダイバーシティの本質』が理解できます。
「井の中の蛙大海を知らず」では進化できません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
