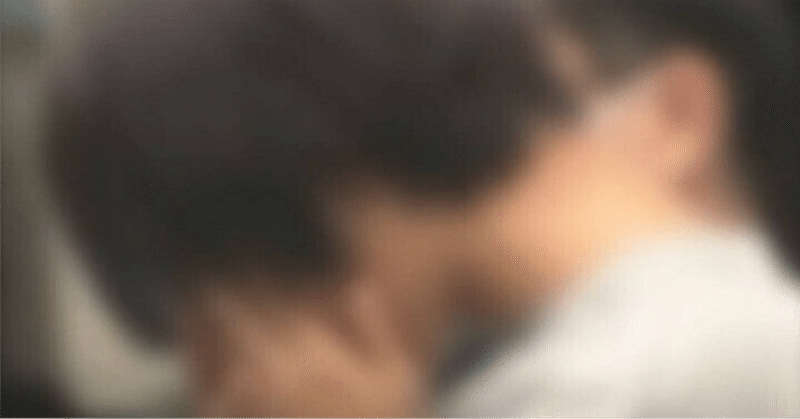
盗撮加害者家族の記 07 警察署へ
※この記事は全文無料でご覧いただけます。お気持ちをくださる方につきましては、記事最下部にてありがたく頂戴させていただきます。
翌朝、私は実母とともに警察署へ向かった。
ひとりで電車に乗ろう思っていた私を制し、「こんな時に1人にさせる訳にはいかない」と母はタクシーを呼んでくれた。普段であればもったいないと言うところであるが、その心遣いが今日はありがたい。
行先を警察署と伝えるのには少し勇気がいった。別に犯罪者の家族でなくとも警察署に行く人は山ほどいるだろう。分かってはいても、加害者家族という後ろめたさが既に生まれていた。
警察署の前に着いたのは義父母と約束した時間より30分も前だった。母には先に夫と住んでいた近くの家で待ってもらおうとしたが、頑として動かなかった。では一緒に話を聞くかとも尋ねたが「よそ様のお宅のことだから」とそれも固辞された。彼女はただ1人、私という家族のことを考えているようだった。義父母が到着してから、母は私たち夫婦の家へ向かうことになった。
暖かい春の日だった。日差しが柔らかく降り注ぎ、行き交う人々も軽装で、足取りまで軽く見える。本来だったら今日、私も夫と出かけているはずだった。今ごろ、他人からしたら下らないことで笑いあっているはずだった。
それがこんなことになるだなんて、誰が想像しただろう。
暖かい陽の光の下を歩く人達が、自分とは別世界の人間のように見えた。
約束の時間を五分ほどすぎて、義母が申し訳なさそうな顔をして横断歩道を渡ってきた。
「ごめんなさいね。あの人が警察署の駐車場に車を停めたくないって……。こんな時にそんなこと考えてる場合じゃないって言ったんだけど」
そうかと、私はその時言われて初めて気づいた。
もしも今回の事件が知れたら。自分の家族が犯罪者として逮捕されたということが周囲に知れ渡ったら。
私と夫は都会にありがちな流れ者のようなもので、実家を出て今の家に住んでいる。2人とも現在の家に来るまでは別の場所で1人暮らしをしていた。1年ほど前に越してきた時に今の隣人に挨拶はしているが、その程度だ。家族構成も知らないし、なんなら名前すらきちんと覚えていない。定住するつもりは毛頭なく、いつか子どもができたらもう少し広い家に引っ越そうだなんて話もしていた。
けれど、互いの両親は違う。
家を買い、土地に根付いて生きてきた。その土地で子育てをし、これからも同じ場所で生きていく。
しかも義父母はいわゆる『堅い』と言われる職業に就いており、今回の事が知れた時にどうなるか考えると慎重にならざるを得ないことも理解出来る。
事の大きさがじんわりと、暗く私の胸を染めていくようだった。
数分待って義父が現れた。
義父はまずもって実母に「この度は本当にご迷惑をおかけして」と謝罪し、私に向き直った。
「少しでも寝られたかな?」
「……少しだけ」
薄く笑うので精一杯だった。同じように義父も薄く笑った。
ふっと警察署の方を見ると、スーツ姿の男性が2人こちらに向かってくるのが見えた。
「○○さんですか?」
制服姿でないことは当たり前だが刑事だろう。「はい」と答えつつ実母に目配せすると、すっと母は離れた。
「こちらへどうぞ」
誘導されて義父母とともに警察署へ歩みを進めると、「先程の女性はご近所の方ですか?」と警察官に聞かれた。
「いえ、母です。私を心配してここまで一緒に」
「そうでしたか」
刑事はなぜかほっとしたように見えた。質問の意図が分からず困惑したのが分かったのか、彼は少し柔らかい顔をして言葉をつけ加えた。
「もしご近所の方でしたら、警察署に入るところを見られてしまうのはご家族のご迷惑になってしまうと思いまして」
今度こそ、あからさまに戸惑った。
「ご迷惑をおかけしているのは、こちらの方ですので。この度は本当に、申し訳ありません」
私は責められるべきで気遣われる立場では無い。気遣われるのは被害者であって、私たちではない。夫と等しく、私を扱って欲しかった。
私たち3人が通されたのは、4畳程度の狭い部屋だった。ただでさえ狭い部屋に無機質なグレーのキャビネットと小さな事務机が置かれ、開放感を与えてくれるはずの窓は向こう側が全く見えない曇りガラスのせいでむしろ閉塞感を感じさせる。
「少々お待ちください」
と言われ、部屋には私たち3人が残された。
不意に、義母がうつむいて肩をふるわせる。両手で腕を強く握りこみ、爪が食い込んでいた。その行為を見て、私と同じだなと思った。
私も昔から同じ癖がある。心が耐えきれないほどに苦しい時、私もかつて色々な場所を握りこんだものだ。身体的に痛みを感じれば感じるほど正気でいられるような、そうすることでなんとか自分を保てるような、そんな気がして。痛みで自分の身体を縛らなければ、がらがらと崩れていくような感覚。
気づけば私も涙を流していた。義母の手を取る。目が合い、どちらからともなくお互いを抱きしめた。
「大丈夫。大丈夫」
言いながら義母が私の髪を撫でる。私に言っているようでも、自分に言い聞かせているようでもあった。
そんな私たちを、義父は読めない表情でじっと見つめていた。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
