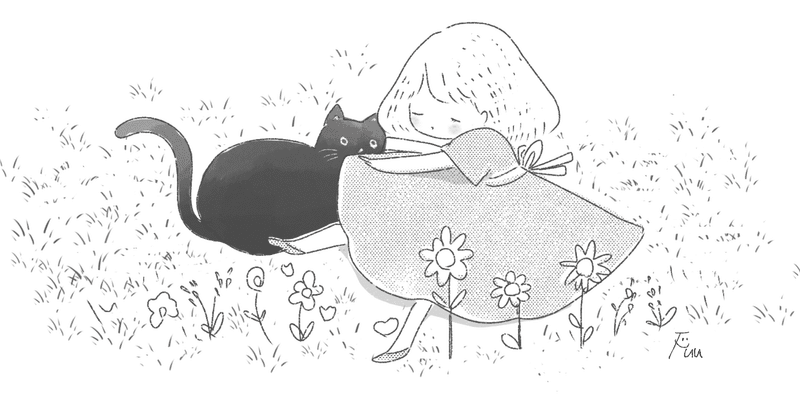
死に語りな猫(下)
向日葵の咲かない夏なんてものはないはずだった。
世界の何処かで向日葵は目障りにも太陽を目指して顔を向けるために咲く。
けれど、死にたがりの猫と約束を交わしたあの向日葵はその夏には咲かなかった。
正確に記すならば、約束の次の夏、枯れた向日葵の後に向日葵はやって来なかった。
まるでこの世界から向日葵という種が消え失せてしまったかのように、いや真実それは消え失せてしまったのだけれど。
死にたがりの猫は落胆などしなかった。そんなものだよなと、むしろ愉快そうに笑った。
それから誰かに頼ることなく、最初から自分で選べば良かったのだと決意を定めた。
けれど忌々しいことに、彼と向日葵が交わした約束のうち、死ぬことも許されないということだけは果たされたようで、高い場所から落下し体を叩きつけようが、獰猛な獣に身を千切られようが、死にたがりの猫の体は再生した。
痛みがないわけではなかった。痛んだ部分が膿み、腐れ、ただれても、しばらくするとそこから泡が発生し、しばらくのち肉体は再生された。
死にたがりの猫は太陽に恨み事を述べる。
「ねえ、あんたと約束した向日葵は、いつになったらやってくるんですか。こっちは、約束が果たされる日を首を長くして待っているんです。もっとも、こちらがどれだけ首を伸ばした所で、向日葵のようにあなただけを見ているなんてことはできませんけれどね」
遥か遠くに見える太陽はそんな声など聞こえていないように、ただ太陽として空に在った。
幾年が過ぎ、また十数年が過ぎた。
猫は旅をして、思い出したかのように毎年同じ時期になると向日葵が咲いていた場所を訪れ、また咲かない向日葵の跡を恨めしそうに睨んでは次の旅へと向かっていった。
飢餓、戦争、宗教、そういったものが生み出す幾つもの闇を死にたがりの猫は見た。いや、それまでも直接的な形でないにしろ、猫はそれを見ていた。食物連鎖の法から逃れた動物たちの狂ったような殺戮を、気まぐれに繰り広げられる享楽を、暴力を見続けていた。しかし、世界のどこに言っても飽きることなく行われるその闇の拡張に猫はうんざりしていた。
猫の体の中の水は濁り続ける。しかし、向日葵との約束は続いており、死にたがりの猫は死ぬことができなかった。幾度もの悪意が彼を切り刻んでも、鋭利な牙が彼の肉体を噛み砕いても、彼の中の水は濁りながらも再び湧きだしては彼を再生させた。
水に囲まれた場所を疎み、恐れながら、そこから逃れることができず、結局囚われてしまったことに死にたがりの猫は気付いていたが、今さらそれを嘆いた所で時既に遅く、向日葵との約束を果たす日を待ちながら死にたがりの猫は太陽を見上げては舌打ちをし続けた。
文明は転がり、時代は消化され、また似たような事柄が似たように繰り返される中、向日葵は咲かなかった。半ば、猫は諦めていた。死ぬことも許されず、太陽に焼かれることを待つだけの日々を受け入れるには、諦める事を諦める必要があったが、そんなことを考えるのもうんざりするほどの時間が死にたがりの猫の前にはあった。
どれだけの歳月が流れたのか、死にたがりの猫が思い出そうとも知ろうともしなくなった頃、猫はある街のゴミ箱を漁っている最中に、女の子から声を掛けられた。
金髪で蒼い眼をした女の子は、まるで葬列に並ぶ姿だった。黒い帽子、黒い洋服、靴だけが朱い。
「こんなところで何をしているの?」
「生きるために飯を食べているのさ。もっとも、生きるために食べているのではなくて、食べることで生きていることを知っているという方が正確だけれど」
「へぇ。ずいぶん難しいことをいうのね」
「そうかな。別にそうは思わないな。君だって毎日ごはんを食べるときにいちいちこんなことは考えないかもしれないけれど、考えることすら疲れてしまった時に、ふとそんなことを考えるはずさ」
「ほら、また難しいことを言う」
彼女は表情は変わらないけれど、声だけは楽しそうに笑った。
その姿を見ながら、猫は自分がどれだけ、それこそ死にたがりの猫が死にたがるようになる前に最後に笑ってからどれだけ笑っていないかをふと考えた。
自分の言葉に呪われるように、考えることすら疲れてしまっていた事をふと思い出した時、死にたがりの猫は思い出す。
それは笑ったことではなく、向日葵が枯れた時に自分が泣いたこと。
向日葵の言葉。
世界の何処で芽を出して、あの場所に戻ってくると言った言葉を。
けれど、向日葵は世界のどこにも咲きはしなかった。何処かに咲いているかもしれないと猫は旅を続けたが、これまで何処にも向日葵の痕跡を見出すことはできなかった。
「あなたは随分と遠くを見ているのね」
女の子は帽子を触りながら、どうでもよさそうに猫に語りかける。
「遠くから来たからね」
「遠くか。私も遠くへ行きたいな」
「いずれ行けるだろうさ。生憎、遠くから来たことはあっても、まだその遠くに行けない自分が言うのもなんだけれど」
年寄りじみたことを言うのねと、今度は少しだけ楽しそうに、けれどうっすらと悲しそうに女の子は言って猫の背中を撫でた。
「わたしも、まだ行けないの。行きたいのだけど」
彼女は少し震えて、それから涙を流した。涙は猫の恐れていた水、けれど背中に落ちるその水を随分と久しぶりに猫は感じた。雨とは違う、温度の混じった水を。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
