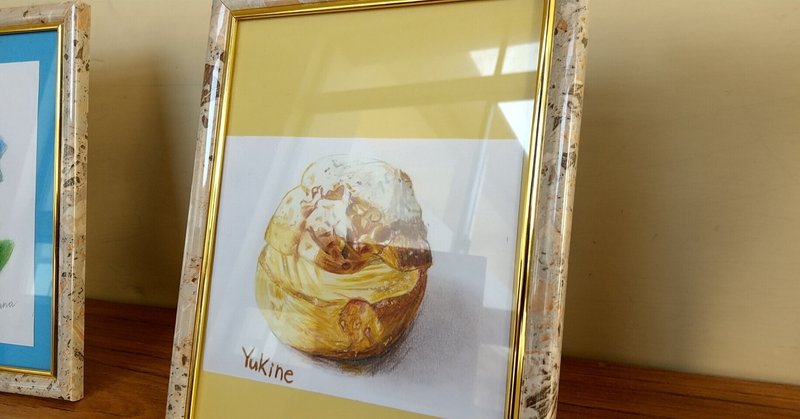
中学生の主体性はそんなに重要か
来年度の公立高校入試では,生徒の主体的に学習に取り組む態度の評価が重視されます。
この主体性を評価する方法としては,ノートやレポートの記述や学習の振り返りシート,授業中の発言などがあります。単純に挙手や発言回数で評価することはありません。
しかし,このような方法で生徒の主体性が公正に評価できるのか疑問を持っています。
今日の読売新聞の「あすへの考」で特集を組んでいました。その中で,こんな意見が紹介されていました。
〇内申書を意識して発揮されるのは,主体性ではなく従順さではないか。〇中学校間の学力差や教師による評価の違いは否めない。
〇主体性の評価は発表や討論を重視した授業改善の契機になるが,教師が成績付けの材料集めに追われては本末転倒だ。
中学生段階で,学習に対する主体性を本当に重視すべきなのでしょうか。この発想は,中学生の自我が完成しているという前提にたっているのではないでしょうか。
37年間教師をやっていますが,中学生はまだまだ未熟だと思います。
自我の完成の途上にあると言っていいでしょう。
教師が黙っていれば,授業中に私語や手遊びや立ち回りなど勝手なことをする生徒は少なくありません。
タブレット学習では,学習と関係ない動画やサイトを見る生徒もいます。
班学習では,自分で考えず,話し合うこともせず,雑談して,最後は仲間の意見をまるパクリする生徒もいます。
4月の授業開きで,こんな話をしました。
「聴くチカラが高い生徒は学力が向上します。つまり,先生の説明を黙って静かに聴く,指示にしたがって作業をする,このように素直な生徒ほど成績が上がるのです。」
主体性が大切ということは異論はありません。しかし,中学生段階で主体性を重視することは授業の成立に関しては危険でもあると思っています。
