
ポケモン対戦に学ぶ試験勉強方法のはなし
サムネ用のタイトルを書くための背景画を描いていただきました。
リクエストしたとおり過ぎたので今後は基本的にこれを使います。
ありがとうございました!
前回の、FP3級を受けたはなしの中で勉強のモチベーションについて書いた。
今回は、勉強方法についてまとめたいと思う。
勉強はしたくないのだが、今後情報系の資格を十数年ぶりに取らなくてはならなくなりそうなので、効率よく(できるだけ勉強せずに)知識を吸収する術をまずは習得したいと考えた。
(特に情報系の勉強は、すでに興味の対象から外れているため全然やる気は起きそうにない)
最近クイズ熱も再熱してきており、昨年末からクイズノックの動画を見漁っている。
そのため、今回の種本は、伊沢さんの本を使用することにした(セールだったし)。
この本を読んだ私の感想は「あー、つまりはポケモン対戦と一緒ね」であった。
このご時世、野球に例えるのはおっさん扱いされるらしいがポケモン対戦に例えるのは、それ以前に一般的ではないと思う。
そもそも、読んだ人が理解できるかという問題もあるが、自分自身が理解できて整理できれば良しとする。そのためのまとめでありnoteなのだ。
ここでのポケモン対戦のルールはシングルレート対戦(6匹ずつ見せ合って3匹を選んで選出する)のルールをベースとして例えに使用していく。
なお、私がガチで対戦していたのはサン・ムーンあたりまでなので現在のソード・シールドの環境と若干考え方が異なる部分もあるかもしれないが、大枠は変わらないと思う。伝説2体入れられるような環境はもうさっぱりわからん。そして主に主観である。
本の内容で重要だと思ったことを、ポケモン対戦と試験勉強に当てはめていく。ポケモンの話の部分が余計な気もする。
対策が大事
なにより試験の対策が一番大事。相手の分析と自分の分析をしっかりおこなって対策を練る。
相手の分析
試験でいうところの、出題範囲、出題傾向、出題形式等である。
闇雲に勉強するのでなくて、毎回出る問題、頻出の問題、近年の傾向を把握して必要なところだけを勉強する。伊沢さんも出演するクイズ番組に合わせて頻出や傾向を分析して覚えてたらしい。
ポケモン対戦でも、現環境で流行ってるポケモンや構成を理解してパーティを組まないといけないので一緒である。
ハッサム、ガブリアスがめちゃくちゃ流行った時期もあれば、バシャーモ、サンダーを毎日見た時期もあり、ガルーラやゲンガーに殺意を覚えた時期がみなさんにもあるだろう。ボルトロス、スイクンなんて思い出したくもないだろう。
自分を分析する
自分の性格を理解して、弱い面を知らないふりするのではなく、知った上で性格を前提として対策をとることが大事である。
例えば、眠いと勉強できない、お腹いっぱいだと勉強できない、SNSの通知が多くて集中できない等々である。全部私のことである。
ほかにも家だと集中できないとか、夜は集中できない等自分の弱点を分析して短い時間でも集中して勉強する環境や時間帯を分析する。人間の性格は簡単に変わらないので。
ポケモン対戦でも自分のパーティ構成の分析はかかせない。地震が一貫するとか、ラグラージで詰むとか。自分の構築の弱い部分は常に考えて補えるように考えていく必要がある。
勉強法を決める
「結果を最大化するために考え続ける」ことが「全力」であるとかかれている。全力で立ち向かうことこそが勉強法なのである。
自分に合った「目的・目標」と「手段・方法」を見つけるために考え続ける必要がある。
そして、今の自分の位置を把握しておく必要がある。
概念的な話なので、ポケモン対戦でわかりやすく例える。
まず、レート対戦で勝ちあがっていくためには、負ける確率を減らす必要がある。
基本的にポケモン対戦は、自分の戦術の強いところを相手に押し付けることが大事で、勝つコツである。いかにして、その強みを押し付けられるかを考え続ける。
これが「結果を最大化するために考え続ける」ことであり「手段・方法」である。
自分に合った「目的・目標」はここでいうところのレートである。過去のレートシステムだと各シーズンは1500から始まり勝てば増え、負ければ減っていく。レート帯によって戦い方は変わってくるが、目標が2200なのか2000なのか1800なのかによってとる戦法も結構変わってくる。ソード・シールドだとマスターボール級を目指すとかである。
これが自分位置を把握し、今のレートで勝つための方法や目標を理解することである。
なんとなく理解できたであろう。または、逆にわからなくなったであろう。
大体こんな感じで進んでいく。
信じる→疑う→信じる
自分にあった勉強法を見つけたらとりあえず信じて実践してみる。
その方法で結果が出続ければいいが、本当にこの方法を続けていくことで結果(試験の合格)につながるかを一度疑い、再び精査してみる。その結果をまた信じて試してみるといったことを繰り返す。
品質管理で使用されるPDCAサイクルみたいなものである。
Plan(計画)をDo(やってみて)してCheck(評価)してAction(改善)するアレである。
まさにポケモンバトルである。
とりあえず構築したパーティでバトルをする。しかしどうしても苦手な並びは出てくる。対策必須の戦術や構築がどんどん出てきて環境が変わってくる。
例えば、過去にバンギランドルカアロー(バンギラス+霊獣ランドロス+ルカリオ+ファイアロー)の並びにボコボコにされた経験が貴方にもあるだろう(無い)。
今のままじゃこの構築には太刀打ちできないなと疑い、改善して試していく。これを繰り返していく必要がある。わかりやすい。
1日1点上げる
受験勉強を想定して書かれていた部分ではあるが、資格試験でも変わらないだろう。1日1点上げることを考えて勉強していく。それを毎日確認する。
「今日は1点分になるような勉強をできたな」と自分で思えたかどうかを考え評価する。
ポケモンのレート対戦の場合下がることもあるし不調な場合全く上がらないので全体の勝率を少しでも上げることを考えるのに近いと思う。
基礎は大事
解き方がわからない問題に直面した際に、自分の知ってるジャンルの問題なのに
「この問題習ってない範囲の知識を使うのか…?」と訝しんでしまう。
全範囲を満遍なく履修し、基本を理解していれば、最低限どのジャンルの問題でどういう解き方を使えばいいかくらいは分かるという。
しかし、未履修の分野や苦手ジャンルがあるとそれができないため、余計な思考や時間を使い正しい選択が出来なくなってしまう。
そうならない為に、基礎を固める必要がある。
ここでいう基礎とは、教科書に直接載っているもののことであり、資格試験でいうと参考書に載っているもの全てである。よって、応用とは、基礎を組みあわせてできることとする。
ということでまずは、基礎の完成を目指す。
基礎の完成とは「どの問題が出てもどのジャンルからの出題かある程度分かること」とされている。
なんと例としてそのまま本の中で、
ポケモンで言うなら「相手のポケモンがどのタイプか一通りわかる」
と書かれていた。ポケモンに例えるのは間違ってなかった。
もっと言うと個人的にはタイプ相性を複合タイプ(ドラゴン・地面タイプのポケモンとか)も含めて全部を覚えておく必要がある。
応用は、型(努力値配分、技、持ち物、特性、etc…)、戦術、並び(上記のバンギランドルカアローみたいなもの)あたりである。どのポケモンがどこの弱点を補完してるかとかを読み取れなくてはいけない。
教科書に書いてあることは全て基礎だから覚えておくって言われると「東大受験生意味わからん…」と思うが、ポケモン対戦に置き換えると「まぁあたり前か…」と思えてしまう。不思議だ。
暗記
暗記は、マクロ暗記とミクロ暗記を活用する。
暗記のプロ、クイズ王らしい考え方だと思った。
マクロ暗記
マクロ暗記は「大枠を覚えておけばいいもの」である。大事な構成要素や繋がりをある程度覚えておけば良いもの。
キーワードや繋がり(物事の流れ、ストーリー)を覚えていれば大丈夫なものは要点だけ覚える。
伊沢さんの場合、ピース(構成要素)が何個あったかを覚えるようにしていた。
記述問題等に役立つ。
ミクロ暗記
ミクロ暗記は細部まで覚える必要があるものである。漢字の書き取り、英単語の綴り、数学の公式等の間違えると点にならないものである。
反復して練習して記憶して行く必要がある。
ポケモンで言うと素早さの種族値の暗記が近いと思う。昔は70族、80族、100族、130族あたりは暗記必須だった。
この辺はミクロ暗記する必要があるが、採用率が低いポケモン等は、大体この辺よりは遅い・速いと感覚で覚えていた。これはマクロ暗記だ。
キノガッサより速いかどうか、ガブリアスより遅いかどうかが分からないなんて、こんな恐ろしいことは無い。
マクロ暗記のとてもわかりやすいポケモンバトルの例として、最初に自分がギャラドス、相手がブーバーンを出したとする。
(持ち物は今回考慮しない)
ブーバーンはあまり対戦で見かけないが、タイプとタイプ相性は基礎だから覚えていて分かるとする。炎タイプだどうみても。水かけたら息絶えそうだ。
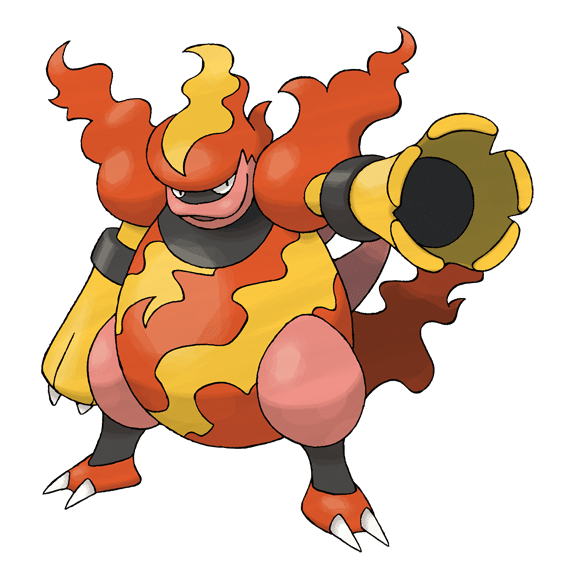
あなたのギャラドスは最速(ようき(1.1倍)、個体値31、努力値252)だが、相手の素早さが分からない。マクロ暗記をしていなかったばっかりに…。
そもそもブーバーンについて知らなかったら殴ってくるのか腕から炎を出すのか、防御が高いのか特殊防御が高いのかもわからない。マクロ暗記をしていなかったばっかりに…。
ギャラドスの素早さ種族値は81だが、ブーバーンなんか速そうにも見えないので、自分はとりあえず水技のたきのぼりを選択する。
結果は、ブーバーンに上から(ギャラドスより先に行動し)電気技の10万ボルトを撃たれてしまう。こちらのギャラドスは水・飛行タイプで電気が4倍弱点なのでやられてしまう。マクロ暗記をしていなかったばっかりに一気に不利になってしまう。

ブーバーンは素早さ種族値が83であり、最速だとギャラドスより僅かに速い。そして電気技の10万ボルトを覚えるし、ギャラドスを倒しきるだけの特殊攻撃力もある。無知ほど怖いものは無い。
暗記はアウトプット
最初に学習したインプット以降の振り返りはアウトプットで覚える。
アウトプットはインプットを兼ねる。
アウトプットする際に絶対インプットを経由する。
具体的な例を言うと、ブーバーンを育てて対戦で使ってみれば良いのである。否が応でもブーバーンと対峙した時に何をして来る可能性があるか覚えることが出来る。
つまり、ミクロ暗記する必要があるポケモンは全部育てちゃえば良いのだ。
復習はとても大事
なんで間違えたか、何を覚えていなかったかをしっかり振り返り復習して覚える。復習と暗記も一緒だと言われている。
ポケモン対戦は運ゲーで負けるクソゲーなので、復習しても仕方ない戦いもあるが、プレイミスで負けたり選出したポケモンが噛み合わなくて負けた時は復習して活かすことが出来る。
おわりに
読んでくれた人の大半を置いてけぼりにして、自分の中でかなり整理出来た。ポケモンに落とし込むとすんなり教えが入ってくる。
まとめると、
まず、試験の内容を把握し対策を練る。
参考書を全部読んで基礎を固めて、問題をやって、苦手なジャンルを理解して、暗記してアウトプットして問題をまたやる。
1日1点分得られたかどうかを日々確認する。
勉強法も定期的に見直す。
ポケモン対戦にすると、
まず、対戦環境を把握し対策を練る。
タイプとタイプ相性を全部覚えて、対戦をして、苦手な構築を理解して、孵化して育成して対戦をまたやる。
1日1ポイントでもレートをあげられたかを確認する。
環境や構築も定期的に見直す。
これで勉強が出来るかどうか、、、それはまた別のお話。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
