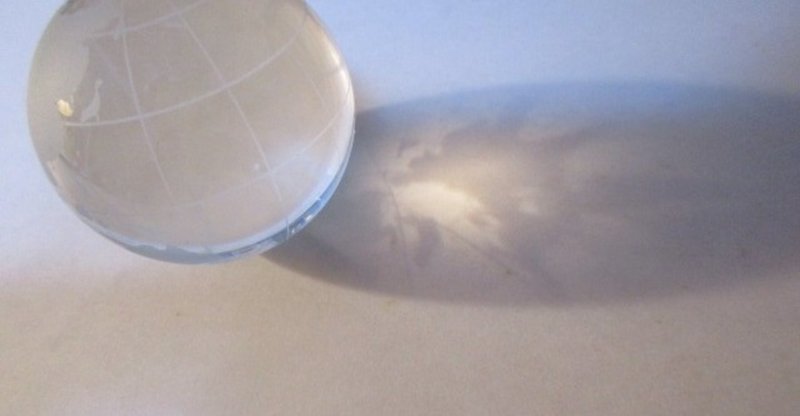
私の詩歌の作中主体は何者だ
こんにちは。銀野塔です。
詩(筆名:塔野夏子)、五行歌(南野薔子)、短歌(桐野黎)、俳句(星野響)と四つの詩型に手を出している不埒者だが、さてそんな私の書く詩歌の「作中主体」とは、としばらく前からあらためて考えている。
作中主体=自分、っていうことがはっきりしている方もいると思うし、そうでない方もいると思う。私の場合、詩歌に書く内容はフィクション100%からノンフィクション100%までグラデーションしているが、どちらかというとフィクション寄りなこともあり、作中主体は必ずしも自分ではない。
特にフィクション味が強い場合など、自分でも自分の作中主体に対して「誰やこいつ?」って思う。年齢とかもよくわからない。あと、一人称で「僕」を使うこともあるけれども、だからといって自分がジェンダーを超えて男になったつもりになっているとか、そこまではっきりした意識で使っているわけでもない。うん、作中主体は年齢もジェンダーも、自分にとってさえ不詳なことも多い。そういや五行歌集『硝子離宮』(市井社)に載せた歌に
男でも女でもない
大人でも子どもでもない
曖昧な生命体として
此の世の生を
呼吸している
っていうのがあるんだけれど、これは詩歌を書いている作中主体の自分の実感という意味ではノンフィクションかもしれない(ややこしい)。まあノンフィクション100%の詩歌でも、たとえば「アラフィフ女性のリアリティ」みたいなものを感じる読者の方は多分いないと思うけれど。
いやまあ、リアルな私も、結構ジェンダーも精神年齢も曖昧なところにいるとは思う。ただ、書かれた詩歌がフィクションだろうとノンフィクションだろうと、私はそこに「リアルな私」を見て欲しいとは別に思ってないな、ということに最近あらためて気づいた。私は私が思ったり感じたりイメージしたりしたことを詩歌にするんだけれど、それを「私が」思ったとか「私が」感じたとか「私が」イメージした、ってことを別に云いたいわけじゃない。それを書いた私がどういう人間かを詩歌を通じて理解してくださいと思っているわけでもない。そういう「私」は透過して、その詩歌を読んだどなたかが、波長が合うと感じてくださって、それを自身の感覚として共有してくださると嬉しい、と願っている。
私にも自己顕示欲はあるけれど、私がどういう人間か、どういうことを思ったり考えたりしてるかを理解して欲しい、という場合は、こうやって散文で書く方が手っ取り早く、かつ、より正確(私の場合は)だと思うし。
ただ、私の場合、上記のように詩歌で「私」という人間をあらわしたいとは思っていない、ということも含めて「どういう詩歌を書きたい人間なのか」ということは、わりとはっきりしているかもしれない。どういうテーマを書くか、どういう語彙を使うかの境界線がわりとはっきりしている方だとも思う。「私はこういう人間です」ということを詩歌で主張したいとは思わないが「私はこういう詩歌を書きたい人間です」ということははからずもかなり主張していると思う。
で『ねむらない樹』(書肆侃侃房)のvol.5で「短歌における「わたし」とは何か?」という特集があって、興味深く読んだのだが、その中にあった大辻隆弘さんの「「私性」という黙契」という文章によると、私の「こういう詩歌を書きたい人間です」というのがあらわれているというのも「私性」のひとつのかたちらしい。
つまりは私の場合、作中主体=自分でないことは多いし(特に恋愛ものなど、語り部の位置で書いていることも多い。読者から見れば、私は作中主体自身に見えるかもしれないようなものでも)、自分である場合もそれが自分であることに重きを置いていないが、作品としてのあり方には強めの私性があるタイプ、ということなんだろう。
ただ、作品中の自分は透過したい、フィクション成分が多い、というのは事実なのだが、それはそれとして、書くものは「自分の中にあるものしか出てこない」こともまた事実である。フィクションであれノンフィクションであれ、私性がどういうあらわれ方をしているのであれ、それは「自分から出たものだ」ということはきちんと引き受けないといけないと思っている。当然と云えば当然のことだけれど。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
