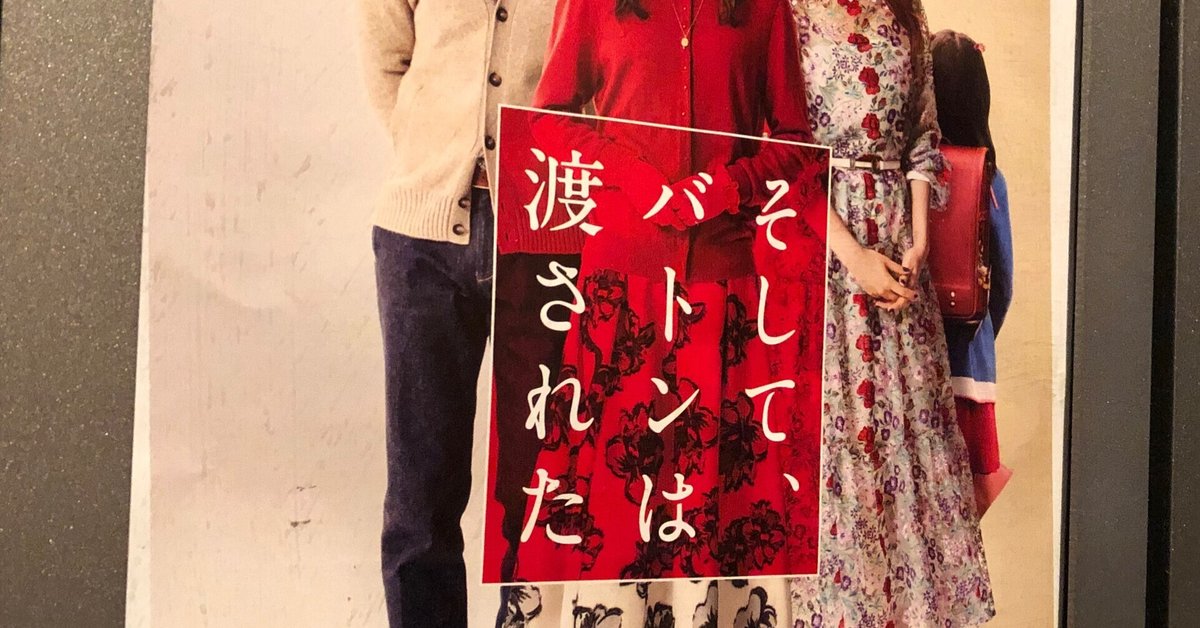
そして、バトンは渡された。もう一人の優子
2021.10.29公開 映画「そして、バトンは渡された」を観賞した。
あらすじは割愛。こちらでは、映画、原作の両方を踏まえての感想を書いていく。
原作未読で観た映画の感想
梨花とみいたん、森宮さんと優子。
中盤でその関係性が明かされるまで随所にヒントが散りばめられていて、意図的に時系列を操作されつつも式場の控え室でのみいたんと森宮さんの対面シーンで、「やっぱりそうだよねー」と、気持ちよく答え合わせができる。
ずっと何も知らずに騙されるというよりは、「これってそうかな?」「そうだよね?」と思わせることで、種明かしの際にはある種のカタルシスを得られるようにしたのでは思う演出だった。
みいたんのと対面シーン。子供がいることを知らされていなかった森宮さんが、さすが「困惑させたい俳優殿堂入り」の田中圭さん(私調べ)だけあって、実にいい困惑っぷりで、作中でも特に好きなシーンの一つとなった。
卒業式で優子と赤いドレスのみいたんと重なるシーンでは、まんまと泣かされる。
幼い頃から優子を守り育ててきた森宮さんの感情がダイレクト伝わってきて、試写会で涙したという92.8%に入ってしまい、少し悔しかった。
終盤で、梨花の病に気づかなかったことで責められ、全て「俺が悪い」と悲痛な表情で受け止めた森宮さんは、優子の人生の喜びも悲しみも全てを受け止める覚悟をした父親の顔で、悲しい場面ではありつつも優しさで溢れる「親子喧嘩」のシーンだった。
早瀬くんも良かった。
岡田健史くんは、天才ピアニスト高校生という設定に負けない存在感がまさに早瀬くんに適任だった。
数年後に再会してお互いの気持ちに気づくシーンの二人は、たっぷりと間を取ったあの静寂にも負けない瑞々しさだった。
今作のキーマンとなる梨花の存在。自由奔放でどこかミステリアスで、文字通り人生と命までも賭けて優子に無償の愛を注ぐ母親を、石原さとみさんが好演していた。
幼いみいたんとのシーンはカラフルな画面が楽しく、同時に描かれる森宮家にも共通して置かれるインテリアを探すのもまた楽しかった。
最後まで優子の記憶には笑顔のままの梨花しかいなかった。「ずっと死なないでほしい」というみいたんとの約束を守って。
「会いたかった」と森宮さんを責めて泣いた優子も、最後には梨花のその想いを受け入れて前を向く。
ラストの優子と早瀬くんの結婚式。
他の二人の父親からも背中を押され、優子の3人目の父親として早瀬くんへとバトンを渡す。
バージンロードを歩く直前の森宮さんと優子のやり取りにもやはりまんまと涙を誘われる。もうここまでくると森宮さんが泣けば自動的にこちらも泣いてしまう仕様が出来上がっている。
そして、バトンは渡された。完璧なタイトル回収。エンドロールの、優子の代々の名前と共に2人の母、3人の父親たちとの写真が結婚披露宴のスライドショーよろしく流されると、優子の半生を見守ってきた擬似家族のような気持ちになってしまった。
境遇だけを考えれば不幸な女の子かもしれない。そして世の中には血の繋がらない親子の悲しい事件や、血の繋がりがあっても、いやあるからこそ悲しい事件もたくさんある。
そんな世界だけど、この世界のどこかに、この親子たちのように、ただただ温かくて優しいだけの物語があってもいいじゃないか、と思えるそんな映画だった。
エゴとも思える親たちの行動を、優子は赦した。愛と赦しの物語だな、というのが映画を見終わって一番に浮かんだ感想だった。
以上が、原作を未読の状態で映画を観た感想である。
原作と映画の相違点
さてここから少し批判的な感想が増えるので、原作未読、または映画について批判的な感想は読みたくない方はお戻りください。
試写会の後に原作を読んだ。面白くて読みやすくて一気に読んだ。
読み始めてすぐに「映画の脚本が敢えて時系列を入り組んだものにして謎を作り出していた」ことに気づく。なるほどこれはエンタメとして面白いことをしたなと思った。
淡々とした雰囲気の原作に映画としていいスパイスになっていたと思う。
特に違う点は
①水戸さんは転勤でブラジルに行った
②森宮さんと暮らし始めたのは優子が高校に上がってすぐ
③優子と友達関係、先生との関係性、合唱は卒業式ではなく合唱コンクール
④早瀬くんとの結婚前まで森宮さんと暮らす
⑤梨花は作中では亡くならないし、優子は梨花と再会できるし、梨花は結婚式にも参列する
①は映画では梨花が水戸さんに惹かれた理由として「夢」をあげており、変更は頷ける
②は、優子がまだ小学生の頃に家族になっており、年齢差の少ない親子(原作では「好きになったりしないの?」などと友達に聞かれたりもする)に説得力が増して、映画の卒業式のシーンの感動を生む要素にもなっていた。
小説ではもっとたくさん二人のエピソードが綴られるが、映画では尺的にもそうはいかない。また生身の俳優たちが演じることで生まれる生々しさが、「幼い頃から親子として暮らしていた」という変更点でいい塩梅で消えていた気がする。個人的にはこの変更点は良かったと思う。
③やはり尺の問題もあるかもしれないが、映画では、友達と先生たちの描き方はかなりステレオタイプになっていた。優子の上部だけしか見ていないようにも感じるし、「調子のいい人たち」に見えてしまう。
合唱コンクールから卒業式になったのは、映画ではみいたんと優子を重ね合わせ、感動を生むいい要素になっていたと思う。
④こちらは、映画では早瀬くんと心を通わせる過程が見られて良かった。映画の森宮さんは原作よりも早くから優子と家族になっていて共に暮らした年数としてはトータルで同じくらいになったかもしれない。
⑤これが最大の相違点。なぜそうしてしまったのかな、と、原作を読んで思ってしまった。
私は映画を先に観たので、原作を読んである意味「救われた」
優子は、梨花に会えていた。映画の優子が「会いたかった」と泣いた梨花に、ちゃんと会えていた。と同時に、映画の優子がとても可哀想に思えてしまった。そりゃ会いたかったよね。会いたかったと森宮さんをなじってしまうほど、梨花に会いたかったのに。
優子と森宮さんのあの悲しい親子喧嘩のシーンは、この変更点があったからこそ生まれたシーンでもあった。あのシーンは確かに森宮さんの大きな愛を感じられるいいシーンではあるけれど、個人的には梨花を作中で亡くならせる必要はなかったのではないかなぁ、と思わずにはいられない。
梨花の深い愛、森宮さんの大きな愛、他にも強調する方法はあったのでは。
フィクションでの生死観というのは、好みにも寄るけれどとても重要で、死が「泣くためのアイテム」になってしまうように映るのは、出来れば観たくない。
泣かせたいのであれば梨花と優子の再会、病をおして結婚式に参列する梨花の様子でも大泣きできたと思う。
優子は親たちの愛ゆえのエゴに振り回されて生きてきた。最大のエゴは、幼い優子を水戸から引き離し、手紙を送らず、届いた手紙を隠したこと。二人が失った時間は取り戻せない。それだけでも十分に理不尽でやり切れない出来事だったと思う。優子が余命いくばくもない梨花と再会し、花嫁姿を見てもらう、そんなささやかな幸せまで奪わなくても良かったのになぁ…と、どうしても思ってしまう。
映画も原作も優しい世界で、多少利己的ではありつつも、いい人ばかりが登場する物語だ。
ならば徹底的に優しい世界でも良かったのでは、と、原作を読んだが故に思ってしまった。なんともやるせない気持ちである。
だが、映画は生身の俳優たちが登場人物たちに命を吹き込み、すべてのキャストがまさにハマり役で、映像も音楽も素敵な世界だった。
最終的には、原作を読んで観るのと、読まずに観るのとではかなり感想が変わりそうな映画、という感想になった。
だが、原作を読んだことを後悔は決してしない。なぜならやはり原作は本当に素敵な物語だし、映画とはまた違う優子たちが生き生きと暮らしているから。
それでも映画の最後には泣いて微笑む
と、ここまで散々相違点について否定的なことを綴ってはきたが、映画は映画としてとても良かった。
映画と原作では、また別の優子の物語だ。梨花との再会は叶わなかったけれど、映画の優子は梨花はどこかで生きていると思って前を向いて笑うし、森宮さんから貰った腕時計を付けてバージンロードを歩くし、早瀬くんにベールをあげてもらって、誓いのキスの前に本当に幸せそうに笑う。
そしてなによりも優子が永野芽郁ちゃんと稲垣来泉ちゃんで、森宮さんが田中圭さんで、梨花が石原さとみさんで、泉ヶ原さんが市村正親さんで、早瀬くんが岡田健史くんで、みんな本当に素晴らしく登場人物たちを生きていた。
また、原作小説とはまた違うアプローチで映画というエンタメで観客を楽しませたいという、製作陣の想いは十分に伝わる作品だった。
あくまでも個人的なひとつの感想です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
