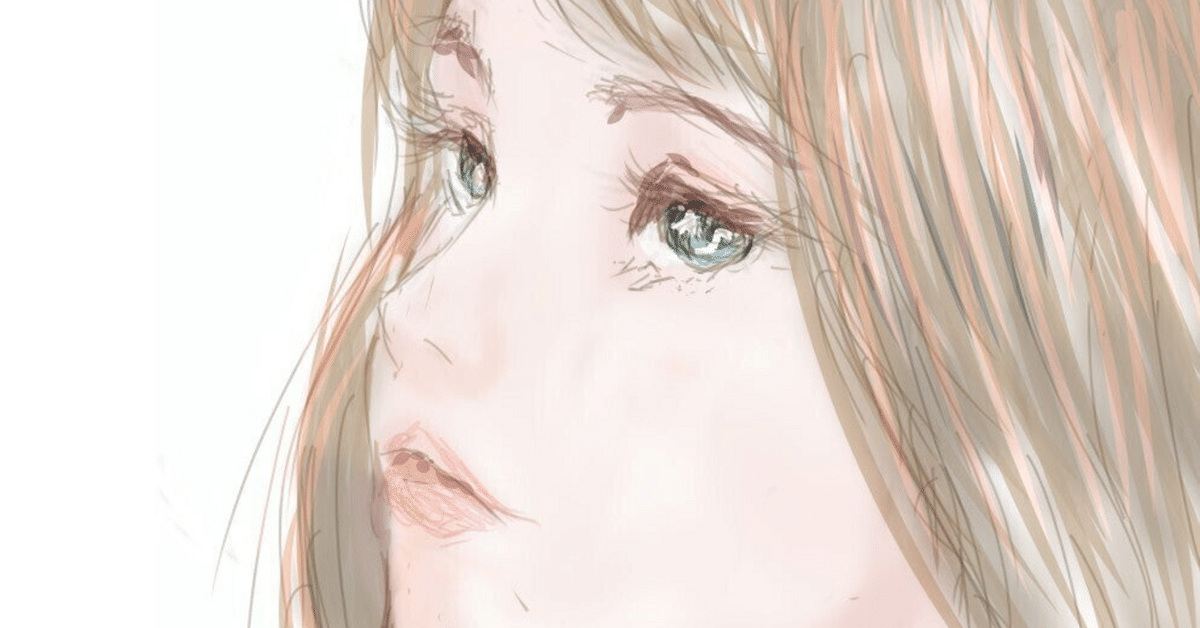
精神現象学批判 草稿
ここに、今から発言されることは、未だ、荒さの残る駄文と見做してもらって構わない。ただ、無用な文章をつらつらと書き上げることに何の意味があろうか。本文の形式は、何かしらの問いを常に孕んだ状態で、進行していく。問いの優位性とは、絶望してしまった精神が、一縷の希望を見出すためには必要不可欠な、そういった可能性の集合である。問い自体の重要さは、ハイデガーもその序文で提示しているわけだが、問いを発する時には、背後にすでに想定された答えを保有しているというのは、些か決定論じみてはいないか。確かに最も絶望すべきは、何をしたらいいのか、何を私は問うことがあるのだろうという緩慢とした情況であって、次いで、私には遂行しなければならなない使命があると思い込んではいるが、それらを解決するためには、矛盾した情況が良くないといったような類の絶望である。問いというのは、たとえそれが、疑似命題のようなものであっても、回答の席は用意がされている。文法的に「神とは何か。」と問うことの何処に不自然さが見られるのだろう。しかし内容が伴わないとすれば、これは正しく第二の絶望の情況ではないか。私らの問いの契機は、可能的な状況を見たい。その為には、物事を現象的に見ることを止めてしまってはいけない。つまりはこうである。こうした絶望の最中でも、我々はその歩みを止めることがない。絶望の形式の中で雁字搦めに取り込まれてしまって、自身の矛盾した有り様を即座に引き入れることはない。ある運命論者、宿命論者が、その決定を我が物にするには早すぎる。世界は未だ不条理な様相を呈していて、我々がそれに倣おうとすれば、人々は狂気的になる。つまりは戦争の翳に埋もれた人たち、つまりは問うことの光の部分。





弁証法運動は、語られなければない。しかし、あらかじめ語られることに何の意味があるのだろうか。とりわけ、『精神現象学批判 草稿』などと題したのは、ヘーゲルの働きが大きいのは事実である。もはや弁証法を使わずして歴史を語るというのが、非常に困難になるくらいには、この発明の功績は大きい。弁証法運動が規定するのは、持続する真理としての自己の関係である。つまり、この関係を記述する為に初めて時間という概念を正確に打ち出したのは、ヘーゲルなのである。この時点を境にエピステーメーは表象から人間に乗り出したのであり、単なる観念論は現象学的なアプローチへと移行していった。では、私は何を問題視しているのか。なるほど彼は、理性が絶対知へと至る過程を円環構造の必然性に仕立て上げた。さて、時折り考えるのは、ニーチェとヘーゲルとの時間への感覚の近さについてである。ニーチェのインモラリストを排すれば、ヘーゲルとの接続はそれほど難しくはない。毎時更新されていく否定は、生成と同義であり、そして、廃棄されて単一化された概念を、無限回繰り返すのであれば、永遠回帰(つまりはこれも円環を象ってる)していると言っても差し支え無いのではなかろうか。両者の類似点はまた、啓蒙的な性質を合わせている。公共的な問題を、私的な問題に還元すること、この原子論者の夢に抗えなかった個人なのである。ニーチェならば、不道徳な道徳という具合に。さて、話を決定論的な事由について戻されたい。我々はこれまでは感じることの無かった時間意識に根差し、過去との関係によって、未来をも関係していると思いがちである。例えば、フーコーの「人間の終焉」、彼もまたアイロニストの枠を出て、大層なことを口にしてみているが、彼の冷静さを押し拡げた文体から、このような言葉が飛び出てくると、まるで女子大生が女子高生に向かって、「若いねえ」と漏らしているような転倒っぷりが見て取れる。我々は、自己同一性のもと、言葉と物との関係を記述することができる。それは確かにそうなのだが、同一性が担保され得ない状況の中で、いかにそれが記述されようか。そういうことを軽々しく現象学と言ってしまえることに躊躇いは無いだろうか。「あるものはある」というパルメニデス流の禅問答なのでは無いか。
同時に、二元論の問題もある。それは、「生と死」の対立だったり、「物質と精神」、「美味いか不味いか」であったりする訳である。では、熟練の話者がその両極に答えがあるわけでは無いと言って、「答えは中間にある。それこそが中庸だ」と発言したとすれば、この問題は片付いたことになるだろうか。では、二十代である私は、「七割生きていて、三割死んでいる。」という言い方が可能なのだろうか。正規分布の平均値のように(中央値、最頻値についても同様)、妥協した中間の値が良い状態とするのはいかがだろうか。質と量の混同のケース、もしくは民主主義の限界。ベルクソンが『物質と記憶』の中で、二元論を解消したように思えたが、実際のところその願いは叶ってはいない。

有名な逆円錐形モデルだが、底面ABの純粋記憶と物質世界、平面Pに対する接点Sは純粋知覚、それらを媒介するイマージュ領域が底面A’B’だったり底面A’’B’’だったりする訳だが、これらのモデルには色々な疑問がある。第一に、質と量の混同を招く表現では無いかということ。確かに連続的なモデルで、二項の関係は解消されてはいるが、上で既に述べたように、量的な感覚が先行してこのような図式を作ったのでは無いかということ。そうであれば、シェリングが同一哲学の中で似たようなことを既に考察している。これらの連続的な底面のそれぞれで質的な変化があるとは考えづらい。第二に、純粋記憶の底面に関して、その地点は何処か。おそらく都合で書いたのだろうが、終局の地点を、無限遠面にすることで必要な厳密性を失い、現実より奇なるものにしてしまった。直感的なプラトニズムであり、彼の想起されたアイデアは、オリジナルとコピーの二重性を否定するものだったけれども、当にその二重性によって自らの思考を否定することとなった。平面や接点の疑惑についても例に漏れない。またはその外部の状況も。
しかし、彼の考察が興味深いことは確かだ。そして実際には持続的時間に対しては質的変化されることは記述されている。これは物書きの悩みだが、実在について、言葉で書き写す時に、空振ってしまったり、余計なことを書いてしまうのは、内容からすれば、ある程度仕方がないことである。では持続は、万華鏡を覗くようにして起こるのだろうか。そこに記憶が絡んでくるのだとしたら、その綺麗な模様の何処に表れてくるのだろうか。ベルクソンは少なくとも決定論者ではなかった。なぜならば筒を回転させた時に新しい模様がどのように表現されるかについてまでは、言及しなかったのだから。彼は多様性についての目利きがある。
いかにして、他者を理解するかというのもまた、哲学の最重要事項のひとつである。そして先程から、決定論を目の敵にしているのは、モラリストとしての一面が反応しているからに他ならない。ただし、運命という概念はある。物語、一般に作品においては、作家と読者の関係は作品を通じて鏡写しの関係にある。そこで作家は、読者という他者に対して、自己の都合を了解可能な形で表現することによって、承認を得る訳だが、読者もまた作家という他者を自己同定する形で承認を得る。つまりこの時、作品は間に立って、互いがエゴイズムを放ってきたのを、それを透過させることはなく、そのまま各々に返却する訳である。もし、この半双方向のコミュニケーションがあるだけならば、どれだけ虚しいかを酷く痛感するだろう。決定論的な思考が常に抱えているのは、このようなリスクである。皮肉なことに、悲劇が多いのである。
自己同一性について、弁証法運動とは、ある場所からある場所へとあるものが移動した時に起こる不連続な断絶を、ある経験的な規則によって連続的に平す恒常性の働きである。ひいては、実存的情況に置かれた現存在が存在者として存立するための効果である。断絶的な場合とは、自己の外部に自己に包摂され得ない存在がある状況であり、同一性とは、その他在している概念を自らに包摂することで、自己に帰する概念となり、それが単一の概念となることで自己を拡大していく性質である。つまりは辻褄を合わせるための機能である。ある複数の場面、例えば、やかんとカップヌードルがあれば、この二つの尤もらしい場合を思考し、私らはカップヌードルにお湯を注ぐ情景をイメージすることができる。しかし、実際には、ポットでお湯を入れたかもしれないし、そもそも作ってすらいない可能性もある。だけども映画なら、フィルムの先にレトロな部屋があって、白いタンクトップのどうしようもない親父がやかんに水を張るシーンと、カップヌードルを食べている描写があれば、間違いなくそうしたと思うはずだろう。
弁証法運動が問題視されるケースは、自己の度量を増す度に抽象化された理性が、歴史を動かした英雄的、象徴的な事態に関心が向くことはあっても、アクチュアルな視点では、庶民的な階級や非常に小さいイレギュラーな事態には関心を示しづらくなることである。ナブコフの『ロリータ』では、カスビームの床屋の主人が、主人公を散髪しながらも、時折り、唾を後頭部に飛ばしたり、息子の栄光譚を話したり、散髪する手が止まってしまう場面があるが、よくよく読んで、主人公の視点から外れてみると、実は亡くなってしまった息子を悼んで、涙していたことを知るというような仕掛けがあったりする。このことは、私たちがいかにいつでも残酷になりうるかを示唆している。
これらの哲学では、目の前にいるたったひとりの人間に対してすら分かるものはない。どうして私はいつも私のことだけしか見れないのか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
