
「ハング・オン・リトル・トマト」 ピンク・マティーニ HANG ON LITTLE TOMATO PINK MARTINI
これぞワードミュージックのニュー・スタンダード
「ハング・オン・リトル・トマト」とピンク・マティーニ
佐藤利明(オトナの歌謡曲プロデューサー/娯楽映画研究家)
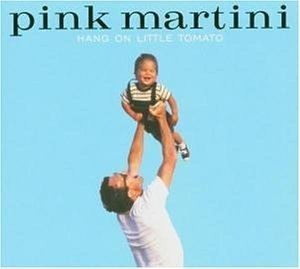
「僕たちは音楽で“世界一周”をしているようなものさ」。かつてピンク・マティーニのリーダーでピアニストのトーマス・M・ローダーデールは、こう語った。オレゴン州ポートランドをホームタウンとする、12人編成のオーケストラ・グループ、ピンク・マティーニは、21世紀の現在に居ながらにして、まるで1940年代のハリウッド映画の中に入り込んでしまったような体験を提供してくれる。
彼らのCDを聴いたり、ライブを観ていると、ある時はパリのバーレスク劇場、またある時はリオのカーニバル、そしてナポリでカンツォーネを楽しんでいる、そんな不思議な気分を味合わせてくれる。1970年生まれのトーマス・M・ローダーデールは、自らを“音楽考古学者”と自認しているように、彼らはこれまで世界中で作られた、様々な音楽のなかから、自分の琴線に触れる“美しいメロディ”を発掘し、再現することで、リスナーに心地よい時間と空間をもたらしてくれる。
トーマスの音楽の窓は、ポートランドにある中古レコードの店のワールドミュージックの棚や、テレビの深夜放送や週末映画館で上映される往年のハリウッド映画。リアルタイムに間に合わず、遅れてきた世代の“悔しさ”や“歯がみ”が黄金時代への探究心を掻き立て、博覧強記の“音楽考古学者”へと仕立て上げているのだろう。
ぼくが初めてトーマスと出会ったのは、2010年3月10日。アメリカツアーとアジアツアーの合間に、アルバム「草原の輝き」のプロモーションも兼ねて来日したときのビルボードライブ東京のリハーサルの場だった。トーマスはピアノに向かって、ビンセント・ユーマンの「カリオカ」を弾いていた。「フレッド・アステアの曲だね」と声をかけると「君、アステア好き?」とトーマスはニッコリ笑った。
それから二人は、MGMミュージカルのスターで誰が好きか? どのナンバーが好きか? どのスターがまだ健在か? という、マニアックなミュージカルの話題でひとしきり盛り上がった。そこでトーマスが「今後、ジェーン・パウエルとハリウッド・ボウルで共演するんだ」と嬉しそうに話してくれた。ジェーン・パウエルといえば1940年代末から50年代にかけて『スイングの少女』(1948年)や『略奪された七人の花嫁』(1954年)などのMGMミュージカルで活躍した可憐なスター。もう80代を迎えている筈の彼女とピンク・マティーニがステージで共演する! オリジネイターとリスペクターが一つのサウンドでつながる、これこそピンク・マティーニなのである。
そのとき、ぼくはピンク・マティーニが、なぜ由紀さおりや和田弘とマヒナスターズ、美輪明宏といった日本のアーティストの楽曲をカヴァーし、時にはご本人と共演するのかが、なんとなく判った。とにかく“好き”なモノやコト、ヒトに対して、最大の讃辞を送りたい。自ら素晴しいと思ったら、すぐに行動を起こす情熱がトーマスの原動力なのである。
この「ハング・オン・リトル・トマト」は、1997年にリリースされたファーストアルバム「サンパティーク」から実に7年ぶり、2004年10月19日に、彼らのレーベルであるハインツ・レコードからリリースされた。ちなみにハインツとは、トーマスが飼っていた犬にちなんで名付けられた。アルバム・タイトルにもなった“HANG ON LITTLE TOMATO”は、カリフォルニアの“ハンツ”というトマトケチャップ・ブランドが、1964年に雑誌「ライフ」に掲載した広告“Hang On, Little Tomato”にちなんで付けられたという。
古き良きアメリカの雰囲気が漂う、ポートランドのダウンタウンにある、1930年代からそのまま変わらない建物が、トーマスの住居であり、ハインツ・レコードのオフィスでもある。このビルの前に立つと、それこそフレッド・アステアやジェーン・パウエルの映画の中に入り込んでしまったような、不思議な気持ちになってしまう。
このアルバムは、カヴァー中心だった前作のテイストそのままだが、今回はほとんどが、バンドメンバーが書いた曲で構成されている。しかもフランス語、イタリア語、日本語、クロアチア語、スペイン語、そして英語と6つの異なる言語の歌が収録されている。曲調もジャンルも多種多様。なのに違和感は全くない、それどころか、実に心地よい世界となっている。これぞピンク・マティーニの味。
<楽曲解説>
1. レッツ・ネバー・ストップ・フォーリン・イン・ラブ
"Let's Never Stop Falling in Love"
イントロのキャッチーなヴァイオリンはザ・ハーヴェイ・ローゼンクランツ・オーケストラのヴァイオリン・セクション。作詞、作曲はバンド・シンガーでトーマスとはハーバード大学の同窓生のチャイナ・フォーブスと、トーマス。「レッツ・ネバー・ストップ・フォーリン・イン・ラブ」というフレーズは、フランク・シナトラ全盛時代のスタンダードのような味わい。それもそのはず、コード進行、曲の構成は、50年代のアメリカのスタンダードを踏襲。ストリングスとコンガ・セクションに、絶妙のタイミングで絡んでくるギャビン・ボンディのトランペットの官能と、チャイナのヴォーカルの絶妙な案配が楽しめる。
2. アンナ ”Anna (El Negro Zumbón) ”
“エルバイヨン”と男性コーラスが印象的な、この曲は1951年のイタリア映画『アンナ』(アルベルト・ラットゥアーダ監督)で、シルヴァーナ・マンガーノ(吹替えはフロ・サンドン)が歌った曲。1957年には、チェット・アトキンスがギターでカヴァーしたインスト版がヒットしてスタンダードとなった。ここでは映画ヴァージョンのテイストそのままにカヴァーしている。日本では、江利チエミが『サザエさん』(1956年東宝・青柳信雄)で歌ったものが、イタリア映画版を踏襲しているので、聞き比べも楽しい。
江利チエミ アンナ
3. ハング・オン・リトル・トマト ” Hang On Little Tomato”
キング・オブ・スイングと呼ばれたベニイ・グッドマンの演奏を思わせる、温もりのあるクラリネットは、ゲスト・プレイヤーのノーマン・レイドン。1940年代ハリウッド映画などでおなじみの、スイング黄金時代にタイムスリップしたかのような心地よいサウンドで、リラックスしたチャイナのヴォーカルが堪能できる。
4. サンプソンとビーズリーの庭で ”The Gardens of Sampson & Beasley”
ロマンチックなチャイナの歌詞、リリカルなトーマスのメロディ。まるで水彩画のような、美しいイメージが拡がるオリジナル・ソング。曲間にトーマスがピアノで「愛しのクレメンタイン」のフレーズを奏で、タイトルのサンプソンとビーズリーの庭に生茂る、色とりどりの草花を明るく照らす月光を感じさせてくれる。
5. ヴェロニーク ”Veronique”
前曲から一転、ブルーでジャジーなマイナーコードの「ヴェロニーク」は、トロンボーンとトランペット奏者、ロバート・テイラーのヴォーカルをフィーチャー。ここでは、ロバートがトランペットも担当。トランペッッターでヴォーカリストというと、チェット・ベイカーを連想する人も多いだろうが、この曲はまさしく50年代ジャズの味。ロバートはPink Martiniだけでなく、様々なステージの音楽監督も務めており、レコーディングでは、ホットで直感的なトーマスに対して、クールで知性的な面でサウンドに目と耳が行き届く人でもある。
6. 貴方とダンスを ”Dansez-vous”
こちらは、そのロバート・テイラーとチャイナが作曲と作詞を手掛けたフランス語のナンバー。タイトルは「貴方とダンスを」という意味。エキゾチックな “Dansez Dansez Dansez-vous”のコーラスはロバートのヴォーカル。この曲も以前から歌い継がれて来ているような、そんなデジャヴ感に包み込まれる。
7. リリー ”Lilly ”
トーマスとチャイナのオリジナル。ギャビン・ボンディのトランペットをフィーチャーし、ロバート・テイラーのセカンド・トランペットがクールな味わいを倍加させている。リズム・セクションとホーン・セクションのアンサンブルが、ウキウキした気分にさせてくれる。エンディングのダン・ファンレーのクールなギターは、007映画の作曲家ジョン・バリーのサウンドを思わせる。また2分45秒という演奏時間は、ジュークボックス時代のアメリカン・ポップスの平均的な長さでもある。
8.ただ一度 ”Autrefois”
ジェーン・バーキンのフレンチ・ポップスのような"Autrefois"もまた、チャイナとトーマスのオリジナル。“Autrefois”とは“ただ一度”の意味。
9. 青い夜明け ”U Plavu Zoru(In the Blue Dawn)”
パンシー・チャンのチェロの静かで力強い演奏に、忍び寄るチャイナのコーラス、そしてトーマスのピアノが歯切れ良くメロディを奏で、パーカッションがリズミカルにテンポを刻み出す。クロアチア語のヴォーカルのエキゾチシズム。ギャビ・ボンデイのトランペットの官能、渾然一体となって押し寄せるサウンド・・・ピンク・マティーニというグループの魅力が凝縮された一曲。コンサートでも必ず演奏され、観客が陶然とする名曲。"U Plavu Zoru"とは“青い夜明け”という意味。
10. クレメンタイン ”Clementine”
チャイナらしいリリカルな歌詞、トーマスの優しいメロディ。ロバート・テイラーのトロンボーンとチャイナのヴォーカルの透明感、1960年代のアメリカン・ポップスを思わせるテイストのサウンド。チャイナの等身大の魅力が発揮されたナンバー。
11. ナポリの夜 ”Una Notte a Napoli (A Night in Naples) ”
作詞は、1970年代にイタリアのステージやテレビを代表する女優アルバ・クレメンテと、NYのナイトクラブ“ジャッキー60”を中心に活躍していた人気DJ。作曲はチャイナとトーマス。イタリア語の歌詞は「ナポリの夜、月と海で、私は天使に会いました」という歌詞のロマンチシズム、アルバ・クレメンテのハスキーなナレーションが味わい深いカンツォーネ。
12. 菊千代と申します ”Kikuchiyo to Mohshimasu”
日系のティモシー・ユウジ・ニシモトが日本語で歌うのは、和田弘とマヒナスターズの「菊千代と申します」。作曲は鈴木庸一、作詞は山上路夫。1963(昭和38)年、マヒナが10吋のLP「魅惑のコーラス 第17集」のために吹き込んだ曲のカヴァー。トーマスが2000年頃、ポートランドにある中古レコードショップEveryday Musicのワールドミュージックの棚のJAPANコーナーで、このレコードを発見。トーマスはこの曲で琴を弾いているティムソン真澄に、和田弘にコンタクトを取って欲しいと依頼、2003年8月に、メンバーが来日してレコーディングに至った。和田弘自らがスライドギターを担当、2004年に病没した和田にとっては最後のレコーディングとなった。
和田弘とマヒナスターズ「菊千代と申します」オリジナル版
13. アスペタミ ”Aspettami ”
ダン・ファンレーのギターをバックに、静かにチャイナが歌い上げる"Aspettami" は、イタリア語で「私を待ってください」という意味。この曲もフランク・シナトラに歌って欲しかったと思わせる、スタンダードの要件を兼ね備えている。チャイナとトーマスは、ポピュラー音楽への造詣が深いだけでなく、その世界を巧みに再現してしまうのには驚かされる。
14. 黒鳥の歌 ”Song of the Black Swan (O canto do cysne negro)”
アルバムのエンディングは、パンジー・チャンのチェロとトーマスのピアノで奏でられる、静かなインストゥルメンタル。この「黒鳥の歌」は、ブラジルの作曲家、エイトル・ヴィラ=ロボスが1917年に発表した作品。ロボスはクラシックだけではなく、オードリー・ヘップバーン主演の映画『緑の館』(59年)のサウンドトラックなども出掛けた人で、クラシックの技法にブラジル音楽を取り込んだことで知られる。
よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。
