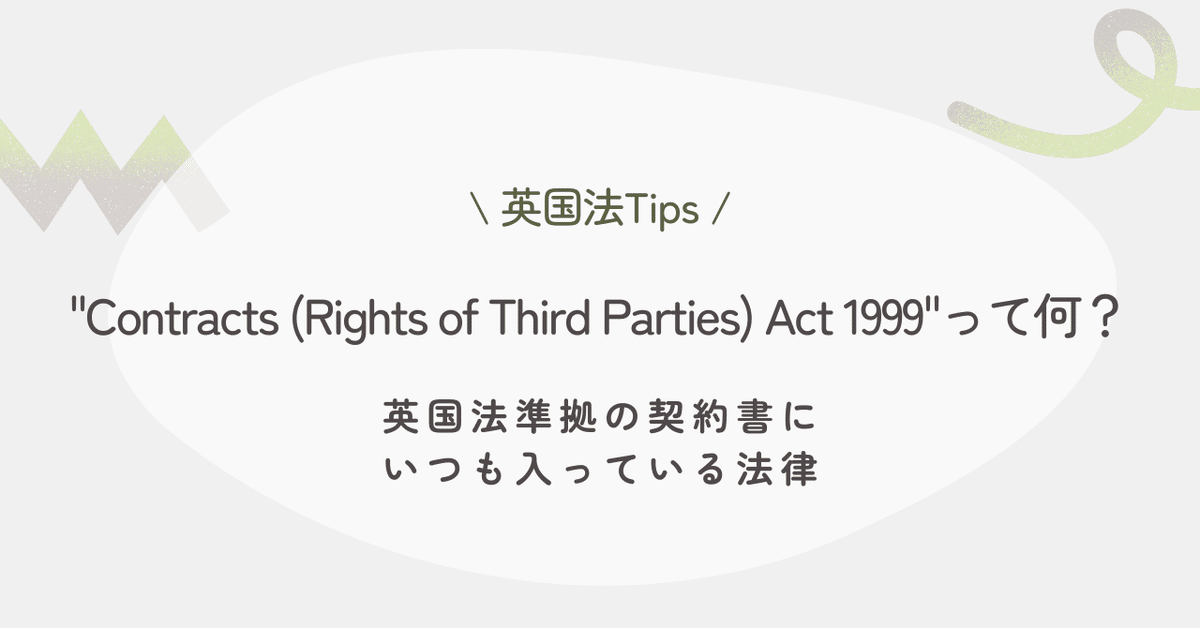
【英国法】Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 ー英国法準拠の契約書にいつも入っている法律ー
こんにちは。
お読みいただきありがとうございます。
タイトルを見て、「あれいつも入っているよね」と、頷いて頂ける方がいれば、ぼくの仲間です。そういう方は、このエントリーを読んで知識を再確認していただければ嬉しいです。
もし、何かの検索でこれにたどり着いた方がいれば、できるだけ分かりやすくまとめたつもりですので、ちょっと読んでやってください。
なお、法律事務所のニューズレターとは異なり、分かりやすさを重視して、正確性を犠牲にしているところがありますので、ご了承ください。
Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999とは?
契約上の第三者の権利について定めた英国の法律です。
なお、英国の法令のうち、日本の「法律」に該当するものがActと呼ばれるもので、「(内容)Act(制定年)」という名称になっています。
正式名称は長いので、ここからは、「TPR Act」と言うことにします。
前提知識:Privity of contact
TPR Actの意義を理解する上で、Privity of contractという概念に触れることが有益です。
日本語でなんと訳せばよいのか分かりませんが、「契約の当事者でない者は、その契約に基づいて訴えたり、訴えられたりすることはできない」という原理です。
日本で法学を勉強した人なら、契約によって生じる権利は「債権」なんだから、そりゃそうだろうという感じですよね。
ただ、英国では、債権/物権という分かりやすい二元的な捉え方はされていないという理解です。少なくとも、ぼくは、ロースクールや英国弁護士試験の勉強の過程で、そのようには教わっていません。
英国法では、債権という概念が無いので、その言い換えとして、Privity of contractが殊更言われているというのが、ぼくの私見です。
もっとも、Privity of contractは、Tewddle v Atkinsonという19世紀の判例(*1)に由来しているそうです。めっちゃ最近ですよね。こんな重要な概念が無い状況で、19世紀までトラブルはなかったのでしょうか(笑)
Privity of contractに対する批判
契約上の権利行使に第三者を関与させないことは、通常は合理的であるものの、これを徹底しすぎると、不都合が生じるという批判がされていました。
具体的には、日本でいう第三者のためにする契約を締結するような場面です。当時の英国法の下では、第三者のために契約がされたところで、日本法みたく第三者に権利が発生するのか否かはさておき、Privity of contractがあるので当該第三者は権利行使ができません。
したがって、当該第三者は、諾約者が意地悪なやつでろくに約束を履行しない場合でも、どうしようもなかったということになります。
そこでTPR Actの登場
このような批判を受けて、1999年にTRA Actが制定されました。これにより、第三者は、次の場合に契約上の権利を行使できることになりました。
① 契約が明示的に第三者に権利を与えている場合、又は
② 契約に第三者に利益を与える条項が定められており、反対の意図がない場合
先ほど例に挙げた第三者のためにする契約は、①のケースですよね。この場合は、契約当事者が合意して第三者に権利を与えているので、契約当事者と第三者の間で紛争が生じる可能性は低いと思います。
しゃしゃり出てくる第三者
問題は②のケースです。
当事者間の合意の内容に、第三者にとって利益となることが含まれることは頻繁に起こります。
例えば、発注者・元請業者の工事請負契約において、元請業者が発注者に対して、「下請業者の従業員の安全にはきちんと注意を払います。」という内容の義務を負うことは、十分にあり得ます。これは、下請業者の従業員にとっては利益になるのではないでしょうか。
そうなると、もし、工事現場で事故が起きて下請業者の従業員がケガをしてしまった場合、従業員は、下請業者だけじゃなく、元請業者にもかかっていくかもしれません。
この事例は、従業員を「しゃしゃり出てきた第三者」と呼ぶのは失礼ですが、場合によっては、本当に急に第三者が訴えてくることもありそうです。
第三者の権利行使は排除できる
TPR Actは、別に、第三者へ権利を与えることを義務付けていません。契約当事者は、これを排除することができます。
ようやく結論が書けそうです(笑)
なので、準拠法を英国法にするときは、我々は、こういう条項を条件反射的に入れちゃいます。
Third Party Rights
This Agreement does not give rise to any rights under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce any term of this Agreement.
これを入れておくことで、当事者で合意した内容に関して、急に第三者から請求を受けてしまうことを防げるというわけです。
この条項が入っていないとヤバいのか?
これを読んで頂いている方の中には、そんなの初耳だよ、今まで入れてなかったよ、という人もいらっしゃるかもしれません。
回答としては、入れておいた方がもちろん安全ですが、実際に第三者が権利行使できる状況は意外と少ないので、こまごまとした売買契約やNDAに入れ忘れたぐらいなら、大きな問題が起こる可能性は低いと思っています。
(ここまで踏み込んで言えるのが、書籍やニューズレターではなく、noteで情報発信するときのメリットですね)
というのも、詳しくは省きますが、TPR Actの恐ろしさを裁判所も認識しているのか、限定的な解釈を行った判例が積み重ねられた結果、TPR Actの適用場面は少なくなっているからです。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
このエントリーがどなたかの参考になれば、うれしいです。
【注釈】
*1 Tweddle v Atkinson [1861] EWHC QB J57
免責事項:
このnoteは、ぼくの個人的な意見を述べるものであり、ぼくの所属先の意見を代表するものではありません。また、法律上その他のアドバイスを目的としたものでもありません。noteの作成・管理には配慮をしていますが、その内容に関する正確性および完全性については、保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。
X(Twitter)もやっています。
こちらから、フォローお願いします!
こちらのマガジンで、英国法の豆知識をまとめています。
よければご覧ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
