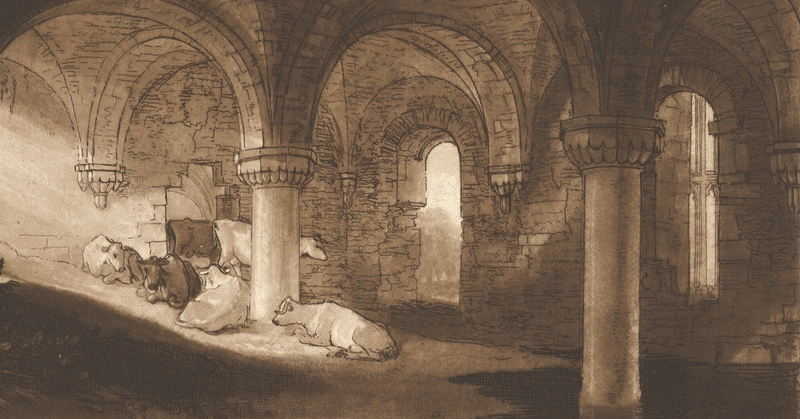
【短編小説】石の心臓
ああ、やっと見つけました。探しましたよ。
謎の石と不吉なナニカを書き綴ったとあるノートの話。
女は必死の形相で文字を書き連ねていた。真っ暗な部屋の中、机についた一本の蛍光灯の青白い光だけを頼りに紙にペンを走らせる。
きっとこれを書き記すのは褒められたことではない。それどころか何の関係もない多くの人を巻きこんでしまうかもしれない。だが女にはもはやこの方法しか残っていないのだ。
ノートに書き連ねた文字はところどころに消し跡が残っており、線が震えてしまっている字もある。お世辞にも上手い字とはいえない。だがそんなことはどうでもいい。内容さえ読めれば目的は果たせる。
ノートをびっしり埋め尽くす文字たち。その書き出しはこのように始まっていた。
『これは私がひと月ほど前に見た夢の話です。』
気づけば私は森の中に立っていました。
森は鬱蒼と茂っていて、杉のような木がいくつも立っているように見えました。なぜそのような曖昧な言い方しかできないのかというと、あたりに深い霧が立ちこめていたからです。厚い霧のベールは全てを飲みこみ、数メートル先は既に輪郭のぼやけた薄い影と化してしまっていたのです。
地面はぬかるんでいて、どこを踏んでも泥が飛び跳ねる始末でした。時には水たまりまであったので、淀んだ泥水を踏みつけないよう、私はなるべく柔らかな苔や木の根っこを足場代わりにして歩くしかありませんでした。
そうすると不安定な根っこの上で霧に濡れた苔に足をとられるので、数メートル歩くだけで私の息はすっかり切れていました。
森はまったく見覚えのない場所でした。人影はおろか、建物らしきものも道すら見当たりません。しかしぼうっと突っ立っていても事態が良くなることはないのです。私はとりあえず足を動かすことにしました。
いったいどのくらい歩いたことでしょう。霧の白、葉や苔の暗い緑、そして地面と幹のこげ茶。それ以外この森には存在していませんでした。
この色彩の乏しい世界は、広さだけは無駄にあり、どれほど歩いても森から出られる気配はありません。あてもなくさまよい続ける私の姿は、傍目から見れば幽霊のように見えたかもしれません。
いつまで歩き続ければいいのか。いい加減足も疲れてきて、これは明日筋肉痛だな、なんて思ったそのとき、ふと私は気づきました。誰かが私を見ている。そして真っすぐこちらに向かってきていると。
瞬間、脳内が警鐘を鳴らしました。
あれと会ってはいけない。出会ってしまったら終わりだと。
それは凶悪な肉食動物と出くわしたときのような、本能的な恐怖でした。
私は弾かれたように走り出しました。無我夢中で走りました。どの方向へ何メートル走ったのか、何分走ったのかそれを説明することは残念ながら難しいです。
本当はなるべく道順まで正確に書き記したかったのですが、なにせ地図もコンパスもなく、あるのは似たような草木ばかりで目印になるようなものはありませんでしたから。あったとしてもそれをまじまじと観察するような余裕もありませんでしたし。
ただ今思えば皆様に説明できないことが悔やまれます。詳細に書き記すことができれば、これを読んだ皆様にもきっと役に立ったでしょうに。
話を戻しましょう。とにかく私は背中にべったりついた視線から逃れようと必死に足を動かしていたのです。
しかし努力の甲斐もむなしく、どこまで走ってもずっと視線はついて回りました。聞こえるのは私の足音だけで、葉擦れの音も私以外の足音もありません。でもずっと視線は外れないのです。
どくどくと心臓が脈打ってうるさいくらいでした。まるで私の心臓がスピーカーとつながっているかのように、心臓の鼓動が植物さえも息をひそめる静寂を叩いているのです。
この心臓が暴れ回っているせいで、奴から逃れられないのではないか。
私の脳裏にそんな考えがひらめきました。こんなに騒がしい心臓を抱えていれば、自分の居場所を大声で知らしめながら逃げているようなものです。
心臓を宥めようと深呼吸を繰り返しましたが、音は落ち着くどころかどんどん大きくなるばかり。
そのときふと私は気がつきました。今もなお刻み続けている拍動が自分のものではないと。極度の恐慌状態の最中でも私の心臓は一定のリズムを刻んでいます。その体の中から聞こえてくる音と、今耳にしている音がわずかにずれているのです。その瞬間、私のズボンの右ポケットがずんと重みを増しました。
何かがポケットの中で脈打っている。そして厚いジーンズ生地を通して私の肌に己の存在を伝えてきました。
――ああ、そのときの気持ち悪さといったら!
たったジーンズの生地一枚隔てた先に肉の塊があるのです。それも自ら動き、ぬめぬめとてかりながら、太い血管を浮き上がらせ、出るはずもない血液を送り出している。
その無意味な行動を延々と繰り返す機械じみた無機質さと、己の中心部ではめこまれたものと同じ器官が今ポケットの中で蠢いているという妙な生々しさがいっそう気味の悪さを助長しました。
私は震える手でポケットの中に手をさし入れました。ぶよぶよとした筋肉が指に触れると覚悟していましたが、予想とは裏腹に硬い感触がありました。指でつまんで恐る恐る引っ張り出すと、それはハート型の石でした。
灰色のザラザラした表面はところどころひび割れていて、縁もところどころ欠けていました。血管が浮き出ているわけでもなければ、理科準備室の隅で埃をかぶった人体模型のような模型でもない。むしろ幼稚園児が作った粘土細工のような、リアルさの欠片もない不細工なものでした。
しかし音はたしかにこの石から響いているのです。平らな面を震わせてドクン、ドクンと命を刻み続けているのです。
恐らく視線の主はこの石を持っているから、私を追いかけてきているのでしょう。それ以外考えられません。
ならば捨ててしまえばいい。ですが、そのときの私はなぜかその場でその石を叩きつける決心がつかなかったのです。まあ夢の話です。きっと思考が正常ではなかったのでしょう。
ちょうどその場所には太い蔦が獲物に巻きつく大蛇のように木に巻きついていました。木は強風にでも折られたのか、一本の枝が折れ曲がって宙に揺れていました。だらりと力なく項垂れているその姿は老人の指のように乾いていて生気がありませんでした。いえ、老人どころかもはや死人。樹海に垂れ下がるモノのほうが近いかもしれません。
ですがその指がゆらりゆらりと体を揺らすその様を見て、私はそれが行くべき方向を指し示してくれているとなぜだかそう感じたのです。私は再び駆け出しました。
そこから体感で約十分ほどでしょうか。走り続けた私の体はついに限界を迎えました。私の息が、未だうるさく鳴り響く鼓動と混ざって醜い不協和音を奏でているのを、千々に乱れた思考の隅でぼんやりと聞いていました。
顔を上げるとそこには大きな二本の杉が生えていました。幹は私の腕では囲えないほど太く、場所が場所なら御神木に選ばれていそうな立派な杉でした。恐らくこの森で一番高い木たちでしょう。
空に向かって真っ直ぐ伸びるその天辺は霧に阻まれて見ることはかないません。夫婦杉のように根っこ同士が手をつないで並びたつ杉の木たちは厳かに私を見下ろしていました。平時であればその厳粛な空気に姿勢を正し、感嘆の息を漏らしていたことでしょう。
しかし事態はひっ迫していました。私はすぐ近くに奴がいることをはっきりと感じていました。石の心臓はうるさいほど脈打ち、奴に私の存在を知らしめようと声を上げ続けています。
そこでようやく私は手の中に収まった、その忌々しいものを手放す考えに思い至ったのです。
これさえなくなれば奴に追われなくなるかもしれない。もう結末の決まった鬼ごっこをする時間も心の余裕も私にはありません。
私は思い切り地面に石を叩きつけました。バンと物が地面に激突する嫌な音が響きわたって、石は粉々に割れてしまいました。と、次の瞬間視界が白に染まりました。
気づけば私は山道の道路の脇に立っていました。
山を切り開いた道は、両脇は鬱蒼と木々が茂っているのに、道路のところだけ切り開かれて妙に明るいのです。空は相変わらず曇天で、真っ白な雲が隙間なくひしめいて、太陽のきらめく金の髪の毛一本すら差しこみさせやしませんでした。
どうやら私が立っている場所は坂の途中だったらしく、右手を見れば上り坂が緩やかなカーブをかけながら木々の向こうに消えていくのが見えました。下るほうも同じくカーブを描いて木立の中へと消えていき、その先までを見通すことはできません。
しかし上りと違って下りには一本道路から脇に逸れて森の中に入っていく細い道がありました。道とはいってもアスファルトで舗装されたものではなく、獣道のような草木を踏み固めてようやくできた細い小道だったのですが。
小道の先は先ほどまで私が彷徨っていた森のように不気味な霧に飲みこまれて、どこにつながっているのか確かめる術はありません。もっともあったとしても私が自ら赴くことはないでしょう。
「森から来たの?」
ふいに話しかけられ、私は文字通り飛び上がりました。いつの間にか私の後ろに少女が立っていたのです。歳は中学生から高校生くらいでしょうか。黒髪を一本に束ね、涼やかな面立ちをしていました。
ただ先ほどのナニカとは違い、彼女から不吉な、忌避すべき雰囲気は感じられませんでした。むしろ味方であるとさえ感じたのです。きっとこの世界で唯一私たちに手を差し伸べてくれる人物でしょう。
私はこくりと頷きました。
「そう。運がよかったね」
少女はにこりともせずに返しました。
「ここから離れたほうがいいよ。昔から悪いものが集まるところなの」
少女は後ろを振り向きました。つられて振り返ると、ちょうど一台の車が坂を下りてこちらへ向かってきました。一見街中でも見かけるごく一般的な黒い軽自動車でした。ですがそれがこちらに向かってくるにつれ、私は異変に気づきました。
なんとその車の運転手席は空だったのです。それなのに車は平然と音もなく私たちの横を通りすぎていきます。そしてすっと小道に逸れて森の中に消えてしまいました。
「もういこう。ここにいたら危ない」
彼女が手を差し伸べました。私はその手を掴みました。ひんやりと冷たい手でした。
突如足元に白が漂い始めました。気づけばどこからともなく霧が忍びよっていたのです。
「っ、まずい。もう来るなんて」
今まで冷静沈着だった彼女が初めて顔を歪めました。その目には明らかに焦燥感がありました。彼女は私の手を掴んだまま走り出しました。
私たちの逃走を阻むように霧が腕を伸ばしてきます。やがて黒いアスファルトも手を引く彼女の姿も白に飲みこまれて全てが白で埋め尽くされました。
再び場面は切り替わりました。
いつの間にか私は真っ白な空間に立っていました。いや真っ白な空間というと語弊がありますね。霧で満たされた、恐らく森の中に私は立っていたのです。湿った土と植物の匂いが混ざりあった森の空気が唯一私が森の中にいることを知らしめてくれる
そのとき突然ぬっと目の前に影が現れました。私の背の二倍以上はある、異様に背の高い人影でした。
――奴だ。
私は直感的に察しました。この目の前に立っている影こそずっと例の視線を絡ませ続けてきたたナニカなのだと。
しかし逃げようにもこの至近距離です。隠れられるような場所も見当たりません。何より見えない視線が私の体を縫い付けて離してくれません。
恐怖で動けない私を嘲笑うかのように人影は腰を折り、ゆっくりと顔を近づけてきました。不思議と肌に息が触れるまで近づかれてもその顔は見えませんでした。そして低い声でこう耳打ちしたのです。
「せめて心臓だけは返してくださいね」
と。
そこではっと目が覚めました。私は濃霧に覆われた森ではなく、見慣れた自分のベッドの上にいました。体を包みこむ羽毛布団がじんわりとした温もりを私に与えてくれました。
しかし私の全身はびっしょりと冷たい汗をかいていて、心臓は全力疾走した後のようにばくばくと脈打っていました。明かり一つない空間は耐えきれず、手探りでベッドサイドの明かりのスイッチを押しました。ぱっと暖色の光が照らしたとき、私は初めて夜に火を灯した先祖の気持ちがわかったような気がしました。
まあしかしここまでであれば嫌な悪夢だったなと息をついて、スマホで馬鹿みたいに明るい動画を見るなり、気分転換に熱い茶でも淹れるためにキッチンに立ったことでしょう。
ただこれで話は終わりではなかったからこそ、私はこうして筆をとることになったのです。
私の枕元には青い目覚まし時計が一個あります。スマホで起きられるか不安なとき、あるいはどうしても寝坊できない大事な用事があるとき、最後の保険として置いてあるものです。普段は時刻の確認くらいにしか使いません。
その日も私は時刻を確認しようと手を伸ばしました。しかしその滑らかな肌に触れるより先にざらりとした異物が私の指に当たりました。
寝る前に何か置きっぱなしにしたのか。それとも服に小石か何かがついてしまってそれが落ちたのかと思っていたのです。
私はひっと悲鳴を上げました。そこには二本杉の前で私が砕いたハート型の石の欠片が一個転がっていたのです。灰色の親指の爪ほどの小さな石の欠片は、牙をむくように鋭くとがった歪な断面を向けて、私をじっと見つめていたのです。
いえもしかしたらたまたまそれに似た石の欠片が紛れこんだだけかもしれません。私は太陽が昇るや否や、窓からその欠片を投げ捨てました。
怪談話のように捨てても捨てても戻ってくる……なんてことはありませんでしたが、その日からたびたび例の森に戻ってくるようになりました。
相変わらず森は濃霧が覆っていました。そのうすぼんやりとした白の中で木々の背よりも高い、ひょろりとした人影が何かを探すようにうろついているのです。私の手には投げ捨てたあの欠片が弱々しく脈打っていていました。
彼は私が欠片しか持っていないせいか、あの日のように私の存在を知覚できているようではなさそうでした。
しかしそれも時間の問題でしょう。
最近は眠るたびに霧が深くなって、彼の姿を察知するのも難しくなってきているのです。それになんとなくですが、彼のほうも私が何度も森に足を踏み入れているのを察知し始めているような気がするのです。
そして何度夢を見てもあの夫婦杉にたどり着けた試しはありません。
これを読んだあなたへ。私はこれからあの欠片をもって彼に会いにいこうと思います。そのとき例のあの場所にたどり着けるか、最後の挑戦をしようと思います。ですが最初に見たあの日から私はあの場所にたどり着くことはおろか、あのとき道を指し示してくれた枯れ枝にさえ出会えていないのです。たどり着く可能性は低いでしょう。
心臓が元に戻るまで、彼はきっとバラバラになった心臓を求めて探しまわります。そして私が全て返しきれなかったそのときは、心臓の在処を知っている人に会いにくるはずです。そう、つまりあなたのもとへやってきます。面倒を押しつけてごめんなさい。でもこうするより他はないのです。
もしもあなたがベッドで瞼を閉じ、次に瞼を上げたとき、濃霧たちこめる深い森に放り出されていたら、どうか粉々になったハート型の石を探してください。それか一つ結びの少女を探してください。彼女ならあなたを助けてくれるかもしれません。
どうかご武運を。その「もしも」がないことを祈っています。
S市のアパートで発見された二十代女性の変死体の件について現場に残された文章は以上である。
司法解剖の結果、女性の心臓が鋭利な刃物等による切創のような損傷がみられたことから事件の可能性を疑ったが、心臓以外に特に大きな損傷もなく疑わしい人物も浮上しなかったことから、事件の可能性は低いと見て、本日をもって捜査を打ち切ることにする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
