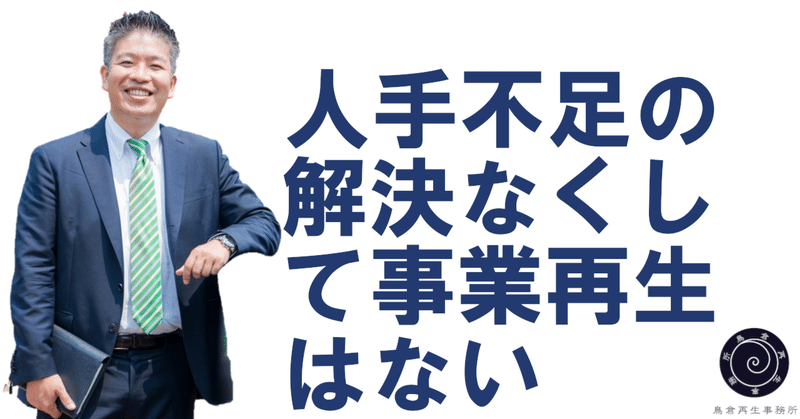
人手不足の解決なくして事業再生はない
採用ができないという課題に真剣に向き合う企業しか再生できません。財務を改善しないと、多くの採用ができないという課題のパターンに対処ができないためです。 以下、東京商工リサーチの記事を引用致します。
コロナ禍で隠れていた人手不足が経済の再活性化のなかで表面化し、生産計画に狂いが生じ、現場担当者は頭を抱えている。
東京都の有効求人倍率は、2019年12月まで2倍を超える高水準で推移していた。だが、新型コロナウイルス感染拡大で宿泊業や飲食業、小売業など対面型サービスが打撃を受けると状況は一転し、2020年12月は1.1倍台にまで落ち込んだ。その後、2021年春から緩やかに回復し、2022年3月は1.34倍の水準まで回復した。
こうした状況で、中小企業や一部の業種では、再び深刻な「人手不足」に戻ってしまった。2021年1月以降、東京都の新規求職者数は3万人台で推移するが、求人数は2021年初めの7万人台が、2022年には10万人台まで急増した。明らかな人手不足の再来だ。
少子高齢化の日本では、コロナ禍の回復期に人手不足が起きることはわかっていた。コロナ禍で人手不足が隠れていたに過ぎないからだ。日本の15歳以上65歳未満の生産年齢人口は、1995年の8,716万人をピークに減少に転じている。こうした中でのモノ不足、人手不足。いきなり、DX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組むのも難しい。
https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20220613_03.html
もともと人手不足はわかっていたはずですが、事業再生と言えば、バブル崩壊以後の処方箋であるBS調整型(過剰債務のカット)、リーマンショック以後の処方箋であるコストカット型(無駄を省く)である時代が長く、人手不足が企業の損益に大きなインパクトを与える時代に対応できていません。
コロナ禍後の事業再生は、仕入原価の高騰、円安の影響、人材採用の難易度があがった事も踏まえたコストアップ反映型の事業再生となると想定されます。

2022年から来年にかけてより一層の原価高が想定されます。コスト管理に厳しい大企業でも、価格維持が難しいことを承知しているので2022年は仕入先が要請する値上げを容認する姿勢が見られます。
経営改善計画を作成する際にも、バブル脳、デフレ脳からの脱却が必要です。値上げによる売上増や、人件費UP、原材料費UP、仕入コストUP、物流コストUPを反映させ無くては、実行性の高い計画とは言えなくなります。コストアップ反映型の事業再生を断行してください。
従来よく見られた人員整理による人件費カットが主軸の計画では人繰り倒産の危機がいよいよ具現化しています。計画を忠実に履行すると倒産しかねません。
値上げの目線は10%が基本になると思います。この値上げは売上構成比で人件費3%、原価5%に吸収されます、幸いにして利益2%が増加したとしても、別なコストのUP(社会保険の適用拡大、インボイス制度の導入など)に吸収される恐れが高いです。

人手不足の悪循環の中、一人当りの労働強化や残業時間の延長、若い世代のワークライフバランス重視の働き方もあり、結果として更に人材流失し、赤字事業の立て直しに取り組む前に、人手不足により組織が破綻しかねません。
早期にこの問題へ対処しないと売上のトップラインにも影響がでます。経営者の中にはこの問題の深刻さを適切に受け止めていない方も多いです。採用広告費を増やしても採用は改善しません。
人材派遣や外国人技能実習生により、足下の人手不足をごまかすことも難しくなってきています。人材派遣会社は人が集まらない地域で広告を行って人を集めても効率が悪く利益も上がらないため、依頼を受けないケースも見られるようになってきました。外国人技能実習生はコロナ禍で期間満了で帰国する方が多い一方、来日できずに人員が減少するばかりです。コロナ禍が収まった後の補充も、国際的な給与比較と円安で日本で働く事の魅力が減少しています。

このように人手不足は広範に広がっており、コスト転嫁せずに安い想定原価のまま受注拡大すると、稼働率が高まる可能性があります。
人的に余裕がない中、不採算取引で稼働率が上がる危険があり、不採算の質の悪い売上構成が高く利益が悪化し赤字になります。さらに事業再生に挑戦するためリスケジュールしている場合は、資金調達余地のない増加運転資金に苦しむ可能性もあります。
人員不足の中では値上げにより、受注選別しなければ、残業時間の増大などを理由に退職者が相次ぎ、財務問題以前に組織が破綻するスピードを上げる危険があります。

人材を集めるのはどうしたらよいのか?会社としての戦略はありますか?人が集まらない理由を偶然の産物(景気・募集広告の質・時の運)と捉えてはなりません。
企業のPR方針の再定義、取引先の選別、賃金、残業時間、休日日数、職場環境、有休の取得しやすさ、人事部人材の確保など、企業の構造改革に取り組まないと採用は改善しません。
人材を集めることが、他社に勝ち抜くための競争戦略となる時代になりました。これに成功すれば事業再生は自ずと達成されます。改めて企業は人であることを捉え直して、時代に合った再定義を致しましょう。会社を統合的に捉え直す必要があります。誰の仕事でも無い、経営者が最優先で取り組むべき仕事です。
無料面談のご予約はこちらから https://torikura.com/contact/ あなたの事業再生が優しくできるようご支援します。 難問解決を得意としています。あなたの仕事にきっと役に立ちます。 フォロー、スキでの応援お願いします。
