
2023/06/24発表内容まとめ
0.初めに
誰かを愛していますか?あるいは愛した経験はありますか?
おそらく、多くの人が愛した経験があると思います。
では、自分自身を愛することはできていますか?
今回は自己肯定感のトリセツ
平たく言うと自分を愛する方法をメインにお伝えいたします。
1.発表内容
内容は図1の通りです。

盛りだくさんとなっておりますが、
メインテーマは自分を愛することについてです。
そして、それを達成するために
自己肯定感やプライドをうまく扱いましょうといった
内容となっております。
また、自分を愛するためにリフレッシュする方法などもあわせて
共有できればと思っております。
2.大人になるまで障害が顕在化しなかった理由

大人になるまで障害が顕在化しなかった理由として、
3つの要因が挙げられます。概要は図_2 に示しています。
幼少期から厳しく、そして「普通にしなさい」と言われて育ったことが
挙げられます。幼稚園の頃、みんなが教室でお弁当を食べているのに
一人だけ「お外で食べる」と言って聞かずに集団から外れて
行動しがちでした。そのような行動について速やかに矯正されて
"ふつう"しぐさを覚えさせられました。
次に、小学校6年間柔道を習っていたことも障害が障害として問題にならなかった要因だと思っています。私の通った道場は、武道あるいは格闘技としての強さを追求するよりも精神性を重んじるタイプの道場でした。善く生きること、年長者や先輩を敬うこと、下のものに対してやさしく接することを学びました。これは、発達障害の特性の一つである場の空気が読めず不適切なふるまいをしてしまうことを防ぐことに繋がっていたと思います。空気が読めずとも、そして相手の気持ちを理解していなくても"型"として最適なふるまいを出来てしまうようになりました。
3つ目に、妹が生まれたことも障害が顕在化しなかった理由の一つだと考えています。親に甘えにくくなったと同時に、〈兄、そして長子〉としての役割が与えられ、その模範的振る舞いをするように育てられました。
以上3つの要因によって、自分を理性あるいは精神力によってねじ伏せ、抑圧して生きる癖がつきました。これによって、障害特性を表面に出さずにいたため障害の発覚が遅れたと思っています。
障害が顕在化した理由としては、シンプルにストレスの限界値を超えてしまったからだと思っています。社会人になり、コップに表面張力でギリギリこぼれずにいた水が溢れるようにしてストレスが決壊して、二次障害である双極性感情障害を発症させたと認識しています。そして、限界状態に陥ったためにこれまで精神力でねじ伏せていた発達障害的な特性が、私の外の世界に顔を出してしまうようになったのだと思います。発達障害については当時の元婚約者から発達障害を疑って検査を受けるように促されました。
これが大人になるまで障害が顕在化しなかった理由です。
3.障害の発覚と受容

図_3に示した経緯で障害が発覚しました。
率直な感想として
「自分は“普通”だと思っていたのになぜ?そして、みんな私と同じ苦しさや生きにくさを抱えて生きていると思っていたのに、私が異常だったのか?」と思いました。それと同時に、私がなんとなく“生きにくい”と感じていたことを医療や先人たち(特に借金玉氏)の叡智をもってある程度解決できるのでは?と希望も持てました。
生きにくさの解消のためには、障害受容が必須になると考えたので、長い休職期間を使ってひたすらに内省を行いました。主な障害受容の方法としては、哲学的な手法 平たく言うと一人問答や一人カウンセリングの真似事を行いました。その上で、自分は生きていてもいいのだという理由を探しました。
図_3の髭モジャはソクラテスで、右の画像にはグノーティーサウトン 汝自信を知れと描かれています。一人問答では主に私が、世界に一人だけ唯一無二の存在として実在していることの確認作業と、私を私たらしめる要素・私の本質(イデア?)とは何かについて考え続けました。
4.自己分析と受容 生きやすさの見つけ方

図_3で触れた、内省、哲学的な手法について具体的に説明します。
まず初めに、自分が無意識に形成した認知のゆがみを探します。
これは精神/発達障害者に限ったことではないのですが、人は誰でも生存戦略的に無自覚のうちに心に色眼鏡を持って生きています。そしてその色眼鏡はいつの間にか、24時間ずっとかけているものなので、例えば青い色眼鏡をかけている人は自分が青い世界を生きていることには気が付きません。当然のことですが、他の人の目線や気持ちを100%理解したり、世界観を共有することは不可能なので「私には世界が青く見える。ほかの人もおそらく青く見えているのだろう」と考えます。自力でその色眼鏡を探すことは困難を極めるため、勇気をもって親しい友人や家族に自分の特性、どんなキャラクタに見えるのかを聞いてみると内省の足掛かりになります。
色眼鏡については、私が持っていた色眼鏡「性悪説」をはがしたエピソード(https://note.com/toriikunn/n/nae09de18a573)を読んでいただけると幸いです。
ここでは、認知のゆがみとしてプライドの肥大化と自尊心の低さを例に説明していきます。
認知のゆがみ、プライド肥大と自尊心の低さを自覚したら、内省による自己認識の作業にうつります。ひたすらに自分自身に問いを投げ続けてください。
「どうやら私はプライドが高いようだ」(認知のゆがみの発見)
「なぜ?」(以下、ゆがみを深掘りしていく)
「そもそも、プライドは常に高く設定しないと
いけないものだと思っていた」
「なぜ?」
「自分に課した理想やハードルを下げてしまうと
成功できないと考えていたから」
「では、その理想やハードルは超えられた?」
「超えられなかった。そして理想、すなわちプライドの大きさに対して
思うような成果が得られずにプライドが傷ついた。それは自尊心にもダメージを負わせた」(自己分析)
「それなら、プライドを下げればいいのでは?」
「プライドを下げるのは、プライドが許さなかった」
「だから、ずっと肥大化したプライドを抱えていた」
「プライドと成果のギャップでたくさん自尊心が傷ついた」
「プライドを縮小させるという選択肢を捨てていた。
というよりその発想がなかった」
「…もしかして、、プライドって実力に応じて上げたり下げたりしてもよい?」(自己認識)
「そうか、プライドは必ずしも常に全力で大きくしていなくてもいいのか!!!」(自己認識・心の色眼鏡の発見)
このような具合です。
私自身、プライドの高さを調節していいということに気が付いたときは
価値観の崩壊が発生して混乱して泣いてしまいました。
自己認識ができたら、自己受容の作業にうつります。
自己受容では、先程発見した自分の色眼鏡の観察を行い、その色や形を確かめます。それから、なぜ自分がその色眼鏡を持っていたのか考えます。色眼鏡の存在に気が付けたということは、それを外すという選択肢が生まれます。試しに一日、色眼鏡をはずして生活してみてください。最初は裸眼で世界を見ると眩しくて目がくらみますが、きっとクリアな視界に感動すると思います。
これまで話した内容は、すべて内省することなので自分の内面世界だけでものが動いています。これをそのままにせず、アウトプットする作業が青枠のステップになります。
自己表現(図_4右下の青枠部)では、認知のゆがみ探しでヒントをくれた人に対して発見した色眼鏡のことや、色眼鏡を外したクリアな視界で見えた新しい景色のことを話すといいです。もし対人では話しにくい場合は、Twitterやnoteに書いてアウトプットすると効果的です。考えをテキスト化することで自分の発見を整理できますし、いつでも後から見返すことができるからです。
アウトプットを行うと、他者からの反応が得られる場合があります。
話を聞いてもらって反応を見たり、ツイッターやnoteであればいいね、投げ銭、スキ等のリアクションがもらえます。自分の考えを認めてもらえたときや、ときに意見を投げかけられたりすることで承認が得られます。
承認が得られると、自尊心が回復します。大げさに表現すると、生きやすさの回復といえます。(図_4 緑の枠)
認知のゆがみは一つとは限らないため、何度もこのサイクルをまわすことで
自己理解、自己受容を深めていきます。
5.生きることに理由を見つける

受容の次には、自分が生きていてもいい理由を探しました。当時、自分の生命をこの世に繋ぎとめている一番大きな理由は、元婚約者の存在でした。彼女から別れたいと言われるまでは彼女のそばにいたいと思っていました。この状態は、容易に依存を形成してしまうため危険だったなと、今振り返ると思います。
そこで、元婚約者との日常の他に生きていてもいい理由を探しました。
まず、自分の存在の本質、先に述べた自分を自分たらしめる私の本質(イデア)を探求したいと思いました。その方法として、未挑戦のことにトライして自分を試しました。
今も続けている合気道や、やめてしまいましたがキックボクシング、表現の手法としてカメラ、今回で二回目となるようこそ先輩で自分なりの思想や哲学を多くの人にぶつけてみること、それから動的座禅としてのダーツに挑戦しました。どれも皆、教科書的なスタイルから入り何か一つ自分の得意技を獲得するという傾向をつかめました。
次に、社会貢献していることも生存していてもいい理由の一つだと考えました。前職では都市を構成する社会インフラ、現職では電力関係の仕事をしており、日本国民の健康で文化的な現代の生活を支えているというやりがいを感じています。
最後に、未来に楽しみをもつことで、その未来が来るまでは生存しようと考えました。例えば趣味の鉄砲のおもちゃ新商品の発売を待つなどが該当します。
6.障害と”生きること”について考えてみた結論

前の章では、なんとかして、生きていてもいい理由や目的を見つけ出そうとした方法について書きました。しかし、そもそも生きることに理由や目的は必要なのだろうか?とある日突然疑問を持ちました。そこで、人間以外の生命、動物や植物の場合はどうなのだろうかと一般化してみました。
図_6_1を見てください。生まれた瞬間からお肉になり、私たち人間に食べられる運命にある牛さんの人生に意味があると思いますか?
季節を感じさせてくれる花、雑草、サル、シカ、イノシシやクマなどの害獣、それからペット。彼らは生きていてもいい理由や生きる目的を持っているのでしょうか。そして彼らの生命に重みはありますか?

ぐるぐると考えた過程は省略しますが、結論としては生命に意義や意味、理由や目的はなくてもいい。しかしながら、それと同時に価値を持っていると考えることにしました。(図_6_2) ダイヤモンドは何の機能も持っておらず生活に役立つわけでもない炭素の塊です。ところが、その輝きに価値を見出されています。生命もダイヤモンドと同じく理由や目的、意味がなくても価値があるという考え方です。
7.自己肯定感/自尊感情との付き合い方

自己肯定感や自尊感情を満たす方法は沢山あります。この章では2つの段階に分けて自己肯定感や自尊感情の満たし方、付き合い方についてご説明します。
段階は、図_7の黄色い枠と赤い枠の2つに分かれています。
黄色の段階は、誰かから必要とされるという、他者の存在や承認ベースで自己肯定感や自尊感情を満たす段階です。この段階は大きく2つに分かれます。まずは理由なく愛情をもらうパターンがあります。これは家族や恋人、パートナーから得られるものです。もう一つのパターンには、何かを成し遂げた成果、結果を認められて自己肯定感が高まる現象が挙げられます。わかりやすい例として、仕事で売り上げを出して褒められたり、認められることで達成感を得ることが挙げられます。
この段階の弱点は、他者がいないと自己肯定感が得られないことです。また、承認を与えてくれる人が少ないとその人に負荷が集中してしまうため相手を困らせてしまう場合もあります。さらに、他者の持つ価値観で自分の価値を測ることになるので、思うように承認が得られなかったりすることも少なくないです。
一方で赤の段階は、自己肯定感を高めるために他者の存在を必要としません。
自分で満足するか否かがすべての世界です。自分の得意なことや好きなことを自己評価して自分自身を褒めることで自己肯定感を満たします。たとえ他者から評価されなかったとしても、自分は自分の努力や工夫を知っているので、それを自己評価して等身大の自分を受け入れて認めていいと思っています。そのためには自己分析・受容のスライドで例として出した、プライドの拡大縮小が必要になってきます。
8.自己完結型の自己肯定感/自尊感情の取扱い

前職で上司から、「職場は承認を得る場所だよ」と言われたことがあります。大変心に響きました。
自分の努力や工夫を評価してもらい、それを認められて社会に貢献することによって承認が得られると説明していただきました。それまで私は職場と承認を結びつけることが出来ていなかったため、目からうろこが落ちました。
しかし、職場では必ずしも承認が得られるような成果を出せるとは限りません。反対に、ミスや成績不良、段取りなどで注意、指摘を受けることもあります。第9章で詳しく説明いたしますが、このとき人格や人間性にダメージを受けたり、自分自身を責めたりする必要はありません。
成果を出せたときはその理由を分析すれば再現性が得られますし、思うような成果が得られなかったときには、「上手くいかない方法を発見した」と捉え、他の方法を試せばいいだけの話です。そのうえで自分の中で目標を設定して、それをクリアしていくことで自分自身を褒める習慣をつけると自己評価が高くなっていきます。
つまり、自分や自分が大事にしていることを自分の価値観の物差しで測り、評価することで自己肯定感を保つことができるようになります。
9.プライドの最適化

第4章で例に出した、プライドの拡大収縮による心の保ち方についてかみ砕いていきます。プライドは常に高く設定しなければならないという思い込みが生じているとき、自分がプライドを高くしたままであることを忘れ、プライドを不可視化してしまうことがあります。私の場合はありました。この状態では、何かうまくいかない物事があったときに透明になったプライドが傷つき、それに連動して自尊感情にもダメージが入ります。しかし、プライドを透明にしていまっているので自分のプライドの高さを自覚しないままそれを維持してしまいます。そのため、まずは自分のプライドの高さ、大きさを自覚する作業が必要です。これは身近な人に聞いてみるのが最も確実です。
プライドの高さを認識できたら、それを等身大の自分に見合った高さまで調節します。身の丈以上にプライドが高い場合、本来できなくて当たり前な事をできなかったときに、受ける必要のない精神的ダメージが発生して自尊感情が傷つきます。プライドの拡大縮小はゲーム等でいうところの当たり判定範囲の調節にあたります。
第4章で紹介した自分の受け入れ方を実践、等身大の自分を受け入れることによりプライドの高さ調節ができるようになります。
10.自分を愛することは可能か

メインテーマである「自分を愛するということ」です。
今回伝えたい2つのテーマのうちの1つ目です。
私は、人を愛するためにはその対象をよく知る必要がある。それと同時に、愛していればもっと知りたいと思ってしまうと考えています。
恋愛では、意外な一面を知ったときにより親しくなりたいと思い、自分の好みつまり自分の持つ物差しで測ったときに魅力的だと判定される対象に惹かれますよね。そして相手の好みを把握してプレゼントを選ぶと思います。自分を愛する場合でも、これに近い現象が起きるはずです。
最初に行うべきは、よく知ることです。図_10青枠部分を見てください。
等身大の自分を受け止めて許すために、第4章で説明した方法を用います。そのうえで、自分のプライド・誇りの大きさを把握します。
そして、自分なりの価値観で形成された物差しで自分自身を測り、自分をよく知ります。
その結果、オレンジ枠の段階に進めるようになります。
自己受容と自分自身が生きていてもいい理由を見つけて(もちろん理由などなくても構いません)生命の価値を自覚することで自分自身を愛せるようになります。
11.自信家の抱える問題

プライドの適切な拡大縮小が行えない場合、どうなるか。
私の解釈をまとめました。
自信家ほど自分に対する要求水準が高く、できない自分を認めてあげられない傾向にあると思っています。これは、弱い自分を認めてしまうと自分がすがっている空想上の「デキる自分像」が揺らいでしまうからだと思います。そのままプライドを下げずにいると、どんどん自尊感情が傷つき、いつか倒れるので認知のゆがみに気が付いて軌道修正する必要があります。私がそうでした。
12.中間まとめ

今回私が伝えたかったことは、自己肯定感を高めるためには、他者の存在によって得られるものもあるが、自分自身で自己肯定感を高める方法もあるということです。そして、他者からの指摘や注意を過度に恐れる必要はないということも知っていて欲しいと思います。
適切な自己肯定感の維持方法やプライドの取扱いを覚えて、皆さんが自分を愛せるようになっていただけると今回いまでのnoteまとめを作成してみてよかったと思います。
13.リフレッシュの方法
リフレッシュには色々な方法があり、人によって合う合わないがあるかと思います。いろんな人に勧めてみて、効果があったと報告が多かった二つの方法を紹介します。
まずは気力も体力もないときのリフレッシュ方法です。

リラックスチェアを用意して、心が落ち着く音楽を聴きます。アロマを焚いたり、蒸気でホットアイマスクを使うとさらにリラックスできます。アロマは鎮静系のもの、例えばネロリやジャスミン等がおすすめです。リラックスチェアはAmazonから1万円前後で購入可能です。折り畳み式のものも多く、そちらがオススメです。
この方法のコツは二つあります。まず一つ目は、絶対に仕事のことや悩みをチェアに持ち込まないことです。二つ目は、リラックスしたいとき以外絶対にリラックスチェアに座らないことです。読書、ゲーム等娯楽の場としては使わないようにしてください。リラックスしたいとき以外はチェアを折りたたんで、すぐ出せる場所にしまっておいてください。理由は、チェアに座る=リラックスするという条件反射をつくるためです。一度この条件反射が形成されれば、チェアに座って数分でリラックスできるようになります。
多少体力があるときには、体力を消費して気分を切替えます。

天気がよければ自転車で少しお散歩をしたり、カメラを持って降りたことのない駅で降りてみて迷子になったりすると楽しいです。自宅でできるリフレッシュとしては、ひたすら筋トレをしたり、ダーツを投げたりすることがオススメです。どちらも無心になって行うと動的座禅的な側面があります。
14.自傷行為について

今回登壇依頼を受けた理由、話したかった内容の2つ目です。前回登壇時に質問タイムで「自傷を抑えるためにはどうすればいいのか、紹介していただいたリフレッシュの方法で解消されるのか」と質問がありました。これに回答したいと思い、二度目の登壇を決めました。質問者さんに届くかは分かりませんが、ここでお答えします。
自傷行為について、私は肯定的立場でも否定的な立場でもありません。止められるならやめた方がいいと思いますが、それを行うことでなんとか精神を保っているのであればやむをえないと考えています。私も自傷行為をした経験があります。それを行うと気分が落ち着くと知ってしまったため、複数回行いました。細かい仕組みは忘れてしまいましたが、エンドルフィンが分泌されることによって心が落ち着く作用があるようです。跡が残ると人生のうえで困ったり、何かを失うこともあるので私が見つけた代わりになる行動を紹介します。
衝動的な自傷を防ぐためには、べつの方法で体をいじめると効果的です。腕立て伏せでもスクワットでもなんでもいいので限界まで筋トレをしてみてください。体に負荷が大きいですが、サウナも効果があります。それでもダメなら、息を止めてみてください。ある程度衝動が治まるはずです。詳しいメカニズムは分かりませんが、脳が生存本能優位になるからだと思っています。
頭に鉛がこびりついたような、もやもやを剥がしたくて自傷を選択しそうになる場合は、リラックス状態になるように調整をいれることで誤魔化しが効きます。先程紹介した、リラックスチェアによるリフレッシュを行ってみてください。鎮静系の効果があるアロマを使うこともオススメです。ジャスミン、ネロリ、イランイラン、サンダルウッドにゼラニウムあたりが適しています。
ただ、結局のところは自傷を止めたいと思うのであれば、自傷に逃げないという決意を持ち、自分の抱えるもやもやと戦うしかないのだと考えています。
15.再就職3年目 感想とアドバイス
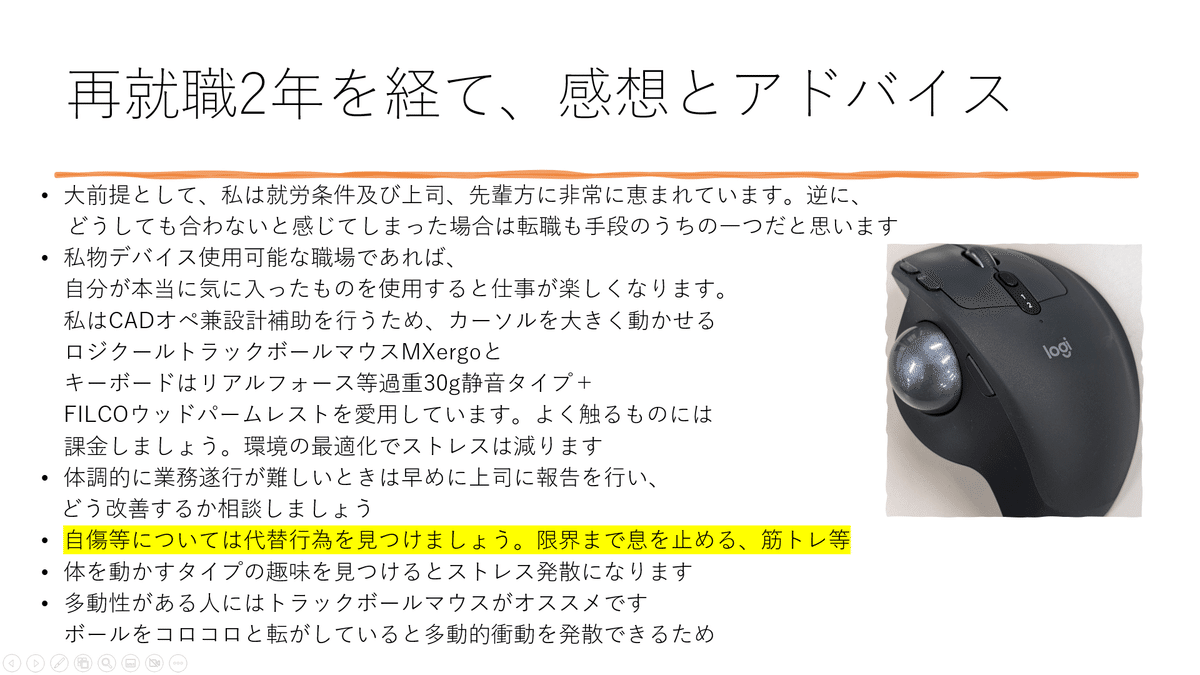
私はたまたま就労環境、上司、先輩方に恵まれて、沢山の合理的配慮をしていただけたので就労し続けられています。どれかが欠けていたら続いていなかったと思います。これに関しては入ってみないと分かりません。どうしても合わない場所にいる場合は環境改善を試みて、それでもダメだと感じたら撤退も手段のうちの一つだと思います。メンタルは不可逆なので、壊れてしまう前に早めに判断しましょう。私は前職からの撤退が遅すぎました。
自分のモチベーションを上げるために、お気に入りの道具をもちこんで仕事をすると楽しく仕事ができます。私物デバイスに課金してみて欲しいです。私はトラックボールとキーボードを持ち込んでいます。トラックボールはすばらしいです。
体調不良は、本格的にダメな状態になるまえに早めに上司に報告をして、対応をしましょう。言いにくいかもしれませんが、無理してデスクでフリーズしてしまうより、早めに強制終了→再起動した方が結果的に動ける時間が長くなると思います。
自傷行為について。代わりになるリフレッシュ方法、ルーティンを作ってください。
多動気味な人にはトラックボールがオススメです。親指で無意味にボールをコロコロしていると落ち着きます。トラックボールはすばらしいです。(大切なことなので二度言いました)
自傷行為について。それが救いになっているのであれば、誰も止める権利はありません。ただ、止めたくなるときがきたら私の発表やこの記事を思い出してくれるととても嬉しいです。
16.まとめ

生きていくことに理由はなくてもいいです。
もちろんあるにこしたことはないです。
等身大の自分を認めてあげること、そして自己表現を行うことで自尊感情を満たすことができます。その結果として、
自分自身を愛せるようになれます。なって欲しいと思っています。
自動的にリフレッシュできるようなルーティンを持つことで、ストレス解消やうつの波が来た時のやり過ごし方が分かってきます。
自傷行為を止めたい場合は、他の方法に置き換えて衝動を抑えることもできます。
長くなりましたが、発表は以上となります。
鳥居
