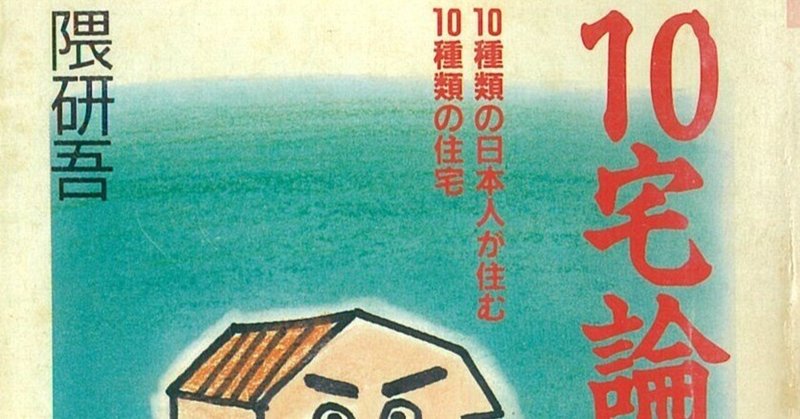
建築家の住宅論を読む<6>~隈研吾の『10宅論』~
隈研吾は、国内外で数多くの話題作を手がける、今や名実ともに日本を代表する建築家のひとりです。
建築家の住宅論を読む<6>は、初版当時(1986年)32歳の若き日の隈研吾による『10宅論』(ちくま文庫、1990年)を読んでみます。
卓抜な日本住宅論にして、日本文化論
本作はユニークな日本住宅論であると同時に、鋭い現代日本文化論でもあり、30年以上たった現在もその有効性を失っていません。
本書のあとがきで著者本人は、「この本は一種のでっちあげであり、いわばフィクションであり、日本の住宅事情とか、住宅をめぐる現実とは一切関係ない」と煙に巻いていますが、「フィクション」ゆえに有するリアリティは、日本の住宅と日本文化のある側面を鋭く射抜いています。

日本型<場所中心象徴作用>とは
西洋の古典建築では、例えば、イオニア式の頭注(柱の頭に渦巻きが2つ載ったような装飾)が学問を表しているように、モノがあるイメージや内容を象徴しています。
一方、日本では、象徴はモノそのものに由来するのではなく、モノが置かれて「場所」に依存しています。「場所」とは物理的な空間だけではなく、共有される感性や価値観など、広義の意味で使われています。
日本においては、床の間に置かれた茶花は、主人がわざわざ花を摘んできて客人を歓待していることを象徴しています。野の片隅のありふれた花が、茶会の席や床の間という「場所」に置かれることで特別な意味を持つようになる、日本型の<場所中心象徴作用>の例です。
コロニアル、プレイリー、フレンチ、スパニッシュ、和風、モダン、折衷など、日本の住宅は、なんでもありの百花繚乱の状態です。日本の住宅は、いろんなモノが節操なく置かれ、複雑で繊細な象徴作用が発動する「場所」なのです。
本書は、なんでもありの日本の住宅を10種類に分類し、その象徴する意味を解明していきます。
「○○派」と呼ばれる10の住宅スタイル(「場所」のこと)に対応して、その根底にあるイデオロギー(信条や捕らわれている価値観)や家族属性や信奉するメディアや参照される建築様式などが列挙されます。各スタイルをイメージした間取りや使われる素材なども詳しく記述されます。
「神は細部に宿る」との言葉どおり、隈研吾による、具体への落としこみと微に入り細を穿つディテールへのこだわりが本書の読みどころのひとつです。「フィクション」がリアリティを纏う瞬間です。
反ブルジョア的ディレッタンティズムの<アーキテクト派>から住宅の人生化を目指す<住宅展示場派>まで
例えば、<アーキテクト派>と称される一派は、「反ブルジョア的ディレッタンティズム」が根底にあり、「建築ジャーナリズム」を信奉し、「RC打ち放しシリコン系撥水材吹き付けけ」の外観を好む。隈研吾の慧眼は、この世界における簡素だが決して「貧乏くさく」はない美学を切り開いたのが、安藤忠雄だったことを指摘します。
例えば、<住宅展示場派>の根底にあるのは、「住宅の人生化」という価値観であり、婦人雑誌のインテリア記事やおもてなし記事からの影響を見て取ります。そしてコロニアルやプレイリー風(フランク・ロイド・ライト風)などのデザインが選ばれる理由を、日本と西洋(アメリカ)文化との関係から解き明かしてくれます。
<建売住宅派>は<住宅展示場派>の親戚です。同じ持ち家一戸建て信仰に基づいています。両者の相違は<建売住宅派>の「品数の多さ」だとされます。部屋数の多さに始まり、ベージュの壁にまっ青なタイル、和風の屋根にフランス風ドーマーウィンドー、玄関はイタリアンタイルに木目の下駄箱の組み合わせなどなど、同じ値段の買い物なら品数が多いほうがいい、というおなじみの発想法です。
例えば、億ション風の外観や高級クラブに居るような豪華な空間にこだわる<クラブ派>とは、現実の家庭に居心地を見出せなくなった空虚感が、高級クラブという、理想化され、商品化された「家庭」を逆輸入する形で実現した象徴であると喝破します。
<料亭派>とは高級料亭にみられる数奇屋風の意匠にこだわった一派であり、そのメンタリティは<クラブ派>と同様に、理想化された「家庭」の逆輸入であるののの、唯一、違う点は<料亭派>は自分の方が<クラブ派>よりも趣味が良く高級であると考えているところだというオチは、思わずぷっと吹き出してしまいます。
10という数はたまたまのオープンエンドな数に過ぎません。本書の初版からすでに31年。新しく生まれた「場所」を考えてみるというのも、ゲーム感覚のノリを持った本書にふさわしい読み方のひとつといえるでしょう。今なら、さしずめ<無印派>や<ミニマル派>や<トランスパレント派(透明派)>や<新町屋派>などが登場するのでしょうか。
これらはすべて「でっちあげ」だ、との露悪的な告白の陰に

冒頭に引用したやや露悪的な「でっちあげ」の告白の後に、隈研吾はこう記しています。
「住宅とか空間に対するこだわりとか熱意といったものは、基本的に機能や美や真実とかいったものに対する欲望から派生するのではなく、まさに階級に対する欲望に基づいて生まれているのである」
一見、高尚そうにみえる<アーキテクト派>も、高級を自認する<クラブ派>や<料亭派>も、持ち家一戸建てに捕らわれた<建売住宅派>や<住宅展示場派>も、しょせんは同じ欲望の記号のひとつにすぎない、隈研吾はそう言ったのでした。
隈研吾(1954-)
東京大学および同大学院で建築を学ぶ。東京大学教授。国内はもとより世界をフィールド活躍する日本を代表する建築家のひとり。個人住宅から、店舗内装、ブティック、美術館、新国立競技場までと作品は多数多岐に渡る。和に由来するルーバーなどをモチーフにした表現は、今日の多くの建築に影響を与えている。実作の前から建築批評を発表するなど著書も多い。代表作は『水/ガラス』、『根津美術館』など。
初出:houzz site
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
