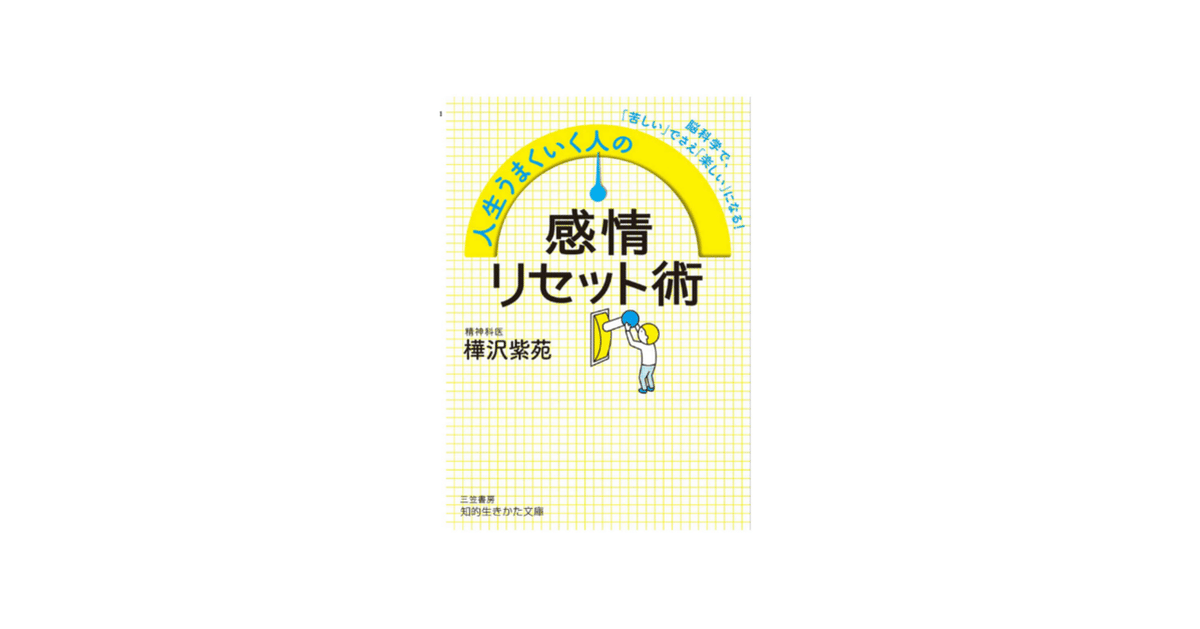
【要約&感想】感情リセット術
今回の要約も、樺沢紫苑先生の本です✨
Kindle Unlimitedで読み放題になっていた、感情リセット術を読みました📚
樺沢先生の本は、分かりやすくて、すいすい読めちゃうので、理解力のない私には大変有難い本なのです🙏✨
_______________
【要約】
〜3つの脳内物質が、幸福の決め手である〜
・「苦しい」人の脳内物質は、ノルアドレナリン/アドレナリン/コーチゾールで出来ている
・「楽しい」人の脳内物質は、ドーパミン/エンドルフィン/セロトニンで出来ている
・「楽しい」脳内物質を出すことは難しいことではない。仕事の取り組みや、姿勢、ちょっとした受け止め方など、頭の中の回路を切り替えるだけで「苦しい」脳内物質が分泌されている状態が「楽しい」脳内物質が分泌される状態へとチェンジするのだ。
〜苦しい時こそ、物事の全体を見よう〜
・「苦しい」人は、必ず視野狭窄という、周りが見えない状態になってしまっている。今ある目の前の「苦しい」で頭がいっぱいになってしまい、それ以外のことが考えられなくなってしまっているのだ。視野を広げるだけで、誰でも「楽しい」を発見できるし、「苦しい」が大部分でも、今の状況、仕事、生活の中に、どこか楽しい部分、ホッとする一瞬は、よく探せば必ず発見できるのだ。
〜人生、苦なければ楽なし〜
・「苦しい」のあとに、「楽しい」がやって来るという、脳科学的な理由がある。それは「苦しい」のあとに「幸福物質」のドーパミンが分泌されるからである。ドーパミンは、目標を設定し、困難を克服し、自分の壁やハードルを突破した時に、分泌される。何かにチャレンジし、人間を進歩と向上へ駆り立てる、モチベーションの源となる物質なのだ。しかしドーパミンは、簡単すぎる課題をクリアしても分泌されず、ある程度の難易度、困難を乗り越えてはじめて分泌される。つまり、ドーパミン分泌の特性から考えると「苦しい」の後に、「楽しい」がやって来るのは当然のこと。「苦しい」は「楽しい」の前兆とも言えるのだ。
〜一瞬で笑顔になる方法〜
・UCLAで、一つは楽しい記憶を思い出す、二つは気が滅入る記憶を思い出してもらうという実験を行った。その結果、2つのグループをの免疫機能を継続的に調べたところ、楽しい記憶を思い出したグループの免疫細胞も多く活発だった。それに対し、気が滅入る記憶を思い出したグループは免疫細胞の数が著しく低下し、その活動も低くなり、感染症にかかりやすい状態になっていた。つまり「悲しい」「苦しい」「辛い」ことをイメージするだけで、わずか一日で免疫力が低下するという身体の変化が観察されたのだ。つまり苦しいからといって「苦しい」ことばかり考えていると、余計にストレスホルモンを増加させ、悪影響を受けてしまうのだ。
・「楽しい」ことをイメージするのが難しい!というのであれば、「苦しいを乗り越えた自分」をイメージすること。具体的には「今の困難を乗り越え成長した自分」をイメージしてみるのだ。そうすると、不思議な事に「苦しい」は消えてなくなり、「まだ頑張るぞ」というモチベーションが湧いてくるのだ。また、「楽しい」をイメージするだけで、モチベーションを高める物質「ドーパミン」が分泌され、やる気を引き出してくれる。そんな究極のスーパー脳内物質を分泌させてみよう。
・苦しくてたまらない時は、「自分には伸びシロがある」と考えよう。伸びシロとは「まだ能力を出し切っておらず、まだ成長する余地がある」ということ。「苦しい」を超えることで飛躍的な成長が、あなたを待っているのだ。
~失敗が怖い時は~
・失って、敗れると書いて「失敗」。この言葉の後には、マイナスなことを言いたくなる。例えば「失敗した。もうコリゴリ」「あんな失敗はしたくない。何もチャレンジしたくない」など。では、「失敗」をは言わずに「経験」と置き換えてみよう。すると、「今回の経験から学んだことは多い。次は間違いなく上手くいくだろう」など、「経験」という言葉の後には、自然にポジティブな言葉が続いていくではないか。このようにちょっとした言葉の置き換えによってネガティブな感情はリセットされ、次なるモチベーションが湧いてくるのだ。
~「苦しい」を抜け出したいとき~
・苦しい時こそ、「あなたの人生で最も成長する時」なのだ。今は苦しくても、あとから振り返ると「貴重な時間」であり、「成長の時間」であり、「人生の試練」であり、「自分を大きく成長させてくれるハードル」であるのだ。つまり、「どん底」=「貴重な時間」なのだ。今、つらかったとしても、自己成長するための期間なのだと考え、「苦しい」先の「楽しい」を想像しながら、自己成長には大切な、この「苦しい」時期を乗り越えてみよう。
~考えれば、解決できる問題だけ考えよう~
・中谷彰広さんの本で以下の言葉がある。「ぐずぐず考え始める前に、その問題が考えれば解決できることなのか、それとも無駄なことなのかを判断しなければいけない。どうせ解決しない悩みなら、考えない」あるストレスに対する調査によると、最もストレスになるのは「変えられない状況を変えようとすること」であるそうだ。
~未来のことで不安にならず、今にフォーカスしよう~
・人間は、先のことを考えても不安になってしまう。しかし、考えたところで不安が増すばかりで何もメリットはない。「今」どうするかだけを考えて、不安や焦りといった感情をリセットしよう。「不安」のストレスとは、起こってもいないことに対して「〇〇になったらどうしよう」と考えてしまうこと。つまり考えなければ発生しないもの。つまり「無」から勝手に自分でストレスを作り出しているのだ。不安で不安で仕方ない時は「なんくるないさ」「ケセラセラ」と心の中でつぶやき、予期不安をリセットしてみよう。
~苦しい作業(仕事)を楽しくするために~
・人間がもつモチベーションは、以下のたった2つ。「楽しさ、褒美、褒められるために頑張る」ドーパミン型モチベーションと、「恐怖や不快や叱られることを避ける」ノルアドレナリン型モチベーション。「〇時まで」「〇日まで」と期限を設定するだけで、この2つのモチベーションを高める脳内物質が分泌され、モチベーションが上がるのだ。
・仕事に「喜び」「達成感」を見出せないのなら、仕事以外に「自分にご褒美をあげる」ことでモチベーションを維持しよう。仕事そのものが自分の「精神的報酬」になるのが一番だが、それが困難な場合は、仕事と関係ないところで自分に褒美をあげる方法が効果的である。
・何か目標を達成したら、積極的に自分に褒美をあげよう。人間は、物やお金など物質的な報酬でも、脳内では「嬉しい!」という精神的な報酬に置き換わるのだ。そのため、自分に褒美をあげるだけでモチベーションがアップするので、そうすると、脳は勝手に頑張ってくれる仕組みになっている。
・何か目標達成するときはドーパミンが必要不可欠である。このドーパミンが分泌されないと、やる気が続かず、すぐに諦めてしまうのだ。そして、「人のため」「仲間のため」に行動するとき、他者貢献、ボランティアなどをするときは「ドーパミン」以外にも「エンドルフィン」という脳内物質が分泌されている。この「ドーパミン」「エンドルフィン」は「楽しい」「幸せ」という気分を引き起こす幸福物質であり、2つ同時に分泌されると、エンドルフィンは、ドーパミンの幸福感を10~20倍にも増強するのだ。
~他者貢献、社会貢献はいいことだらけ!~
・メアリー・メリル博士の研究によると、ボランティア活動をする人は、しない人に比べ、モチベーションが高く活動的なことが分かっている。また、達成感や幸福感を強く感じており、平均寿命も長いことが明らかになった。この理由は、ボランティアによって、エンドルフィンが分泌されるためであると推測されている。
・「自分のため」という囚われを捨てて、「人のために行動しよう」と意識するだけで、苦しい感情は完全にリセットされる。すると、健康でストレスに負けることなく、圧倒的なモチベーションをパフォーマンスを発揮できるのだ。
~仕事、職場は人間関係で決まる!~
・どんなに好きな仕事、やりたいことでも、険悪な人間関係の中で「楽しく」こなすのは困難である。仕事自体が「好き」か「嫌い」かとは無関係に良好な人間関係の中で、仕事をするかどうか。「楽しく」仕事をするために大切なのは「人間関係」だったのだ。
・では、人間関係が上手く行く人とはどんな人なのだろうか。それは「人を変えようとしない人」である。大前提として、人の「性格」や「人間性」はそうそう簡単に変えられるものではない。本人に問題意識がない場合は、ほぼ不可能なのである。多くの人は、他人を変えたいと膨大なエネルギーを注ぐが、それこそが人間関係がストレスになる最大の原因なのだ。
・人間関係を変える第一歩は、「相手を肯定する」ということである。相手の欠点や、嫌なところを、いったん認める。それにより初めて人間関係を良好にするスタートラインに立つことが出来るのだ。
・人間は、自分自身の短所や欠点と直面したくない、という心理傾向を持っている。また、自己の悪い面を認めたくないとき、他の人間にその悪い面を押し付けてしまうような心の働きのことを「同族嫌悪」という。なので、本能的に「嫌い」と感じる人は自分と似たもの同士だったなんてことは、良くある。相手と腹を割って話してみると、実は共通点が多かったなんてことも珍しくはないのだ。あなたが「嫌い」と思っている人に、マイナスのラベリングを貼らずに、決して相手の悪口を言わない。なぜなら、陰口や悪口は、全て自分に返ってくる。そこで、おすすめなのが「かげほめ」である。本心でなくても、嫌いな人を褒める・擁護することで、相手の「いいところ探し」に繋がり、人間関係は好転するのだ。
・相手に親切をすると、相手も親切を返してくれるという「好意の返報性」という心理法則がある。これは、あなたが相手に悪意を示すと、相手も悪意で返してくれるということを意味しているのだ。この法則で重要なのは、最初に「好意」を差し出すのは自分でなければならないということ。口で言うのは簡単だが、これがとても難しい。あなたがもし、嫌いな相手を泥沼の人間関係になっているとしたら、その状態で「好意」を投げるのは、相当の勇気と、思い切りが必要だ。一度、「嫌い」のラベリングをしてしまうと、「その人と話したくない」という感情を引き起こし、嫌いな相手とは、コミュニケーション量が圧倒的に少なくなってしまう。一度、泥沼の人間関係になってしまった状態の相手でも、積極的に、「挨拶」「雑談」「聞く」の3つをこなし、コミュニケーション量を増やしていこう。
・人間は、自分の嫌いな人に対して「聞く耳を持たない」傾向がある。しかし、そんな時こそ大切なのは聞く姿勢。人間は、自分の話をしっかり聞いてくれる相手に好意を抱く。話を聞いてもらえたことで、自分が承認されたという、承認欲求が満たされるからである。その反対が「話をないがしろにされた」状況。一生懸命話しているのに、相手がそれを受け止めてくれないと、強いマイナスの状況を抱くのだ。「聞く」ことをきちんと実行する。それだけで人間関係は、かなり改善される。おすすめは、「話す」と「聞く」の割合を2:8くらいにすること。会話では、相手が大部分を話、自分は相槌を打ち、時々コメントを挟むような状態だ。
~笑う・泣く日をつくろう~
・人間、苦しい時は苦しい表情になる。心理学の実験で「感情」より「行動」が先に生じていることが分かっている。脳は「楽しい」から「笑顔」を作るわけではない。「笑顔」になった後に「楽しい」という感情が生じるのだ。さらに笑顔は、ストレスホルモンの働きを低下させ、血圧や血糖値も下げ、副交感神経を優位にしてリラックスをもたらすのだ。
・「笑う」の反対「泣く」ことにより、感情のリセットが可能である。東邦大学名誉教授の有田氏の研究で、涙を流して「泣く」ことによってセロトニンが活性化することが分かっている。逆に、泣きたいときに涙を我慢すると、アドレナリンが高い、交感神経が優位(緊張状態)のストレスがかかった状態が続いてしまう。泣きたいときは、泣く。感情を表に出して、リセットしていこう。
~怒りをコントロールする~
・「怒り」は、3代ストレスホルモンの1つ、アドレナリンと直結した特別な感情で、アドレナリンが、ドカーンと分泌される。つまり「怒り=ストレス」なのだ。さらに、怒りっぽい人は、そうでない人と比べて、心筋梗塞のリスクが3倍以上も高くなるというデータもある。このことから、怒れば怒るほど、ストレスを引き起こし、寿命を縮めてしまうことが分かるだろう。
・もし「怒り」の感情を突き動かされたら、深呼吸をゆっくり3回しよう。1回20秒、5秒で吸って、15秒以上で吐くイメージだ。深呼吸することで、副交感神経が優位になり、自律神経を介して「怒り」の感情を強制的に発散してくれるという、即効性のある感情リセット術が「深呼吸」なのだ。
~ストレスを受け入れる~
・絶対に変えられないストレスに関しては、「戦う」のではなく「受け入れる」ことが対処法である。戦うことは、コルチゾールというストレスホルモンが分泌され、免疫抑制作用があるのだ。
・諦めるというのは、もともと仏教用語で、本来の意味は「明らかにする」である。「出来るかどうかを見極め、出来ないと分かったらやらない」というポジティブな選択をする行為なのだ。
・「戦うことをやめる」とは「受け入れる」ことだ。「受け入れる」とは「腹をくくる」「じたばたしない」と言ってもいい。受け入れるとは正反対なのは「敵対する」ことだ。「敵対心」は、あなたを苦しくする。敵対心が強いと、ストレスホルモンである、アドレナリンと、コーチゾールが分泌されるからである。敵対心が強い人は、他人と自分を比較して、敵対心を燃やす。そうした人たちの25歳から50歳までの死亡率は、敵意を習慣的に持たない人と比べて4倍も高くなる。敵意の強い人、他人を攻撃する人は、人に「苦しい」をぶつけているようで、実は自分自身を「苦しい」状況へと追い込んでいるのだ。
~ストレスは、受け入れるのではなく、受け流す~
・ほとんどの人は、ストレスに対して真剣に取り組み、何とかしようとするがストレスに本気で立ち向かうほど、ストレスの力は全て自分に返ってくる。そこで、物事を真に受けず、自分の心を「のれん」にしてみよう。具体的には「まあ、そんな時もあるか」「何とかなるだろう」「しばらく様子を見てみよう」的な対応である。もし、あなたがネガティブな話を聞いているとき、のれんよのうに話を受けとめると、話している方もフワッと優しい感覚に包まれるのだ。
_______________
【感想】
やはり、樺沢先生の本は分かりやすいですね✨
私は、周りから「感情があまり表に出ない」「ポーカーフェイス」と言われることが多いのですが、実際は全く違います。笑
心の中では、とてもイライラしてることが多いし、むしろ自分の感情をどこにぶつけて良いのか分からないくらいです。
そんな自分が嫌で、この本を読んでみようと思いました。
実際に読んでみて、私が印象的だったのは「苦しい時の乗り越え方」ですかね(*^^*)苦しいのあとには、楽しいが待っているなんて、今までは考えられなかったです。
まさに視野狭窄になっていたのでしょう。笑
例えば、今回の妊娠。医師から切迫早産の診断を受けて、私は「何で私が、こんな思いしなければならないの」と思っていました。
仕事も頑張りたいという想いはある。ですが、医師からは「動いちゃダメ」「基本の体勢は、横になること」と言われてしまったので、働きたくても働けないことに、苛立ちと覚えました。
しかし、徐々に切迫早産体質である事実を受け入れていき、「仕事に復帰できるか現時点では分からないけど、先のことを考えるのやめよう」と考えるようになっていきました。
それでも、1日中寝ている状態なので、要はやることなくて毎日暇なんですよね。(笑)暇な状況だと、時々は先のことを考えてしまう時があります。
すると、「正直、今苦しいけど、楽しいことなんてあるのかな。そもそも子育てなんて、私に出来るのかな」と、出産後の不安までもが、頭をよぎってしまいました。
そんな時に、本書を読んで、
・「苦しい」のあとには「楽しい」が待っている
・「苦しい」は自己成長の時間
・「苦しい」自分を乗り越えた自分をイメージし、モチベーションを高める
という言葉が、非常に心に刺さりました。
正直、出産は怖いです。生死がかかってますからね。。。
でも、この妊娠・出産を乗り越えたら。私のお腹の中に来てくれた「我が子」に会えるということを楽しみに、残りの妊婦生活を楽しもうと思いました(*^^*)♥
出産してからも、我が子の前で感情が乱れそうになったら、本書の感情リセット術を、日常生活にも取り入れていきたいと思える一冊でした✨
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
