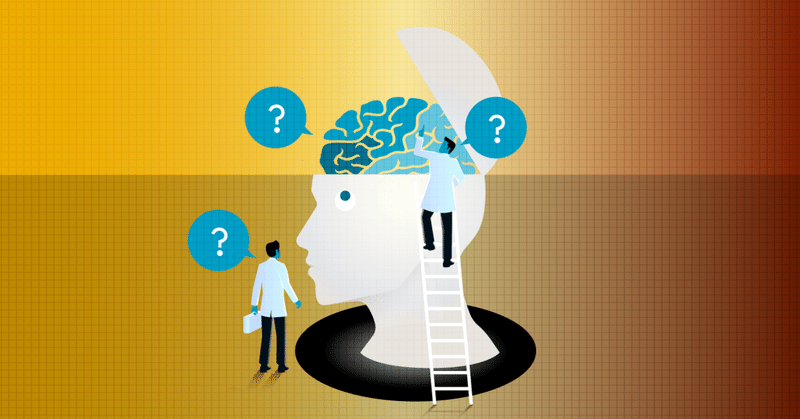
エビデンスは、誰かを殴る道具ではない
今日は、久しぶりに「女医」らしいことを書こうかと思う。まあ、そんな大それたことは書けないので、ごくごく一般的な医師が、ごくごく一般的に知っている範囲内のことになってしまうのだが。
今回のテーマは「エビデンス」について。
最近、「エビデンス」という言葉をよく耳にするようになった。サイエンスや研究の世界だけではなくて、そうでない方も口にされているのを聞く。新型コロナウイルスの広がりとともに、様々な政策や対策に対して「そのエビデンスはなんですか?」と問う声が増えた気がする。
当たり前のように使われる「エビデンス」という言葉に、私は密かに、違和感を感じている。
科学におけるエビデンスとはなにか。
ここでwikipediaを見てよう。
エビデンスとは「証拠・根拠、証言、形跡などを意味する英単語 "evidence" に由来する」言葉であり、「医学および保健医療の分野では、ある治療法がある病気・怪我・症状に対して、効果があることを示す証拠や検証結果・臨床結果を指す」とされている。
「エビデンスがある」ということは「科学的根拠がある」という意味になる。
”エビデンス” 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本で「エビデンス」という言葉が使われ始めたのは、ここ20年くらいのように思いう。いわゆる「EBM(Evidenced Based Medecine, 根拠に基づいた治療)」とともに、広く使われるようになった。
誤解して欲しくないのは「エビデンスがある=絶対に正しい」ではないということだ。エビデンスというのは、膨大なデータや研究結果によって積み重ねられたものであり、信頼できる要素はある。ただし、エビデンスによって「正しさの度合い」「信頼できる度合い」というのは変わってくるし、その根拠となった研究結果が、目の前の患者さんに当てはまらないこともある。
エビデンスとは、不完全で偏りがあるものである。
そのことが見落とされがちな気がする。
エビデンスには”レベル”がある。

https://life-kakumei.com/evidence/
エビデンスは試験や調査などの研究結果から導かれた科学的な裏付けなのだが、実はそれぞれ「エビデンスの信頼度」というものが違う。これを「エビデンス・レベル」という。
エビデンス・レベルには「Ⅰ〜Ⅵ」まである。レベル Ⅰが最も信頼性が高く、レベル Ⅵが低い。レベルは、根拠となった研究デザインなどによって決められている。
もっとも信頼性が高いと言われているのが、メタ・アナリシスという研究だ。これは、大規模な無作為研究(大勢の人をランダムにA群とB群に振り分けて比較した研究)をいくつも集めて、その結果を分析したものだ。大規模な研究を複数なので、被験者数は膨大な数になるし、調査期間も長い。一つの無作為研究が5年10年の単位で行われていて、それが複数集まっているので、20年から30年くらいの幅が出ることもある。
膨大な時間と労力を費やし、膨大な人数を対象とした研究によって、「レベル Ⅰ」が作り上げられる。
一方で、もっとも信頼性が低いと言われる「レベル Ⅵ」は「患者データに基づかない、専門委員会や専門家個人の意見」と言われている。「どこかの偉い先生が○○だと言っていた」というのは、レベルの最も低いエビデンスになる。
いわゆる「論文」と呼ばれる様々な研究(無作為研究、比較研究、コホート研究、症例報告)は、レベルⅡ〜Ⅴに含まれる。
「ある患者さんに対してAという薬が効きました!」というのは「症例報告」と呼ばれる。症例報告のエビデンスレベルはVなので、まあまあ低い。「○○を食べたら私は10kg痩せた!」というのも症例報告と似ていて、同じくレベルは低い。確かにエビデンスではあるけれど、信頼性が高いかと言われたらそうではない。
エビデンスには信頼性の高いものから低いものがある
エビデンスがあっても「使えない」ことがある。
今、いろいろな病気で「ガイドライン」が作られている。
ガイドラインとは「診療上の重要度の高い医療行為について、エビデンスのシステマティックレビューとその総体評価、益と害のバランスなどを考量し、最善の患者アウトカムを目指した推奨を提示することで、患者と医療者の意思決定を支援する文書」(Minds 2016)」と定義されている。
なんだかちょっと難しい。
言い換えるとすると「ある病気について、エビデンスを集め、そのメリットデメリットを検討し、患者さんにとって最善と考えられる治療を提示することを目指した文章」とも言える。
そう、ガイドラインはエビデンスで出来ている。
Mindsというデータベースによると、563のガイドラインがある。「がん」に関連するものや、NICU入室中の患者さんの呼吸管理についてなど。多種多様なガイドラインがある。
これだけあれば、「ガイドラインを見ればどんな病気でも大丈夫!」と思いがちだが、実はそうではない。例えば『A』という病気に対するガイドラインがあったとしても、目の前いる『A』の病気の患者さんに当てはめられないこともある。
ガイドラインには限界がある。
ガイドラインに載っている「エビデンス」というのは、いくつもの研究や報告をもとにして作られている。でも、欧米人の40代男性を対象とした信頼性の高い研究があっても、目の前にいる患者さんがアジア人の90代女性だったら。体格も年齢も性別も違う人に、果たしてガイドラインの内容をすべて当てはめてもいいのだろうか。
すべての試験や調査が完璧な精度でエビデンスを導き出せるわけではありませ ん。様々な要因によって、一定の偏りを含んでしまうこともあります。また、年齢や人種、 医療行為の量や頻度など、診療ガイドラインで取り上げる課題と、エビデンスとして取り上げた研究の課題とにずれが生じていることもあります。
——「エビデンス(科学的根拠)とは何ですか?」Mindsより
ここで紹介したいのは「EBM(Evidenced Based Medicine, 根拠に基づいた治療)」という用語だ。
EBMは「入手可能で最良の科学的根拠を把握した上で、個々の患者に特有の臨床状況と価値観に配慮した医療を行うための一連の行動指針」と言われている。
大切なのは、しっかりとエビデンスを考えた上で、「目の前の患者さんに適応できるのかどうかを考えて」医療を行うということだ。エビデンスだけではダメ。患者さんの状況だけでもダメ。エビデンスと患者さんを掛け合わせることで、目の前の患者さんに対して良い医療が提供できる。それがEBMの基本だと思っている。
データや検査結果があっても、それを「医療」にするときは必ず、目の前の患者さんに適応があるか、を考える。この”考える”作業なくして良い医療は提供できないし、それがプロフェッショナルの仕事でもある思う。
ちなみに、コロナウイルスのPCR検査は100%正確ではない。偽陽性(陽性と見せかけて陰性)や偽陰性(陰性と見せかけて陽性)もありうる。その不完全さを認識した上で、どうやって有効に使っていくかということを、現場の医療従事者や、専門家たちは頭を抱えながら考えている。その点では、PCR検査も、エビデンスも、ガイドラインも同じだ。
この世に存在しないエビデンスもある。
エビデンスの不完全さを伝えたところで、もう一つ。
この世には、エビデンスが存在しない病気、というものもある。
その際たるものが、世間を騒がせている新型コロナウイルスだ。
エビデンスレベルの箇所でも説明した通り、エビデンスというのは膨大な時間をかけて築き上げられる。一朝一夕にできるものではない。だから新しい疾患や珍しい病気の場合、十分な時間や症例数がないために、エビデンスが蓄積できないこともある。
新型コロナウイルスについての「信頼性の高いエビデンス」というものは、この世に存在しない。エビデンスを作る時間もデータも存在しない。これから一年二年、あるいは五年十年をかけて積み上げられていくだろう。
エビデンスがない中で、いかにして一般の人や医療従事者を守り、社会や経済活動を保つのか。その難題に、行政や公衆衛生の専門家たちは挑んでいる。
答えのないものに挑む。それが専門家が専門家としての存在を試される瞬間なのかもしれない。
エビデンスは振りかざすものではない。
ここでタイトルに戻る。
エビデンスとは、長い時間をかけて積み上げ、検証され、改良されていくものだ。そして同時に、不完全で、偏りがあるものでもある。
よりよい未来に繋げていく道具の一つに過ぎない。エビデンスを使う時は、賢く考えて使っていかないと、状況を悪化させてしてしまうかもしれない。
「この政策にエビデンスはあるんですか!?」とか
「エビデンスとは違いますよ!?」とか
そうやって誰かを詰問したり、殴る道具ではない。
国境を超えた感染爆発の中で、エビデンスのない感染症に挑んでいる専門家たちがいる。彼らは他のエビデンスを検証し、手探りで方向性を探り、進むべき道を示し、時に立ち止まって振り返り、修正し、また検証して方針を打ち立てている。それは途方もない作業だ。彼らの方策にはエビデンスはない。そんなものは、この世のどこにも存在しない。それでも立ち向かわなければならないから、踏ん張っているのだと思う。
だからこそ、今、私は願っている。
エビデンス、という言葉が溢れる中で。
それが誰かを傷つける言葉にならないように、と。

お心遣いありがとうございます。サポートは不要ですよ。気に入っていただけたら、いいねやコメントをいただけると、とても嬉しいです。

