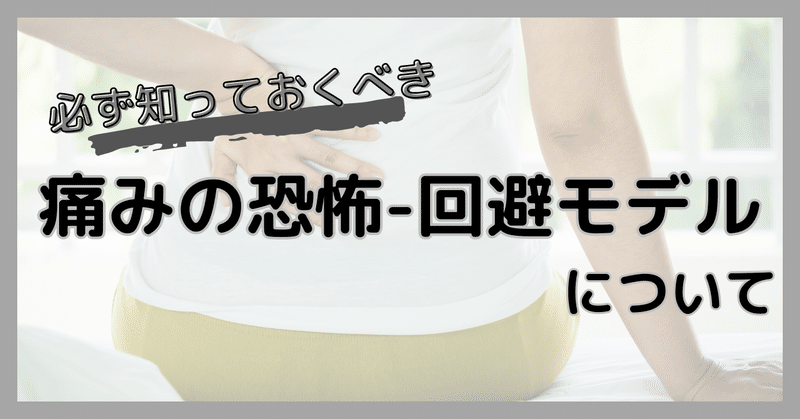
【痛み】痛みの恐怖-回避モデルについて
こんにちわ!
今日は痛みの恐怖-回避モデルについて説明していきます。
●痛みの恐怖-回避モデルとは
痛みの恐怖-回避モデル(Fear-Avoidance Model of Pain)は、痛みが持続する主要な要因の一つとして提唱された心理社会的なモデルです。このモデルは、急性の痛みが慢性的な痛みに移行するメカニズムを説明するために使用されます。
●痛みの恐怖-回避モデルのプロセス

痛みの恐怖-回避モデルは以下のようなプロセスを説明します:
① 組織損傷・疼痛
個人が怪我や疾患による痛みを経験します。
② 破局的思考・疼痛に対する恐怖
痛みに対する恐怖や不安を抱きます。この恐怖回避信念は、痛みが悪化したり身体に損傷を与えたりするという考えに基づいています。
③ 回避・過剰警戒
個人は痛みを回避するために活動制限や避ける行動をとります。これによって日常生活や社会的活動への参加が制限されてしまいます。
④ 不活動・抑うつ・身体機能障害
回避行動や活動制限によって不活動となり、身体的な活動や運動が制限され、筋力・柔軟性の低下などの機能障害を起こします。合わせて心理的な不安や抑うつ症状が増加する可能性があります。
⑤ 疼痛の増強
活動制限や身体的・心理的な機能低下によって、痛みが増強される可能性があります。これは痛みの恐怖回避信念が強まり、慢性的な痛みのサイクルにつながることがあります。
このモデルは心理的な要因(恐怖回避信念)が痛みの体験と活動制限の関係に影響を与え、慢性疼痛を増悪させると考えられています。
疼痛を回避するための行動が日常生活や活動を制限し、身体的・心理的な機能低下を引き起こすことによって痛みが増強されるというサイクルが生じるのです。
●どのように対処するか
このモデルでは痛みの治療や管理において特に心理社会的な要因の考慮が重要です。
痛みの恐怖-回避モデルから具体的に次のようなアプローチをしていきます。
・患者教育
患者さん自身、痛みに対する考え方や認識が間違っている・ズレていることがあるので、現状の痛みのメカニズムや生理学的な変化について教育・指導を行います。
それによって痛みに関する誤解や恐怖を解消し、適切な対処方法を学ぶことができます。
・段階的に活動量を増やす
痛みの怖さや「動いたら痛い」という過剰な認識が患者さんの不活動につながり、それによって身体機能障害が生じます。
もちろん痛みはあると思いますがセラピスト側でどういうように動かしたら痛くないのか?を探りつつ患者さんと確認しながら段階的な運動を進めていきます。
・認知行動療法
認知行動療法では扱いにくい感情そのものではなく、認知(考え方)や行動に注目し、患者さんに根づく考え方の癖や習慣 づいた非機能的な行動パターンの修正を行ったり、リラクセーションを用いて不快な身体反応を抑えながら不快な感情体験を軽減させ、患者が徐々に適応的な生活習慣を身につけていくことができるようにサポートしていきます。
詳しくは以下の記事からどうぞ!
・セルフケアの強化
患者さんにセルフケアを行うためのスキルや戦略を指導していきます。
リラクゼーション法や痛みの管理技術、適切な姿勢や体力の維持などの方法を教え、患者に痛みに対処する能力を身につけてもらいます。
●まとめ
今回痛みの恐怖-回避モデルについて書かせていただきました。
痛みに対しての怖さが強いのは人それぞれだと思いますが、間違った認識をしてしまっている場合にはセラピストで修正していく必要があります。
身体機能的な問題だけでなく、こういったことも痛みに関与してくるので痛みについて組織学的、力学的に考えることだけでなく患者さんの考えもしっかりと考えて治療に取り組んでいきましょう。
ではでは。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
