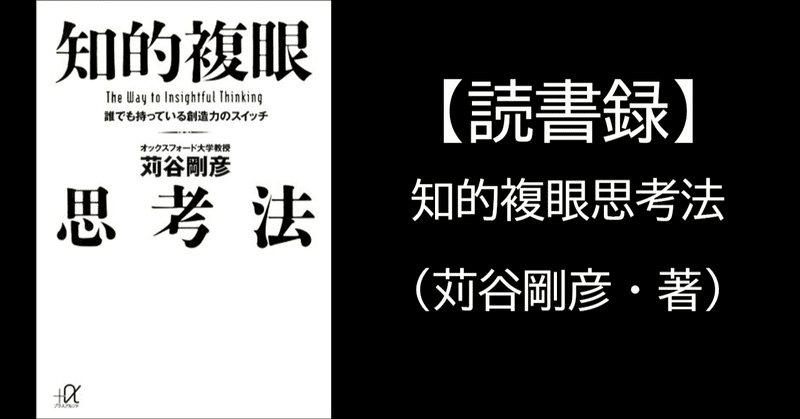
【読書録】知的複眼思考法 誰でも持っている創造力のスイッチ(苅谷剛彦・著)
なぜ、読んだ本を公開するのか
毎週日曜日7時~『ビジョナリー読書クラブ』というオンライン読書会に参加しています。そこでは、読んだ本の一部を引用し、自分の気付きを伝え、最後に何をするのかを宣言します。
いつも発表するときに、引用箇所を入力したり、Kindleでコピペしたりするのですが、それを消すのってもったいない。
あ!noteに残しておけば一石二鳥。
ということで、発表内容をまとめた記事を書き続けています。
お試し参加もできるので、興味のある方はぜひ!
読書が苦手な方も、きっと好きになりますよ。
読書が得意な方は、ワンランク上の読書が身につきます。
今回読んだ本はこちら。
ちょっと古い本ですが、Kindle Unlimitedで見つけて興味を持ったので読んでみました。講談社のプラスα文庫が、そのときは無料で読めていたようです。ラッキーでしたね。
それでは早速ご紹介しましょう。
【引用その1】正解信仰をしていないか
ところが「知らないから、わからない」という勉強不足症候群の症状は、正解がどこかに書かれているのを見つければ、それでわかったことになるという正解信仰の裏返しです。そして、この正解信仰を突き詰めてしまうと、「唯一の正解」を求める、かたくなで原理主義的な態度にもつながってしまいます。
世界のことすべてを説明してくれる大正解がある。それを求める態度からは、ものごとには多様な側面があること、見る視点によって、その多様な側面が違って見えることは認めがたいでしょう。唯一の正解というひとつの視点からものごとをとらえようとするからです。そうした正解を求める態度は、複眼思考とは対極にある考えかたといってもよいでしょう。
学生時代にずっと正解・不正解で評価されてきました。テストでいい点を取るためには、正解を出す能力を高めなくてはいけない。そのため、すべてのものに正解があると思っていたのかも知れません。
数学が好きだったのも曖昧さがなく、正確な正解があるから。逆に、国語などは「なぜその解釈なのか」と釈然としないこともありました。
著者が言う「複眼思考」を持つことによって、いろんな角度で物事を見ることができるようになります。自分の主観だけで見ていないか、相手の意見もきちんと聞いているか。正解を押しつけないことが重要なのでしょう。
【引用その2】知識だけでは意味がない
もちろん、本を読むことは大切です。知識を得ることも重要です。さらには、必要な知識を理解するための基礎力も重要です。しかし、どんなに知識があっても、そうした知識をどうやって考えることにつなげていくのか、それがわからなければ、何にもなりません。
本は、情報としても確かなものが多いです。逆に、インターネットの情報は蓄積された、精度の低い情報であることも多い。しかし、その検索性の高さから、あっという間に間違った情報が広がることもあります。
私は本をたくさん読んでいますが、それが「仕事につながる」「人生を豊かにしてくれる」という確信があるからです。それがなかったら、一切本を読まないでしょう。
知識があるから、いろんなことを多面的に考えられます。前提条件なども、自分なりに整理することができます。人は、知識以上のものは考えられません。知識があるからこそ、それを糸口に思考を深めていけるのです。
【引用その3】本の価値を考える
「本を読まなくなって失われるものは何か」。この問いを少し展開して、「本を通じて得られるもの」と「本でなければ得られないものは何か」を考えてみましょう。もし本でなければ得られないものが少なければ、本を読まなくなったといって非難されることはなくなるはずです。さあ、あなたなら、どんな答えを思いつきますか。
本でなければ得られないものとは、何でしょうか。私は著者として32冊本を書いてきましたが、私の本でなくても出会える情報はたくさんあるはずです。ただ、私だからたまたま出会えて伝えることができた。それであっても十分価値があると思います。
別に「本」にこだわる必要はありません。それが映像であっても、音声であっても、情報として受け取ることができればいいでしょう。となると、本というのは形状の一つに過ぎず、本であるかどうかの議論は不要なのかも知れません。
ただ、本は一覧性があり、持ち運びができ、貸与することができる。できあがるまでに、多くの人が関わり、編集の手が加わっている。情報の質の高さという意味では、有利なのかも知れません。
【引用その4】ルールの意味を考える
ひとり歩きするのは、数字だけではありません。さまざまなシンボルや概念、それにルールなども一人歩きをします。ある人や組織に貼られたレッテルやイメージ、それにさまざまな規則やルールです。とくに規則やルールといったものは、一度できてしまうと、ひとり歩きしやすいものです。ある目的があってルールを作ったのに、次第にそれを守ること自体が大切にされるようになる。つまり、ルールを守ることが先決になるのです。こうなってしまうと、「それはルールだからしかたがない……」といって思考を停止させてしまう場合が出てきます。
交通ルールをはじめ、様々なルールがあるから私たちは安心して生活ができます。ただ、厳密すぎるルールだと、生きづらさを感じるでしょう。ただ、曖昧なルールだと、拡大解釈されたり、抜け道が生まれてしまうでしょう。
ルールというのは、何かの目的があって作られています。ルールは、目的を達成するために存在し、目的が上位概念です。目的を達成することにつながらないなら、ルールを曲げても良いでしょう。これがわからないと「ルールなのになぜ守らないのですか?」という不毛な議論が生まれることになります。
まとめ&宣言
物事とを多面的に見るために、情報を常にインプットします。
単一的な視点にならないように、常に複合的に考えます。
さらに、目的を考えた情報の活用を目指します!
もっと知りたい!&プレゼントのお知らせ
仕事のスキルアップにつながるメルマガを平日日刊で配信しています。読書、仕事の高速化、思考法、コミュニケーション、様々なヒントを受け取りたい方は、メルマガに登録してくださいね!
今なら、書籍『仕事を高速化する「時間割」の作り方』をプレゼント中。
記事を読んでいただくだけでも嬉しいです。さらに「いいね!」がつくともっと嬉しいです。さらに……サポートしていただけたら、モチベーションが10倍アップします!

