
私たちは子どもに何ができるのか
最近読む本がことごとく非認知能力を扱ったものばかりです。なので最近のnoteでは非認知能力のことばかりを書いている気がします。これからの教育に必要な不可欠な能力で、学校教育でも取り入れていかなければいけないものだと強く思うからです。
非認知能力のおさらいです。
非認知能力(英語ではnon-cognitive skills)は、IQや学力テスト、偏差値などのように点数や指標などで明確に認知できるものではないけど、子どもの将来や人生を豊かにする一連の能力のことです。一口に定義できるものではないのですが、たとえば、やり抜く力、目標に向かって頑張る力、自制・自律性、自己肯定感、他者へ配慮、コミュニケーション能力、論理的な思考力などが該当します。

下のnoteでも書きましたが、非認知能力の重要性を示す一番有名な実験として「ペリー就学前教育プログラム」というものがあります。
非認知能力を上げることで、人生における『成功』や『幸福』を手に入れられる確率が上がるというものです。これまで日本では、下記のような生き方がステレオタイプな「幸福の方程式」とされていました。
一生懸命勉強する⇒”いい”学校・大学に入る⇒”いい”会社に就職する⇒たくさん給料がもらえる⇒幸せになれる
言うまでもなく、この方程式はすでにオワコンになりつつあります。
一生懸命勉強して、"いい"学校(偏差値の高い学校)に入っても、社会が求める人材像が変わっているので、いい会社に入れるとは限りません。そもそもこれまで"いい"会社とされていた会社が今後も繁栄していくわけではありません。バブル時代日本は”Japan as number one”と世界中から注目の的となっていましたが、その当時栄華を誇った会社の中には今は見る影もないようなものもありますし、弁護士や医者といったピラミッドの頂点に君臨するような社会的地位の高い職業もAIの台頭により今後仕事のあり方が変わってくると思われます。
IT革命が起き、これから私たちはSociety 5.0(欧米ではIndustry 4.0と呼びます)という常に変化が求められる時代(VUCAの時代)に生きていかなければいけない中、求められる能力が認知能力から非認知能力に変わっていくのも自然なことだと思います。

では、非認知能力はどうやって身に着けていくべきものなのか、子供たちに何をしたら非認知能力が育まれていくのかというのがこの本の主旨です。
簡単にまとめてしまうと、非認知能力は「こうすれば身につく」という類のものではなく、環境を整えることで涵養していくものだというのが筆者のポール・ダフの主張です。
子どもにとっては彼らの世界の大半を家庭と学校(保育園や幼稚園を含む)が占めます。その家庭環境や学校の環境によってこの非認知能力の高低が決まるというのは極めてシンプルで分かりやすいです。
例えば家庭環境という点で言えば、親の「アタッチメント(愛着)」が子供の成長に大きな影響を与えることは親であればだれでも知っていることだと思います。または、幼少期の「あそび」が知的好奇心や探求心、問題解決能力などを育むことも周知の事実だと思います。
一方で学校教育(とりわけ日本の学校)で非認知能力の重要性がどれだけ認識されているかというと、かなり怪しいと思います。残念ながら私の周りでも「非認知能力」という言葉を知らない先生も多いと思います。
これまでの学校教育において偏差値などの認知能力が子供たちの評価軸になっています。これは大学受験が教育の一つのゴールになっており、そこに至るまでの中学受験や高校受験、そして定期試験や英検などの多くの試験で目に見える学力(認知能力)を図ることが教育の中心になっているからです。世界が急速に変化し、これからの世界で求められる人材像が変わってきている中で、この従来型の価値観を我々教師、生徒、そして保護者も変えていかなくてはいけないと考えます。
とりわけ日本の教育は世界の教育よりも数周遅れだと言われている中で、変えていかなければいけない点は数多あります。
まず、「みんな同じことを、同じペースで、同質性の高い学級の中で、教科ごとの出来合いの答えを、子供たちに一緒に勉強させる」という環境を破壊し、学校の中にできるだけ多様性を取り入れ、個別最適化した学習環境を提供することです。スクラップ&ビルドをしばければ未来はありません。
また、教師が中心の学校運営ではなく、生徒が中心になる学校生活にシフトするべきです。例えば、授業一つを取ってみても、先生がひたすらしゃべっていて、子供たちが発言の機会すらない環境の中で、彼らが批判的思考力を身に着けたり、コミュニケーション能力を高めたりすることはほぼ不可能です。日本の子供たちの自己肯定感が他国よりも著しく低い原因はこのような教育環境(家庭環境も含む)によるものだと思っています。
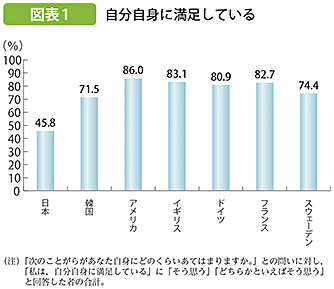
学校教育が変わることで子供たちは今よりも非認知能力を育むことができ、学ぶことの楽しさを覚え、生涯自律的学習者として生きていく。そんな世の中になるように、一つ一つやれることを実践していきたいと思います。
