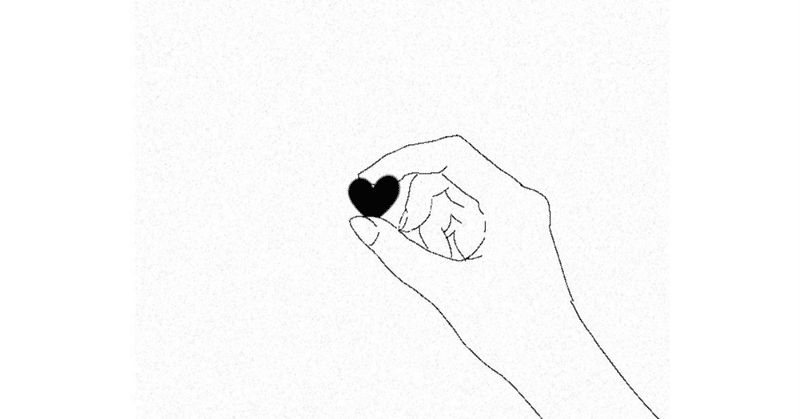
【1分小説】さみしさとチョコレート
「私ひとりでもさみしいって感じないよ」
アカネはアンティーク調のカウンターテーブルで頬杖をつきながらミヤコに言った。
「てか、ふたりでいるより、ひとりのほうがさみしくない」
「どういう意味?」
薄暗い店内にはSwallowtail Butterflyがうっすら流れ、今時珍しく奥に座る客の紙タバコがゆるりと漂っている。
アカネのマットカーキなネイルはそれらにぴったりマッチしてした。
ストローをカラカラ言わせてアカネははっきり明るい声で答えた。
「私、旦那と別れて気づいたんだけど、分かり合えない誰かがずっとそばにいる人生ってすごいさみしい。つらい。ひとりになったらすーっと楽になったんだよね。そんで楽しい!自由だし、私には今可能性しかないから」
「なるほどー。そっか、私は元カレが家出てったあとが人生最大にさみしかった。いや、ポコが死んだ時の方がさみしかったかな」
「犬とか猫とかは、そりゃね。だってお互い信頼して求め合って与え合ってる仲じゃん。
そういう、心がつながってる誰かがいなくなるのはさみしいけど、信じ合ってた相手とだんだん信じ合えなくなって、期待できなくなって、未来が見えなくなって、でも一緒にいなきゃいけない状態ってほんと辛かった。
そういう人と暮らしていかなきゃいけない毎日ってまじでさみしいんよ」
アカネは白く細い指で銀プレートの上のチョコレートをひとつつまんだ。
「チョコの味っていつ知ったんだろうね?」
「この甘さ、知らなければ食べたいなんてことすら思わないのに、知ってしまったがゆえにほしくなる」
「それ。だからさ、こう身も心もフィットした時間を知ってるからこそ、なくなってしまうとつらいんだよね」
「つまり、さみしさの正体は喪失感?」
「うーん、だけじゃないと思うけど、概ねそうなんじゃない?満たされた経験があるから感じられるものなのかもね。
だからもちろんベースのさみしさって残ってるんだろうけど、今はそれが浮上して溺れそうになることはないよ」
ミヤコもチョコをつまんだ。
「......このにっくきチョコめ!」
「でもこの味知らないまま終わる人生はいや!」
「間違いない!えい、食べれるときに食べてやる!」
ふたりは笑いながら次々に小さなチョコをつまんでは口に放り込んだ。
銀プレートは
あっという間に
空になった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
