
隠れオタクとソーシャルゲームーオタクは隠すもの?
オタク趣味の一般化
最近ではアニメやソーシャルゲームといった、いわゆる二次元コンテンツ・オタクコンテンツと呼ばれるものも一般的に受け入れられ始めました。
魔法少女まどか☆マギカや鬼滅の刃、東京卍リベンジャーズといったアニメ作品が社会現象となったり、あんさんぶるスターズ!やアイドリッシュセブン、ディズニー ツイステッドワンダーランドなどのソーシャルゲームは新宿や渋谷などの主要駅に大々的に広告を打つようになったりしています。
その他、VOCALOID楽曲が大手企業とタイアップすること、VOCALOID楽曲クリエイターがメジャーデビューすることも増えました。
平成初期頃や平成中期にわたり、そういった二次元コンテンツが一般的に受け入れられるようになったことは皆さん肌に感じているのではないでしょうか。
とはいえ、平成を生きた我々の生きる社会には、オタクを犯罪者予備軍としたり、オタク趣味を気持ち悪い・怖いものという風潮がまだまだ残っています。それゆえにオタクの中には隠れオタクとして趣味を明かさず社会生活を送る人も。
今回は特にソーシャルゲームの趣味としての扱いから、最終的にオタクは隠すべきなのか?を考察していきます。

隠れオタクとソーシャルゲーム
最初に隠れオタクについてですが、これは文字通りオタクを隠している人のことです。
先述の通り、オタクであることを明かすことでマイナスの印象を持たれることは多いため、それを避けるためにオタクコミュニティでない場所、会社や家族にオタクであることを隠している人のことを指します。
例えば、隠れオタクはスマホのロック画面やホーム画面を普通の写真にしておいたり、絶対にそれらしいグッズを外に持ち出さないようにしたり、イベントの予定は濁したりと、様々な工夫をこらして社会生活を生き抜いています。
仕事中はソーシャルゲームの通知を切る、ゲーム内イベント期間はトイレで体力消費をする……といった工夫もあります。
オンライン・リアルタイムでイベントの多いソーシャルゲームは隠れオタクにとってはなかなかシビアな趣味になるので、結構大変なんですよね。
オタクを隠したい人格と、オタクとしてソーシャルゲームをやりこみたい人格が常に戦っている状態なわけです。
オタク的SNSの使い方
オタクたちは主にTwitterを用いてコミュニティを形成したり、情報を得たりします。
ソーシャルゲームやアニメの公式運営も、基本的にはTwitterで情報を発信し、キャンペーンや企画などもTwitterを用いることが多いですね。
海外企業発のソーシャルゲームでは、Instagramのアカウントがあるものもありますが、特に日本企業発のソーシャルゲームの公式サイドが運営するアカウントはTwitterです。これはユーザーの傾向やニーズに合わせたものであると考えられます。
リツイート機能=拡散機能、引用リツイート=情報の引用、リプライ=コメントといった情報コミュニケーションを主体としたTwitterという媒体は、好きなものの情報を集めたいオタクには最も使いやすいSNSであると言えます。

二次創作を楽しむ
SNS、主にTwitterですが、二次元オタクの中では昔から二次創作という文化があり、それをより楽しみやすくなった気がします。
二次創作はいわゆるファンアートを含めた、公式の設定やキャラクターを借りた様々な創作活動を指します。コミケなどで同人誌が売られている中にも、二次創作は多いです。
もちろん、それらは作る人がいてこそ。
二次創作作品を作る人、見る人がいて、共存している場所は主にインターネットです。
また、中には腐向けと呼ばれるものがあり、同性のキャラクターどうしをカップルとして描いた作品を指しますが、隠れオタクの中にはさらに隠れ腐女子・腐男子もいますね。腐女子・腐男子は腐向け作品=BLやGLを好む人々のことをさします。
このあたり、平成初期頃には各々のオタクが「二次創作は公式に見逃してもらっている、ほぼ黒のグレーゾーン」ということを認識して慎重に動いていたのですが、ここ数年の若年層の認識と古の……平成のオタクとの間に認識の相違が目立ち始めています。
インターネットやSNSの普及、Twitterの人口増加や年齢層の幅が広がったことによって、オタクというものや二次元コンテンツに対する認識の差が広まっていることが原因と考えられます。
暗黙のルールとか
オタクの中にも、先述の二次創作はグレーゾーンだというような暗黙のルールや認識があります。
少し前で言う、オタクは隠すもの・恥ずかしいもの、みたいなこともそうです。
他にも、オタク同士が過ごしやすいようにと時間をかけて形成されてきたものが色々。
それはネット上に強く残り、2ちゃんねる(現5ちゃんねる)で生まれた「半年ROMれ」のようなものも当たり前の認識として残っていました。まずは界隈を知れということですね。
また、腐向けについても細かく色々なマナーがあり、他のオタク、趣味の合わないオタクに向けた気づかいは常々大切にされてきました。
以前は掲示板、今はSNS、Twitterで引き継がれていますね。
隠れオタクの憩いの場・Twitter
隠れオタクは普段の生活の中で、自身のオタクである面を隠して生きていますが、そんな中での憩いの場となるのがTwitter。
普段話せないことを話せる仲間がいて、好きなものの情報を得られ、二次創作の作品が溢れるのがTwitterを始めとしたインターネットです。
名前や顔、職業など、リアルの情報を伏せたまま、趣味だけの世界に没頭できます。
隠れオタクにとってのTwitterは、大切な憩いの場であるんですね。
ただし、二次創作を楽しむの部分で書いたように、ユーザー間の認識の差などから時折議論が巻き起こることも。
時代によって変わりつつある認識
例えば、平成初期から平成中期を生きてきたオタクと、令和初期を生きるオタクとでは社会の風当たりが違いますよね。
そもそもオタクを恥ずかしいものだと言われ生きてきた人たちに隠れオタクが多いのに対し、社会現象として二次元コンテンツが盛り上がる中を生きるオープンオタクが同じ価値観を持つのは難しいです。
更に具体的にいうならアニメが好き、ソシャゲが好きと言うだけで気持ち悪いと言われた人と、「あのアニメ見てないの?」と笑われてしまう人。二次元コンテンツに対する価値観の植え付けが違う人どうしが同じ場所にいても、同じルールを受け入れられないのは納得です。
時代によって変わる社会における認識や人の価値観を理解しつつ、受け継ぐべきものを受け継ぐというのは難しい問題ですね。
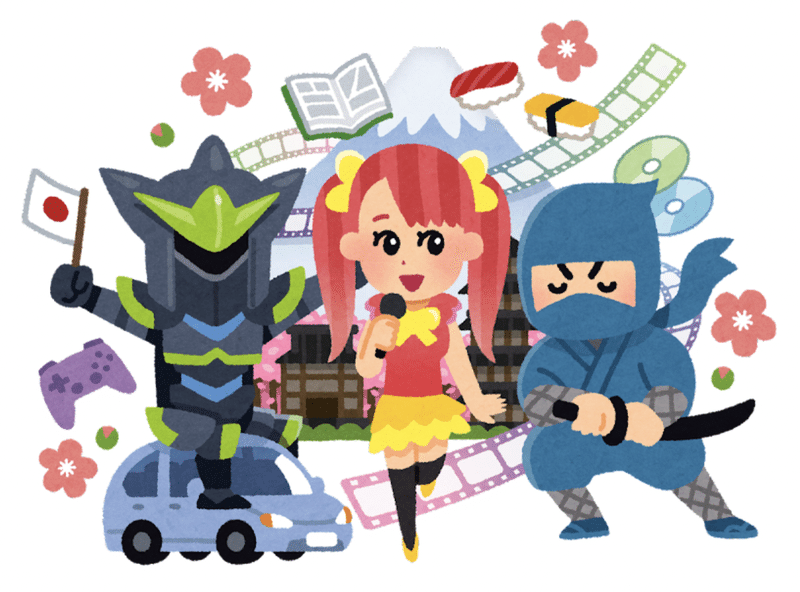
さいごに
ここまでで隠れオタクについて、楽しみ方について、SNSの暗黙のルールなどを書いてきましたが、「オタクは隠すものか」について最後に考えましょう。
結論から言えば、そこは自由です。時代によって変わってきましたしね。
何度か書きましたが、平成初期を生きたオタクはオタクを恥じたり、隠したりしがちです。それはそれで本人が落ち着くのならOK。
平成後期以降、社会的にオタクが受け入れられた中を生きるオタクは隠さず、オープンオタクであることが多い。それももちろんOKです。
ただし、お互いにそのあり方を責めたり、喧嘩のようになるのは良くないですよね。
あくまで趣味、自由であっていいものです。
そういう時代かな、そういう時代だったんだな、という程度で良いのです。
他者への強制や押し付けはせず、時代に合ったオタクのあり方でいいのだと思います。
それがまた難しいんですけどね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
