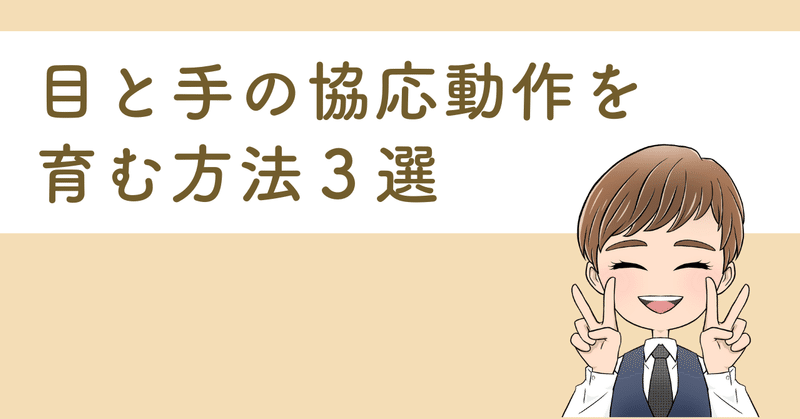
【目と手の協応動作】を育む方法3選
こんにちは。
特別支援学校教諭のしんちゃんです。
子どもを育てている時に、こんな場面はありませんか?
⚪︎靴を上手く履く・脱ぐことができない
⚪︎服のボタンを掛ける・穴から取ることができない
⚪︎はさみが上手く使えない
⚪︎スプーンやフォークで食事をすると口まわりが汚れる

こうした背景には、目で見て手を操作する力(目と手の協応)が十分に養われていないことが多いです。
今回は、特別支援学校教諭と2児のパパとしての経験をもとに具体例を用いて書いていきますね。
①目と手の協力ができないと困る場面
日常生活において、目と手の協応動作は非常に重要です。この能力が欠如されると、様々な場面で困難に直面します。
例えば、上記の他には、手紙を書く、キーボードを操作する、本を読むなど、日常の様々な状況で目と手の協力が必要です。
②目と手の協応動作の説明、具体例
目と手の協応動作は、『視覚的な情報を手の動きに適応させる能力』のことを指します。
目と手の協応動作は、幼少期から段階的に獲得されていきます。
一般的な発達の進行に基づいて言えば、基本的な目と手の協応は、生後数ヶ月から徐々に発展していきます。
生後数ヶ月から1歳頃: 赤ちゃんは手で物を進めることや対立で物を考えることを始めます。
1歳から2歳:この時期になると、手と目の協応が進化し、物を差し出したり、使って物を選んだりすることが増えます。
2歳から3歳: この年齢では、ものを我慢する、通行する、絵を描くなど、より複雑な動きと視覚的な認識が注目します。
4歳から5歳: 手の動きと視覚的な認識がさらに発展し、より複雑な作業が可能になります。対応が求められます。
ただし、これは個人差や環境、練習の度合いによって、この時期はばらつきがあります。
適切な環境や遊び、学習を提供することで、子どもたちが効果的に目と手の協応動作を獲得する手助けができます。
③育む方法3選(自作の動画教材もあります😊)
1.遊びを通じたトレーニング
例えば、ボール遊びや積み木を使った遊び、視覚情報を手の動きに即座に反映させる練習を行います。
息子の保育園で良い教材がありましたので、撮影してみました。
【目と手の協応動作】
— しんちゃん🔆特別支援学校教諭 (@tokushi0601) September 10, 2023
発達障害の子どもによく見られるのが…
①ハサミがうまく使えない
②色塗りが苦手
③文字のバランスが悪く枠からはみ出る
目で見ながら手を使う動作に困難がある場合、専門の知育玩具が有効です。
息子の保育で知育教材があり、その様子の動画を作成しました😊#特別支援教育 pic.twitter.com/5Q4xPGAPBl
2.視覚情報と手の動きを組み合わせた活動
絵を描く、折り紙をする、型造紙で形を切る、動く物を触って追うなど
視覚的な情報を手に動きに直接結びつける活動を行います。
こちらは自作教材になります。
ダウンロードOKです😊
データを整理していたら、PremierProを使い始めた頃に作った動画教材が出てきました!
— しんちゃん🔆特別支援学校教諭 (@tokushi0601) September 10, 2023
【目と手の協応動作】の眼球運動を鍛える教材です👀
ルールは…
①動物が出てきたら画面を触る。
②消えたら離すをルールに行います。
参考になれれば幸いです😊 pic.twitter.com/4IW99eOi34
3.視覚的なフィードバックの活用:
鏡やビデオを利用して、自分の手の動きや姿勢を観察します。
フィードバックを受けながら手の動きを調整する能力が向上します。
これらの方法を取り入れることで、日常生活や学習において効果的に活用することができるでしょう。
目と手の協応動作は、日々の積み重ねが必要になります。
私も支援が必要な子どもを担任していますので、一緒に根気強く、継続していきましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
