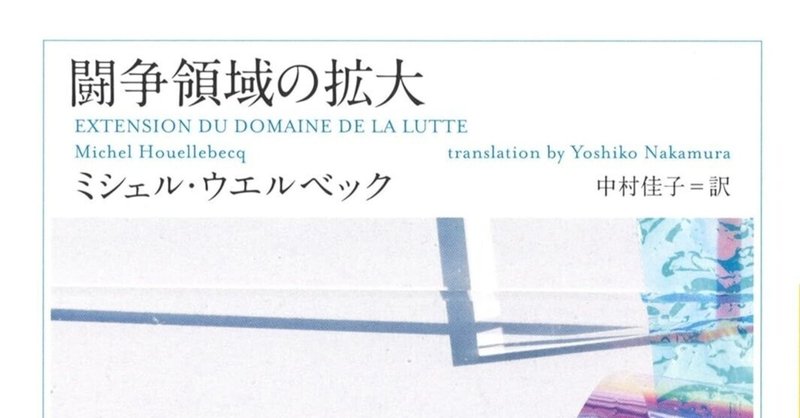
【競争社会の乗り切り方】闘争領域の拡大/ウエルベック②
前回の記事に引き続き、『闘争領域の拡大』について書きます。
否応なく放り込まれる競争社会をどのように乗り越えるべきか?という点についてです。
そもそも、私たちはどのようにして競争に駆り立てられてしまうのでしょうか?
満員電車における座席バトルってありますよね。途中で降りそうな人の前に陣取っておいて、席が空いたら即座に座るという笑
確かにみっともないです。でも、そうしないと誰かに座られてしまうし、ギュウギュウのまま長時間乗り続けるのは嫌ですよね。
別に好きだからやっているのではなく、外部要因によってやらざるを得ないところがポイントです。
ここまで曖昧にしてきてしまいましたが、言葉の整理をします。
「闘争」(struggle)と「競争」(competition)です。どちらも他者との対立を意味しますが、差異があります。
「闘争」の方は本作のタイトルの訳に当てられていますね。直接的に他者を打ち負かすことです。他者のアクションの影響をもろに受けます。座席取りのようにパイの奪い合いが生じます。
一方で「競争」はゴールを目指すことが主としてあり、他者との優劣は間接的に生じるものにすぎません。パイの奪い合いが生じるとは限りません。
「闘争」への対策はシンプルで、出来るだけ避けるべきです。『金持ち喧嘩せず』と言いますが、得るものは少ないですし、本来やるべきことのためのリソースが減ってしまいます。
問題は、「見えない闘争」に巻き込まれている場合がありうるということです。後述します。
「競争」についてはどうでしょうか。競争は、実は悪いことばかりではないんです。
自分が望む理想に向かっているか?がポイントになります。
理想に向かう過程での競争は良い競争です。ライバルとの切磋琢磨を通して自分を向上させることができます。
では、もし自分が望まない方向に競争してしまっていると気づいたら。
競争の前段階で、「見えない闘争」に負けている可能性があります。
僕はこの世界が好きじゃない。やっぱり好きじゃない。僕は自分の生きている社会にうんざりしている。広告には反吐が出る。コンピュータには吐き気がする。コンピュータ技術者という僕の仕事は要するに、照合すべきもの、合致させるべきもの、合理的判断の基準を増やすことだ。なんの意味もない。はっきりいって、ネガティブなものでさえある。ニューロンにとっては、無用なかさばりだ。この世界で、余計な情報ほど要らないものはない。
現代は広告やITを通じて他者の意見が溢れかえっています。
しかし、それらは発信する側の都合のいい情報でしかありません。
レビュー評価のような一見客観的に見える数字であっても、特定の個人の意見の寄せ集めにすぎません。その誰ともあなたは違っているはずです。
望まない方向に競争をしているのだとすれば、それは他者の利益になる価値観に従ってしまっているということ。価値観形成という闘争に負けてしまっているのです。
competitonの原義は、共に(com)+追い求める(petere)ことです。
自分にとっての理想を追い求めていきましょう。
とはいえ、「自分にとっての理想」なんてそう簡単にわからないよ、という問題があります。
こちらについては、次の記事で書きますのでご覧になってみてください。
また、今回の内容を深掘りしたい方はこちらの本もおすすめです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
