
『歩いてみたら』 第1章
1
働き方改革なんて他人事だと思っていた。その影響が我が身に及ぶことになるなど、毛ほども予想していなかった。
水沢博一(みずさわひろかず)が勤める会社はコピー機のリース業を主としている。大学を卒業し、入社してから六年間は営業部に籍を置いた。その後メンテナンス部に移り、客先に出向いて筐体の設置や点検、修理などに五年間励んできた。
とくに希望して就いた仕事ではない。
大学のキャリアセンターに求人があったのでエントリーシートを提出した。それが通ったから面接を受け、採用が決まったというだけの話である。
しかし、たとえばリース先で修理を終え、コピー機から白い紙が吐き出される瞬間などは、ちょっとした達成感を覚えたりする。
客から緊急の呼び出しがない限り残業はない。五十余名の社員同士の仲だって良好だ。住宅手当はつかないが結婚の際には社長みずから祝儀を手渡してくれたし、妻の出産となればミニ・ボーナスが舞い降りてくるらしい。
ブラックと呼ばれる企業を糾弾するニュースがテレビで流れるたび、やり甲斐や給与面において一抹の物足りなさを感じながらも、博一は自分の会社を見直していた。あえて口にするほどの不満はなかった。
ところがこの四月に、事務職への異動を命じられた。
理由はなんとなく分かっていたが、念のためメンテナンス部の部長に理由を訊くと「さあ、俺より上からの指示だからなあ」と言って、天井を指さすだけだった。新卒入社の生え抜き社員は数年ごとに異動させ、長い時間をかけて全部署を経験させる。それが博一の会社の習わしだ。
かたくなに拒む理由はない。だが、すっかり板についた短丈の作業着を脱ぐのは名残惜しかった。
異動先の総務部はオフィス・カジュアル化を推進していた。そのためチノパンやオックスフォードシャツ、そしてストレッチ生地のジャケットなどをユニクロで買いそろえた。ついでに収納が豊富な米軍モデルの通勤リュックと、足ツボを刺激してくれる室内履きの健康サンダルも購入した。
文房具を一新して勉強に精を出そうとする学生みたいだ。
博一はそんな自分がおかしかった。
新部署はとくに忙しくもない会社の中で、とくに忙しくない部署だった。
人事、経費や給与計算、備品管理、そして社長の身辺のお世話など。ある程度以上の規模の企業であれば、それぞれ独立した部署を設けるような業務を一手に引き受ける「なんでも屋」の感がある。しかし、それらがひとつに編成されているぶん、総務部にはやや過剰なまでの人員が割かれていた。担当を細かく振り分け、基本的に自分の仕事のみ集中して取り組むというスタイルだ。
ゆえに、既存のメンバーには各自の役割があるが、新入りの博一はいきなり手持ちぶさただった。
黙っていると誰も仕事を振ってこないので手伝いを申し出ても「うーん、でも俺もやることなくなっちゃうから」と相手にしてくれない。ならば掃除でもするかと意気込んで給湯室を整理してみたら、「ああ、ほうじ茶はそっちの棚じゃないよ。水沢、座ってていいから」などと着席を促されてしまう。
かといってパソコンと向き合っても仕事がない。いちど、あまりに暇なのでネットニュースのエンタメ欄を読み漁っていたら背後を通った部長に「お、熱心にやってるなあ」と言われてしまったものだから、博一は身動きがとれなくなった。
やることがなさ過ぎる、というのもつらいことだと知った。
そうして落ち着かない気持ちのまま三週間が過ぎたころ、社長から昼食に誘われた。新部署に身を置く自分を気にかけてくれたのだと思い、嬉しくなった。
社長との食事など会社行事をのぞいて初めてのことである。会場は築地にある老舗料亭を指定された。懐石ランチのメニューは事前に食べログでチェックしておいた。
いくら社員数が多くない会社とはいえ、創業者のオーナー社長と対座するのは緊張する。お誘いを受けて浮ついた気分をおさえつつ、失礼がないように言葉を選んで異動後の状況を説明した。
「みなさんご自分の仕事があるようで、のんびりやらせていただいています。でも、もしかしたら以前いたメンテナンス部のほうが、私の肌には合っているのかもしれません。もちろん、いまの部署でも精いっぱい頑張りたいと思いますが……」
約一時間半のランチタイムで伝えられた内容は、概してその程度だった。残りは社史を聞かされた。
早急に元の部署に戻れるとは思っていない。だが、「なにか仕事がしたい」という意思表示はした。
古希を過ぎた社長は口元に笑みを浮かべ、しきりにうなずいて博一の話を聞いた。
意を汲んでもらえたと思った。電球の取り換えでも社用車の洗車でも、なんでもやるつもりだった。
そのため、ゴールデンウィークあけの水曜日に総務部長から会議室に呼ばれ、「正式なお達しはまだだけど、水沢、来週からひと月休みだそうだ」と告げられたとき、博一は耳を疑った。
「え、どういうことですか」
「さあ、俺より上からの指示だからなあ」部長が天井を指さす。
「それ異動のときも言われましたよ」
思わず苦笑してしまう。つられるように、部長も笑っている。
「休みの理由は……?」
「社長がな、触発されたそうなんだ」
「誰にですか」
「俺も聞いた話なんだけどさ」
部長が会議室のドアにはめられた擦りガラスに目をやり、声をひそめる。
「近ごろサラリーマンの過労死とか自殺のニュース多いだろ? 社長あれ、けっこう気にしてるんだって。うちでそんなハードに働いてる人間いないって、もちろん承知のことなんだろうけど。中小企業の経営者が集まる懇親会とかでそんなのが話題になったりするらしいのよ」
「へえ」
「それで『昨今話題になっておりますが、おたくのとこは働き方改革についてどうお考えですか』みたいなとこまで話が広がった。その懇親会でな。そしたら社長は返事に困った。顔馴染みの参加者たちは具体的なアイデアを持ってんのに、自分にはない。どうすればいいんだ、って」
「まあそれは、うちが改革する必要ない会社だからでしょう」
「それだよ」
発車前のバス運転手が前方を確認するように、部長が博一を指さした。
「そこなんだよ。働いてるほうからすりゃそうだろ? 給料こそ平均……ちょい下ぐらいだけど、ワーク・ライフ・バランスは安定してる。給湯室のインスタントコーヒーだって飲み放題」
「あれ酸っぱいですけどね」
部長が神妙な顔でうなずく。
「なんにせよ社員の間に大きな不満はない。けど経営者にはメンツってもんがある。いや、俺も雇われだから本当のところは分かんないけどな。とにかく社長はそのへんの対外的な体裁が気になり始めた。よそが社員の働き方に変化を打ち出してんのに、自分のとこがなにもしないわけにはいかない。でも抜本的な改革を行うには痛手をともなう大手術が必要だ。うちも業績がそこまでいいわけじゃない。だったら可能な範囲で、社員がより快適に働ける環境を整えてやろう、それにはリフレッシュのための長期休暇がいいだろう、ってことになったはずなんだよ。ひとりひとりの給料を上げるより懐は痛まないし。これは俺の推測も入ってるけど、まあ正解とみて間違いない。で、ここまで言えばもう分かるな? そんな経緯があって、いま宙ぶらりん状態で、数少ない新卒入社の生き残りで我が子同然、勤続十一年、目立った遅刻欠勤なし、未消化有休もたっぷりの水沢博一君に白羽の矢が立ったってわけ」
「そんなもの立てないでくださいよ」
「俺に言うな」部長はなぜか上機嫌である。
「いいじゃんよ。俺なんて中途の外様だから、あんまり会社からの愛情感じてないぞ? まあ実際のところは、べつに水沢が特別ってわけでもないみたい。仕事の様子をみながら順番に、持ってる有休の日数に応じて休みがもらえるって話だけど」
ふうん、そういうことね――。
スケジュールの面では非常識な告知だったが、部長が伝えてくれた話の筋は理解できた。しかし引っかかるところがあった。
「さっきのって、僕の異動前の話ですか?」
「なに? 懇親会の話?」
「はい」
「いや、後じゃない? そこでほかの経営者に感化されたから、働き方改革として実施する長期休暇なわけだし」
「そうですか……」
「なんで?」
「ええと、休暇のほうは理由が分かったのでいいんです。かなり急ですし、どっちにしろオフィシャルの説明はしてほしいですけどね。それは仕方ないとしても、そもそも僕が異動させられて宙ぶらりん状態になったのはなんでだろうと思って」
「それは水沢なら知ってるでしょ。子思いの会社の方針。新卒には全部署を経験させるってやつ。ちなみに俺はそれ、お遍路さんって呼んでる。八十八部署もないけどな。もちろん皮肉」
「……それは知ってますけど、働き盛りの若手、いや、中堅社員を、そんな理由で暇な部署に異動させますかねえ」
「言っとくけどな」
部長が軽く咳払いをする。
「俺とかほかの連中はそれなりにやることあるの。いま暇なのは水沢だけ」
「たしかに。すいません」
「でも正直言えば、こっちとしても水沢にいられたって困るんだけどなあ。あ、水沢が悪いんじゃないよ。会社が決めたことだし。ただ、人が多すぎてあげる仕事もないし、だからってパチンコ外出許可するわけにもいかないし……。俺だってこう見えて悩んでたのよ。でもあれだな。差し当たりゆっくり休んでくれ。ひと月の間に、なにか動きがあるかもしれないし。俺からも上に言っとく。あんまり当てにはしないでほしいけど」
「……分かりました。お手数かけます。お願いします」
どうも釈然としなかったが、黙って従うことにした。いずれにせよ流されるしかないのだから。

休暇前の最終出勤日は各部署に挨拶してまわった。
部長からは「辞めるんじゃないんだから」といい顔をされなかったが、博一は気が気ではなかった。なにせ一か月も社内から姿を消すのだ。いちサラリーマンの身として周囲にひと声かけておきたい。じゃないとバツが悪い。
営業部の同期からは「お、休暇ライダー一号じゃん。うらやま」と、さして面白くもないあだ名をつけられ、メンテナンス部の上司には、「な、本当に中途の俺らにも休みくれんのかな」と答えを知るはずのない質問をぶつけられた。
博一はどちらも笑ってごまかした。そのほかの社員も今回の休暇に羨望のまなざしを向けているようだった。だが当人の博一としては不思議なことだった。
ある種の戦力外通告を受けたのと同じなのに。案外、自分の番になってみないとこの心境は解せないのかもしれない。
退勤時、いつもはスリープモードにしておくパソコンをシャットダウンした。
モニターが暗くなる。哀愁のサウンドが鳴る。
博一は荷馬車に乗って市場へ売られた子牛の歌を思い出した。もう帰って来られないわけでもないけど……。不安の球根を下腹部に植えられたようだった。
会社から東京メトロと私鉄を乗り継ぎ、急行の停まらない自宅の最寄駅で降りた。
オリジン弁当に立ち寄って幕の内弁当を注文する。出来上がりを待っている間に、斜向かいのコンビニでビールのロング缶を二本買う。普段は家で飲まないが、この日は脳がアルコールを欲しがっていた。幕の内弁当の多彩なおかずをアテに飲むつもりだ。
自宅マンションに帰ると、ビーグル犬のケイティが勢いよく飛びかかってきた。
愛犬の小さな頭を撫でてやり、足早にリビングに入る。L字型ソファの縦線部分に腰をおろす。ガラス天板のローテーブルの上に弁当とビールを並べた。
即座に一本目のプルタブを引く。喉の奥に冷たい液体を流し込む。
うまいなあ。体がほぐれる美味しさだった。足元では、ケイティが自分を見上げて尻尾を振っている。
「ああ、おまえも晩飯だな」
缶ビールをローテーブルに置いて立ち上がる。ケイティのご飯をボウルに用意した。
ソファに戻る。細長いリモコンでテレビをつけた。夕方のワイドショーでは丸の内のランチ事情を道行くOLにインタビューしている。とりわけ興味はないが、チャンネルを変えるのも面倒だった。リモコンを元の位置に戻す。大きなため息をついた。
ま、メシでも食べようかな。休暇の過ごし方を考えるのは、それからだ――。

「ただいまー。あれ」
という声で博一は目を覚ました。どうやら、ソファの上で横になり眠っていたようだ。
「珍しいじゃん。ビール飲んでんの」
「うん」大きなあくびを噛み殺し、帰宅した妻の由梨(ゆり)に顔を向ける。
「おかえり」
「今日はなに買ったの?」
「幕の内。白米大盛り」
「また。好きだねえ」由梨が羽織っていた白いリネンのシャツを脱ぎ、L字型ソファの横線部分に沈み込んだ。
「私はね、取材先でもらったサンドイッチ三つも食べちゃった。でもね、ヴィーガン向けだからきっと体には良いよ。あはは」と、笑って寝転がる博一の脛を叩く。由梨は同い年だが笑うと五歳は若く見える。万年ショートカットであることも関係しているかもしれない。
「またお洒落カフェ特集?」
「そんな感じ。一ページのちょっとしたコラムだけど。そのお店が代々木上原に新しくオープンしたとこでね、私そんなの好きじゃない? だから担当じゃないのに同行してきちゃった」
「自分のことですら忙しいのに働くねえ」
「だって好きな仕事だもん。いいじゃん」
「さすが副編集長さま」
「まあね」由梨が頬に手を当てる。「名刺五枚ぐらいあげようか?」
「もう三枚持ってる」
博一が言うと、二人同時に声をあげて笑った。
妻の由梨は出版社で雑誌をつくっている。女子大生をターゲットにした本だ。
博一が総務部に異動したのと同じタイミングで、由梨は副編集長に昇進した。年齢を考慮すれば早めの出世だろう。
それまでも十分に多忙な様子だったが、ポストの異動後は本人いわく「死ぬほど忙しい」。平日はいつも終電帰りだ。休日出勤も当然のようにある。
博一は朝が早く、帰りも早い。由梨は朝が遅く、帰りも遅い。
したがって水沢夫婦はひとつ屋根の下に寝起きしているといえど、めいめいがひとり暮らしを送っているようなものだった。寝室は別で、土日以外は顔を合わせることも稀だ。
デリカシー不足の同僚からは「プチ家庭内別居?」と言われたりするが、博一は妻と送るこの気楽な生活を気に入っていた。
もともと食事にあまりこだわりがないし、洗濯だって自分でできる。由梨も自分のペースで生活している。
職場で真面目な顔して働く妻が、家ではくだらない話をする。二人の間にケイティを挟んで遊ぶ。週末はカーシェアリングを利用して出かけたりする。
「私いま仕事が忙しくって、ちょっと子供の余裕ないかも」と結婚当初に言われたが、六年経っても不定期にセックスはある。
大学時代にバスケットサークルで出会った妻とこの先も暮らしていく。描いた青写真に間違いはない。それが博一の素直な気持ちだった。
「ねえLINEで言ってた休暇って、結局どうなったの」由梨が冷凍庫から持ってきたアイスキャンディを手渡してくれる。ソファの足元で丸まっていたケイティが顔を上げたが、おやつではないと分かり面白くなさそうな表情で尻尾を揺らした。
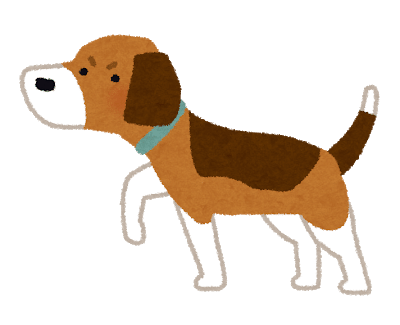
「お、ありがと。休暇はねえ……説明すると長いからあれだけど、有休まとめて使って、ひと月休んでくれってことになった。そんな感じの休みを皆が取れる環境にしてくんだって」
「一か月?」由梨が片眉を上げる。「うちじゃ考えられない。一冊、合併号になっちゃうよ。やっぱ博一のとこはホワイトだねえ」
「いやいや、そんないいもんじゃないよ。いきなりの休みだし。なんて言うか、用無しって宣告されたみたいで落ち込む」
「そんなの考えすぎだよ」
「そうかなあ」
「うん。気にしすぎ。でもあれだね、一か月の休みって……めちゃ長いね」
「な。こういうときに趣味がないと困る」
「ランニングでもすれば?」
「いやあ無理でしょ。もう走ったりなんかしたら死んじゃう」
「じゃあ旅行は? リゾートとか」
「それ会社の女の子も言ってた。プーケット的な?」
「そうそう。家のことは気にしなくても私は大丈夫よん。ね、ケイティ」
由梨がケイティの背をやさしく撫でた。六歳になるビーグル犬はご満悦の体である。
「あ」
「なに」
「もしやることないんだったらさ、休暇の間でいいからケイティの散歩行ってくれたりする?」
「え? ああ、うん。もちろん」
「わあ、やった。最近もう超絶忙しくって、朝ゆっくり寝れたらな、と思ってたとこなの」由梨がアイスキャンディをほおばり、少女のように味わう。
「土日は撮影とか入らなければ私も行けるからね」
「うん。でも疲れてるだろうから、来れるときだけで大丈夫だよ」
博一もアイスキャンディを口に含み、持ち手の平たい木の棒をくるりと回す。無邪気に喜んでいる妻を見て、ふと気づいた。
由梨めちゃくちゃ忙しいだろうに、ケイティの散歩まかせきりだったな――。
俺なんて暇なくせに全然気にかけてやれなかった。
こんなことむしろ自分から言い出すべきだろう。家の中では明るく振る舞っている由梨だって、仕事でへとへとのはずだ。会社でエクセルの列幅を整えて時間を潰しているだけの自分が、平日の朝に早起きして散歩に行くこともできたのだ。にわかに羞恥を覚えた。
よし、そうだな。由梨のためにも、それにケイティのためにも、俺が散歩に行こう。膨大な時間を持て余す自分の役割が分かった気がした。
目の前でアイスキャンディにぱくつく妻が愛おしく思えてくる。
そういえばここのところ、夫婦の営みがご無沙汰だったことを思い出す。
深夜、博一は鼻息荒く由梨のベッドに潜り込んだ。しかし由梨は規則正しく寝息を立てていた。
(2/5へ続く)
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
