
Selectionと戦った10,000時間:第5弾 - 戦略的にスター商品をつくりだす
サマリー
Amazonのプライムデーなどのセールでバカ売れし、その商品がもつ実力以上の売上をつくる超売れ筋の”スター商品”たち。これらがどのように出来上がり、その裏側にどのような戦略があるのかを言語化してみた。セールでの露出という王道の戦い方の中で、如何に戦略的に”スター商品”をつくるかが、Amazonの継続的な事業成長に繋がっていているというお話。
前回までのおさらい
これまでの連載でAmazonのSelection戦略(品揃え戦略)に関して書いてきた。
AmazonにおけるSelection戦略は4つのフェーズに分かれ、前回までにフェーズの①と②に関して書いてきた:
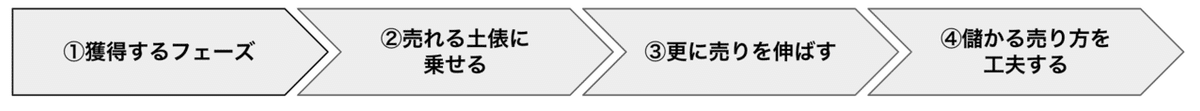
フェーズ①:獲得するフェーズ
- 「どのような品揃えの売場をカスタマーに提供したいのか」を定義し、
- どうしても負けられない競合に対し、どこまで”同質化”、”差別化”するべきかを考え品揃えを獲得していく。
フェーズ②:売れる土俵に乗せるフェーズ
- 獲得した商品が実力を出して売れるように、お客様にとっての”当たり前品質”(値段、カタログ、在庫状態, etc.)を担保する。
お前の実力はそんなもんじゃない
例えばオフライン店舗での売上の順序が、その商品が持つ、他の商品との相対的な実力値だとする。
一つ前の章でお話した、本来その商品が持つ実力値を十分に発揮させるためのレバーが”当たり前品質”の担保だ。
つまり、ちゃんと価格設定や、カタログ情報、在庫の担保によって手をかけてあげて、初めて売れる土俵にたてるということだ。
その実力値を超える”超”売れ筋のスター商品に育てるということは、各小売においても様々な手法で行われていると思う。
いわゆるリアル店舗における”客引きパンダ”というやつだろうか。
今回はこのフェーズ③の「更に売りを伸ばす」という部分に関し、Amazonが如何に既に売れ筋の商品に対して「お前の実力はそんなもんじゃないぞ」と言わんばかりにスター商品を作り上げる際の戦略を説明する。

Amazonにおけるスター商品
Amazonにおいてのスター商品は、早い話セールの時にバカ売れする商品たちだ。
お、、、めっちゃ当たり前な話なのね、、、とページをそっ閉じしそうになるが、もう少しお付き合いいただけると嬉しい。
こういう王道の部分をしっかりと戦略的にできるかどうかが継続的な事業成長に繋がるはずだし、アマゾンの強さでもあったと思うからだ。
アマゾンには派手なセールが年に2回開催される。年によって前後はあるが、大体9月に開催されるプライムデーと11月末のブラックフライデー&サイバーマンデーのお祭りだ。
Amazonの小売事業部にいると、これらのお祭りの何ヶ月も前から事業部のバイヤー、マーケティング、在庫担当、オペレーションの人間は綿密な準備に入る。
お祭りセール時のそれぞれのチームの準備
・バイヤー:どの商品を目玉商品にするかを選定し、
・マーケティング:どの商品にどれくらいの割引をかけ、どこで露出するかを決め、
・在庫担当:どれくらい売れるかの需要予測をもとに在庫を積み上げ、
・オペレーションやSCM:すさまじいピークを乗り越えるための入念な計画をたてる。
祭りの開始時間が迫るとフロアに緊張感がはしり、開始直後に狙った商品がしっかりと売れているかどうか、カテゴリー毎のターゲットに達するかどうかなど、皆で騒ぎながら見守るのだ。
この時はフロアの中で、
「おおおお!開始3分でxxxが売り切れました!」
「トラッフィク多すぎでサーバー落ちてポメラニアン(かわいい)がでてるぅ。。。」
というような会話が飛び交っていて本当に祭り状態だ。

この中で毎回注目されるのが、こいつには力をいれるとカテゴリーが決めたスター商品だ。
通常じゃ考えられない割引率がふられ、どこの広告でも目立つ露出がされている。
これらスター商品は、大抵開始数十分で用意していた数1,000~数10,000個の在庫が溶けていく。
恐らく事前に告知されている情報を元に、新規のカスタマーも既存のカスタマーも、こぞってカートに入れているのだろう。
この祭り騒ぎでトップにくる商品は、事業部がこいつはスター商品にしようと狙っていた商品が並ぶことがほとんどだ。
こんな記事を目にしたことがあるかもしれないが、毎回Amazonではプライムデーなどの後の振り返りとして、その年のお祭りでの一番の売れ筋などを告知している。
僕が担当していた消費財事業部の商品であれば、「ペットボトルの麦茶」、「ボタニストのシャンプー」、「メンズ 除毛クリーム」、「ココア味プロテイン」などが挙げられていた。

Amazon、「プライムデー」の国内売上は過去最高 販売個数は1100万個、最も売れた商品はAmazonデバイスと飲料と「○○」
これらの”スター商品”は、Amazonに品揃えとして獲得した瞬間からスター商品であったわけではない。
数あるナショナルブランドの競合ひしめく売れ筋から、カテゴリー担当が敢えてこの商品を選び、意図的にスター商品に成長させてきたものが多い。
更にすごいのが、スター商品ほどバカ売れすると、これらのお祭りセールの時以外の平常時の売上の向上にも大きく寄与している。
社内データでこれらの商品の売上成長を見てみると、市場の伸びよりも明らかに高い売上伸び率をセール後の通常期間で叩き出しており、世の中のどこかのチャネルや競合から需要を奪っているのだろう。
また、売れ筋の商品をスター商品に育て上げ、更にそれらを定期便として登録してもらうとカスタマーが継続的に購入する、というスキームが成り立つので、どんどんAmazonにおける売上が伸びていくのだ。
とりあえず安くしてもスター商品は作れない
通常、Amazonのセールのような40%オフなどのセールをする場合、明らかに原価割れする商品がでてくるだろう。
ただ、Amazonの場合は、広告宣伝費の補填のような形でベンダーやメーカーから補填をもらっているので、セールの時に死ぬほど安くするということが実現している。
しかし、セールのお祭り期間に大幅な割引をしても、その後の継続的な購買につながらなければ一過性の販売で終わってしまう。
閉店売り切りセールではないのだから、ただの需要の先食いに終わるケースもある。
また、継続して売りにつながらないならば、来年以降おなじような金額のファンドをベンダーやメーカーが補填してくれず、魅力的なセールも実施できなくなるリスクも高い。
じゃあ、これらスター商品はどうやってつくっていけばいいのだろうか。
ここをでしっかりと将来の売上に繋がるような顔ぶれを選び、戦略的に超売れ筋に育てていく必要がある。
Amazonで実践されていたアプローチを言語化すると、1.) 商品の”購入頻度”と2.) 事業部としての”推し度”によって説明できると思う。
図解するとこんなイメージだ:

1.) 購入頻度:カスタマーが日々繰り返し購入するもの
ここはかなりストレートだが、カスタマーが定期的に買う頻度が高い商品は、できるだけ”あれはAmazonで買うべきだよね”と認識付けたい。
そうすることで、カスタマーのお財布(Share of Wallet)の比率をオフラインや他の競合から奪い、Amazonで上げることができるからだ。
2) 推し度:カスタマーに訴求したい商品や商品群を徹底的に推す
事業部が推したい商品や商品群というのは、決してたまたま安く仕入れることができたから、ということではなく、長期的な成長のためになぜそれを推しているのかというWhyの部分を言語化することが重要だ。
僕がこれまで見てきたうまく成長を後押しできていたケースとしては下記が挙げられる:
- 他のカテゴリーに広がるきっかけになるような商品
カスタマーはECで買いやすいカテゴリーとそうでないカテゴリーがあることはデータとしても出てきている。
例えば、ネットスーパーを使い始めたカスタマーは、まだまだネットで精肉や鮮魚を購入することに抵抗を感じているかもしれない。
ここのハードル乗り越えてもらうためにも、効果的にこれらのカテゴリーの商品をセールで訴求し、カスタマーのカテゴリーの広がりを後押しするというのは効果が期待できそうだ。
最初はセールが理由で購入してくれているのかもしれないが、その購買体験を通して品質への抵抗感が除外され、利便性に気づいていただければ、継続的な購入に繋がるかもしれない。
実際にAmazon Freshのプライムデーのセールの顔ぶれを見ると、このあたりの精肉や鮮魚のカテゴリーの割引率に驚くと思うので、次回チェックしてみて欲しい。
- カテゴリーの存在感の醸成
また、まだまだ自社で普段取り扱えていないカテゴリーがあったとして、そこを拡大させていくにあたり、カスタマーへ存在感を主張するためにも効果的だ。
Amazonでもここ数年酒類カテゴリーの品揃えが大幅に増えた。
僕がSelectionをリードしている期間にも、獺祭や一ノ蔵などの超メジャーどころの日本酒の取り扱いが可能となり、日本酒のSelectionを酒類カテゴリーのバイヤーとともにゴリゴリ進めていた。
例えば、セールの期間中にこれらのカテゴリーの露出を上げることで、カスタマーに対して「Amazonって日本酒の品揃え結構あるんだ」という印象を与えることができれば、カテゴリーの長期的な成長にも繋がるだろう。
このように、闇雲に割引をするのではなく、自分のお店でどのようにスター商品を育てていきたいのか、その結果どのようなお店であるとカスタマーに認識してもらいたいのか、を常にカスタマー目線で考えることが重要だと考える。
さいごに
今日はSelectionとして獲得し、しっかりと売れる実力が出せる状態にした商品を、どのように優先順位をつけて”更に売れるようにする”のかを書いた。
どこの小売店舗でも客引きパンダのような売れ筋をつくる施策をしてきていると想像する。
ただ、長期的にその施策がどのようなカスタマーに響き、どのような成長を促進したいのか、改めて振り返ってみると気づきがあるかもしれない。
次でこのSelectionの連載の最終章としようと思う。
皆さん最後までお付き合いいただければ幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
