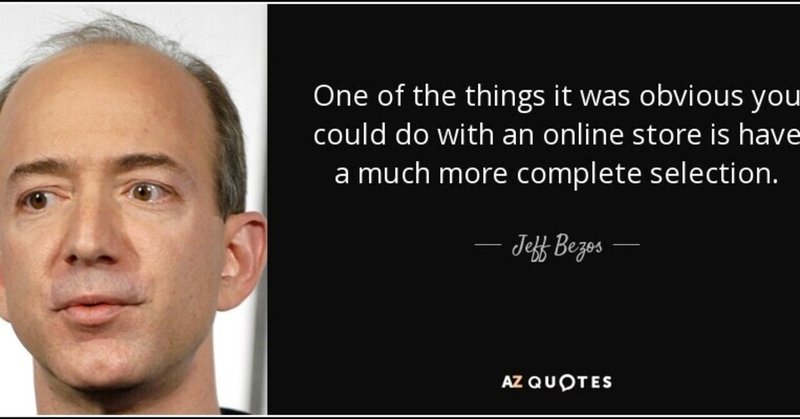
Selectionと戦った10,000時間:【その3】じゃあ、いったいどこまでSelectionを獲得すればいいのよ?
サマリー
前回①獲得するフェーズとして「カスタマーの日用消費財購入のGo to storeとなる」ために「重要な競合に対して徹底的に同質化をとる」と説明。この同質化のロジックを深堀りする。また”同質化”による後追いモデルから、いかに”差別化”するかの説明を加え、このフェーズの締めとする。
どこまでSelectionを獲得するの?
世の中には一体どれくらいのSelectionが存在するのだろう。
Selection大臣として各国の数値の比較は定期的にしていたが、事業規模からいって北米が一番Selectionが多いのはこれを読んで頂いている皆様にも想像がつくと思う。
少し古いデータになるが、2016年時点の調査では北米だけで3億5千万種類あったそうだ。しかもこれは、書籍、メディア、ワイン、その他サービスのSelectionを除き、かつ商品のVariation(色違いやサイズ違い)を除外して、だ。これはマーケットプレイスのSelectionであり、AmazonのRetail部門(Amazon自身がAmazonの在庫として在庫化して商売する)の合計だと1,200万となる。
いろいろな指標が毎年2桁%で成長していたような記憶なので、今はこれと比べ物にならない数のSelectionを提供していることになる。
参考までにだが、普段何気なく通っているお店のSelection数がどれくらいあるのか、気にしたことはあるだろうか?
店舗サイズにも左右されるが、一般的にコンビニは3,000種類、オフラインスーパーは20,000種類、ヨーカドー等のGMSが100,000種類、百貨店が1,000,000種類といわれる。
僕が担当していた部門に具体的にどれくらいのSelectionがあったかは伝えられないが、消費財事業部だけでも、これらの一般的なお店と比べて驚くようなSelectionを保有していた。
このSelectionの数は、ひとえにSelectionの獲得余地を自動的に特定するAmazonの仕組みと、それを、メーカーやベンダーと交渉して獲得してくるバイヤーのたゆまぬ努力の賜物なのだが、ここまで多くなると、一つ問題が出てくる。
一体どこまでSelectionを獲得すればいいのか?
Amazonの各部門(特にバイヤーの皆様)が毎年年初にSelectionの獲得Targetをたてるときにぶち当たるのがこの問題である。
前述の通り、SelectionのMetricsは非常に重視され、進捗はWeeklyで全社で管理され、定期的なBusiness Reviewで社長自らSelectionの獲得進捗をすべてのカテゴリーに対して確認をいれてくる。
言わずもがな、Jeff Bezosもちゃんと各国のSelectionの進捗をみて、コメントする。

曰く「オンラインストアは棚スペースの制限がないのだから、より多くのSelectionをもってて当たり前じゃね」(意訳)とのことだ。
そこに対して”どこまで取ればいいのか”ということにある程度の解を示し、部門全体でスタンスをとって事業を推進していたのがSelectionの”同質化”と”差別化”の考え方である。
同質化と差別化という相反するこれら2つを仕組みの中で実現し、「カスタマーにとってのGo-to store」を実現するということがどういうことかを説明s。

Selectionの”同質化” - 自分たちのユニバースを定義
まず、同質化は前回書いたとおりRelevantな競合(≒Amazonが負けたくない競合)に対して負けないようにするということだ。
消費財事業部にとってのRelevantな競合をもう少し言語化すると、大きく3つあり、
①オフラインのRelevantな競合の売れ筋を持てている
・消費財にとってのオフラインの競合とは例えばコンビニ、ドラッグストア、スーパーマーケット、GMSなどだろうか。
・これらの売れ筋のデータをどうやって取ってくればいいのかは、小売事業に身を置く方なら想像はつくと思うので、データ取得のHowは割愛する。
②オンラインのRelevantな競合の売れ筋を持てている
・ここは前回コメントしたように、全てのカテゴリーは絶対に負けたくない競合を定義している。そこが提供しているSelectionをデータとしてとってくればよい。
③Amazonのプラットフォームにあるセラーの商品で、RetailでもてていないSelectionを持てている
・ここはAmazonだけのチートだが、AmazonのRetail事業において、セラーがマーケットプレイスで取り扱っているブランドやSKUはデータとして取得できる。(どのセラーがどのSelectionをもっているとかの詳細データはRetial事業との間にFirewallはあり護られているが、セラーが特定できないよなメッシュでは取得できた、はず。。。)
これらの3つのデータポイントをしっかりと網羅したSelectionがあれば、少なくともRelevantな競合に対しては同質化をできていそうだ、と納得感がでると思う。
言うならば、これらの①+②+③がAmazonのRetail部門にとってのユニバース(世界)なのである。
今思うと、この考えにたどり着いた時がTurning pointだった気がする。ようやく終わりのないSelectionの戦いに”終わり”を定義づけられると思ったからだ。
後は、ここのユニバースに対してどのカテゴリーがどれくらいGapがあるのかを特定することができれば、Selection拡大余地のあるカテゴリーがわかる、ということになる。
この拡大余地が、カテゴリー単位でちゃんと把握できてくることがとても重要だと考える。
なぜなら、どの小売もこのカテゴリーは強い、ここはまあそれなりにある、ここのカテゴリーは今は弱い、という感覚値はあると思うが、これを定量的に把握し、全体感を認識できている小売はそこまでいないのではないか。
なぜそのカテゴリーに注力したいのか、これを説明してくれるのがこのユニバースの考えなのである。
Selectionの”差別化” - 小売の妙を出す
ここまで読んでもらっていると、なんだかこのアプローチだとバイヤーのセンスとか、こだわりのSelectionとか、そういう”お店の色”を出す要素がないのでは、と感じる方もいるかと思う。
この点はもちろん僕もAmazonのリーダーシップから突っ込まれていた。
話を進める前に一つ断っておくが、上記で特定されたSelectionの伸び代を埋めるだけでもめちゃくちゃ大変である。バイヤーはあの手この手でメーカーやベンダーと交渉して、Selectionを獲得してくれる。数字を使った理詰めのアプローチを取る人や、抜群のセンスでブランドを獲得してくる人、Amazonで出会ったバイヤーは本当に優秀だった。
話を戻すと、この点を補足するのがSelectionの”差別化”だ。
差別化というと、こだわりの商品を取り揃えるという響きに聞こえがちだが、これが100%ではないと考える。
Selectionのユニバースを作ってみるとよくわかるのだが、一つの小売事業者でユニバースを網羅的に抑えられているところはまずない(実際に競合のSelectionをデータでとってきて、網羅性を個別に確認していたので断言できる)。
カテゴリーによるが、低いところは一桁%くらいのSelectionしか持てていなかったり、高いところは80%くらいもてていたり、カテゴリーによる劣後はどうしてもでてくる。
全てのSelectionを取りに行ければ話は早いが、リソースの制限があるなかどうしても優先順位をつけなければならないのはどの業界も同じであろう。
ここでまた立ち返りたいのが「どのような売場をカスタマーに提供したいのか」という最初の問だ。
ユニバースを作り、自分たちの立ち位置を確認し、その上でどのような色を出していき、そのためにどのブランドやSelectionを獲得する必要があるのか。
この論理プロセスがしっかりと言語化できているかどうかで、継続的なSelectionの拡大活動につながるか否かを大きく分ける。
よくありがちな失敗例が、バイヤーが個人プレイで”差別化”に飛びつくというやつだ。
行きあたりばったりの自分たちが取れていないブランドを取りにいこうとするが、往々にしてそういうブランドは先人の優秀なバイヤーがトライし、それでも獲得できていないブランドであったりする。
もちろん、全体を見たときに、自分たちが作り上げたい売場にそのブランドが必要不可欠だと考えるのであれば、組織全体であの手この手をつかって取りに行くべきだ。
実際に僕が在籍していた期間にもいくつもそういうブランドが存在していた。
みなさんが普段の生活の中で毎日のように目にするブランドも、実はAmazonのRetail部門が喉から手がでる程欲しいブランドであったりするものだ。
こういうブランドをとりにいく場合、個人でやっても埒があかないので、それこそTop会談で取りに行ったり、ブランドを導入してくれないBlockerを特定してそれを取っ払うしかない。
イメージをつけるために、ひとつ完全に架空の事例をつくるとすると、
とある未獲得の高級化粧品ブランドがあるとする。そのブランドの提示条件が”対人で用法用量を説明し、アレルギーなどがないということが担保できた状態でないと売らない”と決めていたとする。
EC事業者にとってそのような条件は致命的だ。(そもそもオフラインのチャネルがないので)
Amazonの場合、もしそのようなブランドがあり、それでもどうしても取りに行きたい場合、恐らくオフラインチャネルをつくってしまう。
こういう普通では考えられないようなActionをうったりもする(社内ではこのようなことをThink BigなActionと言われる)。
オンラインでもオフラインでも考え方は同じ
Amazonだからデータが取れるんじゃないの?とよく言われるが、やり方はいくらでもある。
それこそ、どうしてもその競合に負けたくないスーパーマーケットがいたとすれば、一回息を止めてどのカテゴリーにどれだけSelectionがあるかを調べきってしまえばいい。
組織内にテクノロジーに明るい人がいれば、競合のWebsiteをクロールでもしてしまえばしまいだ。
大事なことは、オンラインのお店でも、オフラインのお店でも、自分たちの戦うユニバースがどこにあるのかをきちんと定義し、各カテゴリーでどれだけ獲得できていて、どこに伸び代があるかを把握し、Selection拡大のためのリソースを投下していくことである。
その上で全体の底上げを”同質化”で進めつつ、差別化の中で小売の妙を実現していくのだ。
おわりに
これまで2回に渡りSelection最初のフェーズである①Selectionの獲得について書かせていただいた。
Selection大臣のお仕事はここでは終わらず、獲得したものをきちんと売れるようにしてあげなければならない。次は②売れる土俵にのせるについて書かせていただこうと思う。特に既に数万単位のSelectionがある事業者の方には非常に重要な考え方になると思う。
最後に、もしこの中に小売事業の方がいたら是非もう一度考えてみてもらいたい。
あなたにとって、どのような売場をカスタマーに提供したいですか?
この問に対しての解像度が、あなたがカスタマーに提供できるSelectionの限界値になるのではないか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
