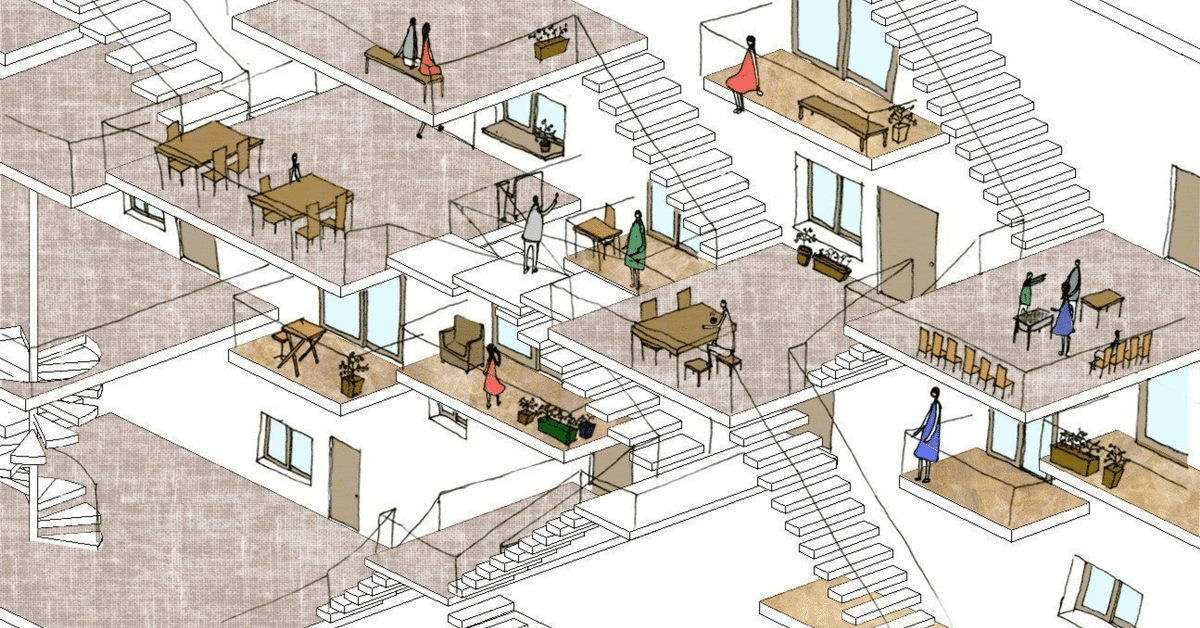
やっぱりポジティブ思考がよい。
介護現場でもイライラしたり怒りの感情を普通に表に出してしまう職員さんがいます。感情労働ですし、僕自身も利用者さんに対してや同僚や部下、上司に対して腹を立てることはあるので理解はできますが、それを表出しても意味がないと思っているので、事ある毎に怒りの感情を外に出すのは自分がその瞬間楽になりたいだけの自己満足だ、と伝えてきたのですが、これがなかなかうまく伝わらないので、怒りのコントロールの方法などの記事は気にして読むようにしていましたが、今回は以下の記事を読んで今度職員に伝えようと思った内容です。
そもそも、サービス業でもあるので当たり前の事なんですけど、そういった接遇やサービスマナーについての基本的な教育をなされないまま現場に送り込まれる介護職が多いので、いったん仕事に慣れた頃に後から接遇がー、サービスマナーがーと指導されるので、だったら最初からそういう指導しろよ、と受けても感じてしまいますので、なかなか浸透しない根深い問題でもあります。
また、そういったサービスマナーや接遇自体を苦手としていて、普通の業種では就労できないので介護をしている、という職員も少なからずいるようです。少なくとも僕自身が指導や面談の中で5人ほど、このような発言や言い訳をする職員を対応した事があります・・・。
恨み・怒りは「持つだけ無駄」と言える納得の理由 不満をぶちまけるのは「一種の快感」だが… (msn.com)
今日は、このネット記事を読んで共感しました。
記事の中に書かれていました。
『不満をぶちまけるのは、一種の快感だ。』
僕は、怒りなど面に出すのはストレス解消だ、という説明をしてきたんですが、確かに快感なのかもしれません。だからこそストレス解消になるんだろうなぁ、と思いました。
『不満を言うだけなら誰にでもできる。そして不満に身をまかせるうちに、頭の中に無価値なゴミがたまり、自由に使えるスペースがどんどん減っていく。』
そうなんですよね、不平不満をいう事なんで簡単な事なんですよね・・・。
言いっぱなしでなくて、その中から何かもっと利用者さんのためにこんな工夫がしたいとか、こんな改善をしたいとか、そういう方向に思考をもっていければいいと思うんですけど、現場の介護職員の多くは言いっぱなしの傾向が強い様に感じています。
『不満ではなく、感謝に注意を向ければ、世界の見え方はがらりと変わる。』
これは本当にそうなんですけど、そう思えない人(信じれない人)に何度言ってもあんまり伝わらなくて、何かのきっかけで本人が気づかない限り難しいんではないかなぁ、と思います。
そのきっかけを作るためにずっと伝え続ける必要はあるんですけど・・・。
「不足思考」(後悔、ねたみ、将来への不安)がいっぺんに消え、「充足思考」(順調だ、恵まれている、将来が楽しみだ)へとシフトする。自分がすでに持っているリソースや資産やスキルを正しく評価し、存分に活用できるようになる。
『ポジティブな気分が高まると、視野が広がり、新たな可能性に目を向けやすくなる。心が開放的になり、創造性が高まり、社会性が増す。』
なんとなくそうかなぁ、と思っていた事をこうして具体的にわかりやすく書いてくれると有難いです。早速職員に伝えたいな、と思いました。
『怒りはあまりいい仕事をしていないことに気づく。リソースを食うばかりで、投資に見合った効果が得られないのだ。その場合、怒りを解雇したほうがいい。』
この部分は面白かったです、怒りを雇用しているという発想はなかったので、そういう視点で感情を考えてみるのは面白いし、なるほどな、と思いました。
『「雨の日にできる最善のことは、雨を降らせておくことだ」』
たとえば認知症の方が何度も同じ事を初めてのように話したり質問したりする場面は、この最善のことは雨をふらせておくことだ、と似たような感じだと思いました。
認知症の方は、何も僕たち介護職を困らせたり怒らせようとしているのではなくて、本人たちにとってはそれが最初であり、どのような行為も本人には正当な理由のある行動なので、それに対して僕たちが言動を制限する事自体が無意味なんです。
もし本当に言動を変えたいのであれば、ちゃんと本人の真意までたどり着いたうえで、本人が自分で言動を変える選択ができるような支援をすべきです。そこが難しくて大変なんですけど、それこそが認知症ケアの奥深さであり専門家の腕の見せ所なんだと思っています。
どれだけ本人の真意に近づけるかは、日ごろからどれだけ本人に興味を持てているか、どれだけ見れているか、どれだけ会話交流ができているかです。
そこにたどり着くには、こちらが怒りの感情やネガティブな感情を持った状態で見ていては、きっとちゃんと見れないと思います。
今日は、このネット記事を読んでそんな事を感じました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
