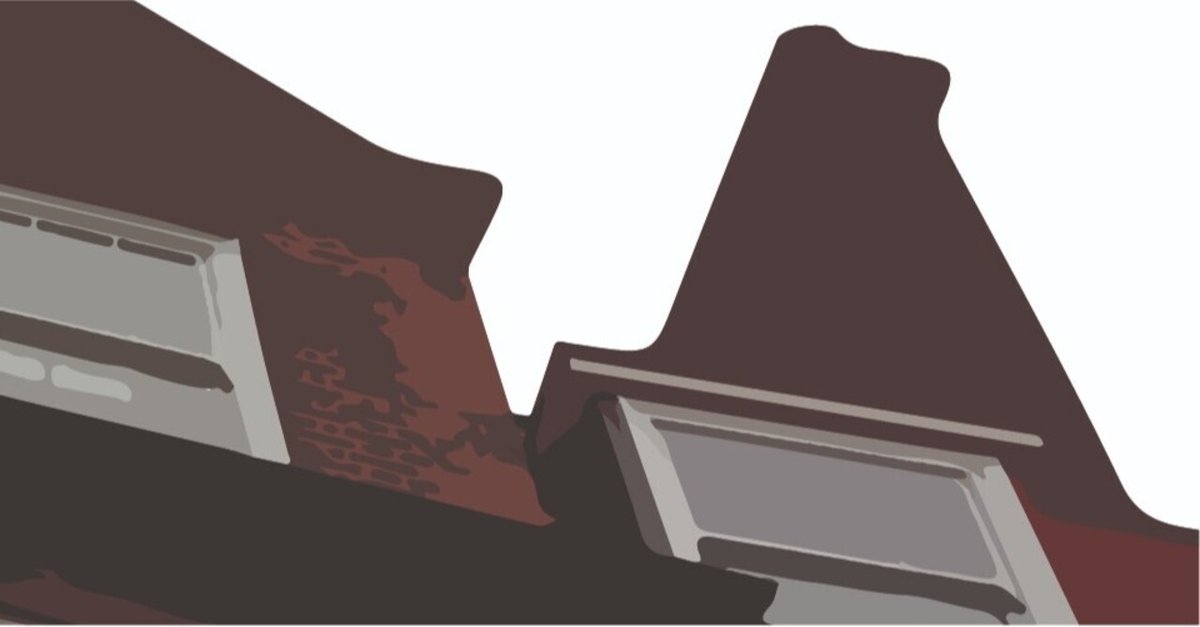
18.十分に発達した幻想迷宮は、公営住宅と区別がつかない。
僕は知らなかったことだけれど、第二次世界大戦が終わってより制定された住居法によれば、それまで労働階級に限られていた条件が撤去され、全ての英国民が公営住宅へ入居する権利を持つ。
ということは、つまり移民を含む住民は、その限りではないのである。
うかつにも、それに気が付いていなかった。
周囲と比較して家賃が低額である理由を、不動産屋の「国営住宅。はいはい。まあ、そうですね。それに近いと、言えなくもないでしょう」という言葉を鵜呑みにしていた(あるいはその歪曲を理解する語学力を、持ちあわせていなかったとも)。
そうして留学生の僕が、この公営住宅に擬態する幻想迷宮、いわゆるダンジョンに居を構えたのが半年ほど前のことだ。その後、各方面から間違いを指摘されたものの、結局そのまま住んでいる。
ただしそれは、一度慣れてしまうとどんな物事をも離れ難く思う僕の、消極的性質による理由であって他意はない。部屋選びの時点に巻き戻せるならこの部屋は選ばないが、今現在やり直すのが億劫な程度、そして周囲に語られるほどには、悪い環境ではないと思っている。
そもそも、公営住宅を求めていたのは、祖母の案による。
九十になんなんとする彼女が、戦後に渡英した友人の話を聞くこと、そして日本人的感覚からくる国営であれば安全、という思い込みによって、僕に示した提案であった。実際にはバブル経済後、都市周辺で高級宅地の地価を下げるために建てられた場所も多々あり、そういうものは逆に犯罪の温床となって治安を悪化させたと聞くので、忠言に添えなかったのは正解だったかもしれない。
そこで第一に、ダンジョンとはどういうものであるか。
ここのは入口横の管理棟を別として、十三棟もが連なる巨大団地様である。
外見は共通しつつ何故か各棟の高さは一律ではなく、四階建てから二十七階までとまちまちだ。建物はなんとなく歪んだ「回」の字の上に配置されているが、法則性を感じられない高低差のため風通しは悪くなく、中央広場にも通路にも閉塞感はない。いくつかの建物はぴったりと隣接し、またあるものは上階が連絡通路でつながっている。
隣の棟を飛ばして、二階から四階へ斜めに接する渡り廊下には、内見で来たときも確かに奇妙だとは思った。
一見は漆喰に赤茶けたレンガの、よくある建築集団である。
しかし、ところどころに古風な煙突がついているのが、全体の様式からすると違和感を与える。おまけにそれがついているところは、ダクトシュートと階段の上だったりするのだ。
これだけ奇異点を見つけていてなぜ、入居するまで気が付かなかったのか、と呆れられるかもしれない(実際、ゼミで一緒になったスコットランド人には馬鹿にされた。「それは事故物件と同列で、部屋探しで気をつけるべき最も基本事項のひとつである」)。
だがこの類の常識は、長くその地に住むか、教えられなければ知りようがない。その環境で育ったものにとっては、その警戒すら自覚しない、ごく当たり前のことなのだ。だから無知な外国人は騙され、カモにされてしまう。
そう言ってしまうと九龍とかスラムみたいな、物騒この上ない場所を想像しがちだろうが、実際には広大な敷地に緑も豊かに、高級住宅街の隅にあるので閑静でもある。
首都の主要な地域のすぐ外にあり、交通のアクセスも悪くない。もちろん、それはこの種の迷宮の性質を少しでも知っていれば、少しも不思議なことではないが。
誰にでも、ダンジョンと言われてなんとなく抱いているイメージがあると思う。
古くなら、地下迷宮に住むミノタウロス。ゲームをする人間なら、洞窟の中にアリの巣状の、モンスターの住処を思い浮かべるかもしれない。どちらも正しい。一説には数千もの種類が存在すると言われるほど、迷宮には色んな形がある。
そんな中で、連想にアリが登場するのは冴えている。
集合的な意思をもつもの、その上でその天敵であるアリジゴクまで思考を広めることができれば、もうそれでダンジョンというものが見えたも同然だ。
つまるところダンジョンとは、超自然的生命力が出現あるいは一定量が停滞することによって発生する、空間的な生物であると定義される。
地球を一つの生命体とみなす、ガイア論にそれは似ている。しかし小規模で、そして遥かに積極的な性質を持つものだ。
というのも、肉を持たないが生き物である限り、彼らも栄養をとる必要がある。
だが可動部がないので、生存には工夫しなければならない。獲物はおびき寄せても、それを確保する手足もなければ、直接的な消化器官も持たないからだ。そして、反撃されても自らを守る術もない。
だからダンジョンは、体内に白血球やバクテリア的な存在ーーこの場合は幻想種の昆虫および動植物――を飼い、安全な環境を提供する代わりに、養分を分配してもらい共存とする。ダンジョンに侵入する外敵は獣たちの餌となり、わずかな食べ残しが宿り主のものとなるのだ。
そしてダンジョンの被食者で、最たるものが人間である。
何しろ扱いに難がない。餌を用意すれば、ホイホイ中に入ってくる。その上、弱い。倒してしまえば、鱗も毛皮もなく吸収しやすい脆さときている。
そう平たく侮られていることがわかっていてなお、人間は有史以来、この空間生物に抗うことができないでいる。
かくいう、僕だってそうだ。
敷地に入ってすぐの芝の中に、小さな金粒が光っていた。慎重に地面を眺めて見たが、罠はなさそうだったので、近づいて拾い上げる。明らかに路石とは一線を画す重さ、輝き。
金でも豆よりも小さいので、大した値段にはならない。がっかりしてみれば、少し離れたところにも一粒落ちていた。そしてまた、その先にももう一つ。
正直にいえば、こうした臨時収入はどのくらいでもありがたい。
留学生は就業が認められているが、僕は仕事に時間を取られたくない。そのくらいなら絵の一枚、描いていたいのだ。だが美術を専攻する者の常で、僕は画材代に貧している。このご時世に、将来の展望が見えない油絵なんかをわざわざやっているのだ、文句をいうつもりはないけれど。
僕は地面の金を三つまで手にし、四つめは諦めて歩道に戻った。
目視できる限り、撒き餌はC棟の裏階段まで続いているようだった。無邪気にホイホイついて行くと、どこかでこちらが餌にされる。
それはわかっているのだが、ちょっぴり恩恵を預かるのは良かろうと、ちょくちょく落ちているものを拾ってしまう。卑しいと自覚しているし、たまにひどく落ち込む。
ダンジョン暮らしで一番辛いのはそこだ。後悔するとわかっているのに、我慢ができない。
もっとも、効果があるから相手も繰り返し同じ罠を張るわけで、だから僕ばかりが愚かなわけでもないのだろう。
不動産屋の話を信じるなら、常時千人近い人がこの団地にはいるらしい。
説明を受けた時は住人の数だと思っていたが、そのほとんどは一攫千金を夢見てダンジョンを訪れる人々だ。宝を探す者、幻想動物を狩る者に加え、彼らを相手にする商売人が集まる闇マーケットもある。
実際に住み着いている人々は喧騒を避けるので、ダンジョンの入り口中央辺りではほとんど見かけることがない。勝手に家の中を冒険されても困るので、だいたい中庭の手前右側、四階建ての「個人宅」と張り紙のあるビルに、息を潜めるように住んでいる。僕の部屋はそこの二階、中庭向きの角だった。
今日は休講でいつもより帰りが早くなったので、まだ共有花壇では朝の掃除をしている最中だった。
雨が多い国のことだから、毎週のようにこまめに芝を刈り、雑草を抜かないとたちまちジャングルになってしまう。それは逆に言えば、管理すれば多種多様な花を育てられるということだ。定番のバラ、顔ほどもある大きなポピー、華やかなハイビスカス、そして肉厚の、色とりどりの名前も知らない植物たち。
清掃員の多くは、黒い人たちだ。
僕は彼らを、いわゆる黒色人種と呼ばれる人たちだと思っていた。
僕が今まで暮らしたことがある地域は田舎過ぎて、人種の違いを見比べる機会がなかったのだ。だから凹凸さえわかりにくいほどの深い肌色も、その上白目まで黒くあろうとも、そういうものだと考えていた。
全身が漆黒の人たちは働きもので、団地の整備を欠かさない。
このご時世になぜか手動で回しながら蔦を切り刻む除草機で丁寧に花壇を整備し、道に赤黒い汚れが落ちていれば、シミも残さず拭き取ってくれる。団地内には、よくわからない生ゴミが撒き散らされていることもある。そんな時でも文句一つ言わず、朝早くから、必要ならば夜遅くであっても、ちょっと人並外れた技術でもって、元通りにできるのだ。
中庭の大きすぎる円形花壇で、木いちごの藪をかき回しているロシを見つけ、軽く会釈をする。
清掃員たちは全身が黒に制服なので、もちろん顔つきでは判断しようがないのだが、区別は結構簡単につく。背が高かったり低かったり、腰が曲がっていたり針のある肌をしていたり、様々な個性を持っている。
ロシは手足がスラリとして背が高く、中性的な印象の人だ。
声を聞いたこともないが、会話はよくする方だから、嫌われているというわけではないようだ。単純に、無口な質であるらしい。
僕に気がついたロシは棘だらけの枝をかき分け、棒を片手に花壇を抜け出てきた。
手の中の物に見覚えがないか、と質問される。見ればただの棒ではなく、それは一振りの杖だった。
つややかな飴色、木彫りの鳥頭の持ち手で、本体にも朱色で幾何学模様が描かれている。枝先が金属製なのは珍しい。ひと目見てわかるほど使い込まれた代物だが、破損はないので遺棄したとは思えなかった。
繁々と眺めてみても、既視感はなかった。
しかし、時々敷地の中で見かける老紳士のものではないか、と検討をつけた。話をしたこともなく、遠くから見たことがあるだけだが、彼の杖も、地に当たっては金属の高い音を響かせていた。
つくための杖先はゴム製が多く、さらに摩耗を減らすためにテニスボールをつける老人もいる。それに歩行補助のためならば、木製では重たすぎるだろう。件の老紳士のように、地盤を確かめる用途に使うのでないのなら。
「なんであんなところにあったのかな、おじいさん困ってないだろうか」
僕は説明のついでに、ふとそう呟く。
その老人は、金拾いを生業としていた。
金拾いとは僕がさっきやっていた、ダンジョンが撒いた餌を上手く掠めとって自分のものにする行為のことだ。難しくなく、しかし十分な金額を手に入れるには時間がかかるので、暇を持つ老人に多い仕事だった。
老紳士は見た目を気遣う性格のようで、いつも古い映画の貴族のような、スーツやマントに身を包み、帽子も欠かしたことがなかった。でも実際には、迷宮マーケット近くの空き部屋で寝起きをしている無宿人だった。金拾いはそうなるのが常なのだ。できるだけダンジョンの中をあるき回っていないと稼げないし、換金するにしても身分証明がいらない敷地内の業者が楽だから。
頭上で何かが瞬いた気がして顔を上げると、楡の木の上枝に、古いが手入れの行き届いたスウェードの上着があった。
四方で引っかかってわかりづらいが、ボタンが全て止まっている。違和を感じて凝視すると、つられてロシも、視線をそれに集中させた。
干したものが落ちたのはありえない。
場所として一番それに近い棟には人が住んでいないからだ。ベランダには洗濯物も植木鉢も出されてあるけれど、この建物には、中に入るための入り口がない。
それに最近、風が巻き上がるほどの強風もなかった。そもそもこれは、妙な枝のひしゃげ方からして、横から叩きつけられて木に留まったものだ。布に寄った酷い皺は、一度濡れて、乾いたからだろう。
発射されたと思しき方向には、壁から斜めに伸びた煙突。
僕は目線をロシへ移す。
掃除人は件の杖をへし折って、ゴミ袋へ入れたところだった。多分、どうにかしてスウェードの上着を降ろし、片付けることを考えている。
僕達は言葉にしなかったけれど、どちらもあの老人がもう、それらを必要としなくなったことに気がついていた。
それらはどれも「食べれない部分」だ。
改めて見れば、C棟の裏からつながる煙突から、スイカの種を飛ばすように捨てられた遺品たちが、花壇の上に散らばっている。野茨の中では、金粒が冷たく光っていた。でも僕は、それに手を伸ばそうとは思わない。
分不相応は破滅に直結する。ダンジョンでは特にそうだ。毎月何人もいなくなり、だいたいの場合死んで見つかる。おちおち、うっかりもできやしない。
そのへんも、国営団地に似ているのかもしれない。
僕の考えが読めるわけではないだろうに、振り返ったロシは、否定を込めてそっと首を横に振る。
読んでくださってありがとうございました。少しでも楽しんで頂けたらうれしいです。
