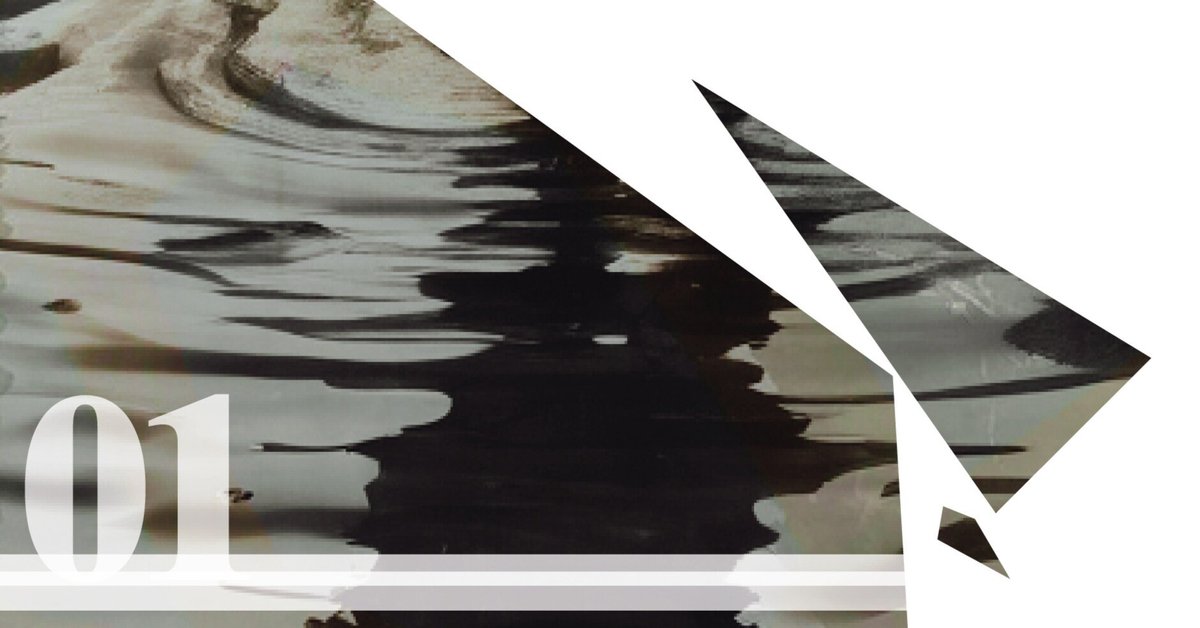
01.床の下
床の下に、罪の証が埋まっているのである。
何が原因でその事件が起こったのかは、くだくだしくなるので省略しよう。ただ、結果そうなってしまっただけで、わたしが心から妻の死を望んでいたわけではない、ということだけ憶えておいてほしい。
息絶えた妻を前に気を失うとか、いっそ狂ってしまえたら楽だった。だがそういうわけにもいかなかったので、わたしは困り果てた挙句、遺体を隠すことを選んだ。街中とはいえ庭の広い一軒家、深夜の出来事に目撃者はないとたかをくくって。
現場である台所には、ちょうど不要の床下収納がある。
暮らし初めの頃は缶詰などを貯蓄していたが、料理の途中に床にあるノブを触って……というのが衛生的・気分的によろしくなく、しばらく忘れていたら内側がカビてしまったものだ。
タイルの色がわからないほど黒く塗りつぶされていたにも関わらず、開けるまで気づきもしなかった。
密封性は折り紙付きだ。容量も申し分ない。ただなんとなく億劫に思って、後始末もそこそこに放置してしまっていた。そのまま、数か月前のリフォームで、上に板を張るように妻が決めたのだった。
改築は業者に頼んだが、安請だから工事の程度は知れている。
フローリング板は強めに押せば、すぐに外れた。下の断熱材もただ挟んだだけというお粗末さだったが、今回に限ってはありがたい。一時間もせず、床下収納の蓋に手が届くようになった。
もちろん、穴を埋めていないことは、工事を見ていたので知っている。
床板一枚、しかも真上ではないものを外しただけでは、さすがに収納の蓋はどかせない。なんとかバールを噛ませて浮かせ、押すと二十センチばかりの隙間ができた。
そこから妻を少しずつ、地中の箱へと詰めていく。
こういう場合、普通なら遺体を細かく切断するものかもしれないが、わたしには血を見ながら作業をする自信がなかった。けれどもちろん、全身そのままでは隠せない。仮に蓋を全開にできたとしても、ヒト一人が入るスペースなど、床下の穴には元々ないのだ。
関節を外すことを思いついた。
まずは足先。
指の関節から丁寧に、骨を外すたびに隙間から妻を押し込んだ。一番大きい大腿骨が床の下に消えてしまえば、後はもう簡単だった。頭蓋骨は流石に無理かと思ったが、首と顎を外しきって力をかければ、案外隙から入ってしまうものなのだ。
蓋を戻すのだけは手間取ったが、金属枠に針金を引っ掻け、引きずり戻す。コトン、と小さな音を立てて取っ手が位置を正した。あとは跡形もなく、元通り。
断熱材を戻し、フローリング板を乗せて、わたしは日常に戻る。
あまりにも元通り過ぎて、三日目には混乱した。
妻が帰らないことに不安となり、警察に捜索届を出した。
官憲は全く関心がない素振りで、提出書類にも目を通したのかどうか、署で事情も聞かれなければ、誰も家へやってこなかった。年間の行方不明者の数を考えれば、それはしょうがないことかもしれない。
一週間を過ぎて、廊下の隅に、妻のピアスが落ちているのを見つけた。
それでやっと、あれは夢ではなかったのだ、との確信を得た。
だからといって、何もしなかった。
仕事をし、買い物に行き、時々人に会い、妻の心配をしたりされたりして、表面上は平穏な生活を続けた。
がらんとした家の中はうすら寒く、どんなに掃除してもきれいにならないフローリングのシミに、日々焦る気持ちを抱いてはいたけれども。
数か月経って、床下収納を開けて見る気になった。
前回と同じくずらして覗いた正方形の穴には、黒い水が溜まっていた。
わたしはその時、ひどい激臭がするかと身構えていたのだが、不思議なことに床下からは何のにおいもしなかった。目立った汚れさえ、穴の周りには見当たらない。あるのはただ、フローリング板の裏に生えた、僅かなカビと埃のみ。
水面は穏やかだった。
窓から零れる月明りに、ちらりともしない。
奇しくもあの日と同じ、夜半に思い立ってやってきた台所だ。やましい心から電気を付けられず、床下の水そのものが黒いのか、闇が濃いのかもわからない。しかし、そうでないなら妻が見えているはずだから、論理的に考えて、やっぱり水は濁っているのだろう。
床の下にあるのは、死体からにじみ出た水なのだから。
目を凝らしても、何にもない。わたしは収納の蓋は開けたまま、手探りで上板だけ戻してその夜は寝た。
翌朝の日の出頃、睡眠中に突然沸き上がった不安に駆られ、飛び起きた。階段を転がるように降り台所へ、床板を剥がして水を確かめる。水はやっぱり、底が知れない鈍色をしていた。
水面が揺れた。
明らかに生物が作り出した波紋を見て、わたしは思わず床下への隙間へ、顔を近づける。
黒の液体は立ち上がると、目にも止まらぬ素早さでわたしの首に巻きつき、伸びたものが跳ね返る力強さで、ぐっと床に引き寄せた。
受け身など、とれるはずもない。額が床板に当たって、血を吹き出した。
首の骨が外れ、二つ折りになる。水はそこで一端わたしから離れ、力なく穴の淵へ垂れ下がった手を握る。関節を外す。指先の第一関節、第二関節、手首。ずるずると惜しむように、水は穴の中へわたしを引き寄せる……
それは、途方もなく長い時間だったように感じられた。
けれど実際には、ほんの数秒の白昼夢だ。
気が付いた時、止め忘れたアラームがまだ寝室で鳴っていた。本当に僅かな間も過ぎてはおらず、わたしはなぜだか、胸が急にいっぱいになった。
そんなわたしの指先へ、水の中の見えない何かが、甘噛みを繰り返す。
指が全て入ってしまいそうな大きな口で、名残惜しそうに、ゆっくりと。
纏わりついてくる濁った水へ、わたしは手の平を差し出したが、撫でられることを厭うてか、それは身をくねらせた。皮膚を切るような一瞬の感触は、顎かうろこか、牙か爪によるものか。
こんなに育ってしまっては、もう外を出してやることもできない。
窓から零れる朝日が、視界を白くぼやかせる。座り込んだ冷たい床の上、食卓とそこに収まるイスが、冷たく澄ました顔でわたしを見下ろした。
ほの暗い水の上、床板をそっと置く。
そうして今日も床の下、罪の証を埋めたまま。
読んでくださってありがとうございました。少しでも楽しんで頂けたらうれしいです。
