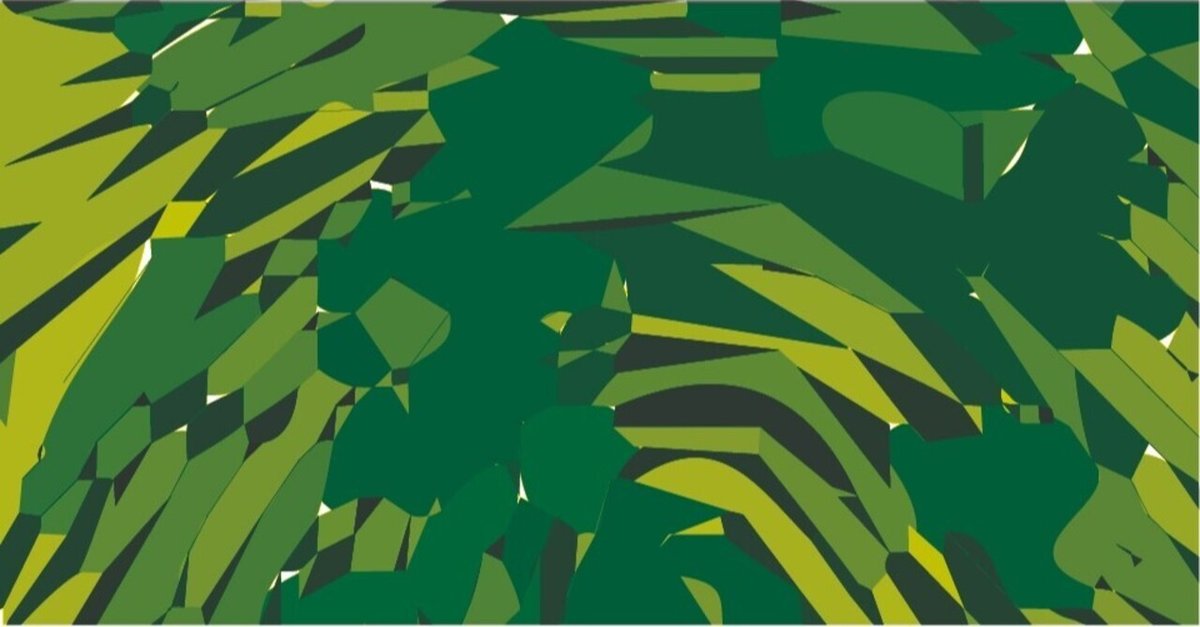
20.指紋
浴室の鏡に、指紋を見つけた。
わたしのものではなかった。壁に鏡を押さえつけているような跡だった。わたしはそんなことをした覚えはない。それに、こんなに太い指も持っていない。
白い線が渦を描いて、湯気の中ではっきりと浮かび上がっていた。タオルで拭っても消えない。どうやらそれはガラスの内側についたもので、設置のときにうっかり素手で触ってしまったものらしかった。
わたしはバスタブから出たばかりで、水滴の残る素肌からは、まだ湯気が出ていた。
でも入浴した記憶がない。
よく考えれば、この浴室にも見覚えがない。骨の浮いた細い腕にも、たわわとは言い難い薄い胸にも。下半身には、ついているべきモノがない。
頭に霧がかかって、明確に物を考えるのを阻んでいる。
一瞬だけ、息を止める。ぼくは「わたし」になった経緯になんとなく察しがつき、ため息をついた。
着るものがないのでタオルを巻き、廊下へと出る。
家中が何年も放置されたように、塵でどこもかしこも覆われていた。汚れているだけで壊れているところはない。まるで住んでいた人だけが、消えたみたいな家だった。キッチンのコンロには、焼いてそのまま黴びるに任せた何かが、フライパンに残っている。
テーブルのコップ、浮かぶ氷と縁の上に埃が積もっていた。
寝室のクローゼットを漁る。咳き込んだかいあって、使えそうなTシャツとジーンズを見つけた。どちらも丈が長すぎたので、ハサミで切って整える。元の持ち主に申し訳ないが、でもそれは、そんな人物がいたとしたらの話だ。
家の中は薄暗く、かけられたカーテンはすべて閉まっていた。
居間の窓にかけられた薄布を引くも、明るさはあまり変わらない。ここはどうやら、団地の一室であるらしい。視界の中、同じ建物が規則的に並び、遠くに教会の十字架付き屋根が見えた。
黄緑、オレンジ、あるいは紫色の落ち葉が、歩道に色を添えている。夕方とも明け方ともつかぬ、時間を知らせる気のない水色の空を、真横からの橙の光が照らしていた。
薄着でも寒さは感じない。けれど、なんとなく冬の日である気がした。冬、朝もまだ早い時刻。
住宅地はしんと静まり帰って人気がなく、しかし上の階がある天井からは、誰かが歩き回るささやかな音が響いてくる。
風がそよともしない窓からの風景は、貼り付けられた写真よりも動きがない。
思い切って玄関を出ると、目の前に外階段の踊り場があり、表の通りが見渡せた。
先程と同じ団地が、理路整然と並んでいる。見えるところに高い建物はない。通りの両側の歩道には、大人が腕を回しても届かないほど幹の太いトチノキが、等間隔で植わっていた。葉は半分以上落ちて、道を埋めている。
アスファルトの車道には数台車が置いてあるが、最近動かした形跡はなかった。
「ナヌーク」
階段を降りる間、声を張り上げて名を呼ぶ。
ナヌークはわたしの侍従で、背が高くて頭がトナカイみたいな形をしている。契約上わたしから離れることはないので、彼も近くにいるはずだった。ただし、わたしの形が変わっている以上、姿形が同じである保証はない。見つけられるか、不安はあった。
そんな心配をよそに、アパートを出てすぐ、あっけなくナヌークは見つかった。
周囲を散策していたらしい、目の前の緩い坂の上の、曲がり角から顔を出す。小走りでやってきて、息を切らしている。それは彼にとっては珍しいことだったので、わたしは目を見張った。いつものように影の中を移動した方が楽なはずだ。それをしないのはできないということで、つまりこの場所では普段と勝手が違うらしい。
「随分お可愛らしい姿になられましたね」
そんなことを言う従僕には、下顎から上がない。濡れた赤紫の舌の周り、頬は引きちぎられたように皮膚が捩れてぶら下がっていたが、痛みはないようだった。目がなくても困らないらしい。まあ、ヒトとは違うからな。わたしはあまり考えないことにした。
「ここ、どこだかわかる? 他に誰か巻き込まれたりしていない?」
「世界線や階層が違うわけでは、ないようです。先回の自立稼働する空間拡張と、構成は似ています。しかし今回は、私達の他に生きたものの気配がありません」
「また新しい数式の実験に、使われたかな?」
「それにしては、手動での圧力を頻繁に感じます。被験者の変形も顕著ですし、試作するにはあまりに未完成かと思われますが」
わたしはため息をついた。
「じゃあ、単に暇だったんだろう」
出てきたばかりの建物の、一階の窓が大きな音を立てた。
濡れた手のひらで叩いた跡が、内側に残っている。水滴の飛び散り方を見るに、結構な力をぶつけたようだ。
風もないのに、道路の枯れ葉が一斉に揺れた。
とりあえず身の安全を確保すべく、わたしは一度アパートに戻ることにした。以心伝心の下僕が黙ってそれに続く。手を添えた外階段の手すりは、下半分がひどく錆びていた。
ナヌークが車寄せに足を踏み入れた途端、家の前の落ち葉が再び動いた。
道路に水が滲み出てきたのだ。それは瞬く間に膝の上まで上がってきて、すでに二階を半分まで来ていたわたしは、追い立てられるまま階段を登る。家の前の坂、下から上への水位に押され、ナヌークは並ぶ隣棟の入り口近くまで避難した。靴の先にも触れさせようとしないのだ。ただの水ではあるまい。
こうなるともう、アパートに連れてはいけなかった。
そもそも、おかしいと思ったのだ。
この間の実験で、ナヌークがこの構成から抜け出すのは容易いとわかっている。おかげでぼくもすぐに脱出することができたのだから、同じことを繰り返しては意味がない。暇つぶしなら尚のこと、この脱出ゲームを早々に終わらせる敗因は排除したいはずだ。早かれ遅かれ、侍従とは隔離されていたのだろう。
あるいは単純に、弟に嫌がらせをして楽しみたいだけかもしれない。昔から、こういうことをするのだ。
苛々と舌の後ろから青白い炎を吐くナヌークを落ち着かせようと、注目を得るために僕は手を振った。
「不愉快です。いつもと何かが違うのですが、それがわからなくて、とても」
四足でその場を回り言う。どうやらナヌークにしても、思考妨害がかけられているらしい。それが故意なら、現状を理解させない所に解決のめどが見つかる気がする。ともあれ、
「部屋に行かなきゃいけないみたいだから、行くよ。ぼくが脱出できたら、君もすぐに帰るんだよ」
多分ではあるが、招かれざる客であるナヌーク一人なら、造作なく現実に戻れる。でも釘を刺しておかないと、ナヌークは破壊の限りを尽くして、まずこの空間を灰燼に帰してしまいそうだ。それはわたしの望むところではない。土地自体で言えば、居心地が良くて実に「ぼくの」好みなのだ。
従者が渋々了承するのを見届けて、わたしは出てきた部屋に戻る。
ナヌークの過保護はいつものことだけれど、なんだろう。何かがひっかかる。最近は特にそれが極端だった。でも、それには理由があった気がする。
考えながら足を踏み入れた住居は、また違った様相をしていた。
今度は清掃が行き届いた、しかし生活感のない白壁の廊下がまっすぐ続いている。左右に四部屋づつドアがあった。病院のように名札が左右に貼ってあるが、どれも白紙だ。
いや、紙ではない。漆喰の壁でもない。室内のものはひとつの接着された――違う、同じ物質を削りだして造ったひとつの塊だ。物質が粘土なのか、紙なのか水なのかもわからない。機能性ではなく外見だけを整え、作られた彫刻だった。
外階段に戻り、唯一行けれる上の部屋を覗いてみようと試みる。
上ることはできた。けれど、その玄関が溶接されていて、開けることはできなかった。ひょっとするとそこも、ドアではなく壁の一部として開かないオブジェなのかもしれない。
腹部の辺りから視線を感じる。目を向けると、そこにある郵便受けの蓋が、ぱたりと閉じた。全身の皮膚が泡立ち、そそくさと階段を降りる。
そういうことをするひとなのだ。
僕には姉が一人いる。
魔女だ。優秀なのはもう、誰の目にも明らかだった。おまけに人当たりがよく、容姿も悪くない。でも性格に難があった。
人格というか、根本的な性質の問題で、とにかく好奇心が強すぎるのだ。
とにかく思いついたら、やってみなければ気が済まない。その頭脳でろくでもないことばかり開発し、問答無用で弟のぼくを巻き込む。身近で手頃、変化がわかりやすい実験台として。
でもまだ、ぼく一人が標的ならばマシなのだ。
人間であれ同族であれ、他人を巻き込むと犯罪になる。これまで起訴されなかったのは、ただ被害者が知り合いだったり親切だったりしただけ。亜空間にいきなりヒトを放り込むなんて、殺意がないと判断する方がおかしい。
幸い十三人の魔女たちが、姉を問題視していた。異変に気がついて外側から助けがくる可能性だって、ないわけではない(もちろん、かなり『無い』寄りではあるが)。
足元がふらつく。見ると床板に、指紋が浮いていた。
先程と同じ手だ。太く、大きく、中指の第二関節まではっきりと確認できる。両脇に人差し指と薬指の腹が、ほんの気持ち程度に添えられていた。誠実そうな手だ。
フローリングの艷やかな床に、はっきりとそんな指紋が見える。
中指が、段々広がっていく。膨らむように見えるのは不安定な楕円であることからくる、ただの目の錯覚だ。水の上を波紋が走る速さで、しかし円はところどころ途切れ、わたしの足の裏を侵食する。そこだけ熱いのか冷たいのか、極端な温度差で皮膚が張り付いた。いつの間にか、肢体の先が冷え切ってしまっている。
わたしは慌てて廊下に足を刻む。
どのドアも動かない。
鍵がかかっているか、後ろから押さえつけられているのであれば、まだ希望が持てた。でもこれは、偽の出入り口とわかっている。それでもわたしは、ドアノブをひとつずつ捻ってみなければ気が済まない。
唯一空いていたのは、浴室だけだった。
これはまったく先程と同じ、使ったままの湯気によって、タイルの壁が濡れている。
バスマットの上に飛び乗った。衝撃でシャワーカーテンから水滴が落ち、浴槽に溜まった水の上を跳ねる。湿気ったタオルもそのままだった。ちょっと埃が溜まった手洗い、洗面所には曇った鏡。
気がつくとまた服が消えて、湯を浴びた直後に戻っている。
相変わらず貧相な体のまま、性別は違うし年齢は違うし、環境からの負荷が違う。
わたしは両手で顔を覆った。大掛かりな実験のはずがない。夢の中に入るとか、そんなところだろう。ただしこれは、わたしが望むそれではない。
姉の夢でも、あるはずがなかった。
そのことを思い出す。わたしは大きく開いてゆく瞳孔に、何も映さないためまぶたを閉じる。
ガラス板をビスで止めただけの鏡の上、指紋がゆっくりと大きく伸びる。広がって立ち上がり、わたしをここに残して、隣の通路と通路を隔離、あるいは融合する。肉眼で見ているわけではない。けれど外へ向かって、迷路が確かに続いていく。どこまでかは、定かではなくとも。
姉は先月、死んだのだ。
自殺だった。どうなるのか気になって、試しに命を絶ってみたのだ。遺書も何もなかったけど、ぼくだけはそれと知っていた。たった一人の姉、その唯一の弟だから。
死んで尚、こういうことをする姉なのだ。
いつ吸ったかわからない息を吐く。それで、湯冷めする前に出られたら、わたしの勝ちで良いのだろうか。
読んでくださってありがとうございました。少しでも楽しんで頂けたらうれしいです。
